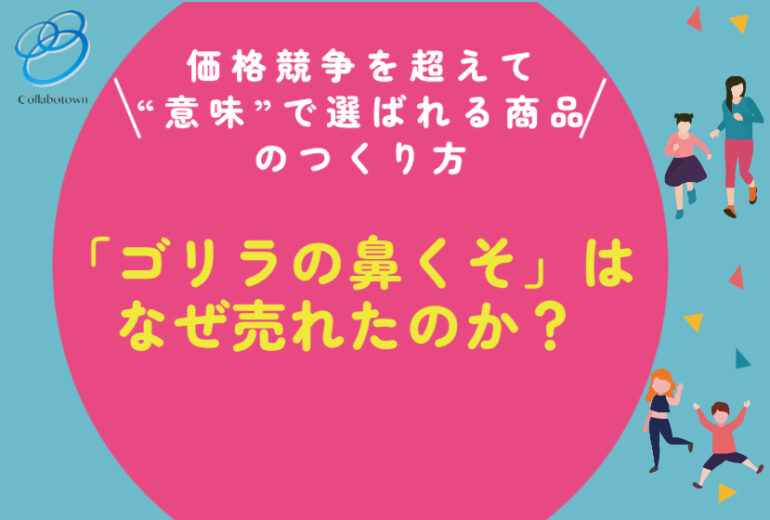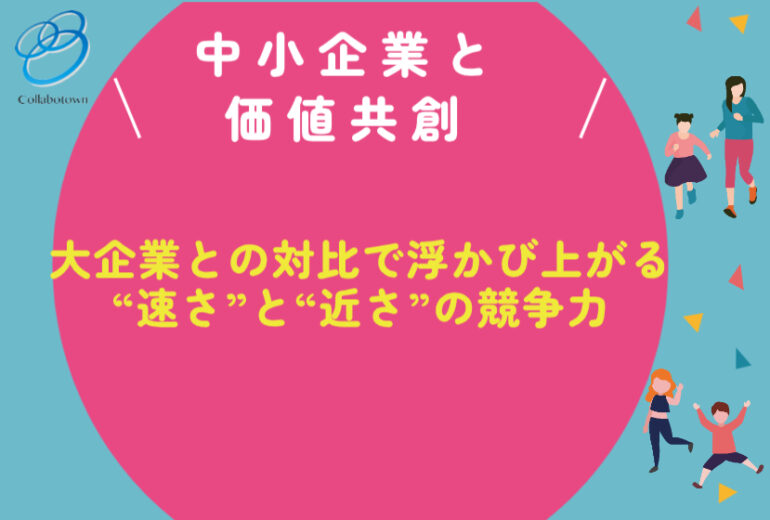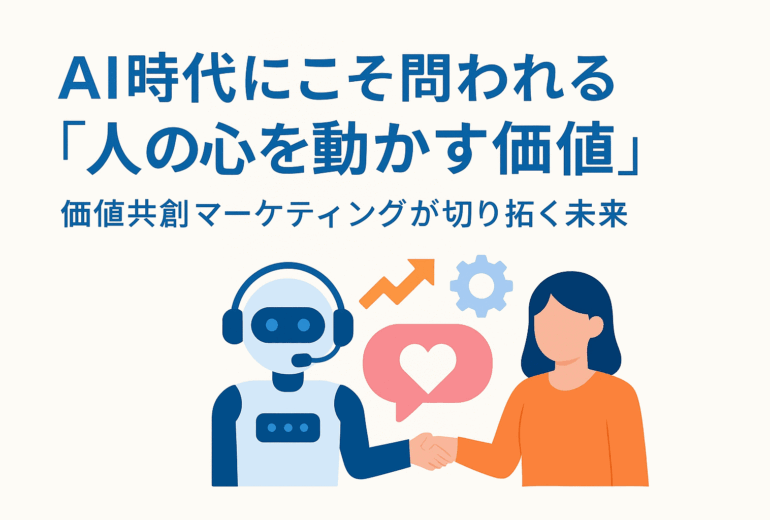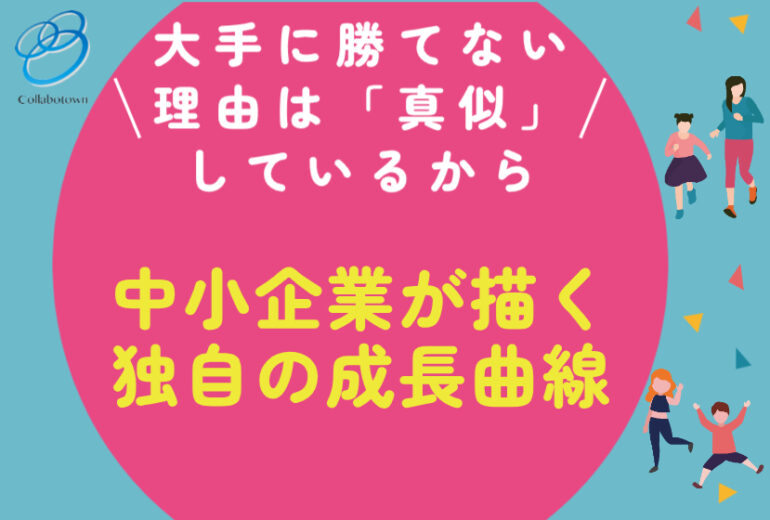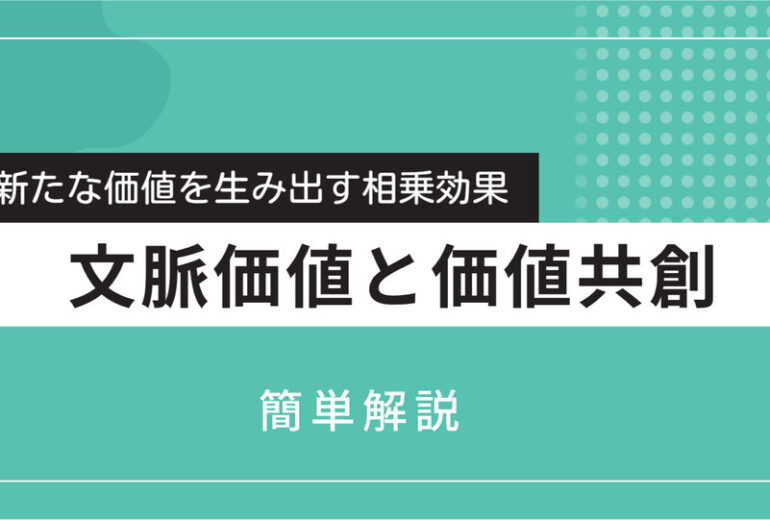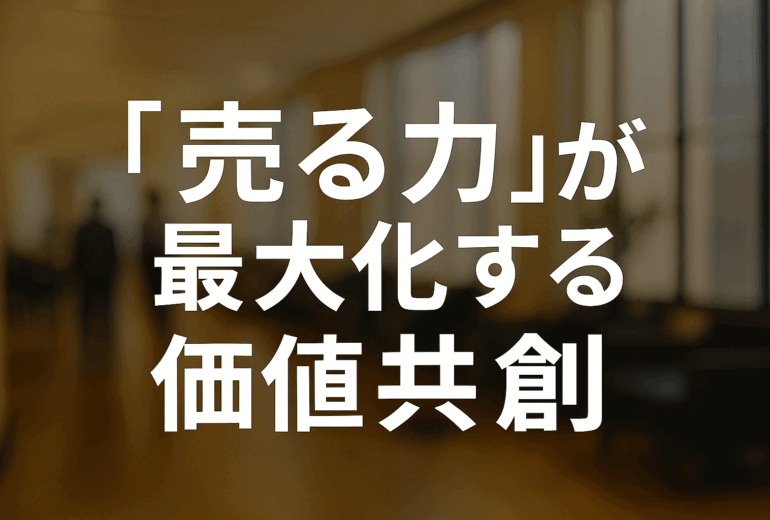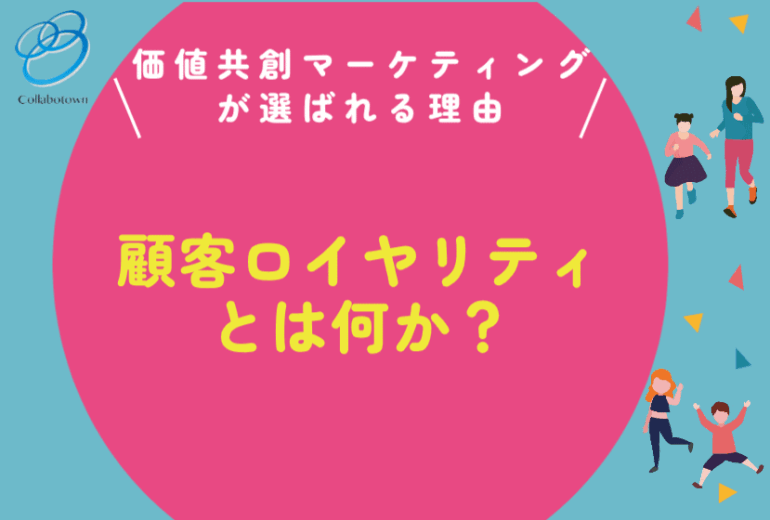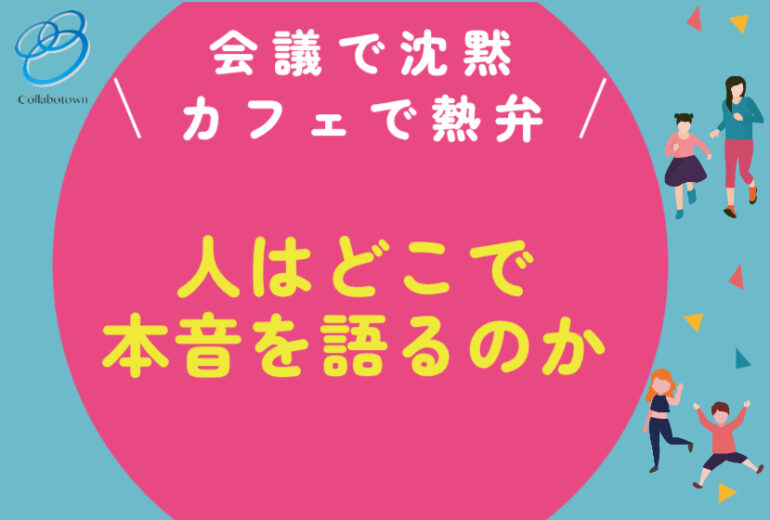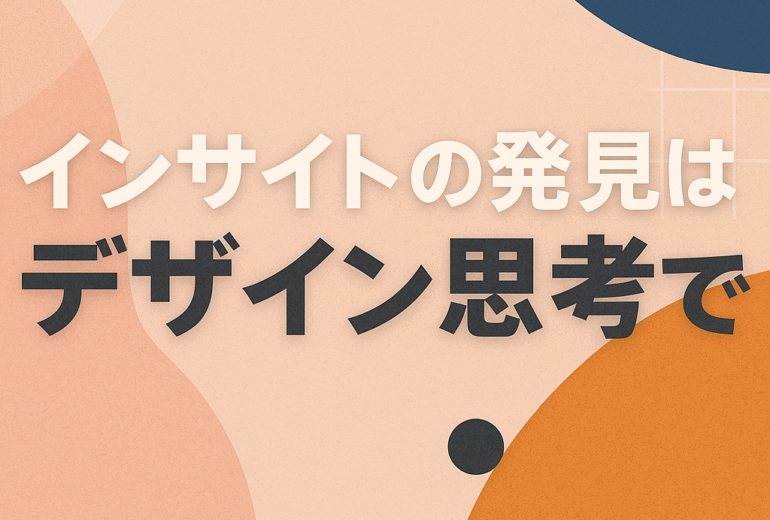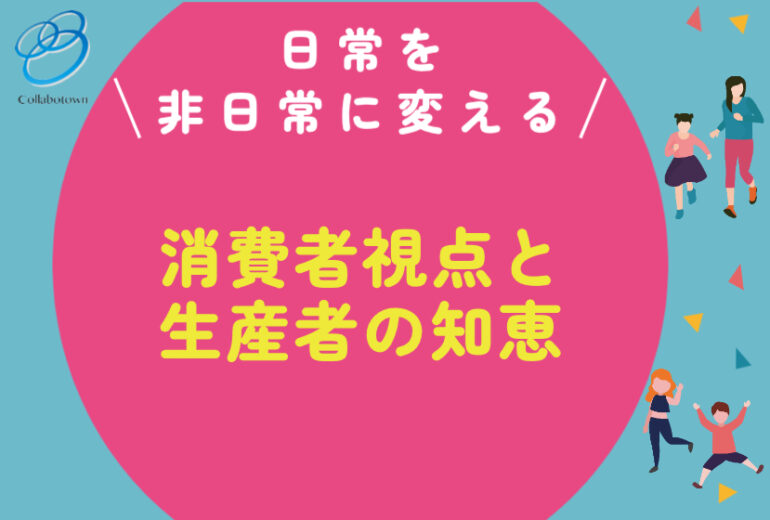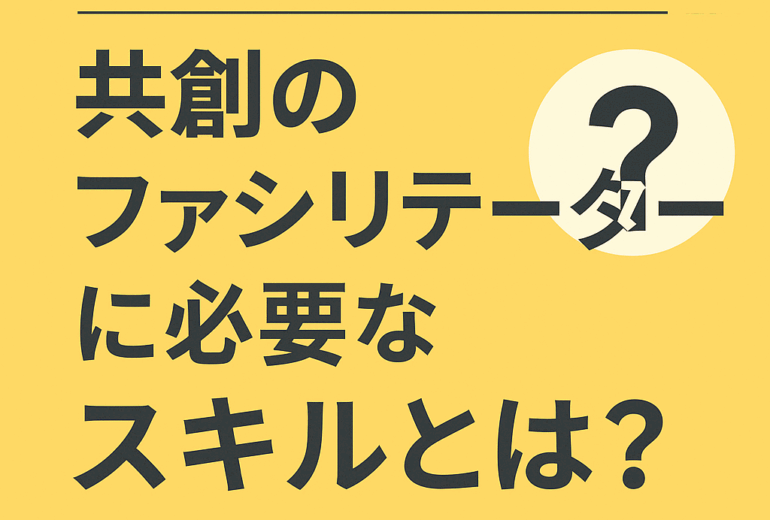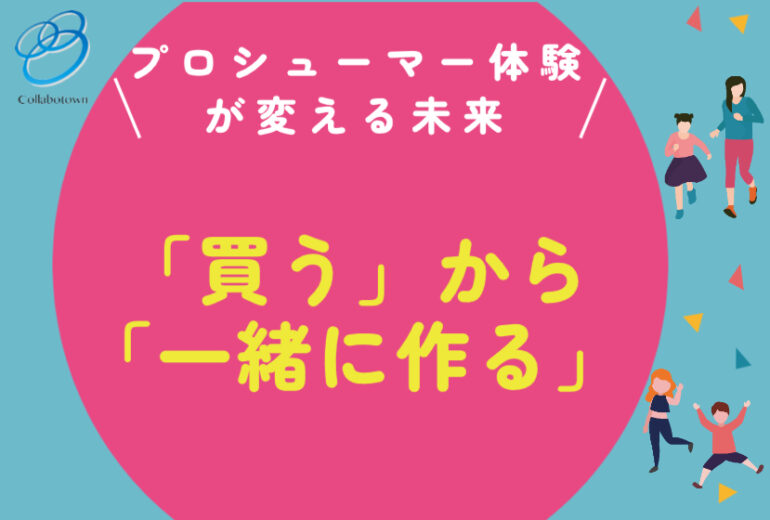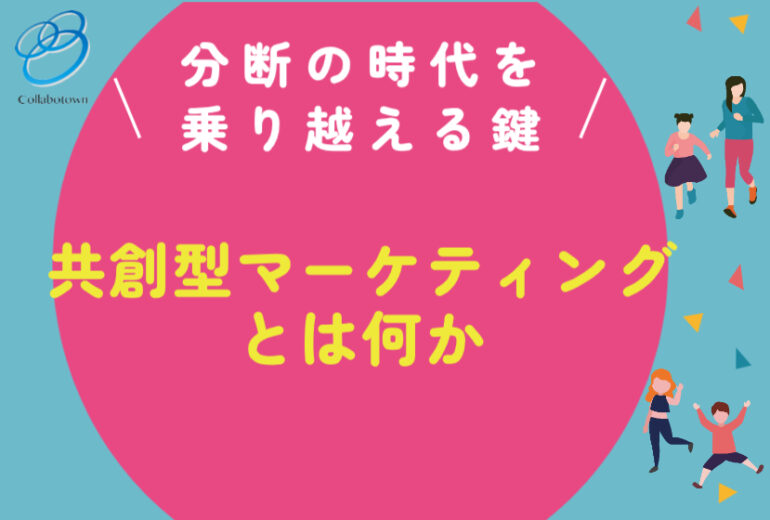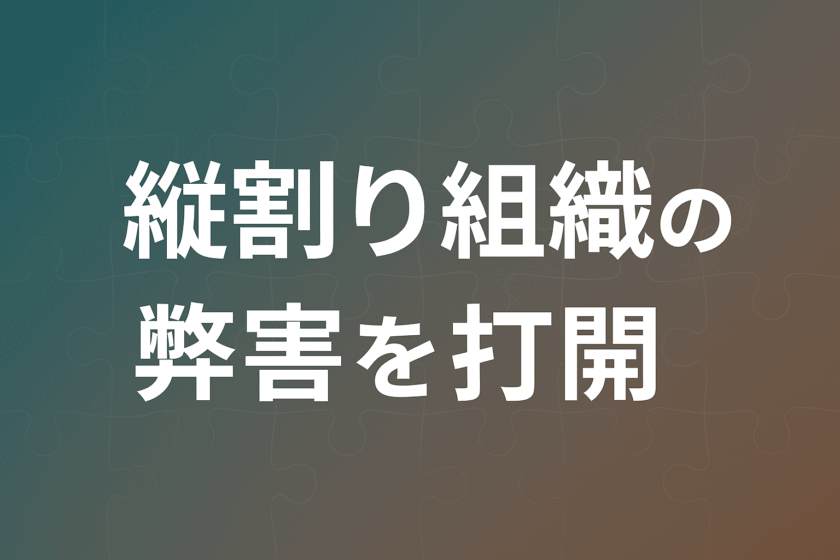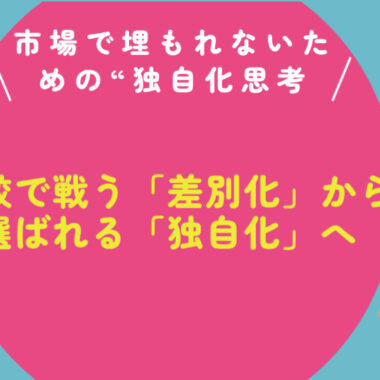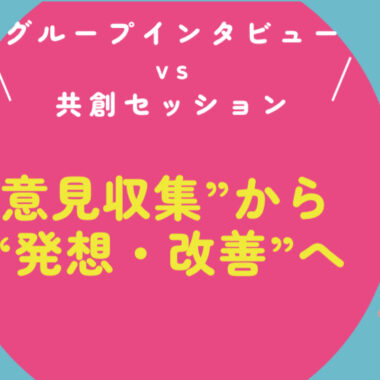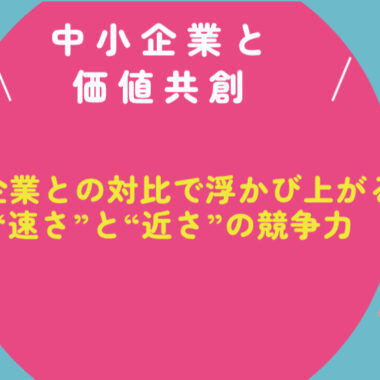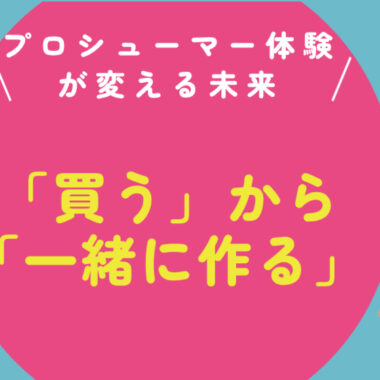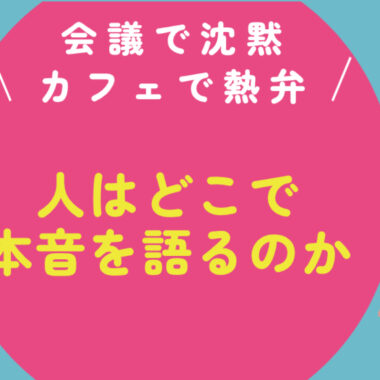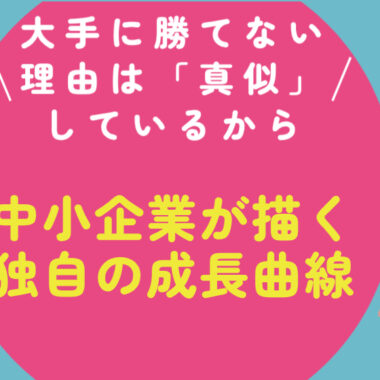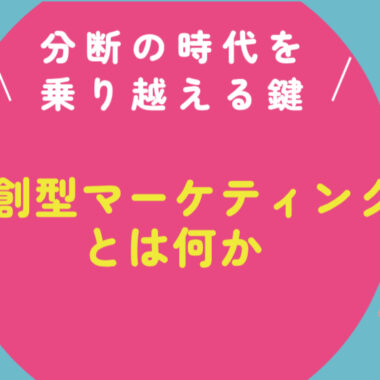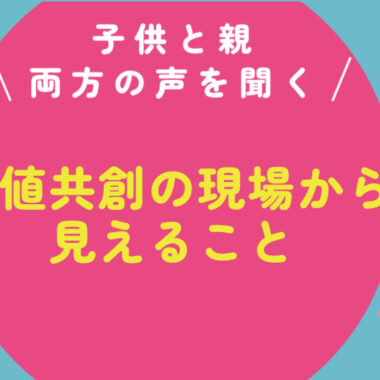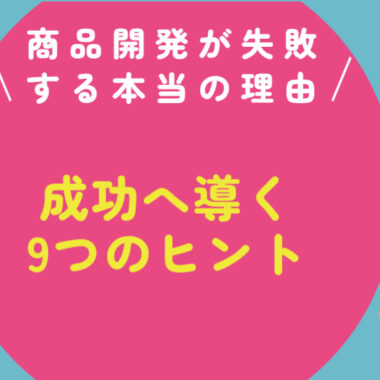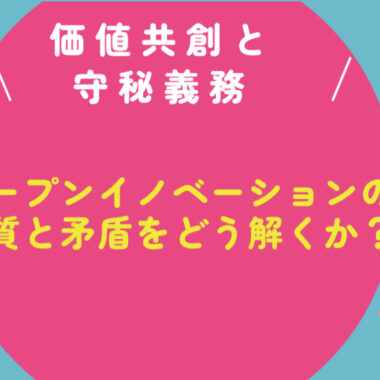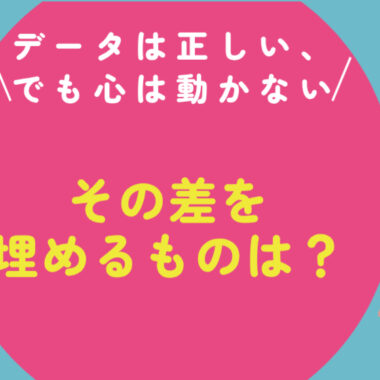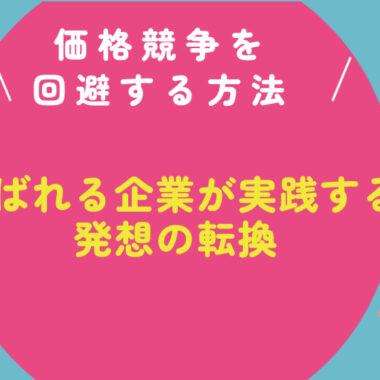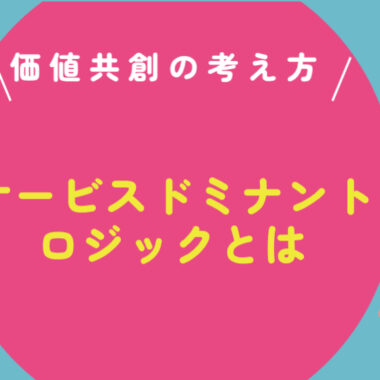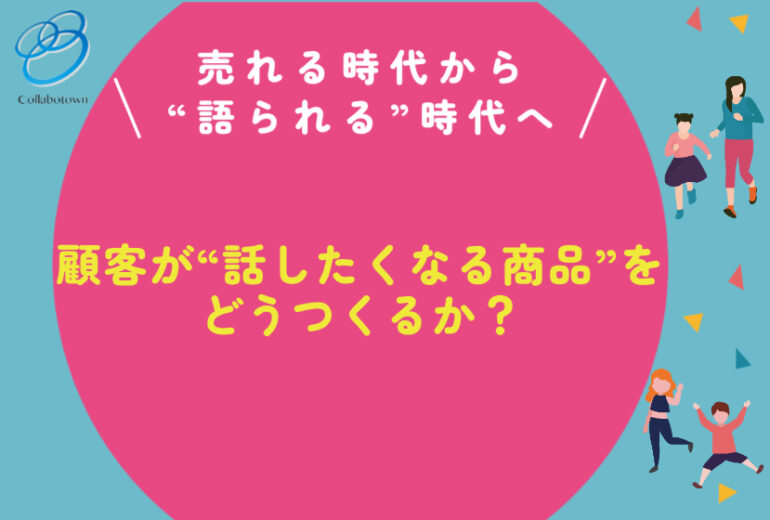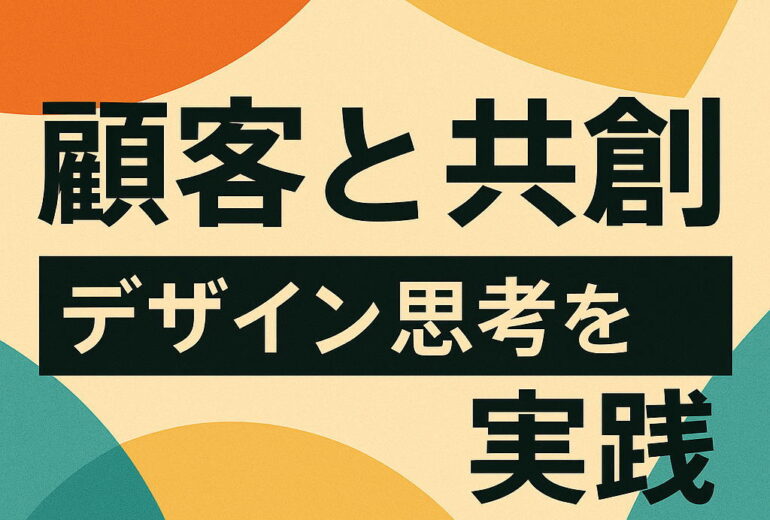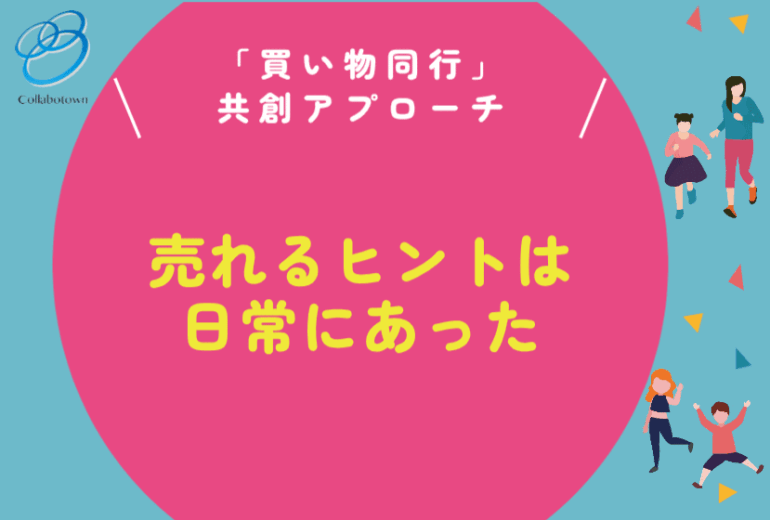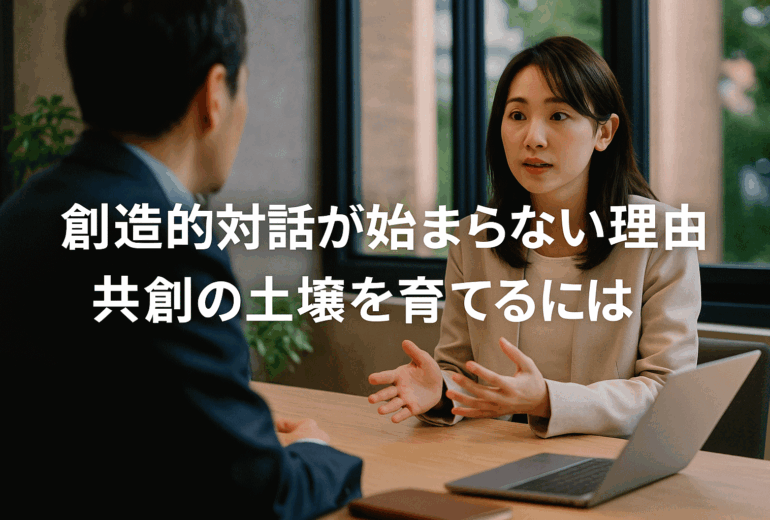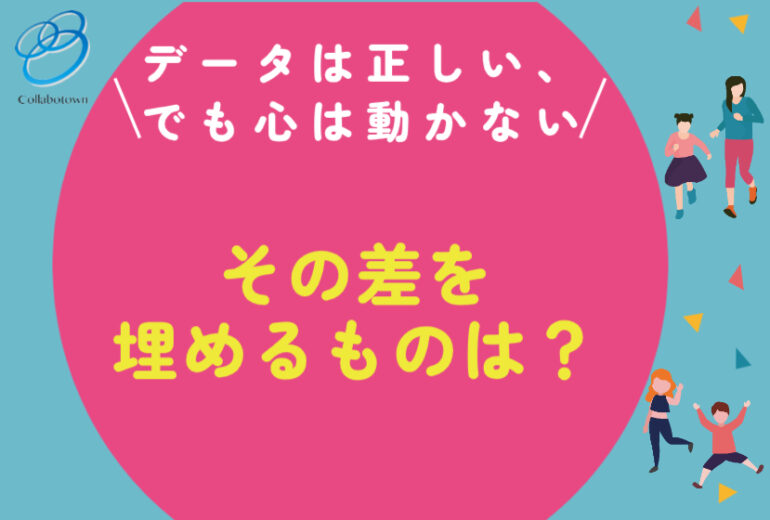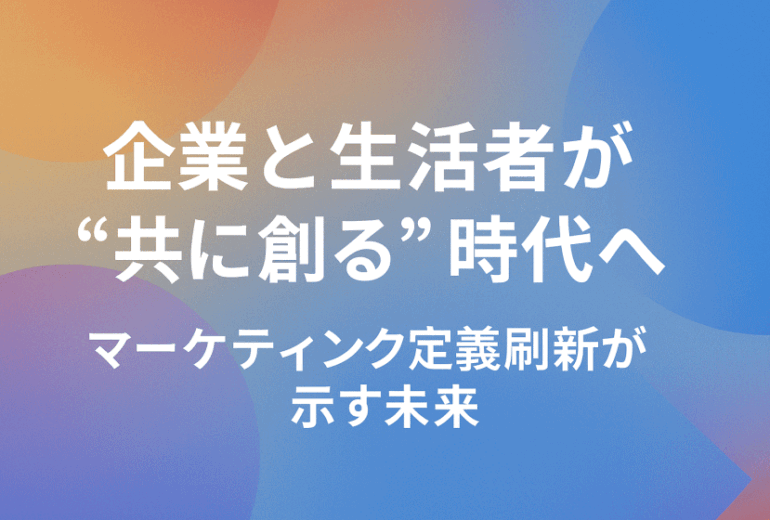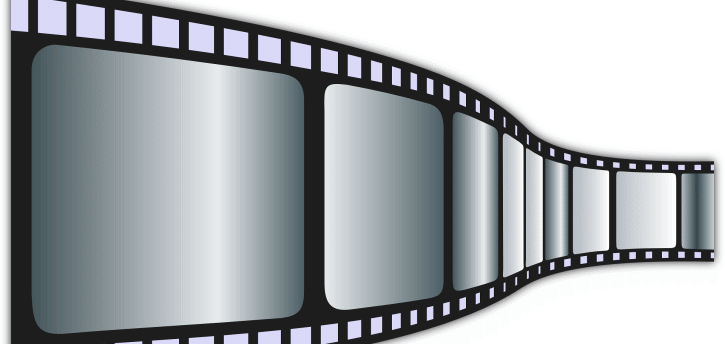縦割り組織の弊害と共創マーケティング
縦割り組織には明確な役割分担や責任範囲があるため、業務の効率化や専門性の高い業務の実現などのメリットもある一方で、意思決定の遅れ、コミュニケーションの乱れなどの、いわゆる「縦割り組織の弊害」が生じる場合があります。
共創マーケティングは、企業と消費者が共にプロダクトやサービスの開発や改善に取り組むプロセスであり、縦割り組織に起因する問題を解決する可能性を秘めています。
縦割り組織の弊害とは
- コミュニケーションの乱れ: 上下関係や部署間の立場の違いが意思疎通を妨げます。
- 変化への適応性の低下: 部署が自己完結していることで組織全体での柔軟な対応が困難に。
- 新規事業やアイデアの阻害: 既存の枠組みに縛られ、革新的な発想が出にくくなります。
- 情報の非対称性: 管理職と一般社員の情報格差により判断ミスが発生。
- 意思決定の遅れ: 判断が上位層に集中し、スピード感が失われます。
- シロアリ現象: 部署間の協力不足が全体最適を損ないます。
- 組織全体のビジョンの欠如: 各部署が独立して動くため方向性がバラバラに。
- 顧客志向の欠如: 顧客の全体像を捉えることが難しくなります。
縦割り組織の弊害が表れるサイン
以下のような行動が見られるようになった場合、縦割りの弊害が進行しているかもしれません。
- 任意参加のイベントに不参加が続く
- 部署間で批判的な言動が増える
- 他部署の業務に無関心・非協力
- 情報伝達を意図的にしない
- 誹謗中傷や他部署への悪意ある行動
共創マーケティングの実践
共創マーケティングは、部署や役職の垣根を越えて、顧客と共に課題を発見し、解決策を創出する手法です。
- 商品企画、営業、開発など、複数部門が初期から関与
- 上司・部下の上下関係を取り払い、対等な立場で対話
- 社内プロセスの迅速化、情報伝達の効率化
- 社員一人ひとりの経験を活かし、新たなアイデアが生まれる
共創マーケティングが縦割り組織の問題解決になる理由
- チームワークの促進: 部署間連携が必要不可欠となり、協力関係が築かれる
- 顧客との対話の促進: 顧客の声を反映し、部門横断で価値を創出
- 社員のモチベーション向上: 顧客との接点が増えることで自己肯定感が向上
- 製品・サービスの品質向上: 顧客のニーズに基づいた改善が可能に
- 顧客ロイヤルティの向上: 参加型の経験がファン化を促進
まとめ
共創マーケティングは、縦割り組織の問題を自然と乗り越え、顧客との協働により企業価値を高める戦略です。
社内外の壁を取り払い、共に創る体制をつくることで、企業の持続的な成長と顧客満足の向上を両立させることが可能です。