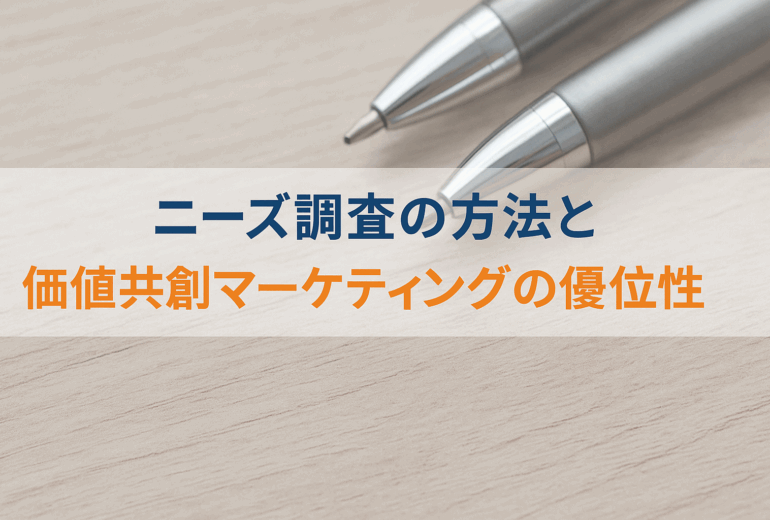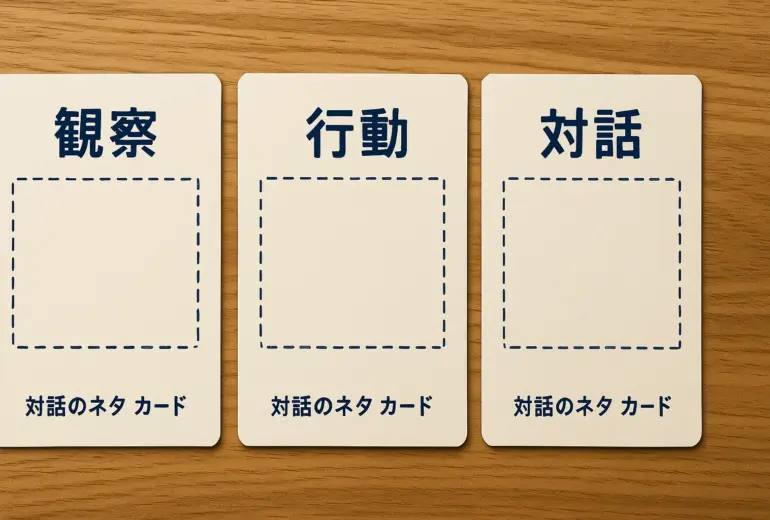企画会議では語られない“選ばれる理由”は、棚の前の迷い、手に取って戻すしぐさ、そして何気ないひと言に潜んでいます。 こらぼたうんが実践する買い物同行(ショッピング・エスノグラフィー)は、生活者のリアルと向き合い、 企業の「当たり前」を揺さぶる共創の入口です。
本記事の位置づけ
-
🎯 インサイト発見ガイド(全体像)
観察・買い物同行・場づくり・拡散/収束などを、索引として整理したガイドです。
-
🔷 価値共創マーケティングとは?(全体ガイド)
価値共創マーケティングの基本概念と導入ステップをまとめたガイドです。
はじめに:調査では見えない“気づき”を求めて
「なぜこの商品を選んだのか」「その棚の前で何を迷っていたのか」—— 生活者の行動には、企画書や統計データには表れない“選ばれる理由”が潜んでいます。
ここで言う“売れるヒント”とは
価格や機能の比較だけでは説明できない、手に取りたくなる理由/戻してしまう理由/安心できる理由。 それらは多くの場合、本人も言葉にしていない「無意識」の領域にあります。
こらぼたうんでは、メーカー担当者と一緒に現場へ出向き、 買い物同行(ショッピング・エスノグラフィー)を通じて、 生活者の視点を“肌で感じる”ことから共創を始めます。
なぜ「買い物同行」なのか?
現代の消費は複雑です。機能・価格・ブランド・習慣・感情…… 人はさまざまな要因を無意識に行き来しながら、棚の前で選択します。
“その場の迷い”は、データになりにくい
購買データは「買った結果」を示しますが、棚の前で迷ったプロセスは残りません。 しかし本当のヒントは、迷いの中にあります。
言語化前の“しぐさ”に本音がある
- 棚の前で足が止まる
- 手に取って、戻す
- 別カテゴリーの商品と比較する
こうした“間”が、インサイトの入口になります。
観察と対話を同時にするから、理由が立ち上がる
買い物同行は、生活者の買い物に企業担当者やファシリテーターが同行し、 観察と雑談を通じて意思決定の流れを共有する手法です。 単なる“ヒアリング”ではなく、行動と会話が同時に起こることで理由が立ち上がります。
こらぼたうん式「買い物同行」3つの特徴
メーカー担当者も「生活者」として同行
「売る側」ではなく「生活者の目線」で店頭を歩いてもらいます。 自社商品が並ぶ棚を“第三者として見たとき”に初めて気づくことがあります。
「あ、うちの商品って意外と地味に見えるんですね……」
自席でパッケージを見続けていると、どうしても自社常識に閉じます。 だからこそ現場で“視点のリセット”を起こします。
質問攻めにしない「対話型ファシリテーション」
買い物中は、あえて“インタビューっぽく”しません。 「何を選びましたか?」よりも、 「どれと迷いました?」や「どうしてその棚に引き寄せられました?」のような さりげない問いかけと雑談で、無意識の選択を言語化します。
場の空気を壊さない“問い”の例
- 「今、手が止まったのは何が気になったから?」
- 「似た商品があるとしたら、どれが近い?」
- 「普段は誰のために買うことが多い?」
すると「これは夫が使うから」「ちょっと高くても時短になるから」など、 生活の背景や価値観が自然に浮かび上がってきます。
現場から持ち帰る“気づきの種”を、必ず言語化する
買い物同行のあとには必ず「気づきメモ」を共有し、振り返りの時間を設けます。 観察は言語化して初めて資産になります。
- A社の製品は棚の目線にあり、取りやすかった
- B社のパッケージは遠目でも目立ち、指名買いが起きていた
- 試食・体験のある売場は、手が伸びるスピードが違った
でも本当に重要なのは、「観察結果」そのものではなく、 私たちはどう見られているのか?という問いに向き合えること。 買い物同行は、そのための“リアルな鏡”になります。
中小企業にもこの方法が向いている理由
「そんな余裕ないよ」「大手みたいに調査予算がない」——よく聞く声です。 でも実は、中小企業にこそ買い物同行は向いています。
中小企業にフィットする3つの理由
- 小回りがきく:現場の気づきをすぐ改善に反映しやすい
- 顔の見える関係をつくりやすい:生活者と“共につくる”関係が生まれる
- 一度の体験が社内を動かす:机上の議論より納得感が強い
特別な設備や大きな予算は必要ありません。 必要なのは、「一緒に買い物をする」というシンプルな姿勢だけです。
買い物同行から生まれた“気づき”の一例

実際に参加したメーカー担当者からは、さまざまな“目からうろこ”の声があがります。 日々売場を見慣れているはずの彼らが、生活者と一緒に売場に立つことで、 まったく違った景色を見始めるのです。
「普段なら気にも留めない他社商品に、生活者がじっと目を向けているのを見てドキッとした」
ある担当者は、生活者が自社商品ではなく意外な競合商品を手に取り、 その理由を何気なく語る場面を目の当たりにしました。 そこにあったのは「価格」や「機能」だけでなく、 見つけやすさ/なんとなく手に取りたくなる感じといった、 企画会議では語られない基準でした。
「うちの商品、棚にあるのに“見えていない”ことがあるんですね…」
「POPを工夫したのに…」「ロゴが目立たないと言われて初めて気づいた」—— そんな気づきが、価値共創の最初の一歩になります。 そして会話の中で「昔から使ってるから」「なんとなく安心感があるから」という 数字には表れない選ばれ方にも出会います。
買い物同行は、単なる観察ではなく、 自分たちの常識に揺さぶりをかける体験なのです。
買い物同行=生活者との“共創のはじまり”
こらぼたうんが考える「共創」は、ワークショップの場だけではありません。 買い物同行のような、“日常に寄り添う時間”そのものが共創の入口です。
共創の素材は、日常の中にある
- 何気ない選択
- さりげない目線
- 思いがけないひとこと
これらを「情報」として処理するのではなく、 「共に育てる価値」として受け止めたとき、 企業と生活者の関係性は変わっていきます。
まとめ:「ともに歩く」から始まる、ほんとうのマーケティング
買い物同行は、言ってしまえば一緒に店内を歩くだけのことです。 けれど、その“歩く時間”には、企画会議100回分の気づきが詰まっていることがあります。
「売れる商品」を目指すより、「使いたいと思ってもらえる商品」を目指す。 そのためには、“誰と、どう歩くか”が何よりも大切です。
こらぼたうんは、企業と生活者の間をつなぐ「共創の案内人」として、現場の声に寄り添いながら価値を一緒に育てていきます。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)