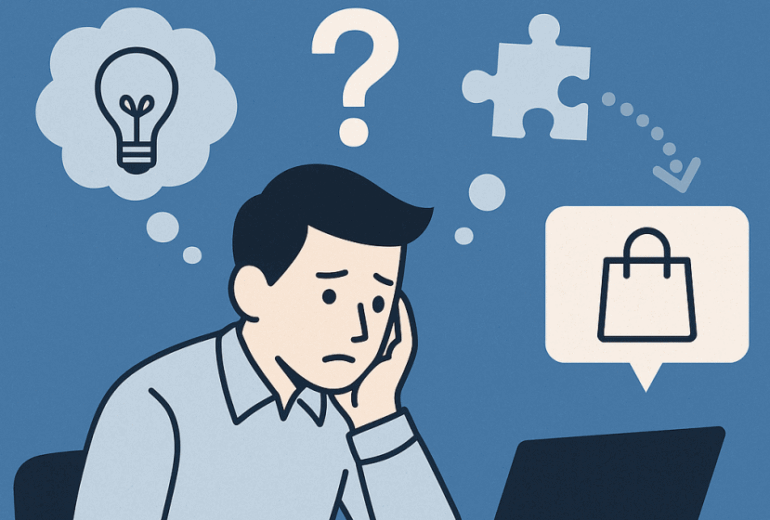この記事は「リサーチから共創へ」をテーマにした実務編ガイドです。まず全体像から把握したい方は、上記のガイドもあわせてご覧ください。
この記事のポイント:
・グループインタビューは「意見収集」に強い調査手法
・共創セッションは「一緒に発想する場」として新しい価値を生む
・両者を組み合わせることで、商品企画の精度とスピードが向上する
はじめに:調査の次に必要なもの
商品企画やマーケティングでよく使われる調査方法のひとつに、グループインタビュー(FGI)があります。数人の生活者に集まってもらい、モデレーターが質問を投げかけて意見を引き出す。多くの担当者が経験している、定番の調査です。
しかし、「調査の結果はあるのに、実際の商品改善や新しい発想につながらない」と感じたことはないでしょうか。そこで注目されているのが、共創セッションです。調査で終わらせず、生活者と一緒に考えることで新しい気づきを得られる場です。
グループインタビューの特徴と強み
まずはグループインタビューの特徴を整理してみましょう。
- 効率的に意見を集められる: 少人数からまとまった意見を引き出せる。
- 傾向を把握できる: A案とB案、どちらが好まれるかなど、比較に強い。
- 数字に背景を加えられる: アンケート結果の「なぜ?」を補足できる。
つまり、「意見収集」や「傾向の把握」には有効ですが、生活者と一緒にアイデアを生み出す場にはなりにくい、という特徴があります。
共創セッションの特徴と強み
次に共創セッションです。こちらは調査とは発想が少し違います。
- 企業と生活者が対等に話す: 担当者と参加者が同じ立場で議論する。
- 体験や文脈を重視: 実際に商品を手に取ったり、使う場面を想像しながら意見を出す。
- アイデア創発につながる: 他者の発言に触発され、新しい発想が広がる。
調査が「答えを集める場」だとしたら、共創は「一緒に考え、新しい答えを生み出す場」です。
グループインタビューと共創セッションの対比

意見収集や傾向把握に向く。

改善点の具体化や新企画づくりに向く。
調査と共創、どう使い分ける?
調査(グループインタビュー)が向いているケース
- 既存商品の評価を確認したいとき
- 複数案のうち、どちらが支持されるかを知りたいとき
- ターゲット層の価値観を整理したいとき
共創セッションが向いているケース
- 新しいアイデアや改善点を生活者と一緒に探りたいとき
- 調査結果を「実際の行動や感情」と結びつけたいとき
- 企画段階から生活者を巻き込みたいとき
組み合わせるともっと強い
調査と共創は、どちらか一方を選ぶものではありません。両方を組み合わせることで強みを発揮します。
- 調査で方向性を確認: A案とB案のうち、どちらが好まれるかを把握する。
- 共創で具体化: 選ばれた案を、生活者と一緒にどう改善できるかを探る。
この流れを作ることで、「調査で終わる」から「調査+共創で形にする」へと発展できます。
まとめ:次の一歩は「共創をプラス」
グループインタビューは、意見を集め傾向を知るのに強い手法。共創セッションは、生活者と共に発想を広げるための場。それぞれ役割は違いますが、組み合わせれば商品企画の精度とスピードが格段に上がります。
すでに調査を経験している担当者だからこそ、次は「共創をプラスする」という選択肢を検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1. グループインタビューと共創セッションはどう使い分ければ良い?
A. 傾向把握や評価比較=グループインタビュー、改善具体化や新規発想=共創が基本。企画初期はGIで方向付け、試作段階は共創で磨き込みが効きます。
Q2. 共創セッションの最小構成は?
A. 5〜6名×90分で十分です。触れる→なぜを深掘り→その場で軽微な改良案の1サイクルを回すだけでも学びが出ます。
Q3. ファシリテーターは社内でも大丈夫?
A. もちろん可能です。私たちはむしろ、企業側の参加者全員がファシリテーターとして進行できる力を持つことを推奨しています。
外部任せにせず、社員一人ひとりが生活者の声を受け止め、中立的に場を動かせるようになることで、共創が「一過性のイベント」ではなく社内文化として根づきます。
Q4. 成果物は何を用意すればよい?
A. 気づきログ(発言要旨+背景)/改善バックログ(優先度付き)/次回検証プランの3点をセットに。次のスプリントへ直結させます。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)