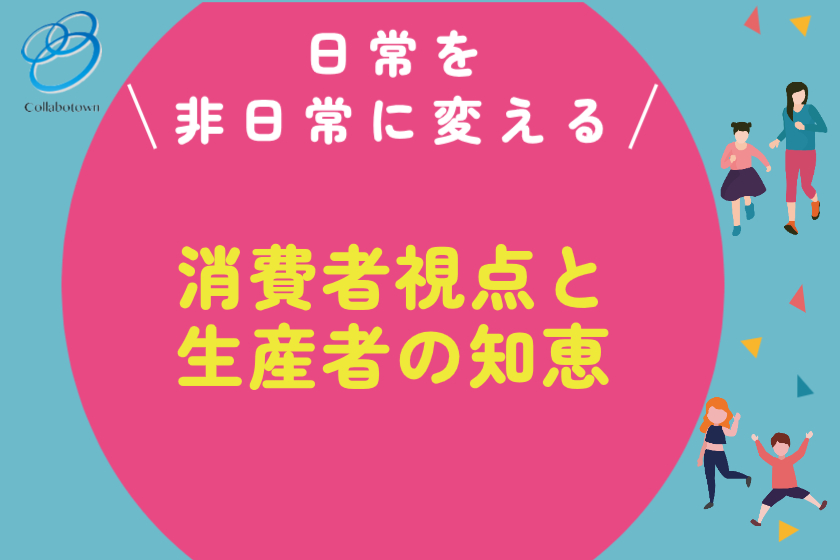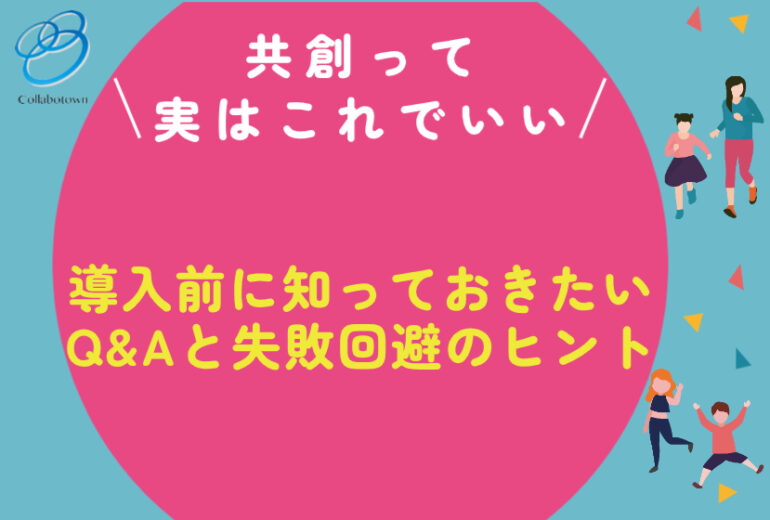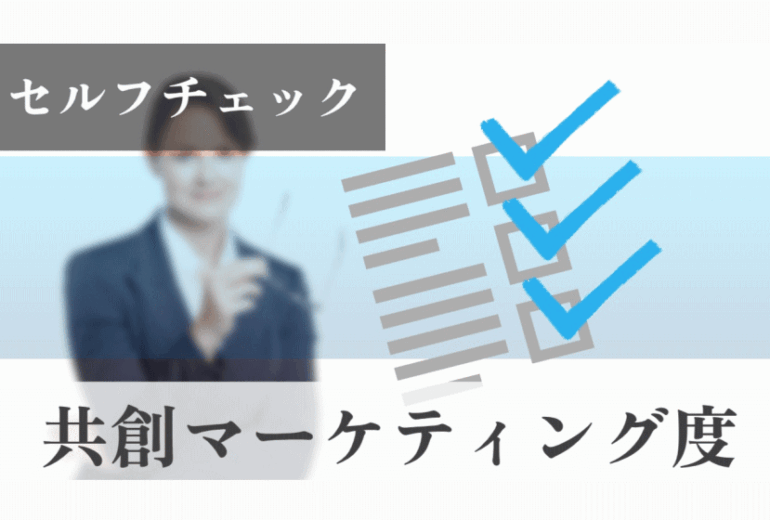実務の位置づけは 価値共創マーケの基本と導入ガイド をご参照ください。
■ はじめに
バレンタインといえばチョコレート。そう考える人は多いでしょう。実際、多くの店舗やメーカーがバレンタインに向けてチョコレート商品の販売促進を行い、街中は甘い香りと華やかなパッケージであふれます。
そんな中、「イチゴ」をバレンタイン企画として販売した生産者があります。しかも、ただのイチゴではなく、品種『恋みのり』を2粒で500円。一般的なイチゴパックと比べると、これは通常の数倍近い単価です。
「そんな高いイチゴ、本当に売れるの?」と思うかもしれません。しかし、この企画は見事に成功し、多くの消費者が笑顔で購入していきました。
しかもこのアイデアは、大きな予算や派手な宣伝を使ったわけではありません。いち生産者が、手持ちの資源と知恵を最大限に活かし、“お金を掛けずに工夫”して生み出した企画だったのです。だからこそ、同じように小規模で頑張る生産者にとっても、大きなヒントになる事例といえます。
今回はこの事例を、日常と非日常の演出、そして消費者視点で考えることの大切さという2つの切り口から掘り下げます。
■ 恋みのりとは?

新品種「恋みのり」を2粒だけ特別包装。愛が実るバレンタイン限定の贈り物。
2粒を特別パッケージに詰め、イベント性とストーリー性を掛け合わせた限定商品です。
通常の10倍近い単価ながら、特別感と贈り物としての意味が支持され、多くの来店客が購入した事例。
このアイデアは、生産者が大きな予算をかけず、手持ちの資材と知恵を活かして実現しました。
「恋みのり」は比較的新しい品種で、果実が大ぶりで美しく、甘みと香りが豊か。酸味が少なく、食べた瞬間に広がる上品な甘さはまさに“スイーツ”と呼べるクオリティです。
名前の響きも特徴的で、
恋=愛やバレンタインとの親和性
みのり=実る、成果、幸せを意味する言葉
この組み合わせが、「愛が実る」という物語性を自然に含んでいます。つまり、この品種名自体がバレンタインという非日常イベントとの相性抜群だったわけです。
■ 日常を“非日常”に変える仕掛け
通常、道の駅で販売されるイチゴは、地元産の新鮮な農産物としてパック入りで並びます。価格は500円前後。しかし今回の販売はあえてパック販売をやめ、2粒入りの特別パッケージにしました。
高価な化粧箱や大量の装飾は使わず、手頃な資材を工夫して高級感を演出。包装やメッセージカードも、生産者が自ら考え、低コストで作成しました。この“身の丈の演出”こそが、無理なく続けられる成功のポイントです。
● 非日常化のポイント
- 数量を減らし、価値を凝縮する:2粒だからこそ「特別感」が増す。数が少ないことが「希少」であり「大切な人だけに贈る」感情を生む。
- パッケージデザインの演出:簡易な資材でも色や形を工夫すれば高級感は出せる。赤・ピンク・ゴールドのバレンタインカラーでイベント性を強調。
- ストーリー性の付与:「恋みのり」という名前と「愛が実りますように」というメッセージをセットで伝える。購入者が「渡す理由」を持てるようになる。
■ 消費者視点の重要性
なぜ2粒500円でも売れたのか?答えは、「売り手の視点」ではなく「買い手の視点」で企画を立てたからです。
売り手が考えるのは、原価・通常価格とのバランス・売上数量の見込みですが、買い手が考えるのは、相手が喜ぶか・特別感があるか・渡す理由があるかです。
さらに今回は、大掛かりな販促や広告に頼らず、生産者自身が顧客心理を想像しながら工夫を重ねた点が大きな違いでした。消費者は「量」よりも「意味」を買っているのです。
■ 「価格競争」から「価値競争」へ
農産物を含む多くの商品は、価格競争に巻き込まれがちです。しかし今回の事例はその競争軸をずらし、「安くて量が多い」ではなく「高いけど意味がある」という価値競争に持ち込みました。
価値競争では、ストーリー・デザイン・イベントとの親和性・ブランド体験が価格を支えます。しかもその価値づくりは必ずしも高コストではなく、“知恵”で実現できることを、この企画は証明しています。

恋みのりを育てるイチゴハウス。2棟へ増設しました。
■ 他業種への応用
この手法はイチゴだけでなく、さまざまな商品やサービスに応用できます。
● 日常品を非日常化するアイデア例
- パン屋さん:ハート型やメッセージ入りの食パンを記念日用に販売。
- コーヒーショップ:特別焙煎・数量限定のブレンドをイベント限定パッケージで販売。
- 雑貨店:普段のマグカップを季節限定デザインにし、ギフトセットとして販売。
■ まとめ:消費者視点と知恵が生む“特別な体験”
『恋みのり』2粒500円という事例は、日常と非日常の境界線を意図的にデザインし、小さな生産者でも実現できる価値づくりの好例です。
- 消費者が求めているのは「量」ではなく「意味」
- イベント性とストーリーを掛け合わせることで、商品は別物になる
- 価格競争ではなく価値競争に持ち込むことで、付加価値は何倍にもなる
- 大きな投資がなくても、知恵と工夫で市場を動かせる
企業側が忘れがちなことは、「商品をどう作るか」より「お客様がどう使うか」に視点を置くこと。
この視点と、生産者の現場発の知恵があれば、日常品を一瞬で非日常の主役に変えることができ、その体験は購入者と受け取った人の両方に長く記憶される価値として残ります。
📚 あわせて読みたい
“味”や“価格”の勝負ではなく、ネーミング/体験/語りたくなるストーリーで選ばれる。
ユニーク商品が「話題止まり」にならずに売れる構造を、共創の視点で整理します。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)