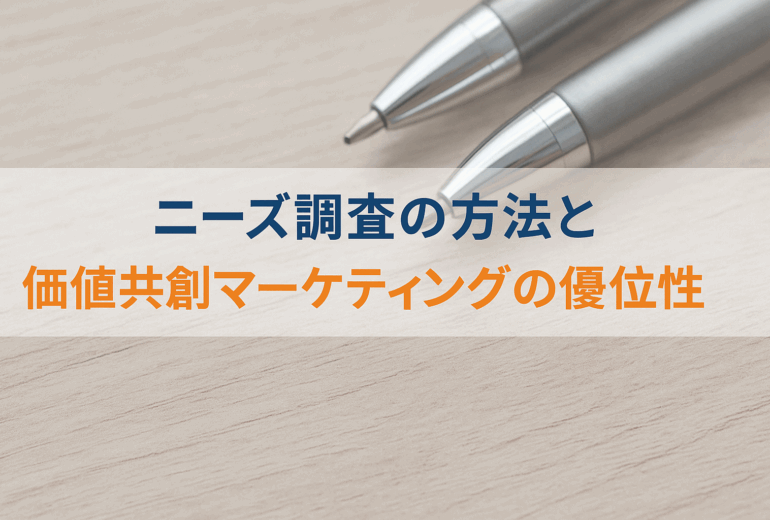この記事は「リサーチから共創へ」の実践編です。まず全体像から把握したい方はこちらをご覧ください。
※本記事は「モニター調査の否定」ではなく、“見えない部分が見える設計”の話です。
同じ生活者の声でも、場のつくり方で「出てくるもの」が変わります。
どれだけ丁寧にモニター調査を重ねても、なぜかヒットに結びつかない──。
そんな袋小路のような状況を変えたのは、意外にも“共創”という対話の場でした。
とくに今回の鍵になったのは、議題の外側で起きた「雑談」です。雑談は“余談”ではなく、想定外のニーズがこぼれる場所でした。
🧩 3行で結論
- モニター調査は「評価」が集まるが、暮らしの摩擦は見えにくい
- 共創セッションでは、雑談から想定外の文脈が立ち上がる
- その文脈をもとに設計を変えると、売れ方が一気に変わる
1. モニター調査の“限界”に直面した瞬間
健康志向の波に乗って新商品を開発していた食品メーカーB社。
発売直前、複数回にわたるモニター調査を実施し、アンケートには「おおむね満足」「味も悪くない」「価格も妥当」という高評価が並びました。
しかし、いざテスト販売を行うと結果は伸び悩み。
数値的には悪くない評価を得ているのに、購入率が上がらない。この「見えない壁」に、担当チームは頭を抱えました。
でも購買を左右するのは、しばしば暮らしの中の“摩擦”や家族関係・空気感といった、質問票に入りにくい要素です。
2. 共創セッションで「雑談が生まれる場」をつくった
そこで試みたのが、生活者との共創セッションです。
従来型の「質問と回答」に終始する形式ではなく、参加者同士が自由に話し、互いの意見を重ね合える対話型の場を設計しました。
🧱 ただ聞くのではなく
- 「正しく答える」圧を外す(非評価)
- 生活シーンの共有から入る(文脈共有)
- 参加者同士が話せる構造にする(相互作用)
🫧 雑談が起きる“余白”
- 開始5分はテーマなしの近況
- 休憩を短くしすぎない(10分)
- 終盤に「今日のひと言」タイム

3. 思わぬニーズは「雑談」からこぼれ落ちた
セッションも中盤に差しかかった頃、何気ない会話の中で参加者の一人がぽつりと漏らしました。
ぽつり:「これ、子どもが食べても大丈夫なんですか? 体には良さそうだけど、子どもってこういう味や匂いを嫌がるじゃないですか」
「うちの娘なんて、袋を開けた瞬間『くさい!』って言って食べなかったんですよ」
その瞬間、場の空気が変わりました。
「うちもそう」「見た目が“健康食品すぎる”と子どもが手を伸ばさない」──そんな声が次々と飛び交い、テーマは「匂い」「子どもの食べやすさ」へと広がっていきました。
これらは、従来のモニター調査の質問項目には一切なかった視点です。
数字では表れない、暮らしの中の“リアルな不便”が、雑談の中から顔を出した瞬間でした。
参加者が安心して話せる空気の中で、雑談として“出ちゃった”からこそ価値がありました。
4. なぜ雑談が、意外なニーズを連れてくるのか
雑談は“余談”ではなく、インサイトにとっては発見装置です。理由は主に3つあります。
🫧 1) 評価から外れる
「正しく答えなきゃ」が薄くなると、言葉の検閲が止まります。
その結果、建前より先に暮らしの実感が出てきます。
🔗 2) 連想がつながる
雑談は話題が飛ぶからこそ、思考がほどけて、想定外の結びつきが生まれます。
🌡️ 3) 温度がにじむ
「くさい!」は“意見”ではなく“感情”です。
感情が出ると、購入を止めている理由(摩擦)が一気に見えるようになります。
🧭 まとめ
つまり雑談とは、生活の文脈と感情の温度が同時に出てくる場所。
だからこそ、想定外のニーズが“こぼれ落ちる”のです。
※「雑談」が本音・学び・アイデアを生む理由は、こちらで整理しています:
👉 雑談はムダじゃない。本音・学び・アイデアが生まれる「非公式な対話」の力
5. 図解:モニター調査 vs 共創セッションで得られる情報の違い
この事例は、同じ「生活者の声」を集める場でも、アプローチが違えば得られる情報の質が大きく異なることを示しています。
| モニター調査 | 共創セッション |
|---|---|
| 定型質問に沿うため、用意された範囲に収まりやすい。 | 自由な会話・雑談から、想定外の視点・感情が出やすい。 |
| 回答は短く、理由や背景が見えにくい。 | エピソードと結びつく文脈情報が得られる。 |
| 数値化しやすいが、本音のニュアンスは薄い。 | 表情・声のトーンなど、非言語のヒントも拾える。 |
| 調査後に分析者が解釈し、一方通行になりがち。 | その場で相互理解が進み、次のアイデアが即時に生まれる。 |
| 主に「評価」を得る場。 | 主に「共感」を育てる場。 |
6. 対話が生んだ変化、そして成果
共創の場を通じて明らかになったのは、商品の品質そのものには問題がなくても、「誰の、どんな日常に寄り添うのか」という文脈が欠けていたという事実です。
🧩 見えてきた“購買の条件”
- 親子で安心して食べられることが購買の後押しになる
- 部屋に置いてあっても生活感を損なわないパッケージ
- 匂いや見た目が“健康食品すぎない”工夫が必要
🎯 価値の重心が変わった
- 「健康食品としての高品質」→「暮らしに自然になじむ」
- 「大人向け」→「親子でいける」
- 「評価」→「共感」
この発見を受け、B社はパッケージ表現・販促コピー・ターゲット設定を大幅に見直しました。
「働くママと子どもが一緒に楽しむ姿」を思い描き、匂いや見た目の工夫を加えたほか、「子どもと一緒に」というメッセージを前面に押し出しました。
その結果、再販売時にはターゲット層の購入率が2.3倍に向上。
SNS上では「こういうのを探していた!」「親子で食べられるのがうれしい」という投稿が相次ぎ、商品の存在意義が明確になったのです。
7. 明日から使える「雑談インサイト」設計
✅ 雑談を“偶然”で終わらせない 4つのコツ
- 雑談が起きる余白を入れる(開始5分/休憩10分/最後にひと言)
- 雑談で出た言葉は直さず拾う(「今の、もう一回いいですか?」)
- 意見より場面に戻す(「それ、どんな時に起きる?」)
- “困りごと”と“願い”を分ける(「困り?それとも理想?」)
すぐに埋めず、少し待って、同じ言葉で返すと深くなります。
▶ 共創は、数値では見えない「暮らしの奥深く」に触れるきっかけです。
そして雑談は、その奥に入るいちばん自然な入口。
本音が交わされる場には、商品を飛躍させるヒントが必ず眠っています。
モニター調査の次は、「暮らしのリアル」がこぼれる共創へ
数字の評価は取れているのに、なぜか売れない──。
そんな時こそ、生活者との対話で“雑談から出る本音”を拾い、
企画・パッケージ・伝え方まで一緒に整えるのが近道です。
こらぼたうんは、企業と生活者が同じ目線で語り合う共創セッションを軸に、 「噛み合う型」へ落とし込み、現場で回る形に設計します。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ