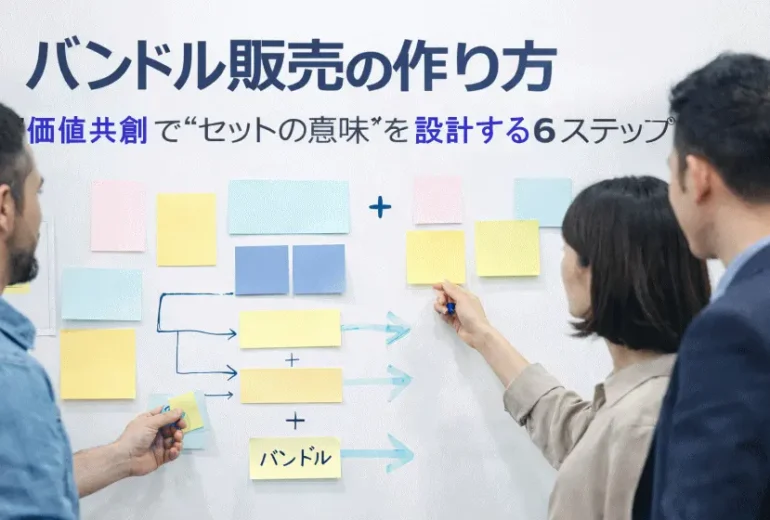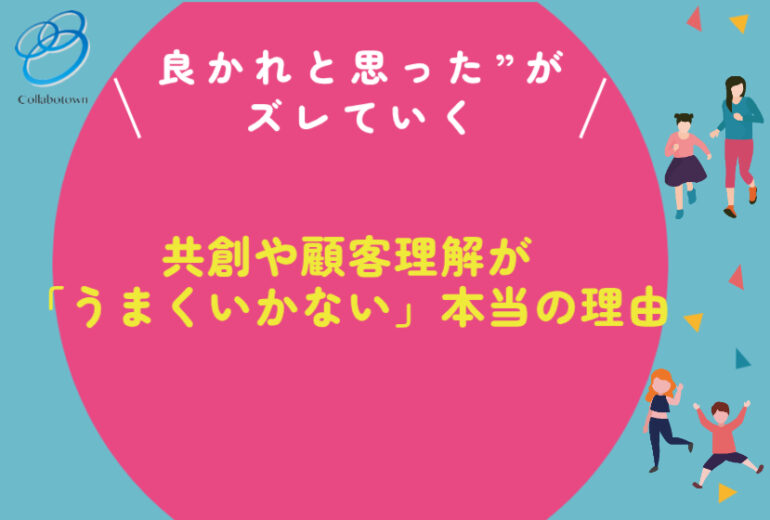まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。
いま「売れる商品」を作るだけでは足りません。
人の心を動かし、思わず誰かに話したくなる商品は、機能や価格の外側にある
“意味・物語・体験”で選ばれています。
本記事では、語られる商品が生まれる心理と設計のポイントを整理し、明日から使える実践手順に落とし込みます。
✅ この記事の結論(要点3つ)
- 人は商品を語ることで「自分」と「関係性」を表現している(自己表現・他者貢献)。
- 語られる商品は「一言で伝えられる魅力」と「体験のエピソード」が設計されている。
- 共創で“参加の余白”をつくると、語る人(応援者)が増えて口コミが連鎖しやすい。
人が「話したくなる」3つの心理的トリガー
まずは「なぜ人はある商品について話したくなるのか?」という本質から整理します。 語りは偶然ではなく、いくつかの心理がスイッチになります。
① 自己表現
商品を語る=自分を語る。選択やセンス、価値観を表現したい欲求が働きます。
- 「それ知ってる私、良いでしょ」ではなく
- 「私はこういう暮らしが好き」を伝えている
- だから“言語化しやすい魅力”が強い
② 他者貢献
人の役に立ちたいという気持ちが、紹介の原動力になります。
- 「これ良かったよ」は相手へのギフト
- 悩みが解決された体験ほど語られやすい
- 関係性の中で“価値提供”している
③ 感情の揺れ
驚き・感動・笑い・共感など、感情が動いた瞬間は記憶に残り語られます。
- スペック表ではなく「感じたこと」
- 言いにくい体験ほど“共有”したくなる
- ストーリーが感情を運ぶ
話題になる商品と、話題にならない商品の違い
「語られる商品」は、単に目立つわけではありません。
“語る理由”が商品側に用意されているかどうかが分かれ目になります。
📣 話題になる
特徴
- 人に話すネタ(物語・驚き・共感ポイント)がある
- 使うシーンが想像しやすい
- 自分ゴト化できる(価値観とつながる)
- 薦める理由が自分の中で言葉になる
🫥 話題にならない
特徴
- 機能・性能の説明だけで終わる
- 強みが「安い」「無難」に偏る
- 代替がきく(どれでもいい)
- 体験に“感情の動き”が少ない
話したくなる商品には、“個人的な意味”と、“共有したくなる価値”が同居しています。
ここからは、その状態を意図的に作るための「設計視点」を具体化します。
商品を“語りたくなる存在”にする5つの設計視点
① 誰かに話したくなる「物語」を宿らせる
人は「理由のあるモノ」に惹かれます。原材料や作り手のこだわり、誕生までの試行錯誤など、 “なぜそれを作ったのか”が語れると、商品は一気に話題の種になります。
チェック
- ✅ 誰のどんな困りごとから生まれたのか?
- ✅ 選んだ素材・形・工程に理由があるか?
- ✅ 失敗や遠回りが“物語”になっているか?
② 「使われ方」を語れるようにする(暮らしの文脈設計)
人が語るのは商品だけではなく、「どんなときに、どう使ったか」という体験のエピソードです。
だからこそ、企画の段階から「使用シーン」を具体的に描ける設計が必要になります。
コツ: 「機能 → ベネフィット」で止めず、“生活の変化(前後のストーリー)”まで言語化すると、紹介されやすくなります。
③ “一言で言える魅力”を明確にする(紹介コピーの芯)
語られる商品には必ず、一言で説明できる“芯”があります。
「これ、◯◯が最高なんだよね」と言えるポイントがないと、話題は続きません。
チェック
- ✅ 10秒で説明できる魅力があるか?
- ✅ 誰にとってどんな場面で助かるのかが具体か?
- ✅ “良さ”が比較なしでも伝わる表現になっているか?
④ 顧客を「参加者」にする(語る人を増やす最短ルート)
「自分が関わった」商品は、自然と語りたくなります。これは心理的所有感が働くためです。
共創の設計を入れると、単なる購入者が“応援者”へ変わり、紹介の連鎖が起きやすくなります。
例:参加の余白を作る
- 開発中の試作品に対する対話レビュー(感想+理由を深掘り)
- パッケージ案の投票(理由も集めると訴求が磨ける)
- ネーミングやコピーの候補案づくりに参加してもらう
- 購入後の使い方共有(ユーザーの工夫が次の魅力になる)
⑤ 「語る場」を設計する(きっかけ×導線)
語りは「気持ち」だけでは発生しません。語るきっかけと、語れる場所の設計が必要です。
きっかけ
- 購入後のメッセージ(QRでレビューへ)
- 店頭POPで“語りのネタ”を提示
- SNS投稿したくなる小さな仕掛け
場所
- レビュー欄/SNSハッシュタグ
- イベント・ワークショップ
- コミュニティ(LINE/メルマガ)
実践ステップ:自社商品を“語られる存在”にする3ステップ
ここからは、社内で回しやすい形に落とし込みます。まずは小さく始めてOKです。
1語れる要素があるか棚卸しする
「物語」「使用シーン」「一言魅力」が言語化できるかをチェック。弱い箇所が改善ポイントです。
- なぜその商品なのか、理由があるか?
- 生活のどの場面で助かるかが具体か?
- 10秒で伝えられる魅力があるか?
2語れる人(応援者)を増やす
スタッフ・顧客が“語りのネタ”を共有できる状態に。共創はここで効きます。
- 社内で商品ストーリーを共有しているか?
- 試作品への対話レビューなど、参加の余白があるか?
- 顧客の声を改善に反映する流れがあるか?
3語る場を用意し、導線をつくる
口コミは“発生待ち”ではなく“設計”。投稿・レビュー・店頭の導線を整えます。
- SNSやレビューに誘導する仕掛けがあるか?
- イベント・ワークショップなど“語り場”があるか?
- 顧客の声を社内で活用し続けているか?
+小さく検証して磨く
いきなり完璧を目指さず、少人数の対話→改善→再テストで“語られ方”を磨いていくのが近道です。
おわりに:「語られる」は、広告より強い資産になる
売上や反応率だけでは測れない価値が、「語られる商品」には宿っています。
それは、信頼・共感・応援といった人と人の関係性を生む力です。
広告で一方的に届けるのではなく、顧客が自ら“届けたくなる”状態をつくる。
その鍵は、商品に「意味」と「物語」と「参加の余白」を宿らせることです。
商品を「売る」のではなく、語りたくなる体験を一緒に育てる時代へ。
まずは今日、あなたの商品の“語れる一言”を作るところから始めてみてください。
FAQ:よくある質問
Q. 「話したくなる商品」は小さな会社でも作れますか?
A. できます。むしろ小さな会社ほど、作り手の物語や現場の工夫が強みになります。少人数の対話(共創)で“語りのネタ”を磨くのが効果的です。
Q. まず最初にやるべきことは何ですか?
A. 「10秒で説明できる一言魅力」を作ることです。次に、その一言を支える“使用シーン(文脈)”と“物語”を整えると、紹介されやすくなります。
Q. 共創が難しい場合、代替案はありますか?
A. 小さく始めればOKです。購入者に「どんな場面で役立ったか」を聞く、店頭で一言コメントを集めるなど、ミニ対話からでも“語られ方”は磨けます。
🗂️ コラム・運営視点 一覧へ
まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)