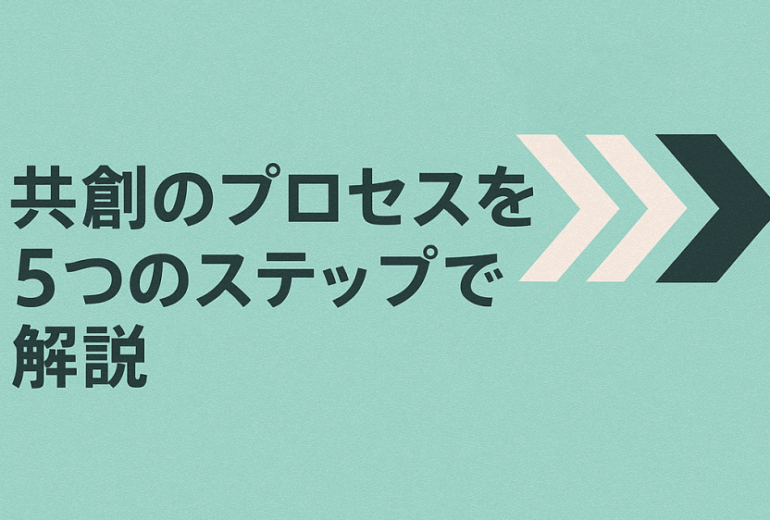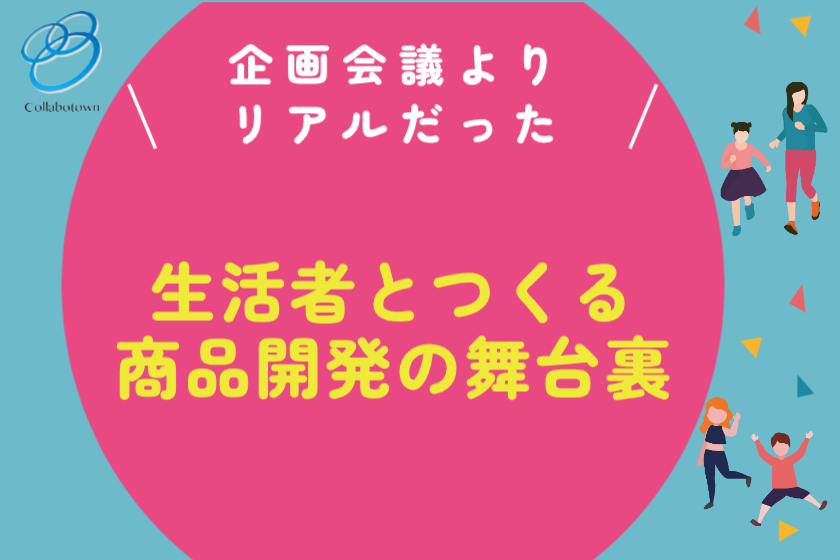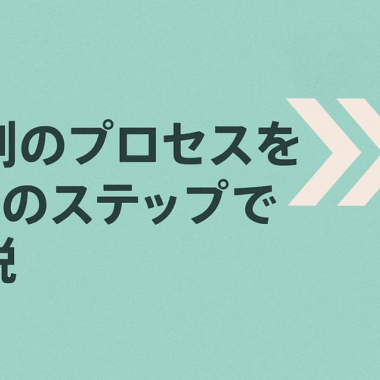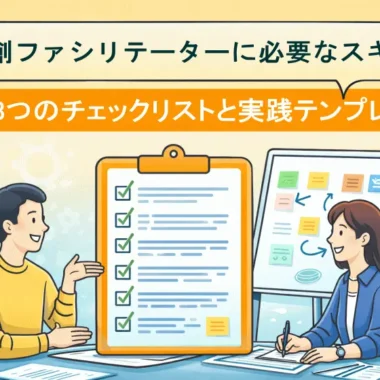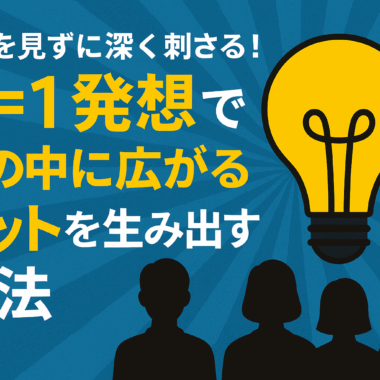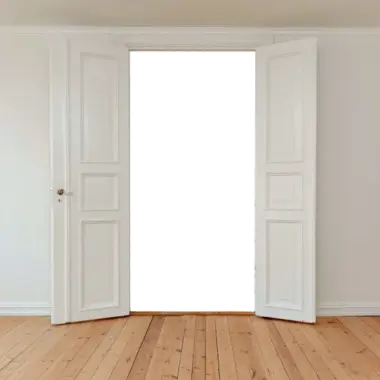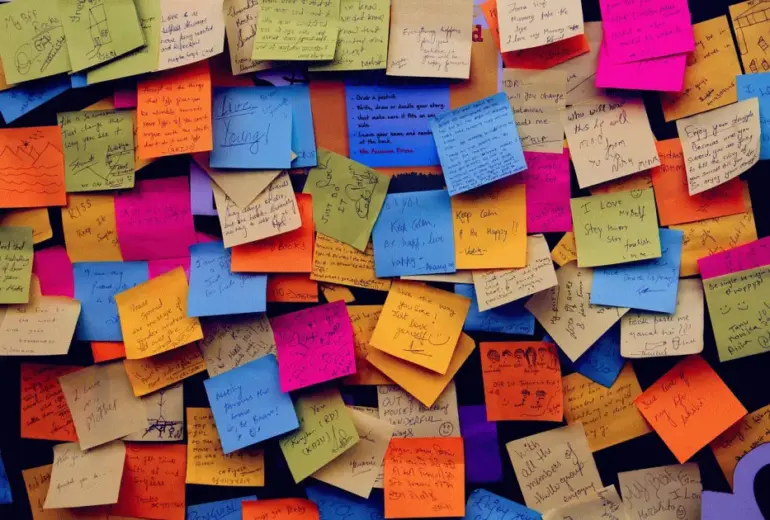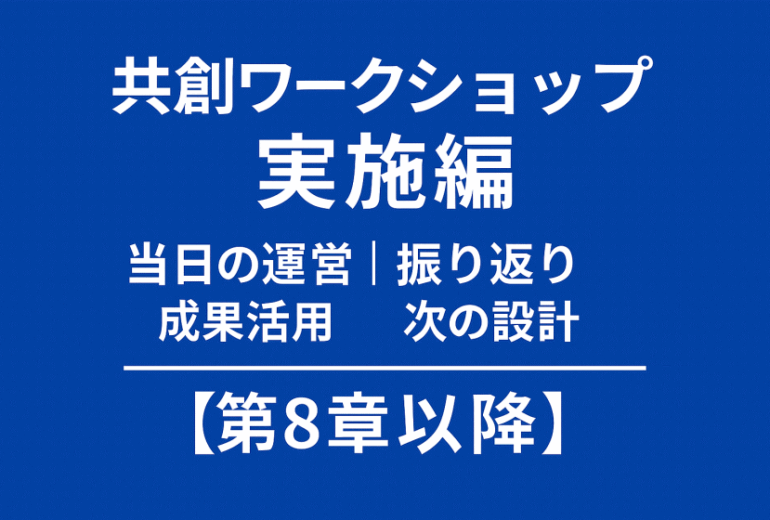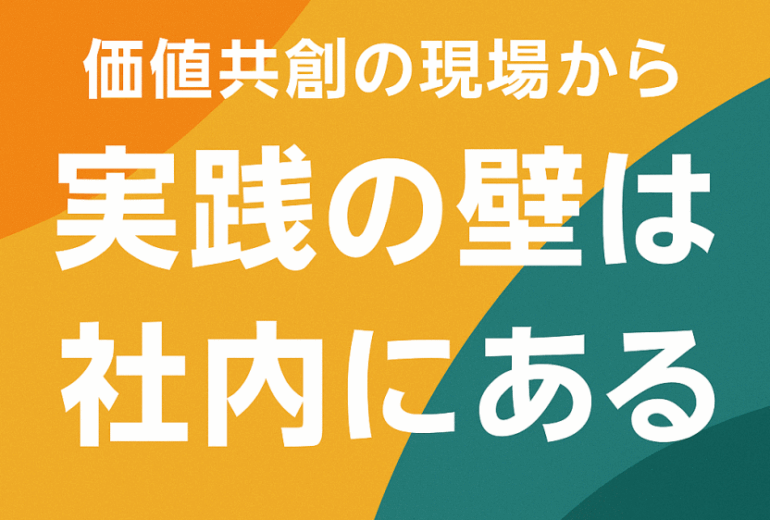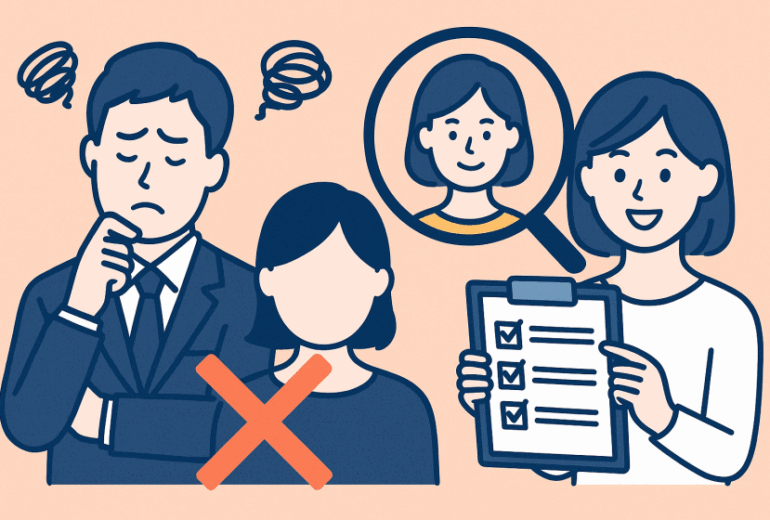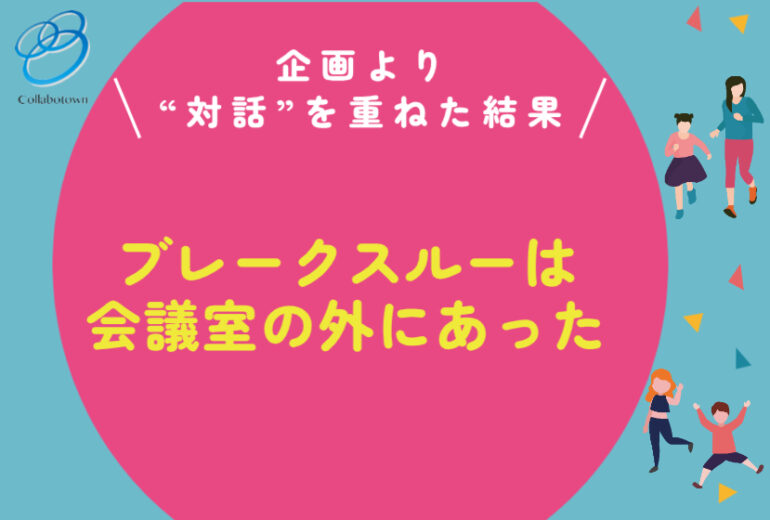この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。
何度も重ねた企画会議。資料も仮説も揃っているのに、最後の“ひと押し”が見つからない。
そんな状況を一変させたのは、会議室ではなく、生活者と同じテーブルで過ごす対話の時間でした。
本記事では、とある企業が体験した共創セッションでの発見と変化をお伝えします。
企画担当者にとって「なぜ社内だけでは突破口が見えないのか」「生活者と交わると何が変わるのか」を考えるヒントになるはずです。
■ 開発チームの壁──「これ以上、どう差別化する?」
クライアントA社は数ヶ月にわたり新商品の立ち上げを進めていました。
コンセプトは固まりつつあり、社内プレゼンでも好感触。しかし同時に、会議の終盤になると決まって出てくる言葉がありました。
「悪くないけど、“決定打”がないよね」
「ターゲットに響く言葉が、どうしても浮かばない…」
この瞬間、企画担当者の多くが直面する“壁”が浮かび上がります。
つまり、頭では理解できても、心を動かす視点が欠けているということです。
そこで導入されたのが、生活者との共創セッションでした。
ターゲット層に近い20名を複数のグループに分け、商品の方向性を「一緒に考える」場を設けたのです。
会議室での議論ではなく、生活者の目線で商品を語り合うこのプロセスは、チームにとって新鮮な体験となりました。

■ 会議では出ない、“暮らしの温度”を帯びた声
セッションが始まると、テーブルを囲む空気がゆるみ、笑顔やうなずきが自然と広がっていきます。
その中で飛び出したのは、調査票や社内会議では絶対に出てこない、生活の温度を帯びた言葉たちでした。
- 「仕事帰りの疲れたとき、パッと気分が上がる香りが欲しい」
- 「家族で共有するなら、可愛すぎないデザインがいい」
- 「SNSに載せるなら、背景映えするパッケージが欲しい」
これらの声は、単なるニーズではなく、生活の文脈と結びついた“リアルな使用シーン”を描いています。
チームの誰もが「会議では絶対に出なかったよね」と頷き合い、企画の視野が一気に広がった瞬間でした。
企画担当者にとって重要なのは、これらの声を「単なる意見」ではなく「新しい発想の触媒」として捉えることです。
■ 「企画会議よりリアルだった」──企業担当者の本音
「社内ではペルソナの仮説で議論していたけど、
生活者本人の言葉にはリアルすぎて反論できない(笑)。
正直、企画会議より価値ある時間でした」
これは若手の開発担当者の言葉です。
企画会議で仮説を検証することも大切ですが、仮説はあくまで「想像の産物」。
生活者が発する“リアルな一言”には、その想像を覆す力があります。
セッション後、担当者は「この商品を育てる責任を改めて感じた」と語り、単なる商品開発を超えた使命感を持つに至りました。
この変化こそが、共創セッションの真価といえます。
■ 共創は「意見集め」ではなく「意味の発見」
共創セッションは、単に生活者の意見を並べる場ではありません。
「どんな暮らしに役立つのか」「なぜその言葉が刺さるのか」を一緒に掘り下げることで、
製品の物語と魂を形づくる場へと変わります。
企画担当者にとって大切なのは、“正解”を求めるのではなく、“意味”を発見する姿勢です。
生活者との対話は、思考の枠を広げ、社内議論では生まれにくいアイデアを呼び込む力を持っています。
会議で行き詰まったときこそ、机を離れて生活者と向き合ってみてください。
そこには、あなたの商品を変える“種”が眠っています。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)