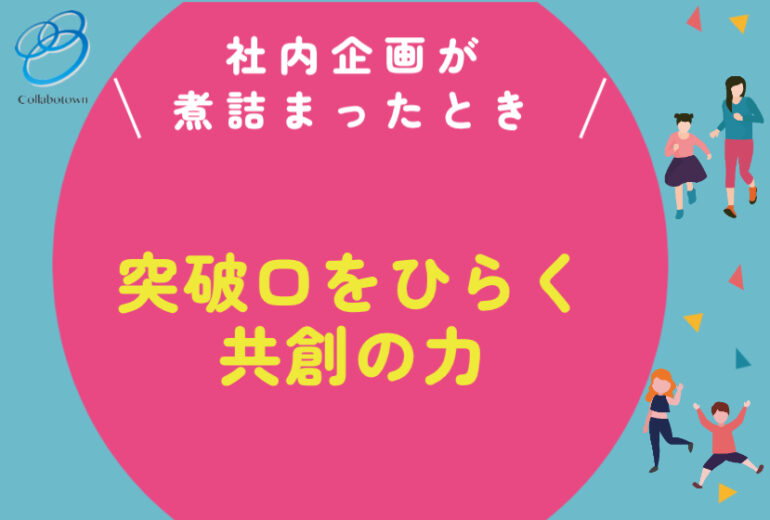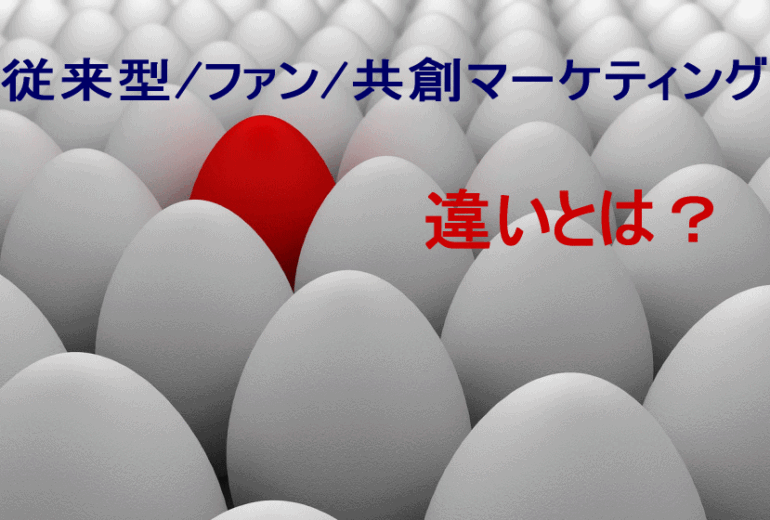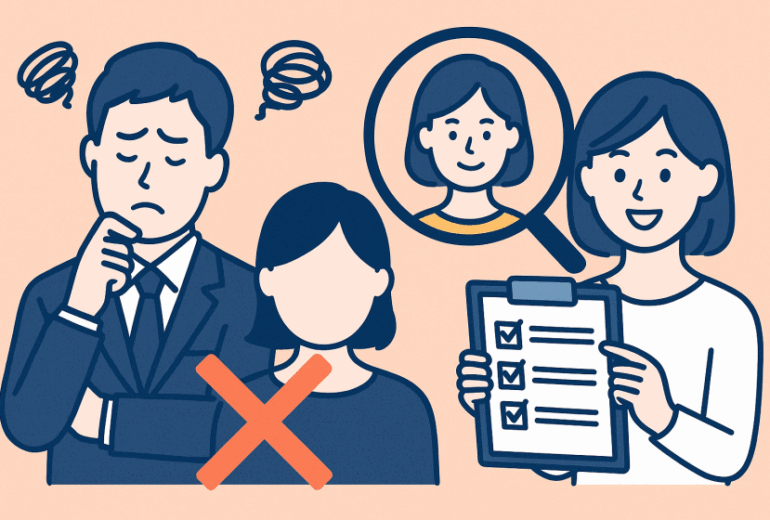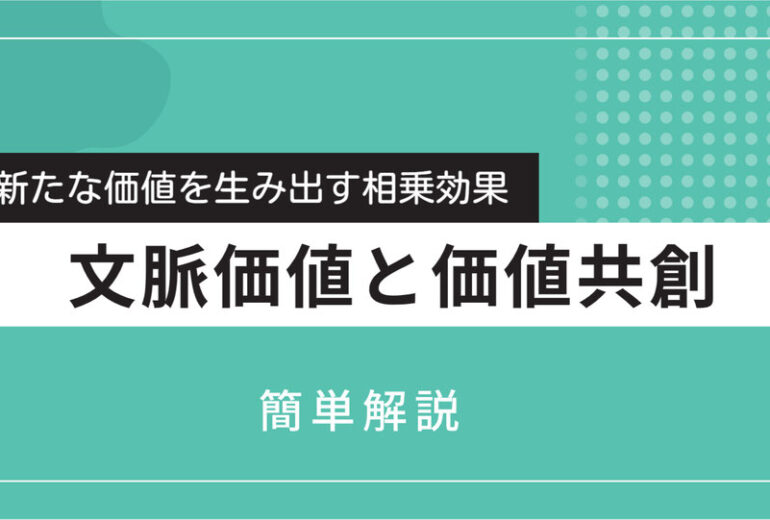実務の位置づけは 価値共創マーケの基本と導入ガイド をご参照ください。
「お客様の本音を知りたい」「インサイトさえ掴めば、商品は必ず売れる」——。
でも実際は、アンケートやインタビューを重ねるほど、“それっぽい意見”は集まるのに、腑に落ちる答えには辿り着かないことが多い。
その原因は、質問の上手さ以前に、“聞かれる関係”ができているかにあります。
🧩 3行で結論(忙しい方向け)
- 本音は「聞けば出る」より、安心できる関係の中で“出ちゃう”
- 鍵は質問術ではなく、心理的安全性・非評価・文脈共有の設計
- 共創は“本音が出る状態”をつくり、声を価値に変える土台になる
はじめに:「本音」はどこにある?
本音(インサイト)は、頭で整理された“意見”の形で出てくるとは限りません。むしろ多くは、迷い・言い直し・笑い・沈黙・ため息の中に混ざって現れます。
だからこそ重要なのは「上手に聞く」より先に、相手が“構えずに話せる状態”をつくること。信頼が育つと、本音は「答えるもの」ではなく、日常の会話の中でふとこぼれるようになります。
1. なぜ「聞いても答えてもらえない」のか
🧱 よく起きる現象
- 質問された瞬間に“正解を探す”モードになる
- 良く見せたい気持ちが働き、社会的に望ましい回答になる
- 本音は無意識にあるため、言語化が追いつかない
🎯 本質(ここが盲点)
- 問題は質問力より関係性と場の空気
- “答えさせる”ほど、相手は自分を守る
- 本音は「言う」よりにじむもの
本音は“深い場所”にあるほど、直接聞くと消えてしまう性質があります。
● 質問に“構え”が生まれる
「何を答えるべきか」「変に思われないか」。この“構え”が生まれた瞬間、相手は自分の表現を検閲しはじめます。 結果、返ってくるのは「きれいに整った回答」。でもそれは、意思決定を動かす“温度”を欠いていることが多いのです。
● 自分を守る“社会的欲求”が働く
リサーチの場では「良い人に見られたい」「まともに答えたい」という自然な欲求が働きます。 その結果、発言が“理想の自分”に寄る。これが、本音が見えなくなる大きな理由です。
2. 本音は「聞かれるもの」ではなく「出ちゃうもの」
● “無意識の行動”にこそヒントがある
本音は、言葉より先に行動に出ます。たとえば売り場で迷う時間、手が止まる瞬間、棚に戻す動作、 そして「つい出る一言」——ここにインサイトの芽が潜みます。
| サイン | よくある“つぶやき” | インサイトの方向 |
|---|---|---|
| 言い直し 言葉が揺れる | 「好き…というか、落ち着く、かな」 | 機能より感情価値が核 |
| 沈黙 間ができる | 「……でも、続かないんだよね」 | 習慣化の摩擦がある |
| 照れ笑い ごまかす | 「本当はラクしたい(笑)」 | 建前と本音のギャップ |
| 比較 迷う | 「こっちは安心。でも高い…」 | 判断軸=不安回避 |
● 対話の中で「出てしまう」構造をつくる
本音を「言わせる」のではなく、言いたくなる・こぼれてしまう場をつくる。 そのためには、相手の答えを評価せず、結論を急がず、安心のベースを先につくることが重要です。
● なぜ雑談だと、本音が「出ちゃう」のか
実は、雑談は“ただの息抜き”ではありません。インサイトにとっては、むしろ本音がこぼれやすい装置です。 その理由は大きく3つあります。
🫧 1) 評価から外れる
「正しく答えなきゃ」「良く見せなきゃ」という圧が弱くなると、人は検閲をやめます。 雑談は“回答の場”ではないので、建前を整える必要がなく、言葉が自然になります。
🔗 2) 連想がつながる
会議はテーマが固定されますが、雑談は話題が飛びます。 この「飛び」が、意外な結びつきを生み、思いがけない気づきを連れてきます。
🌡️ 3) 温度がにじむ
本音は「意見」より「感情」に近い場所にあります。 雑談では“論理”より“感覚”が先に出るため、言葉の温度が残ります。 その温度が、企画や売り方を動かすヒントになります。
🧭 まとめ
だからこそ、インサイトは「質問→回答」の直線よりも、安心→雑談→つぶやきの曲線で現れやすい。 雑談は“遠回り”ではなく、本音への最短ルートになることが多いのです。
● 雑談を「ただ流さない」ための、ひと言
雑談で出た本音は、放っておくとそのまま消えてしまいます。 でも、次のひと言を挟むだけで、会話が“アイデアの種”に変わります。
A「今の、もう一回いいですか?」
相手の言葉を“拾われた”と感じると、話が自然に深くなります。
B「それって、どんな場面で?」
意見ではなく状況(いつ・どこで・誰と)に戻すと、本音の輪郭が出ます。
C「それ、困りごと?それとも願い?」
“不満”と“理想”を分けると、企画や訴求に翻訳しやすくなります。
D「それが叶うと、何がラクになります?」
機能要望ではなく生活の摩擦が見える質問。インサイトに直結します。
だからこそ、そこで“論理”に整えず、場面と感情のまま拾うのがコツです。
3. “関係性”が本音を育てる(条件とNG)
● 「雑談が起きる余白」を設計する
雑談は偶然に見えて、実は設計できます。 重要なのは「雑談しなさい」と言うことではなく、雑談が自然に生まれる“余白”をつくることです。
⏳ 余白を先に入れる
- 開始5分は「近況」だけでOK
- 休憩は短くしすぎない(10分推奨)
- 終わりに「今日の雑談メモ」を1つ残す
🪑 立ち位置を変える
- 対面なら“横並び”を増やす(同じものを見る)
- オンラインなら雑談は「テーマなし2分」から
- 記録係と話す係を分け、取材感を薄める
🧩 話題は「生活」に寄せる
- 「最近、買ってよかったものは?」
- 「それ、どんな気分の日に使う?」
- 「続かない理由って何だろう?」
🌱 目的は“結論”ではない
雑談パートの目的は、答えを出すことではなく、安心と文脈を育てること。 その土台ができると、後半の対話の密度が一気に上がります。
✅ 本音が出る3条件
- 非評価:良し悪しを判断されない
- 対等:「教えてもらう」ではなく一緒に考える
- 文脈共有:相手の暮らし・状況を理解している
🚫 本音を殺すNG
- 結論を急ぎ、“答え”を回収しようとする
- 反論・説得・正解探し(相手が守りに入る)
- 録音・メモの圧が強く、取材っぽい空気になる
● 評価や分析をしない「聞き方」
うなずく、繰り返す、間を待つ。相手の言葉を“直す”のではなく、“受け取る”。
その聞き方が、相手に「ここなら出していい」と感じさせ、結果として本音が出やすくなります。
※「雑談」が本音・学び・アイデアを生む理由は、こちらで整理しています
雑談はムダじゃない。本音・学び・アイデアが生まれる「非公式な対話」の力
4. 共創型インタビューで得られるインサイト
こらぼたうんが大切にしているのは、単発のヒアリングではなく“共創の関係性”を起点にしたセッションです。 相手を情報提供者ではなく、価値を一緒に育てるパートナーとして迎える。すると言葉の温度が変わります。
→ “無香料が安心”ではなく、香りが感情的安心を支えるという発見へ。
→ “隠したくなる家電”から“見せたくなる家電”へ、開発コンセプトが転換。
5. 現場で使える実践ステップ
ここからは、明日からの現場で使える「本音が出る流れ」の作り方です。
ポイントは、一度で当てにいかないこと。小さく回して、関係と理解を育てます。
1“答え”ではなく“場面”から入る
「いつ・どこで・誰と・どんな気分で?」を先に聞く。評価から遠い入り口が安心をつくります。
2買い物同行・観察で「行動」を見に行く
発言と行動のズレが、最も強いヒント。迷う瞬間・戻す動作・比較の言葉を拾います。
3雑談の“こぼれ”を取りこぼさない
本題の外側に本音が出ます。準備した質問より、相手の言葉に乗って深掘りする。
4「言い直し」「沈黙」「笑い」を合図にする
そこが“揺れている場所”。すぐ埋めず、間を待ち、繰り返して返すと深くなります。
5一度で終わらせず“再会”で育てる
初回は表層が多い。2回目以降で「この前の話、今も同じ?」と確認すると輪郭が出ます。
6社内で“解釈”を揃えて、価値に翻訳する
声をそのまま配ると部門ごとにズレる。「背景・感情・場面」を含めてストーリーで共有します。
6. 失敗しないチェックリスト
✅ 本音が出る関係性チェック
- 質問の前に、相手が安心できる空気ができている
- 相手を「回答者」ではなく一緒に考えるパートナーとして扱えている
- “答え回収”ではなく場面・背景・感情を重視している
- 観察や同行など、行動を見に行っている
- 言い直し・沈黙・笑いなどのサインを拾えている
- 社内で解釈の共通理解を作っている(声のまま配っていない)
まとめ:聴くことを“やめる”と、本音は見えてくる?
本音を「聞き出そう」とすると、人は身を守ります。だからこそ逆説的に、“聞くことを目的にしない”方が、本音は出やすくなる。
ただそこにいて、話し、笑い、驚き、共に考える——その時間の中で、本音は“出ちゃう”ものです。
そして、あふれた本音を価値に変えるのが、共創の仕事です。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)