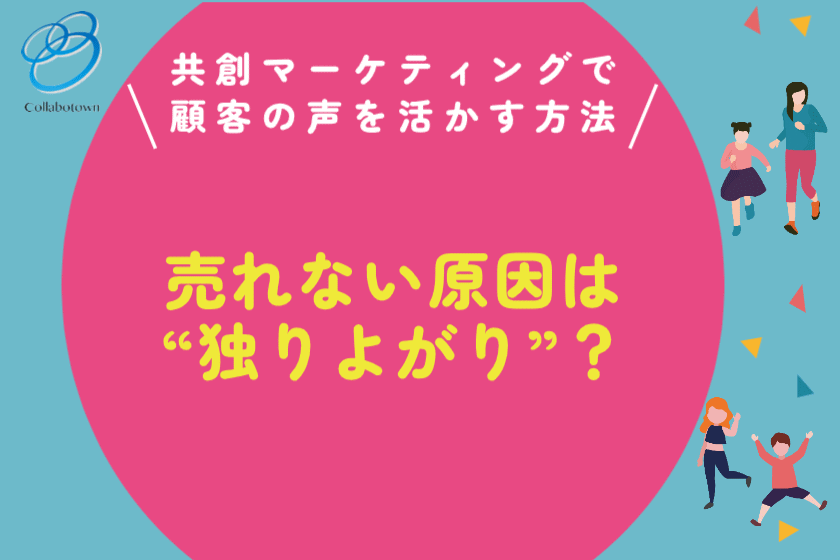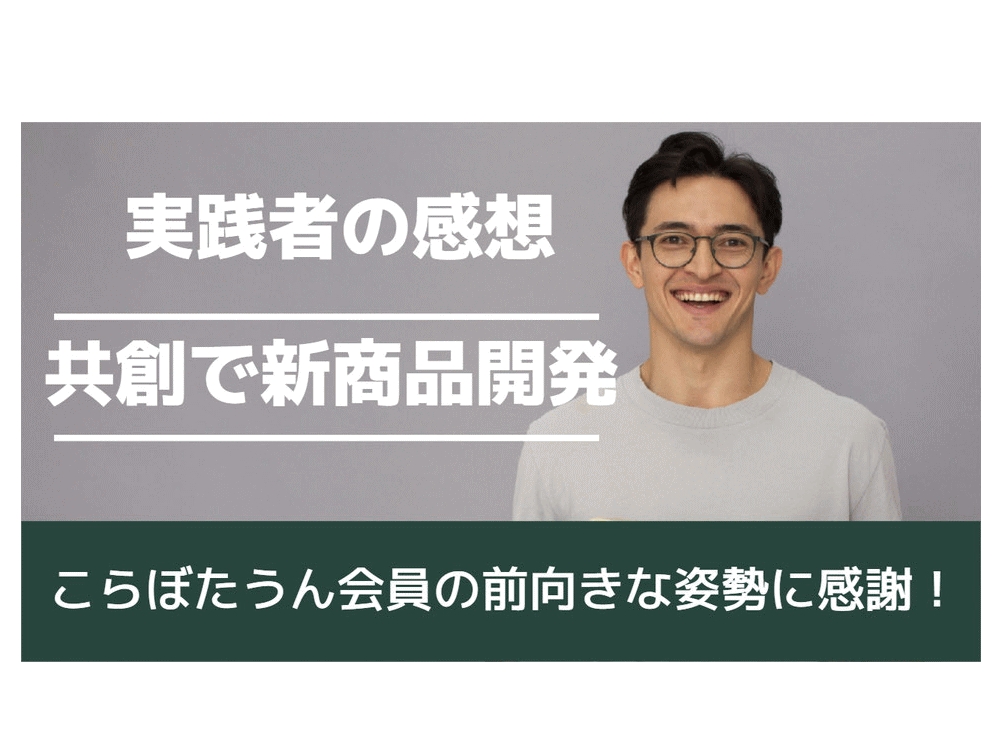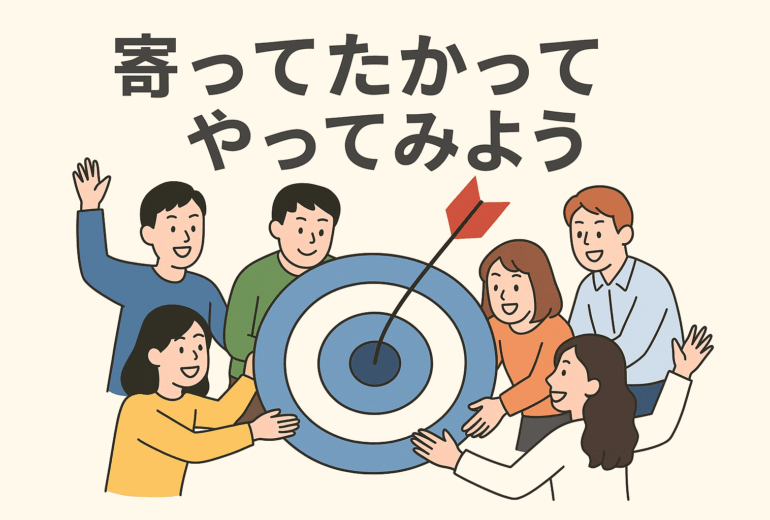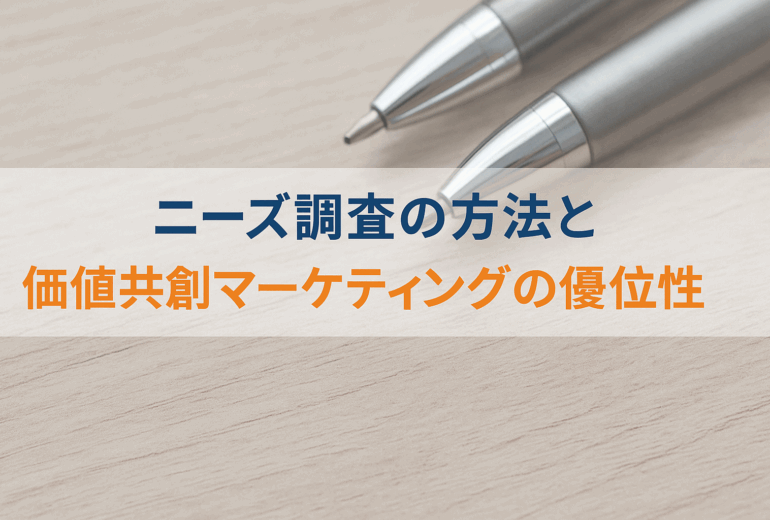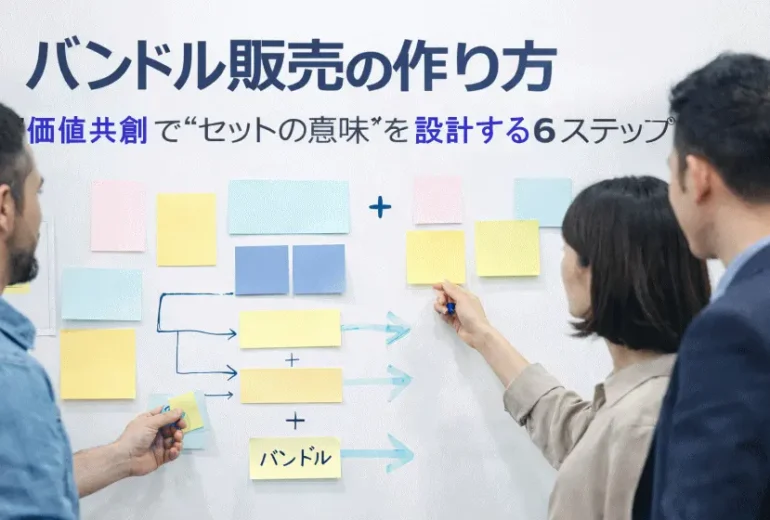この記事は 価値共創マーケティングの全体像 の一部を掘り下げています。
「いいモノなのに売れない」の裏側にある“落とし穴”
「自信を持ってつくった商品なのに、なぜ売れないんだろう?」
この問いは、多くの中小企業や個人事業主にとって切実な悩みです。機能も品質も問題ない。値段も競争力がある。マーケティングも一通りやっている。それでも、売れない。
実はその背景にあるのが、“独りよがり”のマーケティングです。
「この機能が便利だと思ったから」「自分が欲しいと思うものを形にしたから」──このように、企業側の視点だけで設計された商品やサービスは、いくら“良い”ものでも、顧客にとって“欲しい”ものとは限りません。
そこで注目されるのが、「共創マーケティング(Co-Creation Marketing)」という考え方です。
共創マーケティングとは?──“売る”から“一緒につくる”へ
共創マーケティングとは、企業と顧客が対等なパートナーとして関わり、商品やサービスの価値を一緒につくりあげていくマーケティング手法です。
従来のマーケティングが「ターゲットを設定し、ニーズを分析し、それに合わせて商品を提供する」構造だったのに対し、共創マーケティングでは顧客が“参加者”になります。
- 開発段階で意見を聞く
- 試作品を使ってもらい改善につなげる
- ブランドのコンセプトづくりから関わってもらう
顧客と企業の“対話”や“共感”を通じて、本当に使いたい・応援したい商品をともに形にしていくプロセスです。
このアプローチは、特に中小企業やベンチャー、ニッチ市場において強力な武器となります。
独りよがりマーケティングの特徴と落とし穴
① 顧客の使い方を想定していない
企業が想定してつくったものが、実際の顧客の使い方とズレていることはよくあります。
② 売る側の“こだわり”が強すぎる
開発者の思い入れが強すぎて、機能を詰め込みすぎたり、専門性が高すぎて生活者の満足と一致しないケースも。
③ 生活者視点のフィードバックがないままリリース
テストマーケティングや試用モニターの声を取り入れず完成品を出してしまい、「想定外の不満」で売れ行きが鈍る例もあります。
共創マーケティングが顧客の声をどう活かすのか?
ステップ1:声を「拾う」──直接対話・観察・共感
- 購入者へのヒアリング
- 店舗での行動観察
- SNSの投稿やDMの分析
ステップ2:声を「育てる」──共創ワークショップや座談会
「なぜそう思ったのか?」を深掘りすることで、本質的なニーズが見えてきます。
ステップ3:声を「形にする」──すぐに反映し、伝える
- プロトタイプや試作品に反映
- 改善内容を発信し、フィードバックをくれた顧客に知らせる
- 「○○さんの声から生まれた新機能」といったストーリーづくり
成功事例:生活者と開発した「本当に使いたい歯ブラシ」
ある若手起業家が立ち上げた歯ブラシブランドは、立ち上げ当初から「共創」をブランドの核に据えていました。
「市販の歯ブラシは毛が硬すぎる」「持ち手が滑りやすくて使いづらい」──そんな生活者のリアルな声を、ひとつひとつ丁寧に拾い、改良を重ねたのです。
主な改良ポイント:
- 歯ぐきを傷つけにくい、超極細毛ブラシを採用
- 滑りにくく手にフィットするラバーグリップ設計
- プラごみを減らす、環境に配慮した簡易包装
さらに、開発過程はオープンに共有しながら生活者と継続的に対話。
「改良前と後でどこが違う?」「どのパッケージがいい?」といった問いかけを通じて、商品だけでなく“共感”の輪も広がっていきました。
その結果、発売前から熱量の高い“共創ファン”が生まれ、初回ロットは即完売という成功を収めました。
共創を取り入れるために、まずできること
● 小さな声に耳を傾ける
アンケートだけでなく、店頭での会話、SNSのコメント、電話対応の中にヒントはあります。
● 話せる場をつくる
- お客様感謝イベントでの座談会
- 常連さんとの雑談
- 新商品のお試しモニター
● 小さく始めてすぐに形にする
まずは限定商品やオプション機能など、すぐに反映できる範囲からスタート。「これは皆さんの声から生まれた改善です」と発信しましょう。
まとめ:独りよがりから抜け出すには、「対話」と「共感」が鍵
売れない原因は、必ずしも商品そのものの欠陥とは限りません。「誰のために、どんな価値を届けたいか」が不明確なままでは、どれだけ魅力的な商品でも響かないのです。
共創マーケティングは、顧客と一緒に「欲しいと思える商品」「応援したくなるブランド」を育てていくアプローチです。
小さな声に耳を傾けるところから、共創は始まります。
それは、たったひとつの声を起点に、大きなファンづくりへとつながる可能性を秘めています。
今、必要なのは“もっと売る”ことではなく、“もっと聴く”姿勢かもしれません。
Q. 中小企業でもすぐ始められますか?
A. はい。小規模セッションから始め、効果が出たテーマに絞って進める方法が有効です。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)