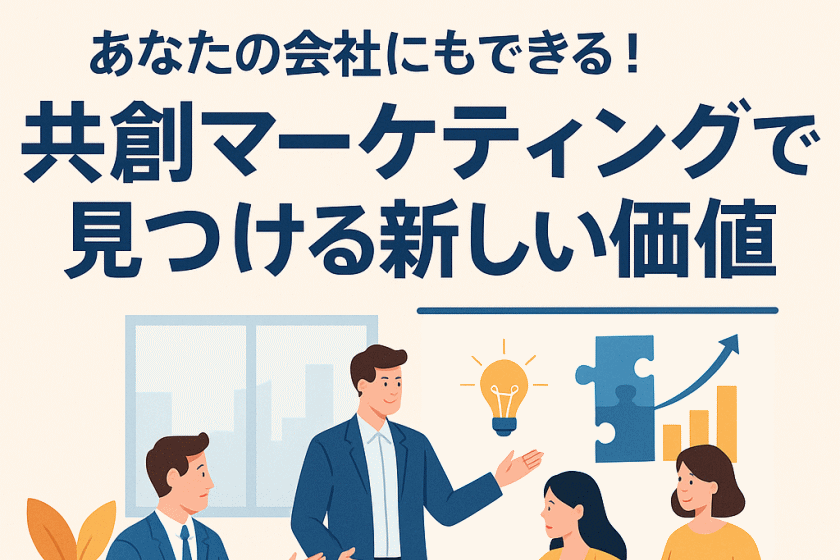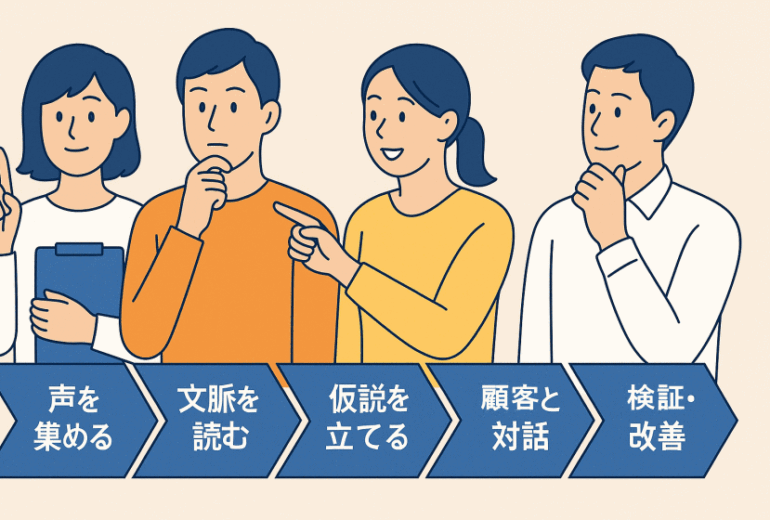実務の進め方(顧客参加型の商品企画・商品開発)は こちら(5ステップ+WS設計)に集約。 本ページでは「共創の基本・背景・効果」をわかりやすく整理します。
目次
はじめに:なぜ今、共創なのか?
「新しい商品を出しても反応が鈍い」「値引きしないと動かない」「SNSで発信しても手応えが薄い」――こうした声は、国内の中小企業から特によく聞こえてきます。
これは単に商品力の問題というより、時代そのものが“企業が作って売る”から、“生活者と一緒に価値を育てる”モデルへ移行しているサインかもしれません。
いまは、口コミ・レビュー・コミュニティ・SNSなどを通じて、生活者が価値の担い手になっています。企業が一方的に語るほど、生活者は「本当かな?」と距離を取る。逆に、生活者が「自分の言葉」で語り始めると、信頼が積み上がる。
だからこそ注目されるのが共創マーケティングです。顧客・社員・地域・取引先などと対等な関係で対話し、価値を一緒に育てていく考え方です。
実はこの発想、特別に新しいものではありません。昔ながらの商いの現場には「会話しながら品揃えを変える」「常連さんの一言で改善する」といった共創が自然にありました。共創マーケティングとは、その“人と人の関係性”を、現代のビジネスで再現性ある形に整えることでもあります。
共創マーケティングとは?
共創マーケティングとは、企業が顧客や社員、地域、取引先など
社内外のパートナーと一緒に価値をつくり出すマーケティングの考え方です。
調査→企画→製造→販売の一方通行ではなく、企画段階から対話・参加を通じて商品やサービスを育てていきます。
「買い手」ではなく「一緒につくる仲間」
共創のポイントは、生活者を“評価者”として扱うのではなく、価値づくりの相手として迎えることです。すると、意見は「要望リスト」ではなく、「背景」「文脈」「迷い」「感情」を含んだ“使えるヒント”に変わります。
共創の代表的なやり方
- 企画の初期からの対話(小さな座談会/共創ワークショップ)
- 試作品やサービス案を見せて、反応を一緒に検証する
- ネーミング・パッケージ・使い方のアイデアを共に磨く
- 地域・団体・取引先と連携し「文脈価値」を育てる
- “社内の現場”も巻き込んで、意思決定を前に進める
共感との違い:共創は「一緒に手を動かす」
共感は寄り添うこと、共創は一緒に考え、一緒に試し、一緒に育てること。ここが大きな違いです。共創は行動が伴う分、信頼が深まり、ストーリーが生まれます。
なぜ共創が必要なのか
「良いものを作れば売れる」が通用しにくい
機能・価格・品質が似通うと、生活者は“比較疲れ”します。そのとき選ばれるのは、スペックより納得できる理由です。共創は、その理由を生活者と一緒に育てる方法です。
生活者は「発信者」でもある
いまの生活者は、購入後の体験を語り、共有し、周囲に影響を与えます。共創で生まれた商品・サービスには「自分も関わった」という当事者感が乗るため、自然な口コミや応援が起こりやすくなります。
社内にも効く:部署の壁を超える“共通目的”ができる
共創は社外だけの施策ではありません。現場・企画・営業・開発が同じ顧客像を共有し、同じ会話を聞くことで、組織の意思決定が揃いやすくなります。
共創のメリットと現場の変化
メリット1:ファン・リピートが育ちやすい
共創に参加した人は「買った」より「一緒に育てた」という感覚を持ちやすく、結果として愛着と継続が生まれます。広告より強いのは、生活者の言葉です。
メリット2:ズレにくい商品・サービスができる
企画の初期でズレを見つけ、すばやく修正できるのが共創の強みです。完成してから直すのはコストが高いですが、共創なら“早い段階での小さな修正”が可能になります。
メリット3:社員の主体性が上がる
「顧客の言葉」を自分の耳で聞く体験は、現場を動かします。共創を続けるほど、社員の言動が“顧客起点”に変わりやすくなります。
メリット4:企業文化が変わる
共創は、外向き施策でありながら、実は内側に効きます。部署間の壁がほぐれ、対話が増え、現場の改善が回り始める。結果として「らしさ」が強くなります。
共創をどう始める?(要点まとめ)
- 小さく始める(まずは30〜60分の“対話”から)
- 参加者を選ぶ(偏らない・本音が出やすい設計)
- 試す→直す→また試す(反復を前提に組む)
顧客参加型の商品企画・商品開発(5ステップ)へ
まとめと次の一歩:共創をはじめるために
共創マーケティングは「特別な会社だけの話」ではありません。むしろ、顧客との距離が近い国内の中小企業ほど、共創が最短距離で効きやすい領域です。
最初は小さくて大丈夫です。たった数人の対話からでも、価値は育ち始めます。
まずはここから
- ✅ 既存商品をテーマに「どこが好きか/どこで迷うか」を聞く
- ✅ 試作品・案を見せて、反応を一緒に検証する
- ✅ 学びを社内共有し、次の一手を決める
共創マーケティング診断ツール|顧客と価値を生む力を10問でチェック
あなたの会社は“共創型”?それとも“旧来型”?
全10問でチェック!お客さんと一緒にアイデアを出したり、商品を育てたりする体制がどれくらい整っているか、今の状態を見える化してみましょう。
こんなお悩みに
- 顧客との関係が“売る・買う”で止まっている
- リピーターやファンが定着しない
- 差別化の限界を感じる
- 新しいヒントが社内から出てこない
▼ 診断スタート
診断結果
よくある質問(FAQ)
Q. 共創マーケティングと「共感マーケティング」は何が違いますか?
共感マーケティングは、お客様の気持ちや価値観に寄り添う「理解」が中心です。 一方、共創マーケティングは、共感を起点に実際に一緒にアイデアを出し、商品やサービスをつくり変えていく行動まで含めた考え方です。
Q. 中小企業でも共創マーケティングは実践できますか?
むしろ中小企業こそ、経営者や担当者とお客様の距離が近いため共創に向いています。 大掛かりなプログラムでなくても、常連さん数名との座談会や、 試作品を見せて感想をもらう小さな場づくりから十分にスタートできます。
📘 中小企業の方へ
中小企業での進め方を具体的に知りたい方は、
▶ 中小企業の共創導入ガイド|3か月モデル完全版
もあわせてご覧ください。
Q. まず最初に何から始めるのがおすすめですか?
いきなり新商品開発をするよりも、既存商品やサービスをテーマに、 「どこが好きか/どこで迷うか」をお客様と一緒に話してみる小さな対話がおすすめです。 本文中の「共創をどう始める?」もあわせてご覧ください。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)