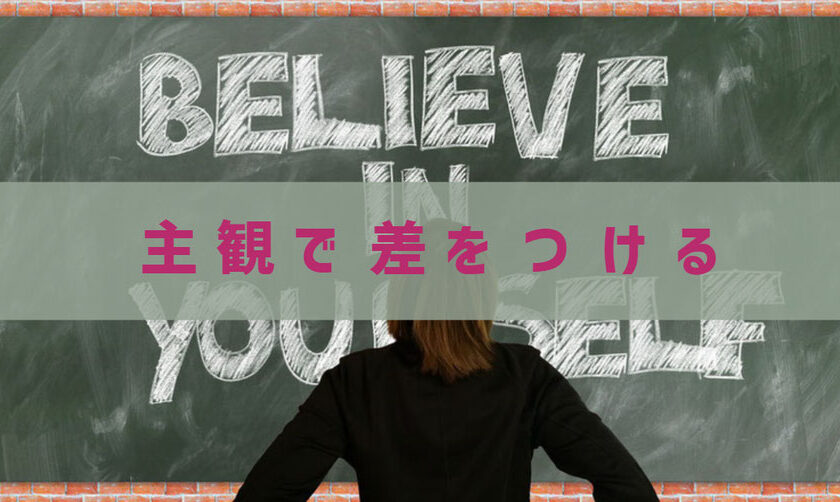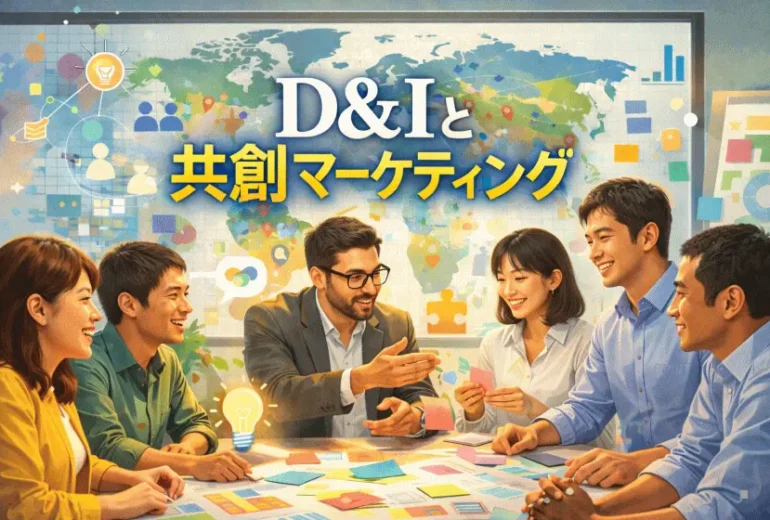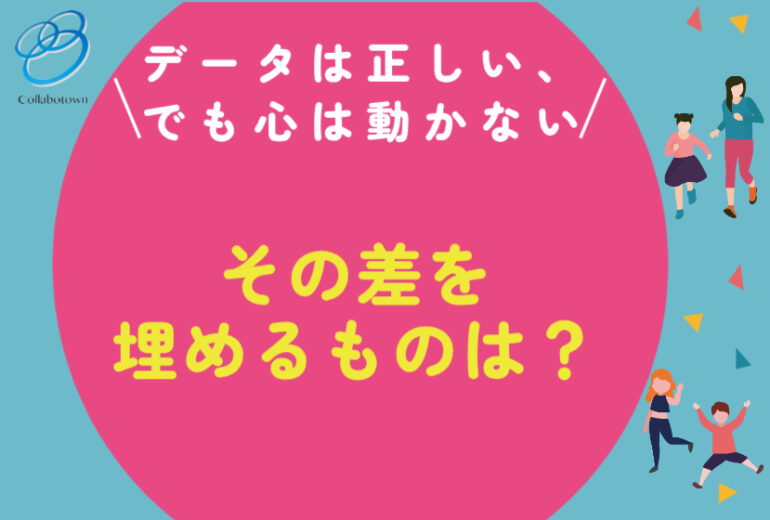主観で差をつける──
AI時代に求められる「自分のフィルター」を持つ力
客観がコモディティ化する世界で、最後に残る価値とは何か?
「どうすればいいでしょうか?」
日々の業務の中で、ついこの言葉を口にしていませんか。かつて金融機関で若手だった頃、私も同じように上司へ問いかけました。しかし、返ってきたのは助言ではなく、「でお前は、どうしたいんだ?」という、突き放すような一言でした。
当時は戸惑い、冷たささえ感じたその問い。しかし、AIが「最適解」を一瞬で導き出す今、あの言葉こそがビジネスの本質を突いていたのだと痛感します。主観こそが、唯一無二の差別化要因になるのです。
1. 客観データは「誰でも使える武器」になった
市場調査、消費者インサイト、購買ログ……。かつては貴重だった「客観データ」は今や民主化されました。誰もが同じデータにアクセスし、同じロジックで分析し、同じ標準化された答えに辿り着きます。
「データがこう言っているから、この企画を通すべきだ」。一見正しいこのロジックは、皮肉にも「他社と同じような、差が見えないサービス」を量産する原因となりました。客観データだけを頼りにすることは、競争優位性を自ら放棄することと同義なのです。
貴社の「主観度」チェックリスト
以下の項目、あなたの組織や仕事に当てはまりませんか?
- □ 企画書の根拠が「データ的に正しい」という説明だけで終わっている
- □ 「私はこれがやりたい」と会議で発言したのがいつか思い出せない
- □ 競合他社のロゴを自社の製品に貼り替えても、違和感がない
- □ 効率や正解を求めるあまり、チームから「尖った意見」が消えている
一つでも当てはまるなら、組織が「コモディティ化の罠」に陥っているサインです。
2. 主観とは「わがまま」ではない
ここで言う主観とは、単なる「好き嫌い」や「思い込み」のことではありません。真の主観とは、多様な意見を自分の経験や直感という「フィルター」で煎じ詰めた結果生まれる「意志」です。
このプロセスを経て生まれた主観には、圧倒的な「熱量」と「独自性」が宿ります。それこそが、他者が真似できない「ブランドらしさ」の源泉となります。
3. AIが担う「客観」、人間が担う「主観」
AIの進化は、「間違いのない平均的な正解」を瞬時に提供してくれます。論理的な分析や客観的な判断は、今後AIの独壇場となるでしょう。人間に残された価値は「正解を出すこと」ではなく、「どうしたいか」という問いに、主体的な意志で答えることにあるのです。
4. ブランドの強さは、主観の鋭さに比例する
主観を欠いたブランドは、スペックと価格を比較される「ただの商品」に成り下がります。一方、主観を尖らせたブランドは、独自の「世界観」を提供し、共感を集めます。
共創マーケティングの現場にて
私たちが支援する現場でも、最もイノベーションが生まれるのは、担当者が「自分たちはこういう未来を見たい」という主観をぶつけた瞬間です。客観データを超えた「人の想い」が、新しい価値の芽を育てるのです。
主観で尖らせる勇気を持とう
正解が溢れる時代だからこそ、間違いを恐れず、自分のフィルターを通した「主観」を堂々と表現してください。
その「尖り」こそが、ビジネスにおける「独自の価値」になります。
あなたの「意志」を、価値ある言葉に変えませんか?
オンライン無料相談で「意志」を言語化してみる
共創のプロが、貴社ならではの「独自性」を引き出すお手伝いをします。
まずは気軽なオンライン相談から始めましょう。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)