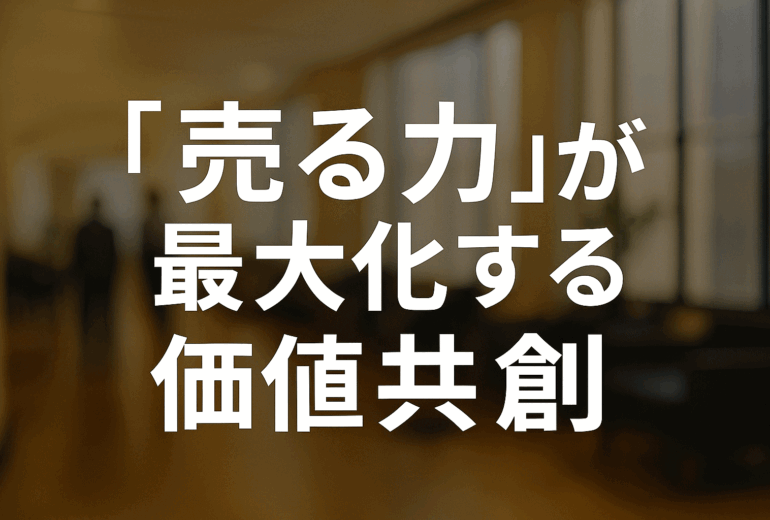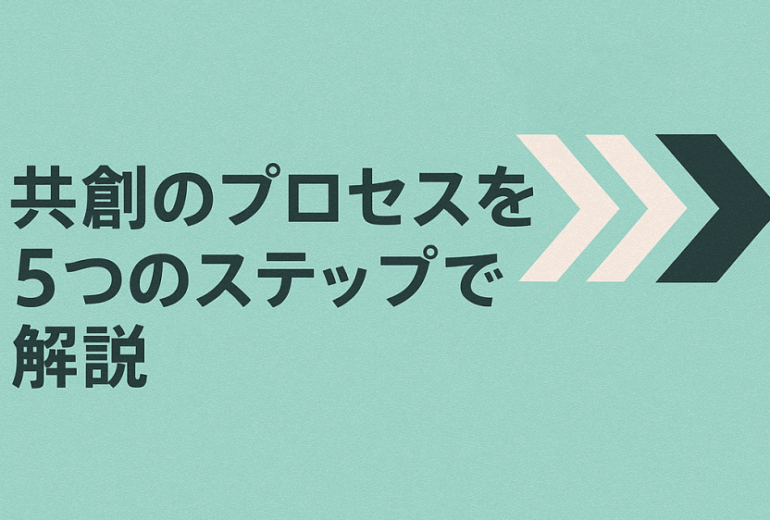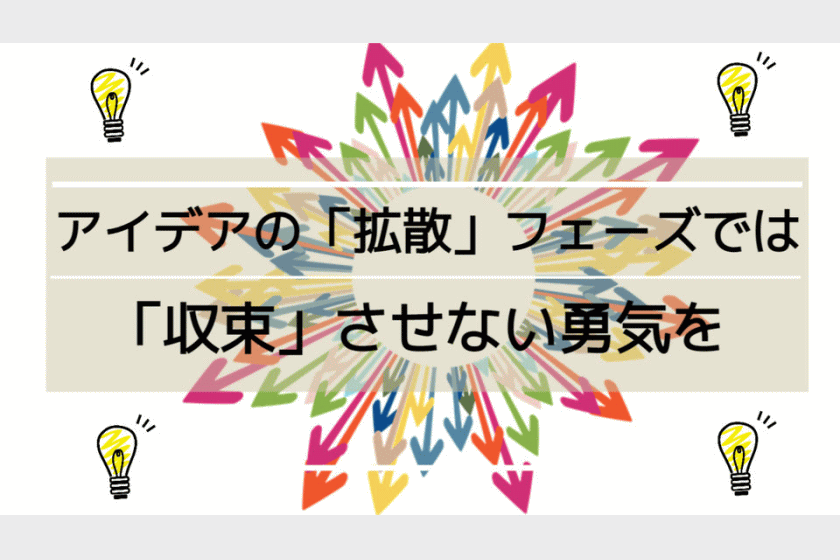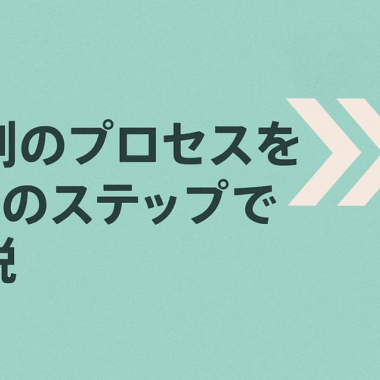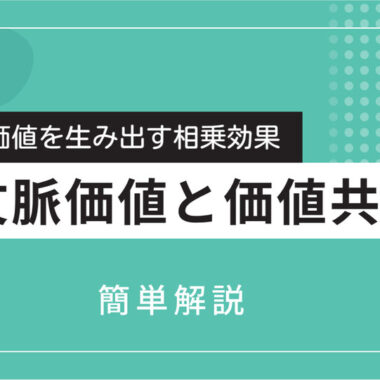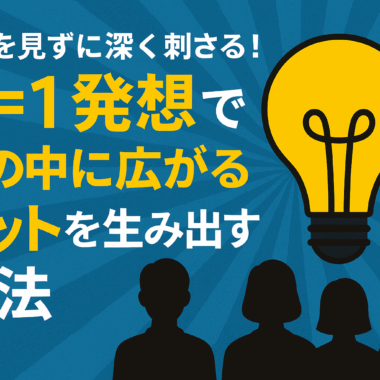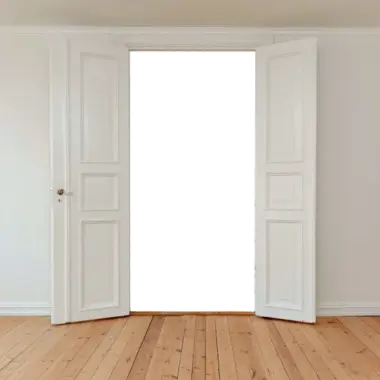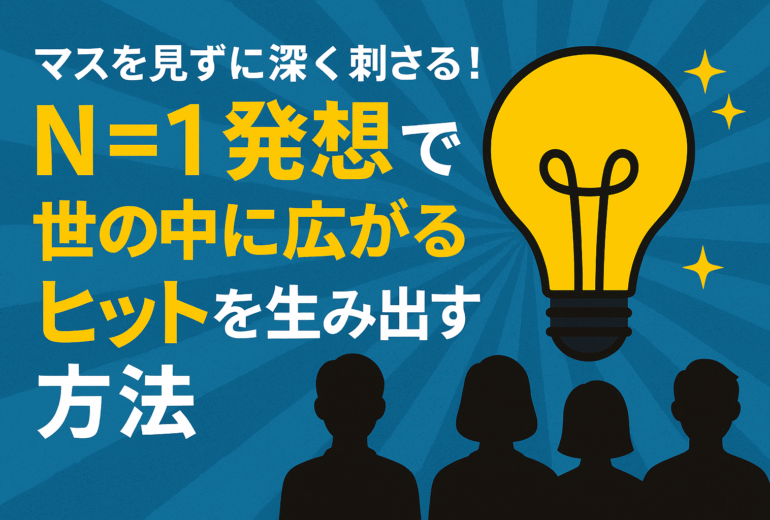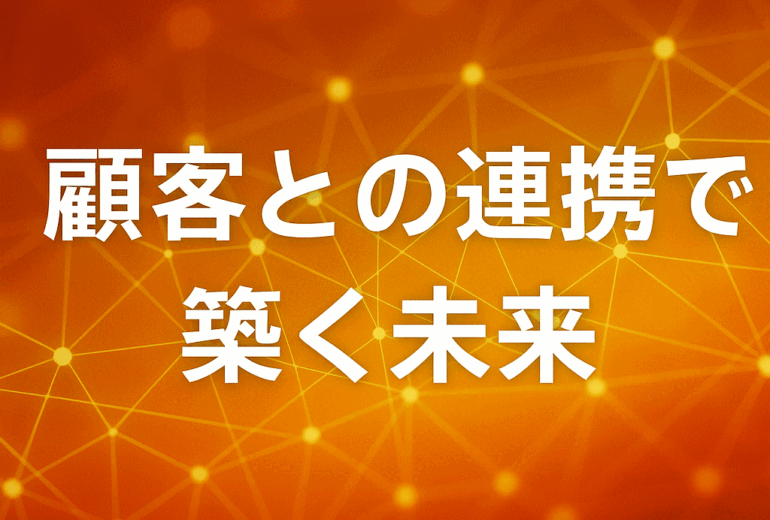📌 本記事の位置づけ
-
🎯 インサイト発見ガイド(全体像)
└ 観察・買い物同行・場づくり・拡散/収束といったプロセスを、全体像と索引として整理したガイドです。 -
🔷 価値共創マーケティングとは?(全体ガイド)
└ 価値共創マーケティングの基本概念と導入ステップをまとめた全体ガイドです。
こらぼたうんでは、企業と生活者(消費者)が一緒に未来の価値を考える「共創セッション」を数多く行ってきました。
その中で気づいたのは、イノベーションの成否を分けるのは「発想の仕方」よりも「発想のプロセスの扱い方」だということです。
特に重要なのが、アイデアの「拡散」と「収束」を切り分けて扱うこと。
多くの現場では、拡散が不十分なまま収束に進んでしまい、「ありきたりな結論」に落ち着くケースが目立ちます。
本当に新しい発想を得るには、「収束させない勇気」を持ち、混沌の時間に耐えることが必要なのです。
■ 拡散と収束──創造の螺旋を回すプロセス
イノベーションのプロセスは直線的ではなく、「拡散(ダイバージェンス)」と「収束(コンバージェンス)」を繰り返す螺旋のようなものです。 拡散は可能性を広げ、収束はその中から軸を見出す。このリズムを何度も往復することで、アイデアは深まっていきます。
- 拡散:「自由な連想」を重視。突飛でもOK、とにかく量を出す段階。
- 収束:「判断と選択」を重視。実現性や方向性を整理して絞り込む段階。
しかし、現実の会議では「拡散が中途半端なまま収束に移る」ことが非常に多いのです。
その結果、目新しさのない「妥協案」しか残らず、参加者は「結局いつも通りだね」と感じてしまいます。 逆に、十分な拡散を経た後の収束は、芯の通った独自のアイデアを生み出すのです。
■ アイデアが“拡がる”瞬間を奪わない
拡散フェーズは「カオス」を歓迎する時間です。 ここでは「非常識」「空想的」「今の会社には合わない」と思える発言が出てくることが成功のサインです。
しかし、現場では無意識のうちに次のような収束発言が出やすいのです。
- 「そんなことはやったことがない」
- 「コスト的に不可能では?」
- 「うちの顧客層には合わない」
- 「現実味がないから整理しよう」
こうした発言は、一見「合理的」で「前向き」に見えますが、実は拡散を殺すブレーキです。
重要なのは「今は広げる時間だ」と明示的に場を守ることです。 ファシリテーターが「まだ判断しません、広げましょう」と声をかけるだけで、場の空気は大きく変わります。
■ 「無理そうでも拡げる」ことがイノベーションの源
革新的なアイデアは、最初から実現性が高いものではありません。
むしろ「今の技術や予算では不可能」に思えるアイデアが、未来の常識になることは珍しくないのです。
例えば「自動運転」や「宇宙旅行」といったテーマも、数十年前なら「SFの世界」と笑われていました。 それが今では実証実験や商業化のフェーズに入っています。
「非現実的だから面白い」──その視点が拡散の質を高めます。
こらぼたうんのセッションでも、生活者から「そんなことできるはずがない」と思われる発想が飛び出すことがあります。 しかし、後から振り返るとその「一見荒唐無稽なアイデア」が新商品の突破口になることも少なくありません。
■ 拡散フェーズで“我慢する力”が求められる理由
拡散を続けていると「まとまりがない」「混沌としている」状態が長く続きます。 この状態に不安を感じるのは自然なことです。 企業担当者は特に「早く方向性を決めたい」「すぐに行動計画を作りたい」と考えがちです。
しかし、この「混沌に耐える時間」こそが、創造に不可欠なのです。 短絡的に収束してしまうと、他社と同じようなアイデアにしかなりません。 我慢を重ねた先に「これだ!」と皆が感じる瞬間が訪れます。
実際に参加した企業担当者の声:
「正直、途中は何も見えなくて不安でした。でも最後に出てきたアイデアは、自分たちだけでは絶対に出なかったものです。」
■ 拡散の質を高めるための工夫
拡散フェーズを成功させるためには、以下のような工夫が効果的です。
- ルールの明文化:「否定しない」「とにかく量を出す」「笑われてもOK」など。
- タイムボックス:時間を区切り「この30分は広げるだけ」と設定する。
- 多様な視点:生活者・未来世代・異業種など、異なる視点から考える。
- 制約の外し:「もし資金が無限だったら?」「もし技術が5年先だったら?」と仮定。
- 可視化:出てきたアイデアを付箋やホワイトボードで並べると、連想が広がりやすい。
これらを組み合わせると、場の空気が自由になり、拡散の幅と深さが大きく広がります。
■ 最後に:収束させない勇気が未来を変える
拡散フェーズは“未完成の宝庫”です。
その時間を大切にできるかどうかで、企業の未来が変わります。
荒削りでも、実現性が低くても、今は関係ありません。 大切なのは「可能性を切り捨てないこと」。
「収束させない勇気」──それはイノベーションを生む最大の武器です。
もし御社が「変化を生みたい」と願うなら、まずはこの勇気を持って拡散の場を守ってみてください。
きっと、まだ誰も見たことのない未来のアイデアが芽吹いていくはずです。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
※本記事は、最新の状況に合わせて加筆・再編集しました(更新日:2025年8月28日)。
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)