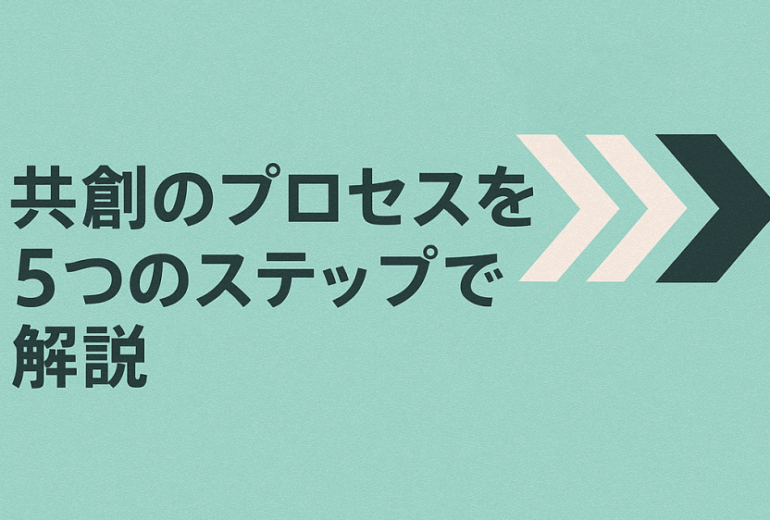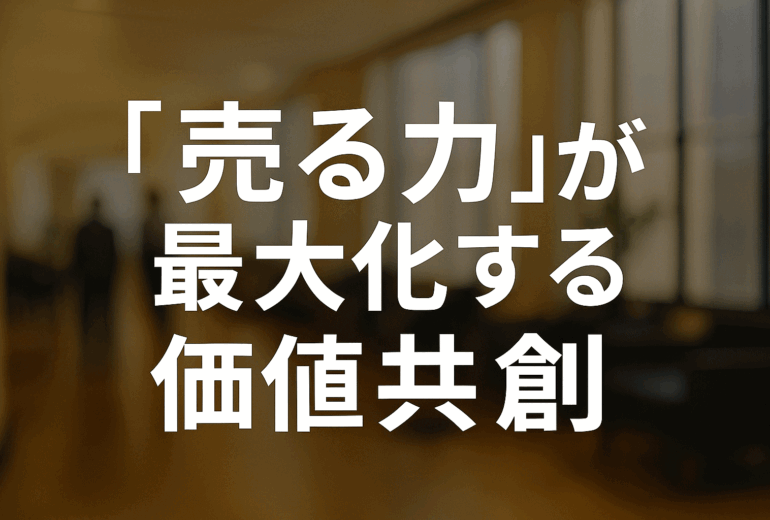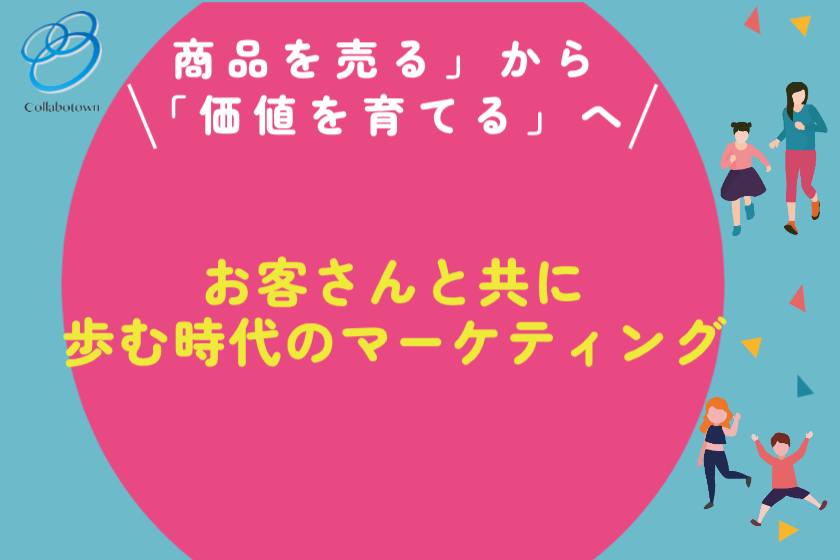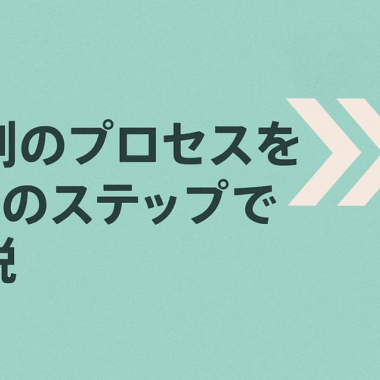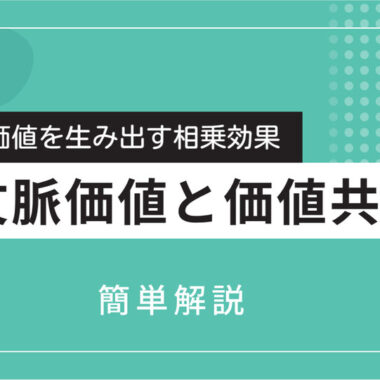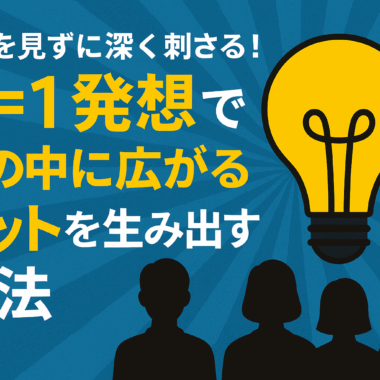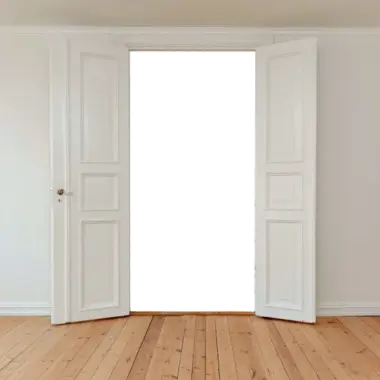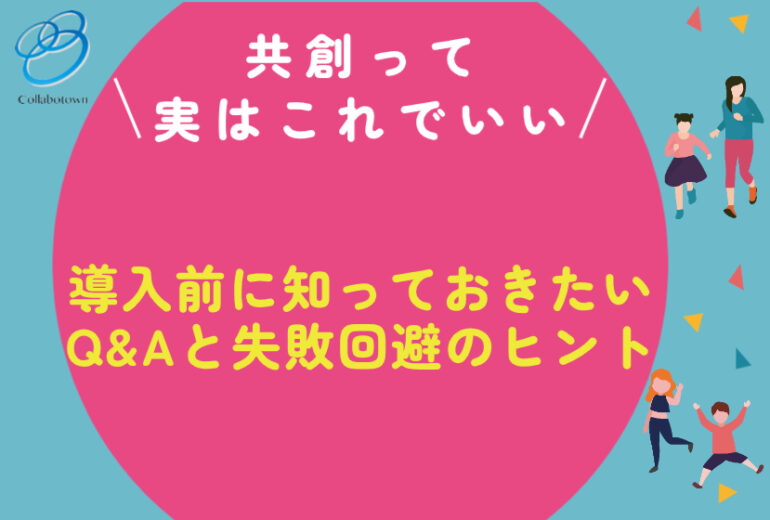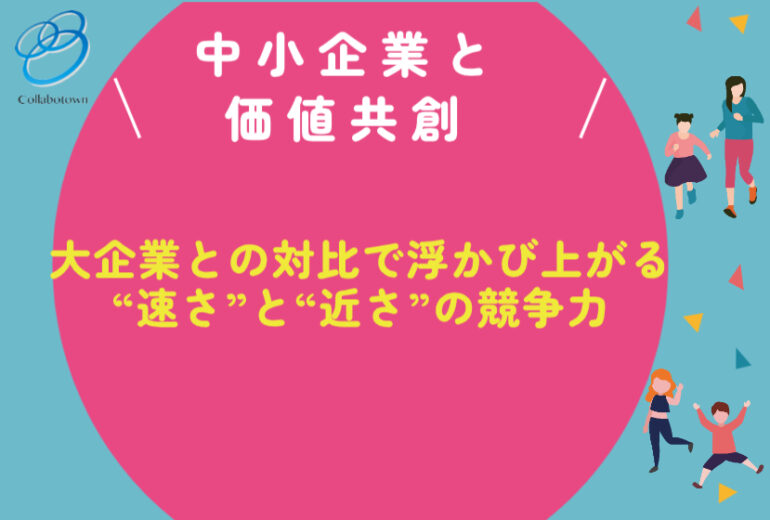実務の位置づけは 価値共創マーケの基本と導入ガイド をご参照ください。
選ばれる理由は、スペックや価格の先にある「体験」です。
これからのマーケティングは、企業が一方的に売るのではなく、お客さんと一緒に価値を“育てる”発想へ。
市場データだけでなく、生活の現場(文脈)に寄り添い、「買ってよかった」を生む体験の設計が鍵になります。
1. なぜ「売る」だけでは足りないのか
これまでのように「良いモノを作れば売れる」という時代は終わりつつあります。技術の差はすぐ埋まり、価格競争は疲弊を招き、消費者はただ安いだけでは動かなくなりました。ここでは、なぜ“売る”発想だけでは限界があるのかを整理します。
差別化が続かない
技術・情報のコモディティ化で、機能差や価格差は短期で埋まります。スペック競争に終始すると、利益が磨耗します。
価値観の多様化
「安いから買う」だけでは動かない時代。自分に合う/共感できる/意味があるが購買動機に。
体験型の購買行動
人はモノより体験を求めています。同じ商品でも、使われる文脈が価値を変えます。
「供給」から「共創」へ
価値は提供ではなく共創される。顧客とともに価値を育てる設計が必要です。
2. 価値共創:売るから育てるへ
次の時代のキーワードは「共創」です。企業が一方的に価値を提供するのではなく、顧客と一緒に体験を作り、関係性を育てていく。その発想の転換を図表で整理します。
| 従来の前提 | これからの前提(価値共創) |
|---|---|
| 企業が価値を作り、市場へ「提供」する | 価値は利用の現場で生まれる。顧客と一緒に「育てる」 |
| 4P中心(Product/Price/Place/Promotion) | 体験中心(CX/UX)。購入前→利用中→サポートの一連で設計 |
| 顧客は「ターゲット」 | 顧客はパートナー/共創者 |
| 交換価値(価格)に焦点 | 文脈価値(状況・意味・感情)を重視 |
3. 生活に寄り添う:文脈を見る
数字やデータだけでは見えないものがあります。実際に使う現場や生活の場面を観察することで、はじめて顧客の「本当の困りごと」や「ちょっとした感情の動き」が見えてきます。ここではその具体的な手がかりを示します。
- 同席する:導入時のつまずきや独自ルールを目視。
- 会話する:数字に出ない「なぜ?」を掘り下げる。
- 共に試す:プロトタイプを一緒に運用して学ぶ。
- 継続する:一度きりで終わらず、循環学習に。
生活者に寄り添う対話

化粧品メーカー × 生活者
“自分らしく輝く”をテーマに、共感と試作を重ねて。

家庭用品メーカー × 生活者
日常生活の声をヒントに、“使いやすさ”と“安心感”をカタチに。

学習塾 × 地域住民
子どもたちの未来を支える“学びの場”を、地域と一緒に設計・共創。

工業用製品製造業 × 主婦
家事や育児の知見を活かし、“一般消費者向けの製品”のヒントを。

家電メーカー × 消費者
日々の“ちょっとした不便”をヒントに、使い勝手のよい家電を共創。

日用品メーカー × 生活者
“あったらいいな”を丁寧に掘り起こし、共感される商品設計へ。
また、フィールドでの学び方の一例は、こらぼたうんの買い物同行(フィールドワーク)にも通じます。
4. 「買ってよかった」を生む体験設計
顧客が「買ってよかった」と感じるのは商品そのものよりも、その前後にある体験です。購入前の不安、利用中の学び、購入後のフォロー。その一連を丁寧に設計することが大切です。
体験の3局面(Before / During / After)
① Before:知る・選ぶ
期待値を設計。比較観点を整理し、「自分ごと化」される情報設計(ストーリー・FAQ・導入例)。
② During:使いはじめる
オンボーディング(初期体験)を滑らかに。チュートリアル、既存環境との接続、初回成功体験。
③ After:困りごと・継続
つまずきに寄り添うサポート、改善の反映、コミュニティ/活用ノウハウの共有。
文脈価値の基礎は、こちらの記事も参考になります:新たな価値を生み出す相乗効果──文脈価値と価値共創
5. 価値を育てる一般化事例
「共創の発想」が実際にどのように応用されているのかを見てみましょう。ここでは業界を超えて一般化できる代表的な取り組みを紹介します。
- サブスクリプション:所有から利用へ。保証・維持・乗り換えの負担を軽減し、使い続ける体験を提供。
- データ連携型の伴走:稼働状況や使い方の傾向を共有し、顧客と一緒に最適化。効果が上がる実感がロイヤルティに。
- コミュニティ共創:利用者同士の知恵や成果を巡回させ、製品価値を「共に」育てる。
6. 実践ステップ:6段階のロードマップ
共創を実際に社内で進めるには、どこから始めればよいのでしょうか。ここでは「小さく始めて大きく育てる」ための6段階の流れを整理しています。
- 顧客像の再定義:ターゲットではなく共創者として捉え直す(参加の動機・貢献の形を言語化)。
- 現場理解:観察・同席・ヒアリング・買い物同行で文脈を掘る。
- プロトタイプ共創:機能ではなく体験仮説を検証(初回成功体験の設計)。
- オンボーディング:初期90日の設計(完了率・初回価値到達までの時間・問い合わせ内容の型)。
- 効果測定と学習循環:短期KPIと長期KPIを接続し、改善→再実装を反復。
- 価格と対価の見直し:成果連動/継続価値型に再設計(例:サブスク、段階課金、成功報酬の一部組込)。
7. KPI:短期と長期をつなぐ指標設計
共創の価値は「場が盛り上がった」だけでは測れません。短期の成果と長期の関係構築をどうつなげるか、その指標設計がポイントになります。ここでは、実際に役立つKPIの例を示します。
8. 社内の壁と対処(失敗回避の勘所)
よくある壁
- 短期売上への過度な偏重で共創が形骸化
- 部門縦割りで体験が分断
- 「顧客の声」を集めるだけで活かされない
対処のヒント
- 短期×長期KPIの二階建て運用
- 共創プロジェクトの横断運営(営業・開発・CS)
- 発見→試作→検証→展開の循環を明文化
導入Q&A/失敗回避の詳しいポイントは、こちらも参考に:
共創Q&Aと「失敗回避」チェックリスト(こらぼたうん)
9. まとめ:選ばれ続けるために
「良い商品だから売れる」から「良い体験だから選ばれる」へ。価値は企業が作って渡すだけでは完結しません。顧客の生活文脈で生まれ、使われるほど深まります。だからこそ、現場に寄り添い、顧客と共に価値を育てるという姿勢が、長期のロイヤルティとLTVをもたらします。
実践の入り口としては、現場観察→体験仮説のプロトタイプ→オンボーディング最適化→KPI循環の順で、小さく速く回すのが有効です。
関連記事(こらぼたうん)
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)