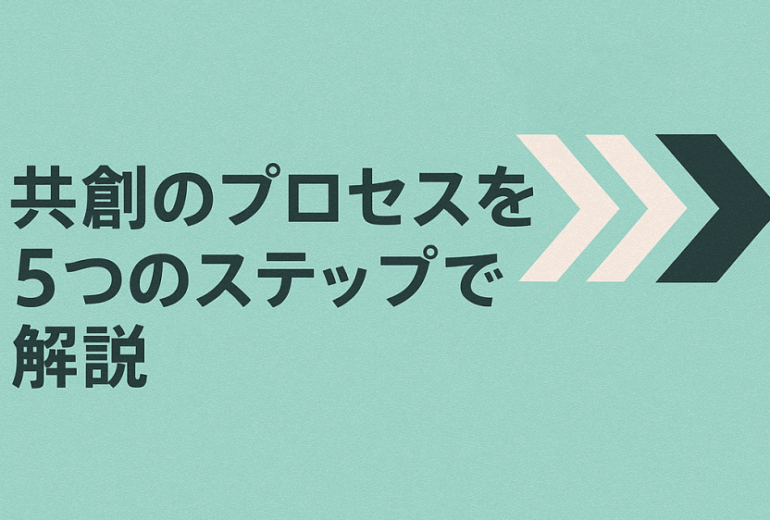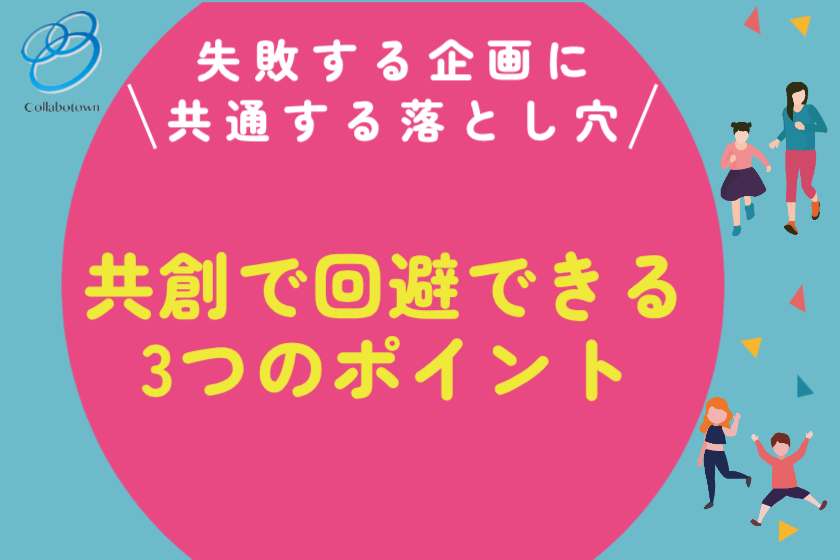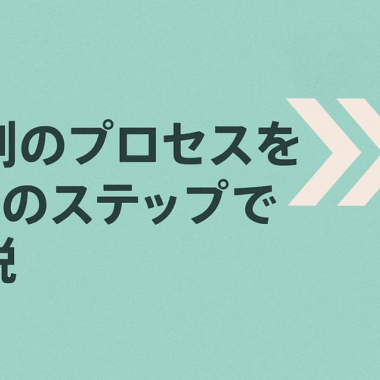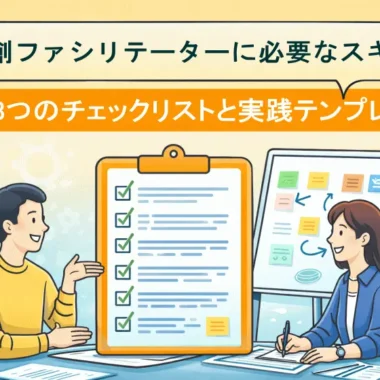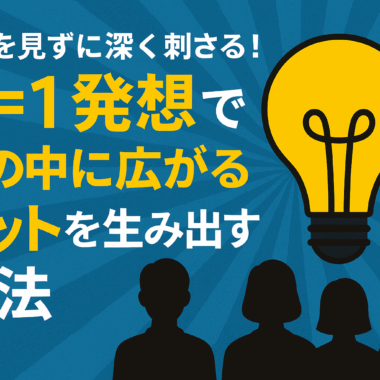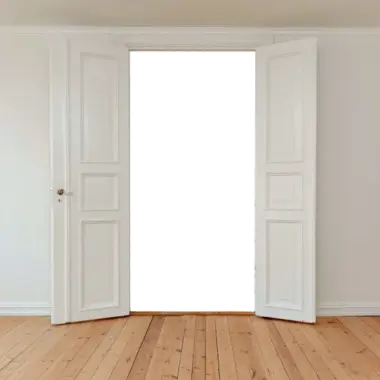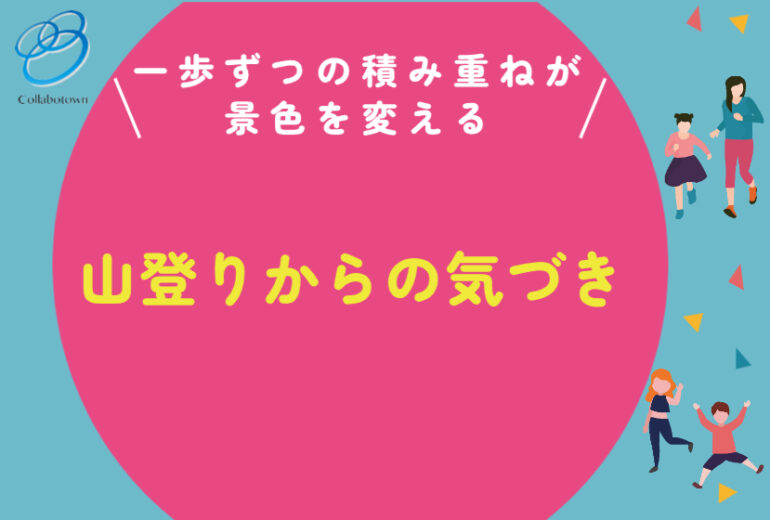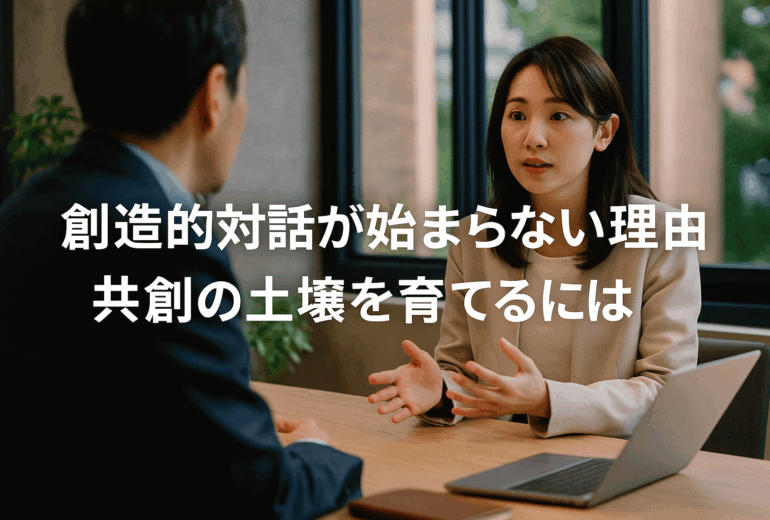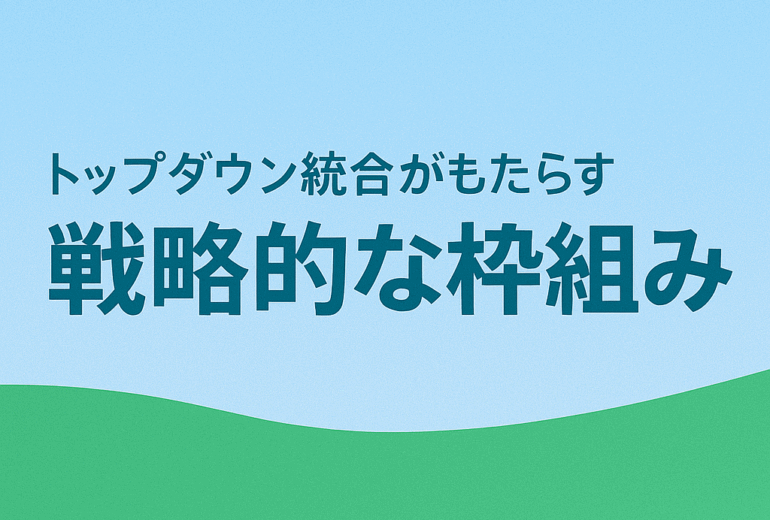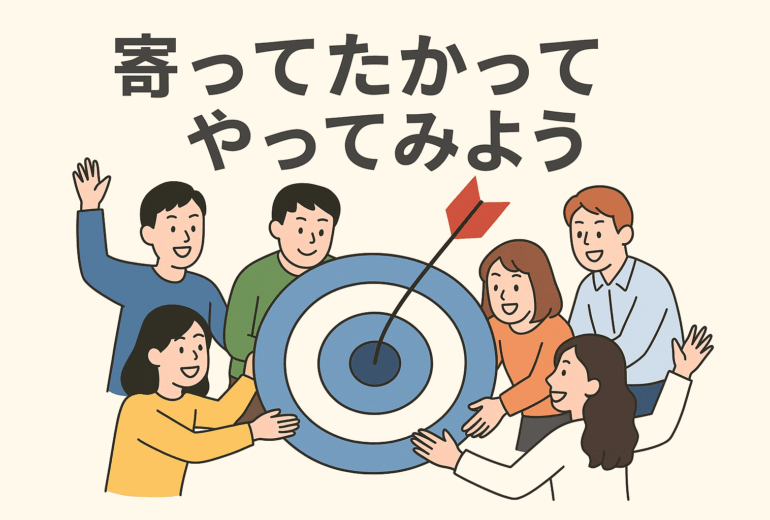どれほど綿密に準備した企画であっても、「なぜかうまくいかない」「当初の狙いと違う方向に進んでしまった」という経験を持つ方は多いのではないでしょうか。 商品企画・販促・イベントなど分野を問わず、失敗する企画には共通する落とし穴があります。
本記事では、20年以上にわたり企業と生活者をつなぐ価値共創マーケティングを実践してきた視点から、 企画が失敗に陥る典型パターンを整理し、 それを共創で回避するための3つのポイントを詳しく解説します。 あわせて実際の現場で見られる事例や副次的な効果についても掘り下げます。
1. 企画が失敗する「3つの共通パターン」
失敗に終わる企画には、単なる偶然ではなく「必然」ともいえる共通項が存在します。 まずはその3つの典型的なパターンを整理しましょう。
1-1. 机上の論理に偏りすぎる
市場調査データや統計分析は企画の基盤として重要です。しかし、数字や仮説に依存しすぎると 「現場の生活者の行動や感情」が置き去りになります。
たとえば、購買データから「20代女性はスイーツを週1回以上購入する」とわかったとしても、 その背景にある心理やシーンは数値だけでは把握できません。実際には「自分へのご褒美としての意味合い」や 「友人と一緒に食べる楽しみ」など、文脈によってニーズが変化しているのです。
机上の論理に頼りすぎる企画は、現実とのズレを生み出すリスクが高いといえます。
1-2. 部署や担当者の自己完結
もう一つの落とし穴は、部署や担当者だけで企画を進め、他部門や現場の視点を取り入れないことです。
典型例として、商品企画部門が一人で新商品を考え、営業には「売ってください」と一方的に伝えるケースがあります。 営業現場の顧客との会話やサポート窓口に寄せられるリアルな不満は反映されず、結果として 「顧客の本音に届かない企画」になってしまいます。
部署ごとの縦割りは効率的に見えても、失敗要因を生み出す温床になりがちです。
1-3. 短期的な成果に縛られる
「今期の売上をすぐに上げる」ことだけを目的にしてしまうと、 長期的なブランド体験や顧客関係の構築は軽視されます。
短期成果を追い求めすぎた結果、一時的に売れたとしても次の企画に繋がらず、 顧客から「一貫性のない企業」と見られてしまうリスクもあります。
2. 共創で回避できる3つのポイント
では、これらの落とし穴をどう避けるのか。その答えの一つが共創(Co-Creation)です。 共創は単なる「一緒に考える」活動にとどまらず、企業・社員・生活者が役割を超えて協働するプロセスです。
ここでは、特に重要な3つの回避ポイントを取り上げます。
2-1. 「仮説」ではなく「共感」を出発点にする
企画の出発点を「仮説」ではなく「共感」に置くことが重要です。 生活者と直接対話し、なぜその行動をとるのか、どんな時に心が動くのかを理解することで、 データでは見えない洞察が得られます。
例えばある化粧品メーカーでは、若年層向けに「映えるパッケージ」を企画していましたが、 ユーザーと共創セッションを行ったところ「忙しい朝に片手で使えることが一番大事」という声が多数。 そこで方向転換し「使いやすさ重視の商品設計」を実現した結果、ヒットにつながりました。
2-2. 「組織横断」での視点共有
企画部門だけでなく営業・製造・カスタマーサポートを巻き込み、多様な視点を反映させること。
ある食品メーカーでは新商品開発の際、開発担当者が営業に同行して顧客訪問を実施。 営業現場で「実際にはこんな使い方をしている」という具体的な声を聞き、 商品コンセプトを修正。結果として、現場に歓迎される商品となりました。
組織横断の共創は現場に根付く企画を生み出し、定着を後押しします。
2-3. 「短期成果」と「長期価値」を両立させる
共創の取り組みは、短期的な成果と同時に長期的なブランド価値を生み出します。
ある日用品メーカーは生活者との共創ワークショップを実施しました。 すぐに商品化につながったわけではありませんが、 「ユーザーと一緒に考えた」というプロセスそのものがSNSで話題に。 ブランドへの信頼とファン層の拡大をもたらしました。
3. 共創の実践がもたらす副次的効果
共創の大きな魅力は、単に「企画の失敗を避ける」ことにとどまりません。 実際に取り組むことで、組織や顧客に思わぬ良い変化をもたらします。 例えば社員の姿勢が変わったり、部門間の連携が深まったり、顧客との関係性が強化されるなど、 企業文化やブランド価値そのものを底上げする副次的効果が生まれるのです。
以下では、そうした副次効果の代表的な3つの視点と、関連する具体事例の記事をご紹介します。
4. まとめ──共創は「失敗を避ける保険」ではなく「成功を育てる土壌」
企画が失敗する背景には「机上の論理」「自己完結」「短期視点」という共通の落とし穴があります。 これを回避するには、 共感起点・組織横断・短期成果と長期価値の両立が不可欠です。
共創は単なる「失敗を避ける仕組み」ではなく、 組織に学びを生み出し、顧客に信頼を育む土壌となります。
おわりに
「どうしてもうまくいかない企画」があるなら、それは共創不足のサインかもしれません。 生活者・顧客・他部門とともに再考することで、新たな成功の芽が芽吹きます。
失敗を恐れるのではなく、共創を通じて学び育てる企画へ。 それこそが、これからの時代に求められる企画の姿なのです。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)