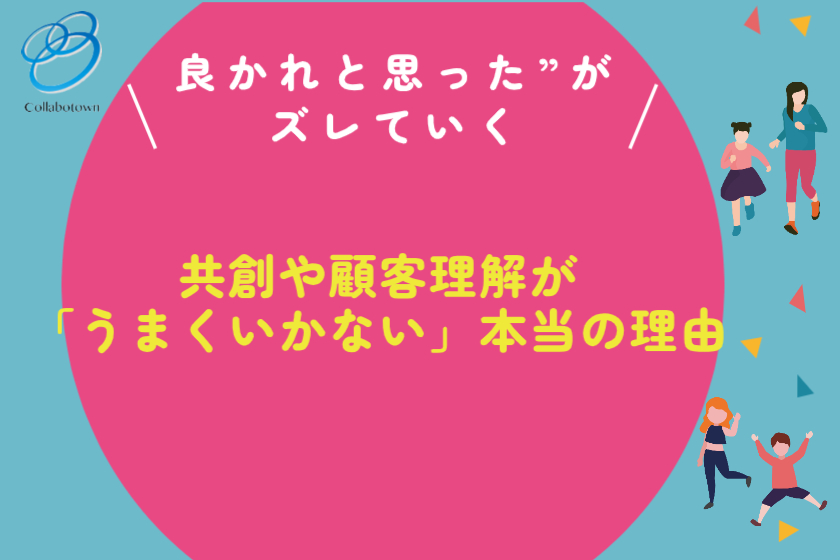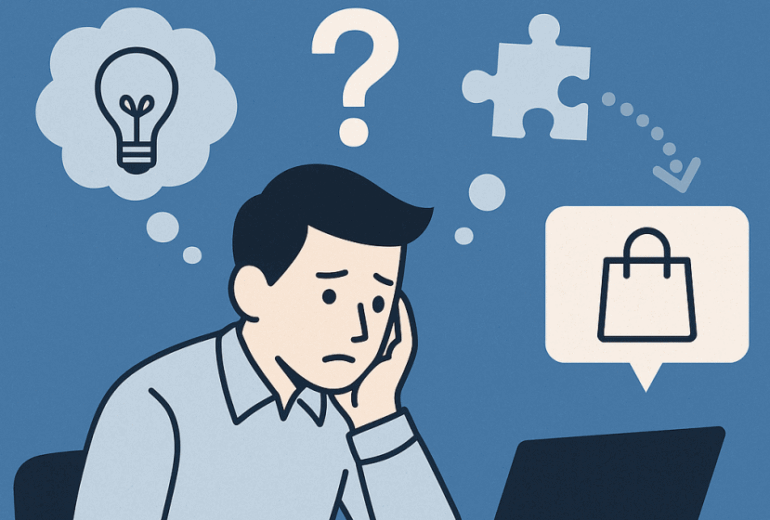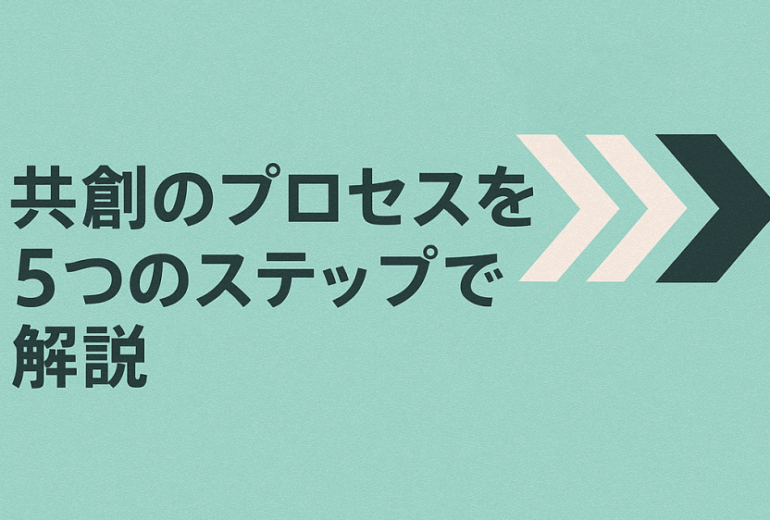この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。
はじめに:「うまくいかない」のは誰のせいでもない
商品開発やサービス改善の現場で、「顧客の声を反映したつもりなのに、反応が悪かった」「アンケート結果をもとにしたのに、売れなかった」という話を耳にすることがあります。
また、共創の場をつくったのに思ったようなアイデアが出てこない、ワークショップを開いたのに参加者が本音を話してくれない──そんな“うまくいかなさ”に直面した経験のある方も多いのではないでしょうか。
一見、正しいはずのアプローチが、なぜか機能しない。
その原因は、やり方が間違っているというよりも、「前提のズレ」や「無意識の誤解」にあることが少なくありません。
この記事では、「共創」「顧客理解」「アンケート」など、一見よさそうに見える取り組みがなぜうまくいかないのかを、よくある誤解のパターンから掘り下げていきます。
第1章:「共創はいいこと」という思い込みが、うまくいかなさを招く
1-1. 共創とは“場”をつくることだと思っていないか?
「共創をやりましょう」といって、ワークショップを開いたり、ユーザーとの座談会を設定したりする企業が増えています。それ自体は素晴らしいことです。
しかし、「場をつくること」が目的化し、「何を共に創るのか?」「誰と、どんな関係性で?」という本質的な問いが抜け落ちてしまうと、単なる形式的なイベントに終わってしまいます。
1-2. “意見”が出れば成功という誤解
「たくさんの声が集まりました!」という報告。でもよく見ると、どれもバラバラの要望で、かえって迷いが深まっていた…そんなことはありませんか?
共創とは「たくさんの声を集めること」ではなく、関係性の中で“意味”を一緒に見つけていくプロセスです。数ではなく、“深さ”と“質”が問われます。
1-3. 企業が“共創するつもり”でも、顧客は“参加しているつもり”でない
共創を仕掛ける側と、参加する側とで、「何を期待しているか」「どんな関わりだと思っているか」がずれているケースも多いのです。
「一緒に考えたい」ではなく、「ちょっと言わせてもらえればいい」というスタンスの参加者に深い対話を期待してもうまくいきません。
第2章:「顧客理解」の罠──聞いているようで、聞いていない
2-1. 顧客の“声”は聞いている。でも、“生活”は見ていない
多くの企業が「顧客視点」を重視しています。しかし、その「視点」は、顧客の言葉レベルで止まっていないでしょうか?
「◯◯がほしい」「△△が不便」といった声の奥には、その人の暮らし方や価値観が隠れています。それを見ずに、言葉だけで施策を決めると、表面的な改良に終始し、「本質的な不満」が置き去りになってしまうのです。
2-2. 顧客の“答え”に頼りすぎていないか?
「この商品は買いたいと思いますか?」「どのデザインが好みですか?」こうした問いは、答えが返ってきやすい一方で、“その人が自分の中で言語化しやすい内容”しか引き出せません。
しかし、生活者のニーズの多くは、未整理で曖昧です。「自分でも気づいていないこと」が本当の欲求であることが多いのです。
ヒアリングでは、“答え”よりも、“迷い”や“矛盾”が出てくる瞬間に注目することが重要です。
2-3. 顧客像(ペルソナ)をつくったら、わかった気になっていないか?
ペルソナの活用自体は有効ですが、それが「想像の中の人」に留まってしまっては意味がありません。
現実の顧客との接点、つまり観察・対話・同行・体験共有といった関係性の中で、常にアップデートしていくべきものです。
第3章:アンケートをとってもうまくいかない“構造的理由”
3-1. アンケートは“限定された問い”の世界
アンケートで得られるのは、あくまで「事前に想定された選択肢」の中からの答えです。つまり、「問いの質」がすべてを決めてしまいます。
本当に知るべきは、「そもそもその問いは適切か?」というレベルの話です。選択肢に現れない感情や生活背景は、そこには表れません。
3-2. アンケートの“回答者”は、本当のユーザーではないかもしれない
- 代理で答えている人
- 興味はあるが購入はしない人
- 「とりあえず答えた」人
こうしたケースが混ざると、サンプル数が多くても“誰の声か”が不明瞭になります。
数値の信頼性ではなく、関係性の明確さの方が、本当の気づきを得るには重要です。
3-3. 数字は「傾向」は教えてくれるが、「意味」は教えてくれない
「〇〇%の人が選びました」は、意思決定の参考にはなりますが、「なぜそう思ったのか」「どんな場面で困っているのか」は数字には現れません。
つまり、アンケートでは“きっかけ”はつかめても、“答え”は得られないのです。
第4章:じゃあどうすればいいのか?──“誤解”を超えていく視点
4-1. 「対話」と「観察」に立ち戻る
生活者のリアルを知るために、遠回りに見えて近道なのが、「一緒に体験すること」です。
- 店頭での買い物に同行する
- 日常の様子を雑談の中で聞く
- 使っている現場を見る
こうした観察・同行・対話の中にこそ、言葉では出てこない“使われ方”や“気持ち”が見えてきます。
4-2. “答えをもらう”のではなく“答えを一緒に見つける”姿勢へ
「顧客が言ってくれたことをそのままやればいい」という姿勢から、「一緒に気づきを育てる関係」へと視点を変えていく必要があります。
つまり、企業と顧客は“受け手と発信者”の関係ではなく、“共に意味をつくる共演者”なのです。
4-3. 「声を拾う」から「文脈ごと聴く」へ
同じ「使いにくい」という言葉でも、
- 忙しい主婦が言うのか
- 高齢者が言うのか
- 子どもと一緒に使っている人が言うのか
では背景がまったく違います。声だけではなく、その人の暮らしごと捉える「文脈理解」が重要です。
おわりに:うまくいかないのは、方法ではなく“前提”のせいかもしれない
この記事で紹介した「共創」「顧客理解」「アンケート」──これらはすべて、正しく使えば強力な武器です。
でも、「共創すればうまくいく」「顧客に聞けばわかる」「アンケートをとれば見えてくる」といった“期待のしすぎ”や“前提の誤解”が、逆に成果を遠ざけてしまうこともあります。
うまくいかないときに見直すべきは、「やり方」ではなく、「そもそも、どんな問いを立てていたか」「どういう関係性で臨んでいたか」というスタート地点です。
答えは、方法論の中ではなく、人と人の間にある“意味のやりとり”の中にあるのかもしれません。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)