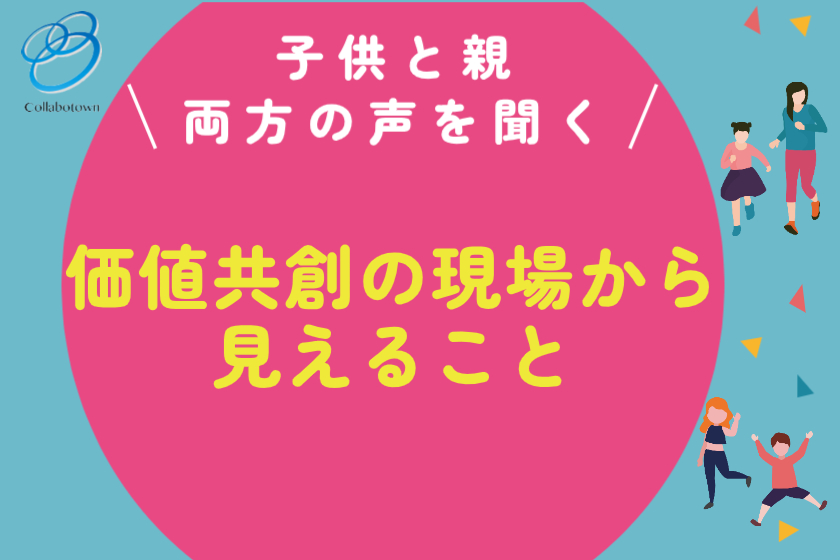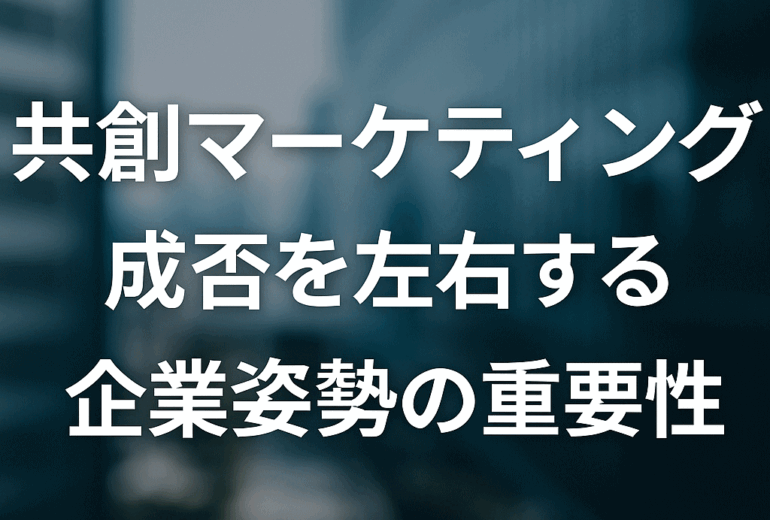実務の位置づけは 価値共創マーケの基本と導入ガイド をご参照ください。
企業の企画担当者が、イベントや店頭で来場者と会話することは珍しくありません。しかし、その会話の中身や順番にまで意識を向けているケースは意外と少ないのではないでしょうか。

子供と目線を合わせ熱心に話を聞く企業担当者。その瞬間、価値共創の種が生まれている。
今回の現場では、担当者がまずしゃがんで子供と目線を合わせ、笑顔で問いかけるところから始まりました。
「この色はどう思う?」「どれが一番好き?」──質問はとてもシンプルです。しかし、その短いやり取りから得られるのは、商品開発において非常に貴重な“生きた情報”です。
さらに印象的だったのは、子供から意見を聞いたあと、すぐに隣にいた親にも感想や考えを尋ねたことでした。
子供と親の両方の意見を同じ場で、連続して聞く──このプロセスこそが、価値共創の実践そのものでした。
購入者と使用者が異なる商品は多い
多くの商品やサービスでは、購入者(親)と実際の使用者(子供)が異なるケースがあります。たとえば、学用品・おもちゃ・自転車・子供服など、生活の中で見慣れたカテゴリーがそうです。
- 購入者の関心: 安全性、価格、耐久性、保管や管理のしやすさ
- 使用者の関心: 色、形、遊びやすさ、友達に見せたくなるデザイン
この2つの価値基準は、しばしば重なりながらも、微妙にズレています。片方だけを見て商品を設計すると「親は満足しているけど子供が喜ばない」または「子供は気に入ったけど親が買わない」という状況が生まれます。
このギャップを埋めるには、両方の声を聞き、統合する視点が不可欠です。
子供の声がもたらす“感覚的価値”
子供は理屈よりも感覚で物事を判断します。今回の会話でも、こんなコメントが出てきました。
- 「この色だと友達に見せたくなる」
- 「もっと軽い方が長く遊べそう」
- 「丸い形だと優しい感じがして好き」
- 「この模様だと、学校に持っていきたくなる」
一見、デザインや色に関する表面的な意見のように思えるかもしれません。しかし、そこには「人に見せたい」「長く遊びたい」「安心感がある」といった、感情や行動につながる本質的なニーズが隠れています。
こうした感覚的価値は、調査票のチェック欄や数値データでは表現しにくく、現場の対話だからこそ引き出せる情報です。
親の声がもたらす“現実的価値”
続いて親の意見を聞くと、まったく異なる視点が見えてきます。
- 「丈夫で長く使えるなら少し高くてもいい」
- 「家の収納スペースに入るサイズじゃないと困る」
- 「安全面がしっかりしていれば色は多少派手でも構わない」
- 「洗える素材だと助かる」
親のコメントは、生活の中での実用性やリスク管理に直結しています。
ここで重要なのは、親の意見は“理性的な基準”として商品の購入可否を大きく左右するということです。
二重のヒアリングが生む“価値の交差点”
この現場で行われていたのは、単なるアンケートではなく、連続した二重のヒアリングでした。
- 子供の直感的な声を先に聞く: 素直な感情や使用感のヒントを得る
- その後、親の現実的な声を聞く: 購買条件や制約、安心感の条件を把握する
この流れによって、開発側は「理想と現実の接点」を見つけやすくなります。
例えば──
子供:「もっと色を増やしてほしい」
親:「派手すぎると部屋に合わない」
→ 解決策:「落ち着いた色味のカラーバリエーションを追加する」
なぜ現場での“同時ヒアリング”が価値共創になるのか
マーケティングの理論でいえば、このプロセスはマルチステークホルダー共創の一形態です。
異なる立場の人々(使用者・購買者)が同じ場にいて、互いの意見を聞きながら企業が開発のヒントを抽出する──これは価値共創マーケティングの核心そのものです。
未来の顧客関係づくりにもつながる
この取り組みは、単なる商品の改善だけでなく、ブランドとの長期的な関係形成にも効果を発揮します。
- 子供にとって: 「自分の意見を大人が真剣に聞いてくれた」という成功体験は、記憶に残る
- 親にとって: 「この企業は顧客の声を大事にする」という信頼感が芽生える
こうした経験は、将来その子供が大人になったとき、またその親が別の商品を選ぶときのブランド選好に影響します。
★ マーケティングリサーチと価値共創の決定的な違い ★
一見すると、この親子への連続ヒアリングは「現場型のマーケティングリサーチ」に見えるかもしれません。しかし、価値共創の現場では単に意見を集めるだけでなく、その場での相互作用や発想の化学反応を重視します。
たとえば、子供が発したひと言に対して親が「そういえば…」と補足を入れる。その補足を聞いた担当者が「ではこんな案は?」と即座に提案し、さらに子供が「それならこうしたい」と返す──この瞬間に、アンケートや事前設計の調査票では絶対に生まれない価値の連鎖が起こります。
- 調査: あらかじめ決められた質問項目に沿って情報を収集する
- 価値共創: その場のやりとりから新しい問いや発想が立ち上がる
この違いは、単なるデータの収集か、未来の価値を共に“創り出す”のかという、本質的な目的の差にあります。
“場”が生む無形の資産
価値共創の場では、参加者同士の関係性や企業との距離感が変化します。
子供が「自分の意見を聞いてもらえた」と感じること、親が「この企業は耳を傾けてくれる」と実感することは、数値化できないけれど確実に蓄積される無形資産です。
これは単発の調査結果とは異なり、ブランドへの信頼や愛着を長期的に育てる土壌となります。次に新商品やサービスを提案する際、この関係性が大きな力を発揮します。
“未来の共創者”を育てるプロセス
マーケティングリサーチは多くの場合「今の意見」を集めます。一方、価値共創では、参加者が未来の発想や次の改善アイデアにも関わりたくなるような関係づくりを意識します。
- 子供:次も意見を言いたくなるポジティブな記憶
- 親:企業と一緒に考える面白さを体験
- 企業:単発ではなく継続的な対話の土台を構築
このように、価値共創は「意見を集めて終わり」ではなく、次の共創を呼び込む循環を生み出す点で、調査とは決定的に異なるのです。
まとめ
- 子供の感覚的価値 × 親の現実的価値 = 新しい商品価値
- 両者の声を同じ場で聞くことで、理想と現実の接点が見える
- この体験は短期的な売上だけでなく、長期的なブランド信頼にも貢献
価値共創は、大規模なプロジェクトや長期間の研究だけで生まれるものではありません。
目の前の一組の親子と向き合い、順番に耳を傾ける──その小さな行為が、未来の大きな価値を育てる第一歩なのです。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)