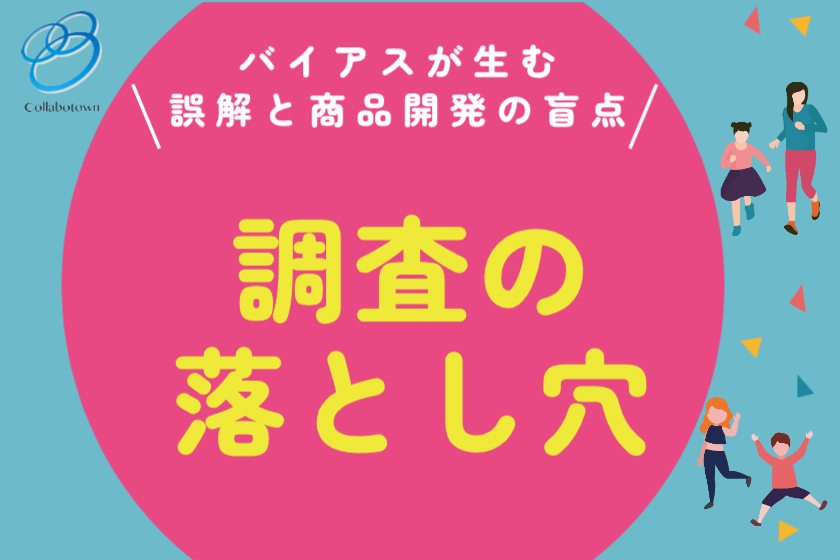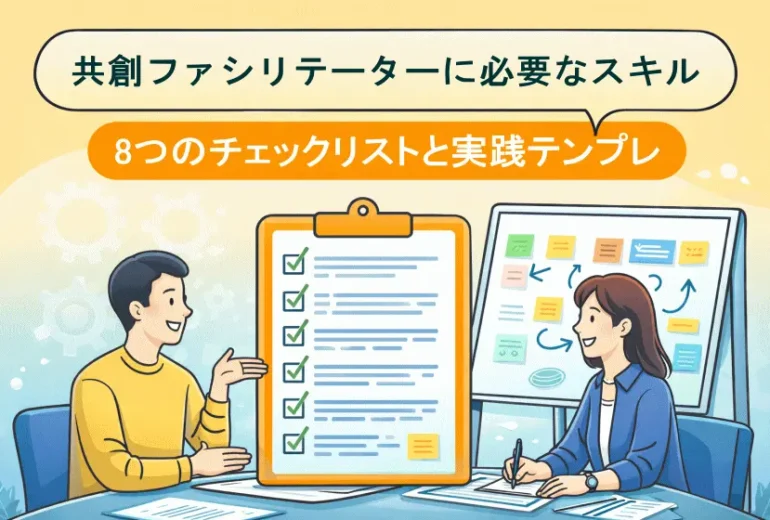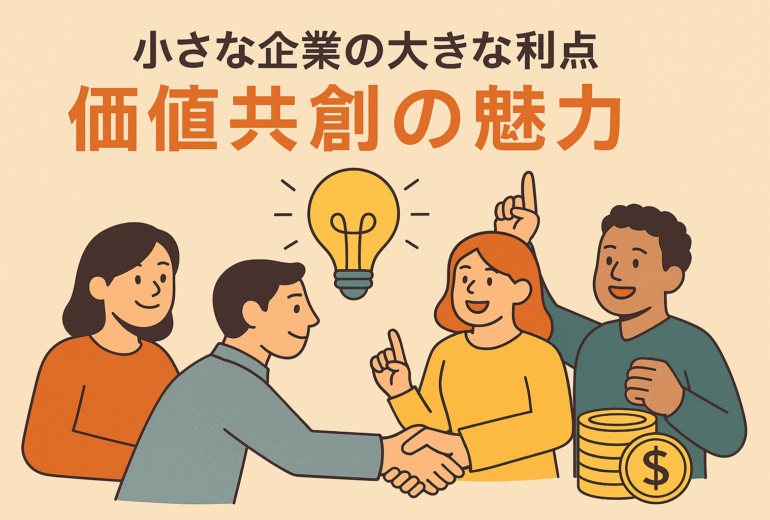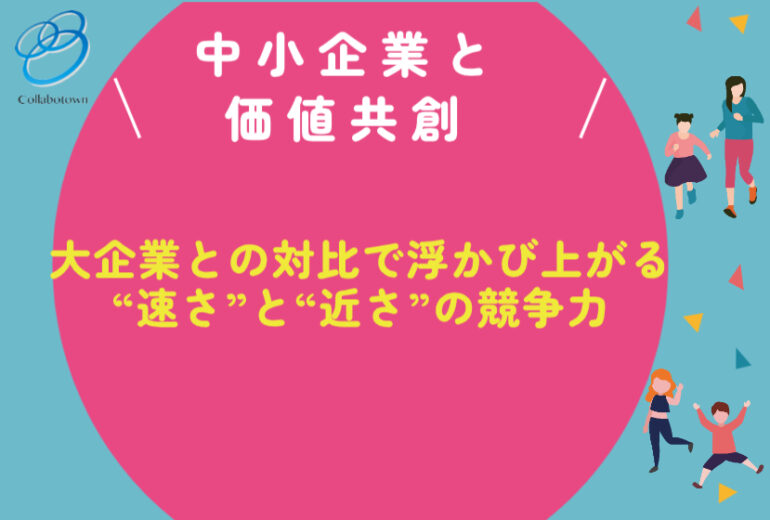この記事は 価値共創マーケティングの全体像 の一部を掘り下げています。
商品開発において、購入意向調査やコンセプト検証は欠かせないステップです。生活者のニーズや反応を把握し、開発の方向性を定めるうえで大切なプロセスといえるでしょう。
しかし、調査設計や進め方を誤ると、思わぬ落とし穴に陥ることがあります。とくに注意したいのが、調査対象者に“過剰な情報”を与えてしまうことによるバイアスです。今回は、その典型的な失敗パターンと、企業が陥らないための視点について解説します。
情報を与えすぎると、購入意向は高く出る
調査では、「商品名」「カテゴリー」「開発意図」「ターゲット」「背景ストーリー」など、商品に関する詳細な情報を最初から提示してしまうことがあります。一見、親切な設計のように思えますが、これは非常にリスキーです。
情報を与えすぎることで、調査対象者は商品をより深く理解しようとし、“自分にとって有用そうだ”と好意的に感じやすくなります。結果として、購入意向が実態以上に高く出る傾向があります。
このような数値を鵜呑みにしてしまうと、商品開発の判断を誤り、発売後に「思ったより売れなかった」という結果を招くことも少なくありません。
“共感”と“違和感”を見逃さないために──数値の裏にある本音を読み解く
購入意向が高いという調査結果は、たしかに心強く映ります。しかし、その数字だけを表面的に捉えてしまうと、肝心の「なぜ評価されたのか」「どこにひっかかりがあるのか」という深層の手がかりを見落としてしまいます。
例えば、「買いたい」と答えた人が本当に“自分のお金を使って買いたい”と感じているのか、それとも“言われてみれば良さそう”という程度の感覚なのか。その温度感の違いを見極める視点が欠けていると、共感が強かった要素が曖昧なまま、商品が市場に出されてしまいます。
また、購入意向が高くても、商品に対して「惜しい」「もう少しこうだったら…」という小さな違和感や、期待に対してのズレを感じていた可能性もあります。これらの“声にならない声”を丁寧に拾わなければ、改善すべきポイントがわからないまま開発が進んでしまいます。
つまり、コンセプトや訴求ポイントを磨き込む上で本当に重要なのは、数値そのものではなく、「なぜその評価になったのか?」という“理由”や“背景”を把握することです。
生活者が何に価値を感じたのか──価格、デザイン、世界観、ストーリー、機能、安心感、社会的意義など──その内訳を分解して捉えることで、訴求軸をクリアにし、プロダクトのポジショニングを明確にすることができます。
同時に、たとえ少数であっても否定的な反応や不安の声があった場合には、その原因を探ることも極めて重要です。否定的意見の中にこそ、コンセプトの曖昧さや言語化しきれていない課題、誤解される要素が潜んでいることが多くあります。
調査とは“数字を集めること”ではなく、“価値の所在とズレを炙り出すこと”。数値の奥にある共感の源泉と違和感の種を見逃さないことが、商品開発の精度を大きく左右するのです。
調査の本質は“答えを得る”ことではなく、“問い直す”こと
マーケティングリサーチやコンセプト検証において、しばしば「正解を得るための場」と捉えてしまうケースがあります。しかし、調査とは決して“評価を得るための発表会”ではなく、仮説の妥当性を検証し、必要であれば大胆に見直すためのプロセスであるべきです。
「自社の考えたコンセプトは合っているか?」「生活者にとって意味のある価値を提供できているか?」──こうした問いに対する“気づき”を得るのが、調査の本質的な役割です。つまり、調査はゴールではなく、“次の問いを導き出す出発点”なのです。
そのためには、調査対象者に提示する情報の質と量に細心の注意を払う必要があります。あらかじめ商品名やブランドイメージ、企業メッセージ、開発背景などを伝えてしまうと、それらの情報が先入観となってしまい、生活者本来の直感的な判断や感情が上書きされてしまいます。
そこで有効なのが、「情報を削ぎ落とした調査設計」です。たとえば:
- ● あえて商品名を伏せて、ニュートラルな状態で印象を聞く
- ● 利用シーンだけを描写して、そこから感じた価値や違和感を尋ねる
- ● 競合製品と並べて評価してもらい、相対的な強み・弱みを浮き彫りにする
このように、先入観を排除した状態での“素の反応”を引き出す工夫が、生活者のリアルな判断を捉えるカギとなります。
さらに、「なぜそう感じたのか?」「どの点にひっかかりを覚えたか?」といったオープンエンドの質問を設けることで、数字だけでは見えない感情の揺らぎや背景のストーリーが浮かび上がってきます。こうした本音や迷い、不完全な表現の中にこそ、価値あるインサイトの芽が眠っています。
重要なのは、良い結果を得ることではなく、“仮説に対する違和感”や“曖昧さ”をあぶり出すこと。それによって、「私たちは本当に、生活者の価値観に寄り添っているのか?」という問いを、何度でも立ち戻って考えることができます。
調査は“自社の答え合わせ”の場ではありません。生活者のリアルを映し出す“対話の鏡”として活用することで、開発・マーケティングの軸足を確かなものにしていけるのです。
開発に進む前に確認したい3つの視点
調査結果を受けて商品開発に進む際は、次の3点を必ず確認しましょう。
- ● どこに共感が集まったのか?
価格、デザイン、ストーリー性など、具体的な価値ポイントを明確にします。 - ● どんな不満や違和感があったのか?
ポジティブな評価の裏に隠れた“不満”や“気になる点”にも注目します。 - ● 実際の行動と合致しているか?
「買いたい」と「買う」は別物。使用シーンや購買優先度も見極めが必要です。
この3点を丁寧に読み解くことで、コンセプトの磨き込みやコミュニケーション設計において“選ばれる理由”を明確にできるようになります。
まとめ:調査は「未来をつくる問いの鏡」
調査の落とし穴は、調査の場での高評価に安堵してしまうことです。実態を見誤り、的外れな商品が完成してしまっては、本末転倒です。
調査とは、答えを得る場ではなく、「本当にこの方向でいいのか?」を問い直すための鏡のような存在。生活者の生の声を正しく拾い、開発や訴求の“意味”を再確認することが、共感商品につながる第一歩です。
調査の限界を補い、本質的な価値に迫るためには、生活者を“調査対象”ではなく“共創パートナー”と捉える視点も重要です。
今後は、調査だけで完結させるのではなく、価値共創のアプローチ──たとえばワークショップやプロトタイプ共創など──を組み合わせることで、より深く生活者と価値を築く選択肢を持ってみてはいかがでしょうか。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)