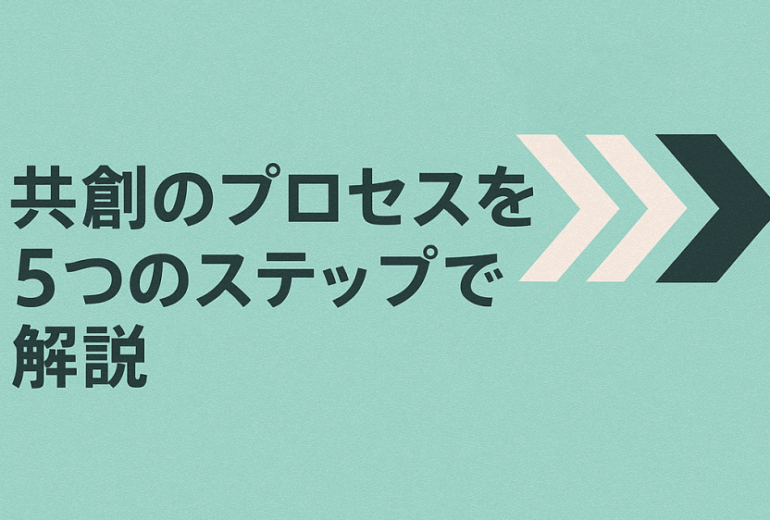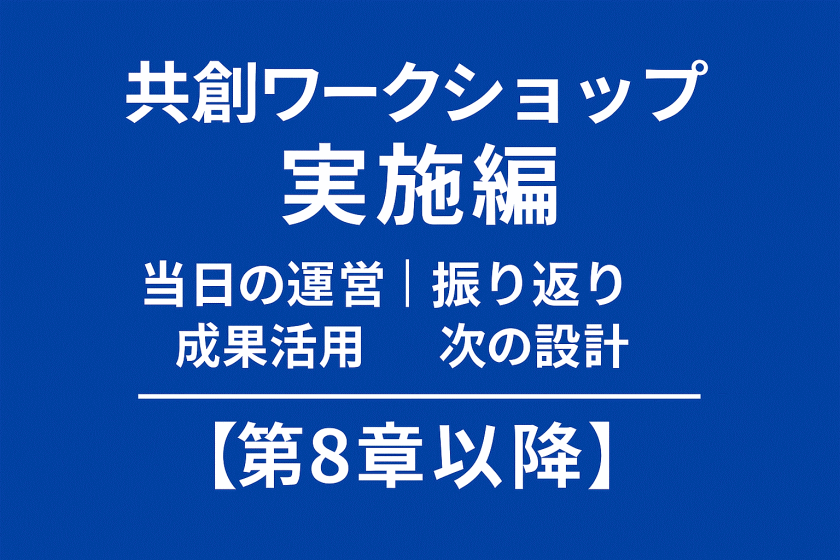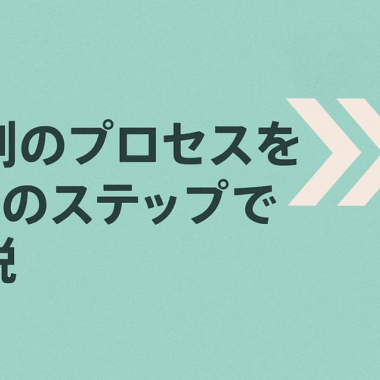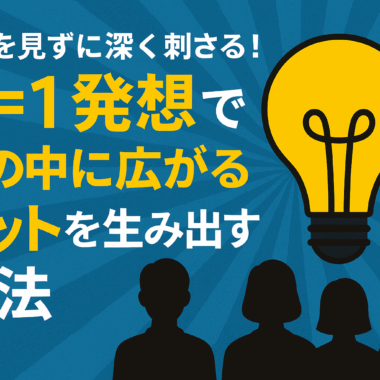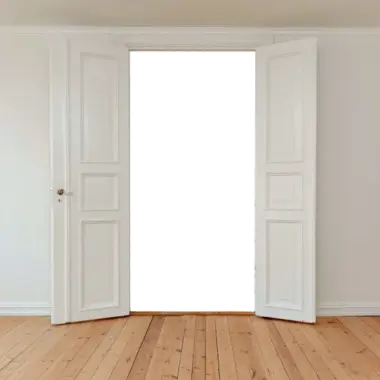📌 本記事は「中小企業の共創導入ガイド」後半にあたる【実施編】です
共創導入の全体像を整理したい方は、まず 中小企業の共創導入ガイド(準備〜設計) をご覧ください。
共創ワークショップ実施編|当日の運営・振り返り・成果活用・次の設計【第8章以降】
当日の「場づくりと進行」→「振り返りと記録化」→「成果活用と展開」→「次の設計」まで、実務で迷いがちなポイントをチェックリスト形式で整理しました。
第8章:セッション当日の運営
予定通りより、意味ある対話。心理的安全性・問いの設計・記録体制を重視し、柔軟に運営します。
当日のチェックリスト
- 目的と姿勢の再共有(運営チーム朝会で 5 分)
- ウェルカム設計(導線案内・ボード・軽い雑談)
- オリエンで共創の意義と期待行動を明示
- アイスブレイクで関係性の土台づくり
- 発言バランスの構造化(個→ペア→G→全体)
- 問いの深度調整(価値観⇄経験⇄具体⇄意味)
- 記録担当と合図・粒度の事前取り決め
- 終盤の言葉選び(次回への期待をつくる)
第9章:セッションの振り返りと記録化
熱があるうちに、言葉+文脈として記録。1枚レポートで共有までやり切る。
直後 24 時間のToDo
- 発言・表情・場の変化をメモ(ファシ観察メモ)
- 付箋・模造紙・ホワイトボードの写真撮影と整理
- 3〜5分アンケート(印象・話しやすさ・改善点)
- A4一枚の振り返りレポート(要点+写真+次アクション)
- データの分類保存(案件/テーマでフォルダ化・タグ化)
- 社内共有会(未参加部門含む)を速やかに設定
第10章:成果活用と社内展開
記録で終わらせない。小さく試し、横展開し、物語で伝える。
活用ステップ
- 言語化と構造化(価値仮説・示唆・判断の根拠)
- 横展開(開発/営業/CSなどへの共有会)
- 小実験(1店舗・1チャネル・1施策で試す)
- ストーリー共有(エピソード+変化の可視化)
- 経営層への報告(数値+組織学習の視点)
- 参加者への成果報告(フィードバックの徹底)
- 社外発信(ブログ・SNS・PR)で信頼を育む
第11章:次の共創の設計
単発で終わらせず、問いの更新と参加設計の見直しで継続を設計。
設計の要点
- 振り返りから次の「問い」を抽出
- 目的を段階再定義(気づき→試作→検証 など)
- 生活者視点のテーマ再構築(誰のどの声起点か)
- 参加者ペルソナの更新(再招集か新規開拓か)
- 体制・役割・ロードマップの再設計
- 前回との違いを意図的に(進行/問い/メンバー)
- 社会・生活者の変化を踏まえたテーマ更新
最終章:共創を文化へ──まとめと総括
- 共創は「関係づくり」であり「価値づくり」
- 成果の質は、準備と丁寧な運営に宿る
- 横断連携と経営の後押しが器を支える
- 継続の中で学習が深化し、共創文化が根づく
- 物語としての共有が共感と推進力を生む
共に創る。そこに、企業の未来がある。
まずは小さく試し、学びの循環を作る。
30分の無料オンライン相談で、御社に合わせた導入計画(3か月モデル)をご提案します。
このテーマの関連ガイド
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)