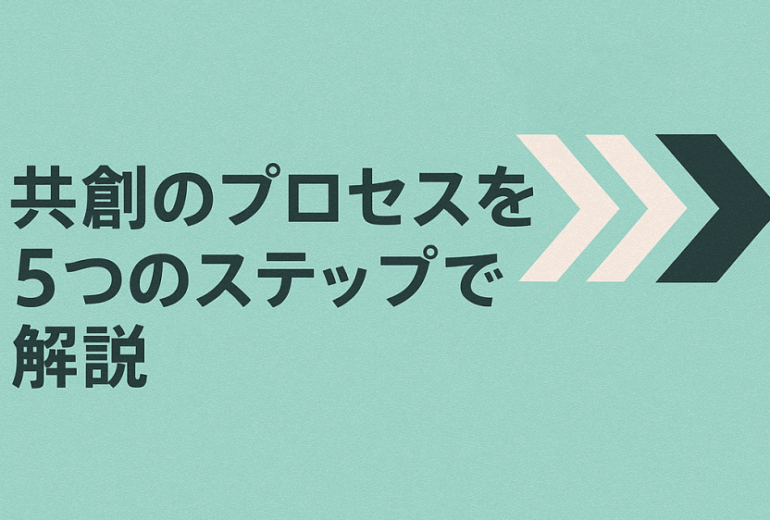Customer Participation × Co-Creation
顧客参加型の商品企画・商品開発とは?
価値共創マーケティングの実践ガイド
顧客の声を“聞く”だけでなく、“いっしょに作る”。顧客参加型(参加型開発)を価値共創マーケティングの実務に接続し、小さく始めて成果へつなげる進め方をテンプレート付きで解説します。
この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)の一部を詳しく解説したガイドです。
この記事の要点(3行)
- 顧客参加型=価値共創の実践。違いは“呼び名”と“視点”。
- まずは5つの手順で、小さく試しながら前に進む。
- 匿名でも伝わる事例フォーマットで成果を残す。
用語ミニ辞書(3つの言葉をシンプルに)
- 顧客参加型
- お客さまが企画や開発の段階から関わるやり方。アイデア出し・試作品づくり・オンラインでの共創など。
- 価値共創(共創マーケティング)
- 会社とお客さまが力を合わせて価値を作る考え方。参加の設計、学びの回し方、社内の進め方まで含む枠組み。
- 共創ワークショップ(共創WS)
- 観察→体験→対話でお客さまの言葉を引き出し、小さな試作につなげる場。会議ではなく“学びの場”。
1. 顧客参加型と価値共創の関係
同じ現場でも呼び名が違うだけ——手段名(顧客参加型)と考え方(価値共創)をひとつの流れとして扱います。
顧客参加型を探す人
やり方・事例・期間・人数・ざっくり費用。現場の担当者。
価値共創を探す人
考え方・効果・導入の順番・社内の巻き込み。責任者/経営層。
つなぎ方(本稿)
小さく試し、学びを製品や体験に反映する手順を提示。
本文中に「顧客参加型」「価値共創」「共創ワークショップ」「生活者参加」の語を同じ段落で自然に使うと、検索エンジンにも関係が伝わります。
顧客参加型(やり方) → 共創の場(ワークショップ) → 学び → 試作 → 改善
↑ │
└────────── 価値共創(考え方) ──────────┘
今日やること
- 自社サイトや資料で「顧客参加型」「価値共創」を同じ段落に1回ずつ入れてみる。
2. 向いているテーマ/向かないテーマ
まずはやりやすい土俵を選ぶのが近道。成功しやすい場面と注意が必要な場面を先に共有します。
◎ 向いている
- 使い心地や気分が差を生む(日用品、食品、雑貨)
- 使い方が人によって違う(BtoBツール、SaaS、家電)
- “価格以外の選ばれる理由”を作りたい新製品
△ 向かない(留意)
- 法規や安全規格で自由度がほぼないもの
- 情報秘匿が必須で外部参加が難しいもの
- 完成度が高く検証余地が少ない微修正案件
3. 進め方(HowTo)5ステップ
悩んだらこの順で。目的→参加者→セッション→試作→改善のミニサイクルで“まず1周”。
① 目的と仮の答えを決める(2h)
「誰の・どんな場面・何を良くするか」を1文で。数の目標(例:購入率)と感じ方の目標(例:使用後の安心感)をセットで置く。
② 参加者を設計・募集(1〜2週)
既存のお客さま+まだ使っていない人を混ぜて異なる視点を確保。募集文は「期待する役割」と「NG(売り込みなし)」を明記。
③ 共創セッション実施(1日×1〜2回)
観察→体験→対話の順で、“気になったことメモ”と“気づきカード”で発言を可視化。中立進行でお客さまの言葉を採掘。
④ 小さく試作・検証(1〜3週)
アイデアを簡易な試作品に。アンケートに頼らない観察視点で行動を再確認。
⑤ 改善・展開(継続)
うまく働いた点・直したい点を1枚に整理。次のラウンドに反映。
[目的・仮の答え] → [参加者設計・募集] → [共創セッション] → [試作・検証] → [改善・展開]
│ │ │ │
└──── 数の目標と感じ方 ───┴── 視点の違い ───┴─ 観察→体験 ───┴── 行動で確かめる
今日やること
- 1文の目的を書く:「誰の・どんな場面・何を良くするか」。例)子育て中の家庭の“夕方の洗い物”で、手肌のつっぱり感を減らす。
4. 共創ワークショップ設計のコツ(現場の型)
安心して話せる場の宣言
否定しない・点数をつけない・完成を求めない。最初にルールを言葉で伝える。
観察→体験→言葉にする
“先に会議”は避ける。行動を見て、小さく体験してから言葉にする。
中立進行
社内の進行でもOK。お客さまの違和感を言葉にする力を重視。
可視化ツール
気になったことメモ/気づきカード/価値マップなど、判断材料を見える化。
設計の詳細は共創ワークショップ設計テンプレートも参照。
今日やること
- 次回の打合せ冒頭に3つのルール(否定しない・点数をつけない・完成を求めない)を宣言する。
5. 事例フォーマット(匿名で見せる工夫)
具体商品名を出せない場合でも、“プロセスと学び”で伝わります。以下の型で統一を。
- 背景:市場状況/課題(価格競争・機能訴求の限界 など)
- 目的:数の目標+感じ方の目標
- 実施:参加者構成/観察と体験/ワークの流れ
- 気づき:お客さまの言葉(匿名引用)
- 打ち手:パッケージ・体験・コピーの変更点
- 結果:売上・申込・満足度などの変化
- 学び:再現できる“効いた要因”
今日やること
- 過去案件の1つをこの型に沿って200字で要約してみる。
6. つまずきやすいポイントと対策
× 話し合いだけで終わる
→ 小さく試作し、行動で確かめる。口頭合意で終わらせない。
× 同じタイプの人ばかり
→ 既存顧客+まだ使っていない人を混ぜ、視点の違いを入れる。
× すぐ“売れるか”判定
→ 早い段階では学びの獲得を重視(理解・好意・使ってみたい気持ち)。
× 事例を外に出せない
→ 匿名フォーマットでプロセスと学びを示す。
今日やること
- 次の回で試せる小さな実験を1つだけ決める(例:言い回し変更のA/B、色の比較、使い方の順番変更)。
7. よくある質問(FAQ)
顧客参加型と価値共創の違いは?
BtoBでも有効ですか?
期間の目安は?
社内の進行役でも大丈夫?
費用感は?
「顧客参加型」を自社版にカスタムしませんか?
💡 無料オンライン相談共創マーケティングに役立つ無料資料
「共創マーケティング導入」「インサイト発見」「成果活用」など、 実務に役立つ資料を複数ご用意しています。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ