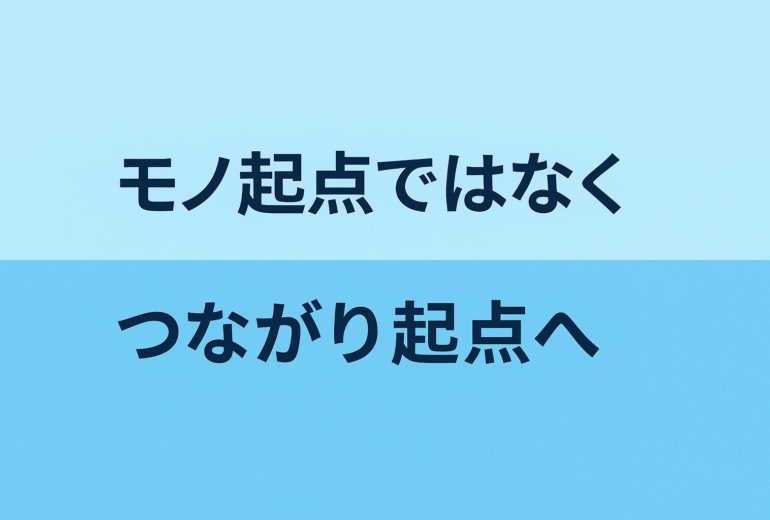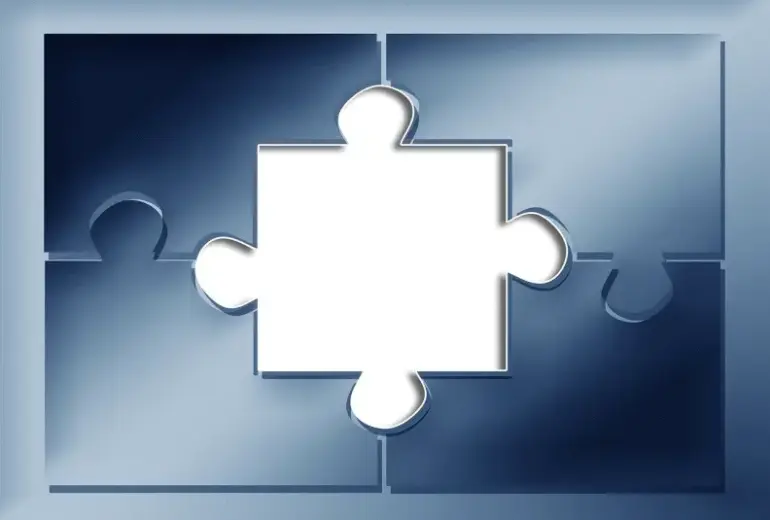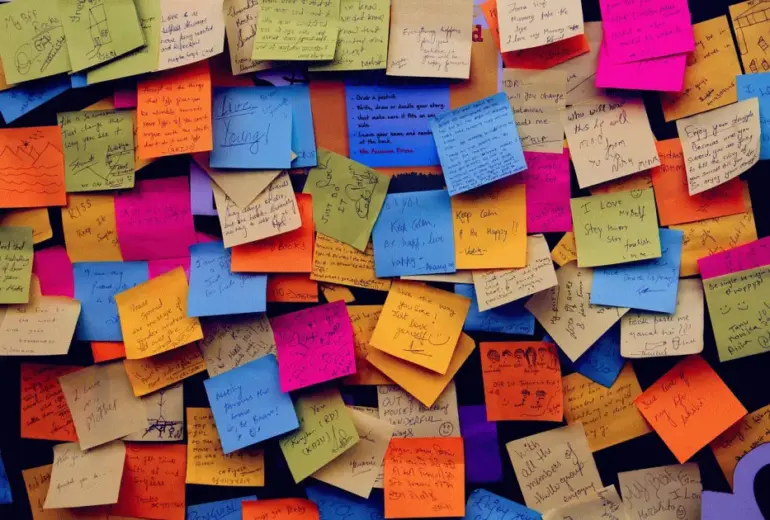変化の激しい時代に、モノよりも「共感」が人を動かすキーワードになりました。
本記事では、共創マーケティングを通して“共感力”を育む方法を、時代背景と実践の両面から解説します。
まず押さえる要点(3行)
- 今は「機能・価格」より“共感できる理由”が選ばれる基準になりやすい
- 共創マーケは対話の中で共感力が鍛えられる実践型のアプローチ
- 共感は“感情移入”ではなく、相手の文脈を理解し価値に翻訳する力
価値観が揺れ動く時代──「共感」が選ばれる基準になった
新型コロナをきっかけに、私たちの生活や価値観は大きく変わりました。
外出や対面の消費が減る一方で、「自分の心が納得できる選択」を重視する人が増えています。
巣ごもり消費・ネット通販・動画配信サービスの普及は、単なるライフスタイルの変化ではなく、
「何に時間とお金を使うか」への問いを生活者の中に生み出しました。
コロナが変えたのは“行動”だけではなく、“価値の感じ方”でした。
いまの生活者は、「安い」「便利」だけでは動きません。
そこに共感できるストーリーや想いがあるか──それが、選ばれる決め手になっています。
共感が求められる理由(現場で起きていること)
- 情報が多すぎる:比較するほど迷う → “心が動く理由”が決め手になる
- 価値観が細分化:平均像が消える → “誰に刺さるか”が重要になる
- 信頼が希少:広告だけでは信じない → “姿勢”や“関係”が評価される
人口データでは捉えきれない「心の多様化」
これまでのマーケティングでは、年齢・性別・所得などのデータで市場を分類してきました。
しかし今や、同じ30代でも「旅に生きる人」「地元を守る人」「推し活に情熱を注ぐ人」など、
価値観の軸そのものが無数に分かれています。
もはや「平均的な生活者像」は存在しません。
重要なのは、“誰の共感を得るか”を見極めることです。
マーケティングの焦点は「属性」から、「どんな人が共感してくれるか」へ。
だからこそ、これまでの「正解探し型(調査→結論→押し出し)」では、変化のスピードに追いつけません。
相手の立場に立ち、想像力を働かせる共感力が、組織の競争力になっていきます。
共感力を育む──共創マーケティングというアプローチ

従来のマーケティングでは、企業がニーズを調査し、商品を一方的に開発していました。
しかし、変化の早い時代にはそのやり方では生活者の心をつかめません。
そこで注目されているのが「共創マーケティング」。
商品づくりの初期段階から生活者と対話を重ねながら、“ともに考え、ともに形にする”プロセスです。
対話の中で、自分も生活者も気づいていなかった本当のニーズが見えてきます。
その過程で自然に磨かれていくのが「共感力」です。
共感力は、机の上では育たない。
人と人の対話の中で、初めて芽を出す。
これはデザイン思考の「共感ステージ」とも重なります。
“相手を理解する努力”が、創造の出発点になるのです。
共感を“価値”に変える:共創マーケの設計ポイント
共感は、ただ「気持ちが分かった」で終わると成果につながりません。
共創マーケでは、共感を価値(提案・体験・言葉)へ翻訳していく設計が重要です。
① 文脈を聞く
「何を」より「なぜそうしたか/どんな状況だったか」。体験の前後を掘る。
② 感情を言語化
嬉しい/不安/面倒/誇らしい…“感情の名前”が、価値のヒントになる。
③ 価値に翻訳
感情を「提案」に変える。誰のどんな場面で助かる?を言葉にする。
共創の場で使える「共感を深める問い」
- それが起きたとき、一番困った(嬉しかった)のは何でしたか?
- その場面で、本当はどうしたかったですか?
- もし理想が叶うなら、何がどう変わると思いますか?
- 同じ状況の人に、どんな言葉をかけたいですか?
共感は「気持ち」ではなく、「相手の世界の見え方を理解する力」。
そこから“選ばれる理由”が立ち上がります。
SNS時代における“共感”の力
情報が溢れる現代では、人々は「自分が共感できる情報」しか受け取らなくなっています。
つまり、共感されない情報は届かない時代です。
SNSの“いいね”やシェアの背景には、「この考えに共感する」「この姿勢が好き」という感情があります。
企業がどんなに発信しても、共感を得られなければ拡がりません。
共感される発信の共通点
- 主語が「会社」ではなく「生活者の物語」になっている
- 成果だけでなく、迷い/葛藤/工夫など“過程”が見える
- 売り込みより、姿勢(大切にしていること)が伝わる
共感されにくい発信の落とし穴
- 正しさだけを押し付ける(生活者の現実が抜ける)
- 抽象的で、自分ごと化できない(場面が浮かばない)
- “いい話”で終わり、行動のヒントがない
マーケティングとは、顧客の共感を得るための活動。
共感力のある企業ほど、人の心を動かす発信ができます。
共感は単なる感情移入ではありません。
他者の視点で世界を見ようとする「想像力」であり、結果としてブランド信頼を育てる源になります。
明日からできる:共感力を鍛えるトレーニング
共感力は“センス”ではなく、日々の習慣で鍛えられます。
ここでは、忙しい現場でも取り入れやすい方法を4つ紹介します。
① 事実→感情→価値でメモする
聞いた話を「何が起きた/どう感じた/何が大事」に分けるだけで、洞察が増えます。
② “前後”を必ず聞く
その行動の前に何があった?終わった後どうなった?で文脈が見えます。
③ 一言要約で確認する
「つまり◯◯ということですか?」で認識ズレを減らし、深い話が出やすくなります。
④ 週1で“共感の振り返り”
「最近、誰のどんな気持ちが理解できたか」を振り返ると、共感の筋肉が育ちます。
共感とは、相手を理解しようとする勇気。
共創とは、その勇気を行動に変える力です。
よくある質問(FAQ)
共感と迎合(何でも合わせる)は違いますか?
共創では、共感で理解したうえでより良い選択肢を一緒に探す姿勢が大切です。
共感されるブランドになるには何から始めれば?
共創の対話で文脈を集め、言葉を整え、発信と体験に落とし込むと、軸がブレにくくなります。
SNS発信が苦手です。共感が伝わるコツは?
「誰のために/どんな場面で/どんな気持ちを救うか」を一文で入れるのも効果的です。
まとめ──“共感”から始まる新しい価値づくり
- データだけではなく、心の文脈を理解すること
- 対話を通じて、共感力を磨くこと
- 共感が企業と生活者の橋になり、信頼を育てること
現代の「共感」は、感情的でありながらも利他的です。
エシカル消費や社会貢献を通して、「共に良くなりたい」という気持ちが購買行動の中心にあります。
企業が「自社さえ良ければいい」という発想を捨て、
お客様の幸せや社会の課題解決に共に向き合うとき、本当の意味で“共感されるブランド”が生まれます。
共感力を育てることは、ビジネスを超えて、人と人が信頼でつながる社会をつくること。
それが、こらぼたうんが目指す“価値共創”の原点です。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)