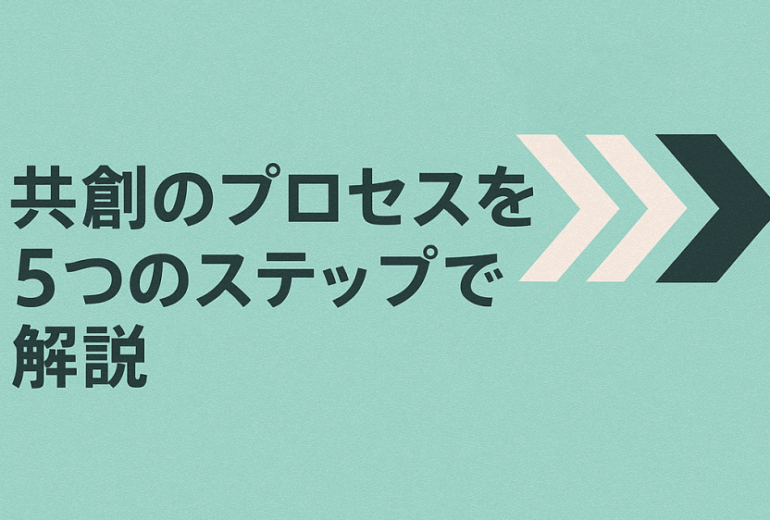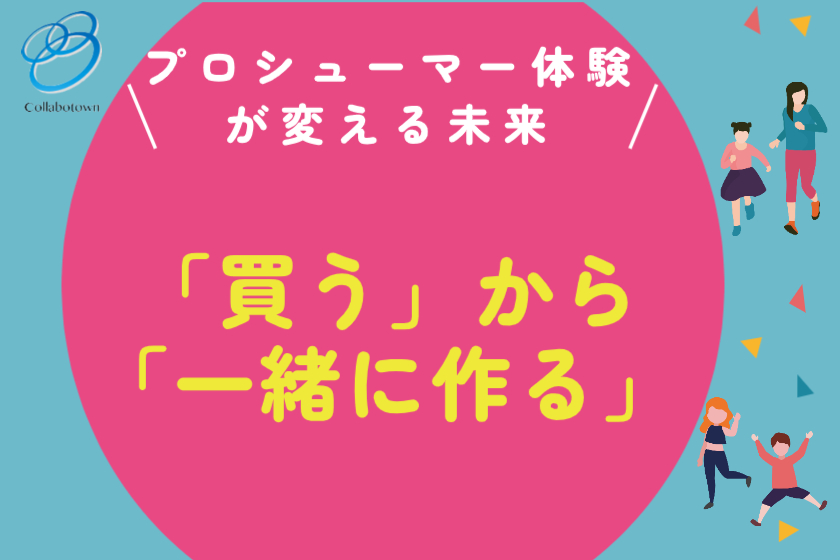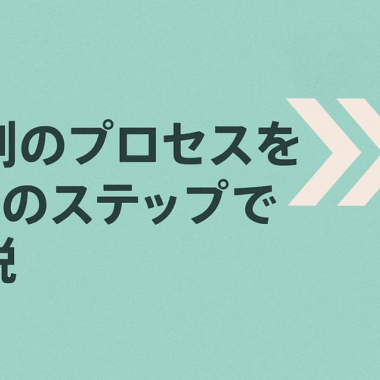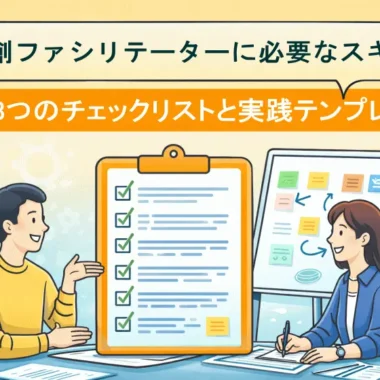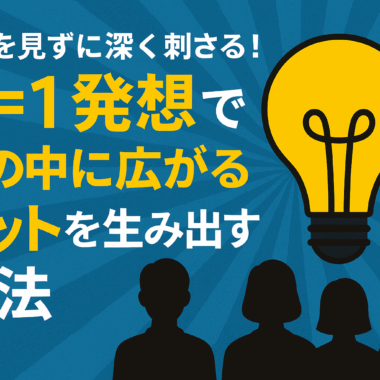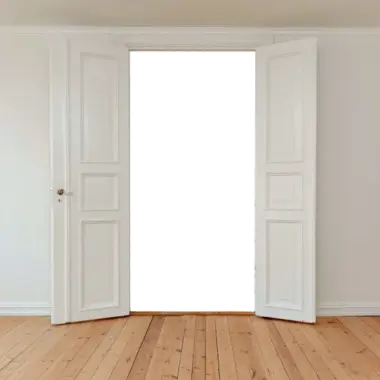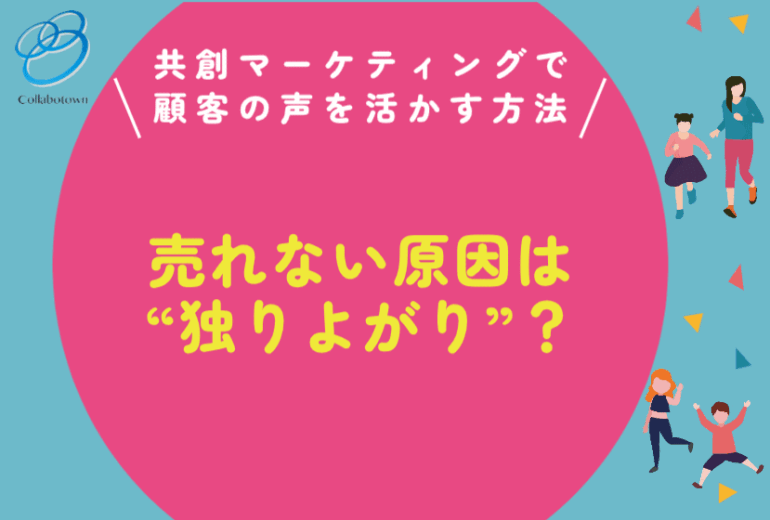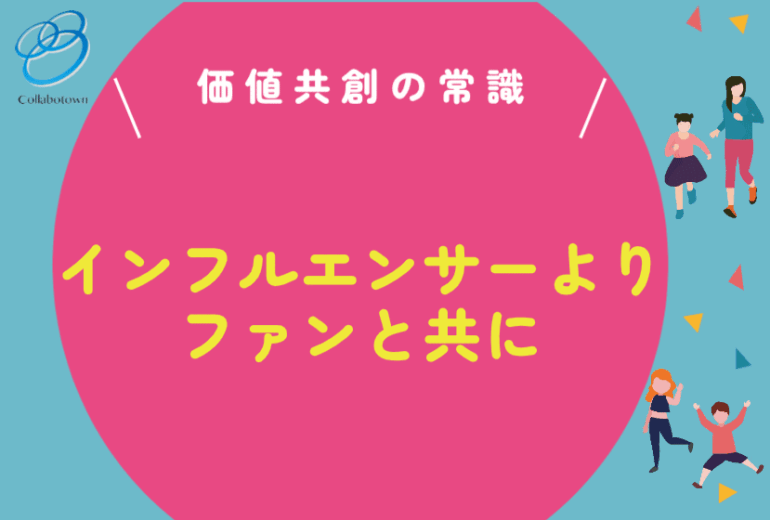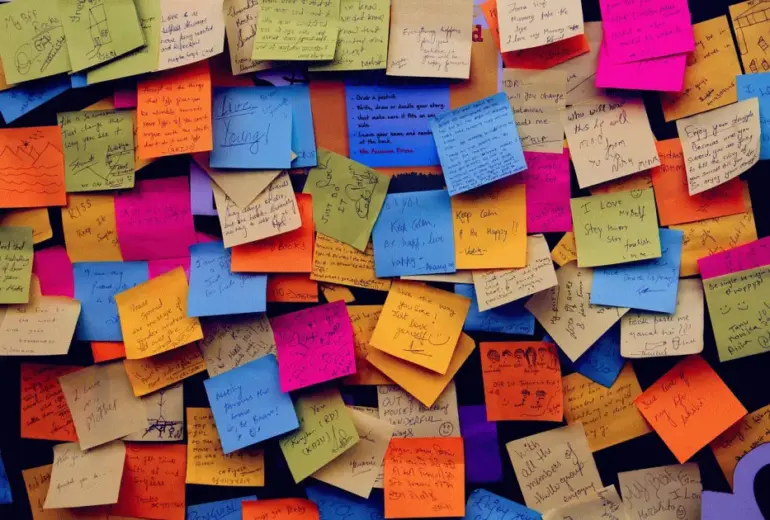まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。
これからの商業施設や地域の活動は、単なる「買い物の場」ではなく、「一緒に作る体験の場」へと進化していきます。
キーワードは「プロシューマー体験」。
消費者(Consumer)でありながら生産者(Producer)でもある──そんな新しい生活者の姿が、私たちの暮らしや社会を大きく変え始めています。
1. プロシューマーって何?
「プロシューマー」という言葉は、未来学者アルビン・トフラーが提唱しました。
これは「Producer(生産者)」と「Consumer(消費者)」を組み合わせた造語で、消費者が自ら生産活動に関わる存在を指します。
例えば──
- 自分で育てた野菜を食卓に並べる人
- ワークショップで手作り雑貨を作る親子
- クラウドファンディングで新しい商品づくりに参加する支援者
これらはすべて、ただ「買う」だけではなく「つくる」ことに関わる行為。まさにプロシューマーの実践例です。
2. 大量生産・大量消費の時代が終わりつつある
20世紀型の消費社会では、誰もが「同じ人」として扱われてきました。大量生産された商品を大量に消費し、大量に廃棄する──効率は高まりますが、そこには「私が選んだ」「私が関わった」という手触りはありません。
モノにあふれているのに、なぜか心は満たされない。
それは「関与」が抜け落ちているからです。
均質な商品やサービスに囲まれる暮らしの中で、人々は「個性」や「主体性」を失いがちでした。そんな背景があるからこそ、今「つくること」に注目が集まっているのです。
3. 「買う」より「つくる」で得られる充実感
プロシューマー体験には、所有を超える価値があります。
- 「自分が関わった」という誇り
- 仲間と一緒に作り上げる楽しさ
- 学びや成長の実感
例えば、子どもがワークショップでおもちゃを作ると、そのおもちゃは単なるモノではなく「思い出」や「自分らしさ」の象徴になります。
屋上農園で収穫したトマトは、スーパーで買うよりも何倍も美味しく感じられるでしょう。
そこにあるのは「所有」ではなく「関与」。これこそがプロシューマー体験の魅力です。
4. こらぼたうんでの実践──生活者と一緒に育てる場
こらぼたうんでは、企業や地域の人々と一緒に「価値を共に育てる」取り組みを続けています。
そこでは、生活者が単なる「消費者」としてではなく、共に考え、共に作るパートナーとして関わっています。
Co-Creation Gallery

化粧品メーカー × 生活者
“自分らしく輝く”をテーマに、共感と試作を重ねて。

家庭用品メーカー × 生活者
日常生活の声をヒントに、“使いやすさ”と“安心感”をカタチに。

学習塾 × 地域住民
子どもたちの未来を支える“学びの場”を、地域と一緒に設計・共創。

工業用製品製造業 × 主婦
家事や育児の知見を活かし、“一般消費者向けの製品”のヒントを。

家電メーカー × 消費者
日々の“ちょっとした不便”をヒントに、使い勝手のよい家電を共創。

日用品メーカー × 生活者
“あったらいいな”を丁寧に掘り起こし、共感される商品設計へ。
取り組みの形はさまざまです。たとえば──
- 地域の店舗を「みんなで考えながら作る」
- 家庭用品の企画に「日々の声を持ち寄る」
こうした場では──
「関わる楽しさ」こそが人を動かします。
参加してくださる方々は、「自分の意見が形になった実感」や
「仲間と一緒に作り上げる喜び」、「地域に少しでも役立てたという誇り」を感じ取っているようです。
私たちにとっても、その一つひとつの姿が大きな学びです。
共創は特別なことではなく、「誰かと一緒に関わり、何かを育てていく」自然な営み。その積み重ねこそが、これからの地域や企業にとって大切な価値になるのだと思います。
5. 人との関わりから生まれる「つくりたい欲望」
欲望や創造意欲は、人と人との関係や対話の中から生まれます。
例えば、
- 「孫と一緒に料理をしたい」
- 「仲間と同じTシャツを作って出かけたい」
こうした欲望は、単なる消費では生まれません。人とつながることで芽生える感情なのです。
プロシューマー体験は、この「人との関わり」を中心に据えるからこそ、人をワクワクさせ、生活に意味を与えるのです。
6. 商業施設も「買う場」から「つくる場」へ
従来の商業施設は効率を重視し、均質な空間で同じようにお客様を迎えてきました。
しかしZ世代を中心に、そうした「型通りの買い物」よりも、フリーマーケットのような交流や体験を求める声が強まっています。
商業施設がDIY工房や料理教室、地域と連携した商品開発ワークショップを提供するようになれば、
そこは単なる「買い物の場」ではなく、生活者のウェルビーイングを高める拠点へと変わるでしょう。
7. 未来のマーケティングは「どう売るか」から「どう一緒に作るか」へ
従来のマーケティングは「いかに売るか」を重視してきました。
しかしこれからは「いかに一緒に作るか」が問われます。
生活者はもう「消費者」ではなく共創者。
企業はその声を受け入れ、ともに物語を紡ぐ存在にならなければなりません。
「買ってもらう」から「一緒に作る」へ。
それが未来のマーケティングの姿です。
8. まとめ──プロシューマー体験が社会を豊かにする
プロシューマー体験は、人が主体性を取り戻し、暮らしに意味を与える大きなカギです。
こらぼたうんが実践するように、謝金がなくても人々が集まり、笑顔で活動する姿は、その証拠です。
これからの商業施設や地域社会に必要なのは、「買う場所」ではなく「一緒に作る場所」。
そこにこそ、未来の可能性と希望が広がっています。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)