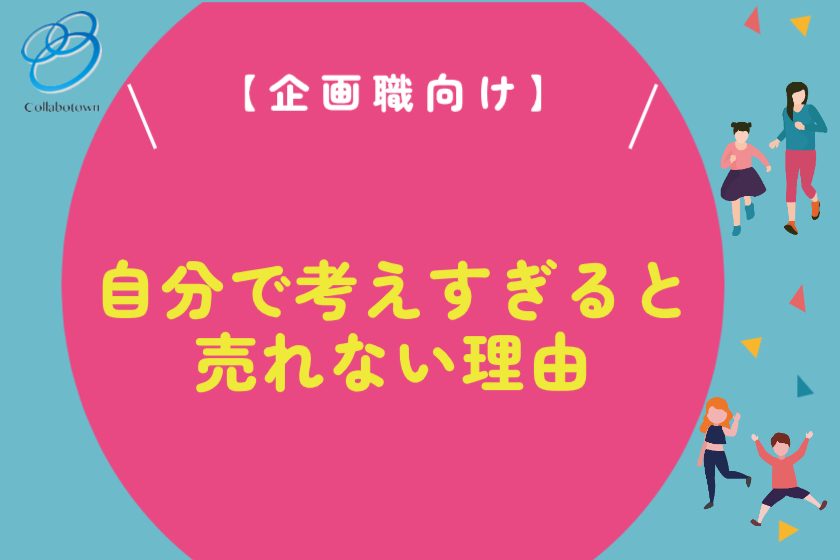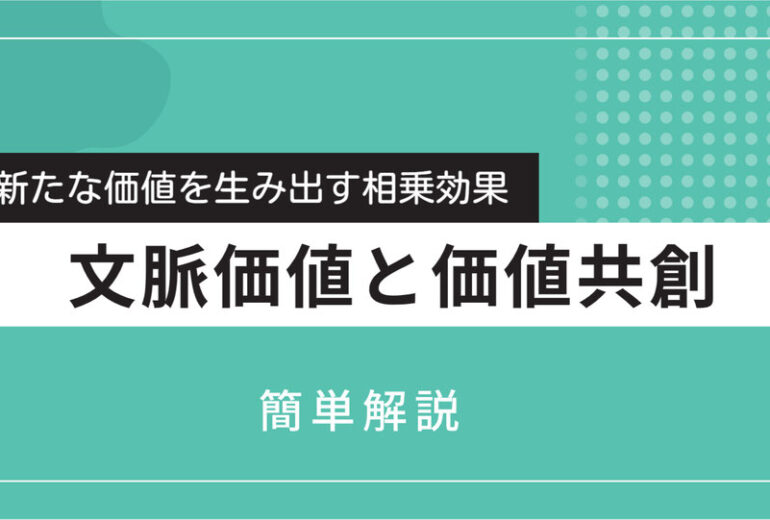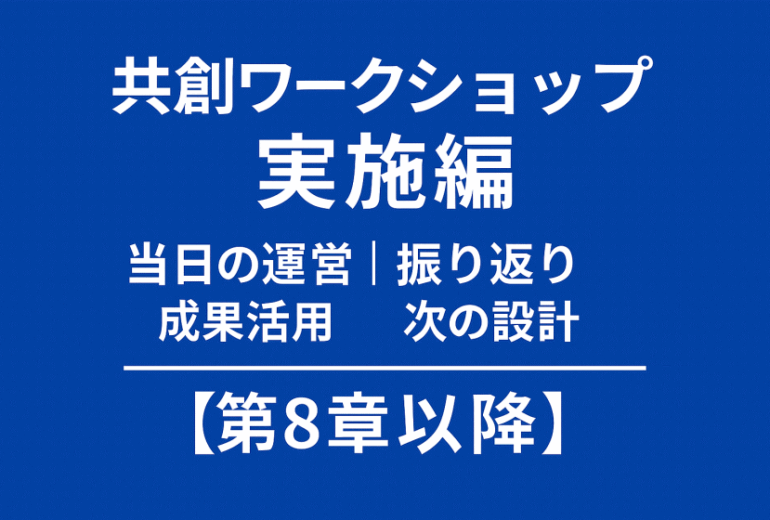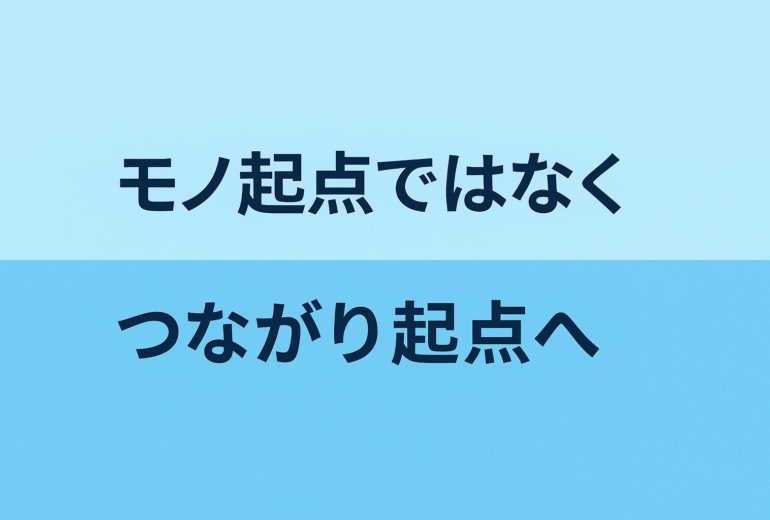この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。
はじめに:「考え抜いたのに売れない」という苦しさ
「何度も会議で検討を重ねた」「競合分析もした」「差別化も意識した」——にもかかわらず、売れない。そんな悔しさを感じたことはないでしょうか。
特にマーケティングや商品開発に携わる企画職の方にとって、「考える」ことは仕事そのもの。しかし皮肉なことに、「考えすぎる」ことが、かえってお客様とのズレを生み、ヒットを遠ざけていることもあるのです。
この記事では、企画職が陥りがちな「考えすぎの罠」と、そこから脱却するためのヒントを、「価値共創」の視点も交えながら解説していきます。
1. 「自分たちで考え抜く」がなぜズレるのか?
● 顧客視点の“つもり”になっていないか?
「これはお客様にとって嬉しいはず」と確信して出したアイデアが、まったく響かなかった──。これは、顧客視点の“つもり”で実は自分たちの都合になってしまっている典型例です。
企画職の多くは優秀で、「ユーザーを想像する力」が高い。でもその想像は、あくまで自分たちのフィルターを通したもの。実際の生活者の「文脈」や「感情」には、思った以上に届いていないことが多いのです。
● 市場調査が“納得の道具”になっている
よくあるのが、「調査結果はある。でも本当にそれが“生の声”かはわからない」という状態。
多くの企業で使われるアンケートや定量調査は、数字で安心感を得るための道具になりがちです。しかし、定型的な選択肢の中で集められた声は、企画者の問いの範囲内。つまり、「想定の範囲を超えた気づき」は得にくいのです。
結果として、調査→分析→企画という閉じたサイクルの中で“最適解”を追求しすぎ、マーケットのリアルから乖離していく危険があります。
2. なぜ「売れない商品」は生まれてしまうのか?
● 完成度が高いのに、共感されない
売れない商品が必ずしも「品質が悪い」「工夫が足りない」というわけではありません。むしろ完成度が高すぎて、「余地」がないことが原因の場合も多いのです。
お客様が商品を手に取るとき、その背景には「これは自分のためだ」「私の声が反映されている」といった共感の感情があります。それが欠けてしまうと、どんなに優れたスペックでも心を動かせません。
● 「想像の中の顧客」との対話に終始している
企画の初期段階から「お客様の声を聴く」という姿勢があっても、それが机上の空論で終わっているケースも少なくありません。
- 顧客像はペルソナに過ぎない
- 実際の文脈では何が起きているかは見えていない
- 商品使用の場面をリアルに知らない
このような状態では、現実の顧客の行動や感情との接点が極めて薄くなり、結果として「売れない商品」が生まれてしまうのです。
3. 考えるより“聴く”ことがヒットへの近道
● “生活者の世界”に入り込む
今、注目されているのが「価値共創(co-creation)」という考え方です。これは、企業が一方的に商品を設計するのではなく、生活者と一緒に価値を生み出していくアプローチです。
その第一歩は、「想像」ではなく「観察」と「対話」によって、生活者の世界に入り込むこと。
- 実際に使っている様子を見る
- 不満や不便を直接聞く
- その人の暮らしや価値観まで含めて理解する
こうしたプロセスは、単にアイデアを集めるだけでなく、企画者の認知バイアスをほぐす効果もあります。
● アイデアは“場”から生まれる
優れた商品は、優れた企画者の頭の中だけで生まれるわけではありません。
- 顧客とのやりとりの中で出た一言
- 試作品に対するリアクション
- チーム内でのちょっとした雑談
こうした“偶然の気づき”を拾える場をつくることこそが、売れる企画の源泉です。
4. 企画職が取り入れるべき「共創」の姿勢
● 完成品より「たたき台」を出す
優れた企画職ほど、「完璧な資料を出そう」としがちです。しかし、共創型のプロセスでは、未完成な段階での提示がむしろ効果的です。
たたき台をもとに、ユーザーの反応を受け取り、改善のサイクルを回す。その過程で、想定外の価値やニーズが浮かび上がってくるのです。
● 生活者を“リサーチ対象”ではなく“共演者”と捉える
「この人はどんな答えをくれるか?」ではなく、「この人と一緒に考えたら、何が生まれるか?」
そう考えるだけで、会話の質が変わります。顧客を“対象者”と見るのではなく、“共演者”と捉える視点が、共創の核になります。
5. 実践ステップ:考えすぎから脱却する3つの問い
最後に、「考えすぎ」から脱却するために、企画時に使える3つの問いを紹介します。
① このアイデアは、誰のどんな“困りごと”に触れているか?
抽象的なニーズではなく、「その人の生活の中で何が起きているのか?」に焦点を当ててください。
例:
・通勤時、荷物が多くて片手がふさがる → 片手で操作できるパッケージ
・子どもの歯磨き時間が毎日バトル → 楽しみになる歯ブラシ
② 本当にこれは、机の上だけで考えたものではないか?
自問自答してみてください。誰と話したか?どこで観察したか?リアルな接点があるかどうかが鍵です。
③ この企画は「関わった人が語りたくなる」要素があるか?
社内外の人が、「あの時、こうやって一緒に考えたんだよね」と物語として語れるかどうか。 それが“共感”を生み、“選ばれる”ブランドづくりにもつながります。
おわりに:考えすぎるあなたへ
考えることは、企画職にとって大切な力です。
でも、考え抜いたからといって、必ずしも売れるとは限らないのが現実。
そのときに必要なのは、「もっと考える」ことではなく、「もっと一緒に考える」こと。
生活者、現場の声、仲間の直感。そうした「他者の視点」を取り入れながら、アイデアを磨き続ける姿勢こそが、これからの時代の企画力ではないでしょうか。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 51 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)