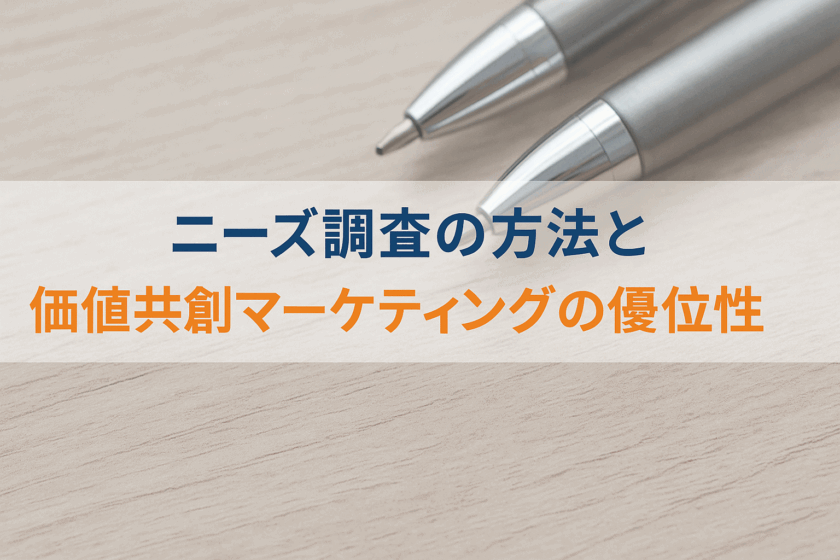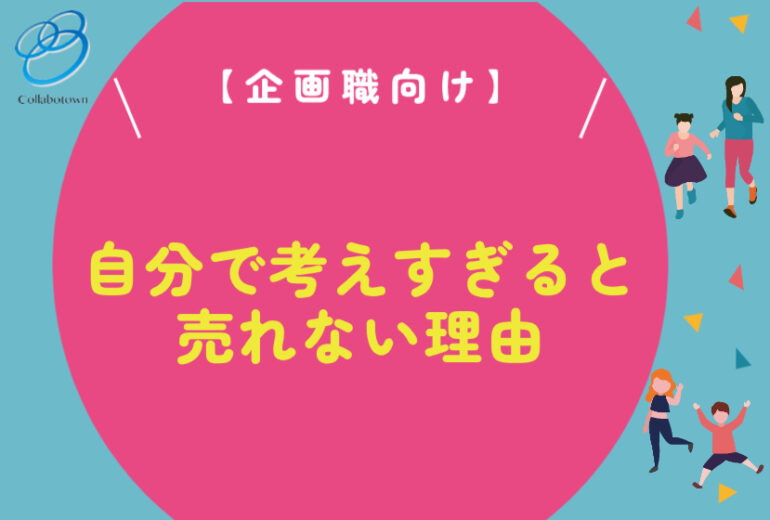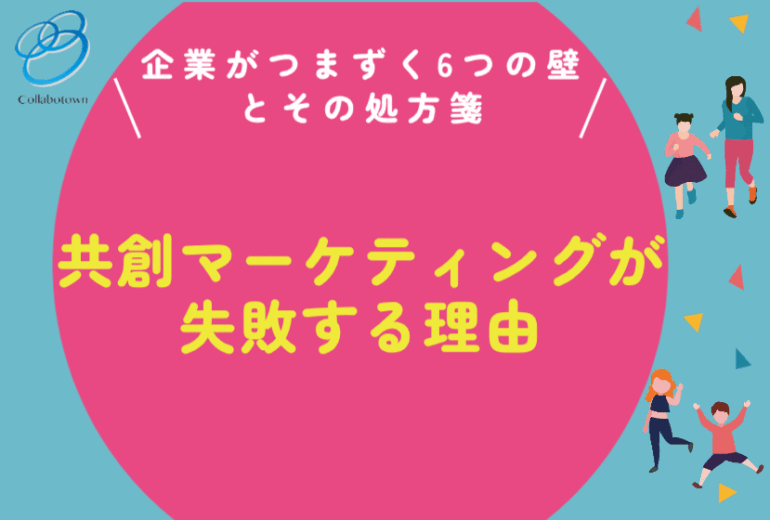企業が商品開発やサービス改善を行う際に欠かせないのが「ニーズ調査」です。市場に何が求められているのか、どのような価値が生活者にとって重要なのかを知ることは、ビジネスの出発点となります。
しかし近年、従来のニーズ調査手法に限界が見え始めています。表面的な要望にとどまることなく、深層にある“本音”や“意味”を捉えるためには、より参加型で共創的なアプローチが求められているのです。
本稿では、まず一般的なニーズ調査の手法とその特徴を整理し、その後、価値共創マーケティングの視点から見た優位性と、実践に向けた考え方を丁寧に解説していきます。
第1章:一般的なニーズ調査の主な方法
ニーズ調査にはいくつかの代表的な方法が存在します。以下に、企業がよく用いる5つの基本手法を紹介します。
1-1. アンケート調査(定量調査)
- メリット:短期間で大量のデータが取れる/数字で示せるため社内提案に使いやすい/属性別に集計しやすい
- デメリット:深掘りができない/形式的な回答や社会的バイアスが入りやすい/設問設計次第で結果が歪む
1-2. インタビュー調査(定性調査)
- メリット:自由回答なので意外な気づきがある/発話や表情から感情の動きが見える/具体的なエピソードが得られる
- デメリット:実施に時間とコストがかかる/調査者のスキルに結果が左右される/少人数では統計的信頼性が低い
1-3. グループインタビュー(FGI)
- メリット:他人の意見に刺激され、潜在ニーズが出てくる/話題が自然に展開する/会話の流れから生活実感が伝わる
- デメリット:強い発言者に場が支配されるリスク/雰囲気に合わせた意見が出やすい/データの客観性が低い
1-4. ユーザーテスト・モニター試用
- メリット:実使用時のリアルな反応が得られる/意図しない使い方や不満点が見える/継続利用の意向も評価できる
- デメリット:開発コストやスケジュールとの兼ね合いが必要/観察者の主観が入りやすい
1-5. ソーシャルリスニング・購買データ分析
- メリット:大量データを客観的に分析できる/潜在的な話題の把握に強い/リアルタイム性が高い
- デメリット:発信者は一部に偏る(声の大きい層)/ニーズの“背景”は見えにくい
第2章:なぜ今、従来のニーズ調査だけでは不十分なのか?
商品やサービスの企画・開発において、従来の「ニーズ調査」──すなわちアンケートやインタビューを通じた情報収集は今なお主流です。しかし、そうした手法にはいくつかの限界が存在しており、特に現代の生活者の多様で複雑な価値観を捉えるには不十分な場面が増えています。本章では、従来型調査の限界について3つの観点から詳しく解説します。
2-1. 表層的な回答が多く、真のインサイトが掴めない
アンケートや定量調査は、「はい/いいえ」や5段階評価といった選択肢の中から回答を求める形式が多いため、回答者の深層心理までは届きにくい傾向があります。
たとえば、「この商品を使って満足していますか?」という問いに「はい」と答えたとしても、その背後には「本当は他にもっと良い選択肢がないから」「不満もあるけど妥協している」などの複雑な感情があるかもしれません。しかしそれらは、設問の構造上、表に現れてこないのです。
こうした「表層的な答え」は、企業が安心する材料にはなりますが、競合との差別化や真に心を動かす提案を行うには不十分です。真のインサイトとは、「言語化されていない本音」や「矛盾した感情のなかにある無意識の価値観」を指します。共創マーケティングでは、こうした深層ニーズを発見するために、対話・観察・共体験といったプロセスを重視します。
2-2. 企業と生活者の間に「距離」がある
従来の調査では、企業が「聞き手」、生活者が「答え手」として明確に分かれており、双方向のやりとりや関係性の構築がありません。こうした関係性では、生活者も「本当のことを話していいのか」「どうせ聞き流されるのでは」といった心理的なバリアを抱えがちです。
さらに、企業側が持つ前提(たとえば「この機能は便利だろう」「価格を下げれば売れるはず」など)に引っ張られると、調査設計自体がバイアスを生んでしまい、自由で率直な意見が引き出せません。
一方、共創マーケティングの場では、生活者と企業が「フラットな関係」で共に考える時間を持つことが重視されます。ワークショップ形式や体験型セッションを通じて、生活者が自らの価値観や経験を自然に語る場をつくることで、企業側も新たな視点を得ることができます。
2-3. 市場に現れていないニーズは調査できない
ニーズ調査の基本的な前提は、「すでに存在している/気づかれているニーズを把握すること」です。しかし実際には、イノベーションや新しい提案に必要なのは、「まだ表に出ていない」潜在的な欲求や問題意識──いわゆる“ラテラルニーズ(周辺ニーズ)”です。
例として、スマートフォンの登場以前、人々は「ポケットに入る電話」や「持ち歩けるコンピュータが欲しい」といった要望を明確に持っていたわけではありません。だからといって当時アンケートを取っても、「スマートフォンが欲しい」という声は上がりません。つまり、「未来の価値」は、今のニーズ調査では拾えないのです。
共創マーケティングは、この点で大きな強みを持っています。生活者との自由な発想のキャッチボールの中で、彼ら自身も気づいていなかった欲求や未定義の課題が浮き彫りになります。市場の“外側”にある可能性を共に探るプロセスこそが、変化の激しい時代において企業が生き残るヒントとなるのです。
従来調査の限界を超えるには、「ともに考える」という姿勢が不可欠です。
次章では、実際にどのように生活者と共創の場を設ければよいのか、共創型リサーチの手法と実践事例を紹介していきます。
第3章:価値共創マーケティングが実現する“ニーズのその先”
単なる「調査」ではなく、生活者と企業が“共に価値を発見し育てる”ことを目指す。
3-1. 共創によるインサイト発見プロセス
| フェーズ | 内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 共感的傾聴 | インタビューや観察で生活者の思いや背景を聴く | 「気持ちの奥」を探る |
| 対話・内省 | 生活者と企業側が一緒に感じたことを言語化 | 真の課題と意味を発見 |
| 価値仮説づくり | 発見した気づきを価値アイデアに昇華 | 新しい可能性の提示 |
| 共創プロトタイピング | モデルを生活者と一緒に検証 | “使ってわかること”を反映 |
| 意味の再発見 | 「なぜこの価値が響いたのか」を共有 | ブランド知見の蓄積 |
第4章:価値共創マーケティングのニーズ把握における5つの優位性
前章では、従来型のニーズ調査が抱える限界について解説しました。そこで本章では、価値共創マーケティングがもたらす「ニーズ把握の進化」に焦点を当て、その優位性を5つの視点から紹介します。共創の視点は、単なる情報収集を超えて、企業と生活者の関係性そのものを変革する力を持っています。
4-1. 表面的でない「意味価値」を捉えられる
従来の調査では、「機能が便利か」「価格は適切か」など、比較的表層的な満足度や要望に留まりがちです。しかし現代の消費者は、単なるスペックではなく「それを使うことが自分にとってどんな意味を持つか」という“意味価値(シンボリック・バリュー)”を重視しています。
たとえば、同じコーヒーでも「リラックスした時間を象徴する」「自分らしさを表現する」といった意味づけが購入理由になる場合があります。価値共創マーケティングでは、生活者との対話や観察を通じて、そうした文脈的・情緒的価値を抽出できます。
これは、単なるニーズ調査では得られない、深い顧客理解に繋がります。
4-2. 未知の課題や可能性を発見できる
共創の場では、生活者が自ら気づいていない課題や、「まだ言語化されていないけどモヤモヤしている何か」に光が当たることがあります。これは、企業が仮説ベースで行う従来調査では難しい成果です。
たとえば、「この機能は不要」と思われていたものが、共創セッションを通じて「実は○○な場面では重要」といった逆転の評価に繋がった事例もあります。
このように、共創の過程では“発見”が起きます。市場に現れていない新たな可能性を見出す力が、価値共創マーケティングには備わっているのです。
4-3. 共創プロセス自体が“選ばれる理由”になる
いま、消費者は「企業の姿勢」に敏感です。価格や性能だけでなく、「どんな姿勢でモノを作っているか」「自分の声を本当に聞いてくれているか」といった“共感価値”が、購入や応援の理由になりつつあります。
企業と共に創った商品、プロセスに自分が関与しているという実感──これは単なるモノ以上の意味を持ちます。共創に参加した生活者はもちろん、そうした取り組みに共感した顧客が「この会社は信頼できる」「姿勢が好き」と評価することも多くなっています。
つまり、共創という姿勢そのものが“選ばれる理由”になっているのです。
4-4. 社内にも“ユーザー起点”の視点が芽生える
共創型の取り組みは、社外だけでなく社内にも好影響をもたらします。特に、マーケティング部門や開発部門が実際に生活者と対話し、想定外の声やリアルな価値観に触れることで、「売る側の論理」から「使う側の視点」へと意識が転換します。
この変化は、現場の企画力・改善力に直結し、部門横断的な連携を促す効果もあります。「顧客の声を聞く会」ではなく「一緒に創る場」を持つことで、社員のモチベーションも高まり、持続的な共創文化が育まれます。
4-5. 持続的なブランド価値の源泉となる
短期的な販促や価格競争に頼ることなく、共創によって築かれる「共感」「信頼」「物語性」は、ブランドの中長期的な価値を高める要素となります。
特に、同じ商品カテゴリで競合が多い市場において、「このブランドを応援したい」「この会社と一緒に未来をつくりたい」と感じてもらえる状態は非常に強力です。
共創マーケティングは、モノの差別化だけでなく、「関係性」によってブランドの唯一性を生み出し、それを持続可能な価値に昇華させていく力を持っています。
次章では、実際にどのように共創型の場を設計し、意味のあるインサイトを引き出すのか──その具体的なプロセス設計についてご紹介します。
共創マーケティングは、“ニーズを聞く”から“一緒に育てる”へと、企業と顧客の関係を根本から変えるアプローチです。
従来のリサーチが「対象者から情報を引き出す一方通行型」であるのに対し、共創マーケティングは「企業と生活者が共に価値を創り出す双方向型の関係」です。顧客は単なる情報提供者ではなく、“共創パートナー”として企業の一員となり、自らの言葉や体験をもとに、新たな価値の種を芽吹かせていきます。
では、実際にどうすればそのような関係性を築き、意味のあるインサイトを得ることができるのでしょうか。ここからは、価値共創型のニーズ探索を行うための実践的なステップを、3段階に分けてご紹介します。
第5章:共創型ニーズ探索の実践ステップ
共創マーケティングにおけるニーズ把握は、「場づくり」「対話の工夫」「組織での共有」の3つの柱で成り立っています。以下、それぞれのステップを詳しく解説します。
ステップ1:生活者との共創接点を設ける
まず重要なのは、生活者と企業がフラットに関われる“共創の場”を意図的に設計することです。これは単なるヒアリングではなく、互いに学び合い、気づき合う場でなければなりません。
具体的な手法としては以下が挙げられます:
- オンライン/対面での共創ワークショップ
- 共創型モニター体験(生活者が実際に商品を使って記録・共有)
- 顧客インタビュー+観察セッション(行動観察×会話)
重要なのは、生活者を「情報をくれる存在」ではなく、「一緒に創ってくれる存在」と捉えること。肩書きや立場に関係なく、自由に語れる安心感のある場づくりが信頼と本音を引き出す第一歩となります。
ステップ2:顧客の声に“問い”を返す
共創におけるインサイト探索は、「聞く」だけでは不十分です。むしろ、出てきた意見や感情に対して、「なぜそう思ったのか?」「それはどんな体験に基づいているか?」「もしこうなったら?」といった“問い返し”によって、潜在的な価値観や背景を掘り下げていくことが肝になります。
このステップでは、以下のような対話の工夫が有効です:
- 感情に注目する(「楽しい」「不安」などの言葉に注目して掘り下げる)
- 過去の経験を尋ねる(「いつ、どこで、誰と」などの具体化)
- 仮説ではなく好奇心で問う(正解を探るのではなく、“意味”を探る)
このように、対話のなかで「本音」と「意味の構造」を可視化することで、企業側の先入観を超えた発見が得られます。
ステップ3:共創の学びを社内で共有
共創セッションで得られた“気づき”を個人の経験で終わらせず、組織全体の財産として活用することが重要です。具体的には、以下のような仕組みづくりが効果的です:
- 共創セッションの内容を「ナレッジシート」「発見マップ」などに整理
- 定例ミーティングで他部門とも共有し、開発・販促に活かす
- インサイトごとに“意味付けの仮説”を明文化し、施策案に反映
また、可能であれば共創のプロセスに社員が同席し、生活者と“同じ空気”を感じ取ることが、もっとも強く行動変容を促します。「現場で見て、聞いて、感じた」体験は、ペーパーレポートの何倍もの説得力を持ちます。
共創は、単なる調査手法ではなく“企業文化の変革装置”です。
企業が生活者と共に価値を育て、インサイトを起点に商品やサービスを進化させていく仕組みを整えること──これこそが、変化の時代において真に選ばれるブランドを育てる土台となるのです。
まとめ:これからのニーズ調査は「共に創る時代」へ
従来のニーズ調査は、生活者の声を“情報”として集めるものでした。しかし、今の時代に必要なのは、“関係”として生活者とつながり、価値を共に創る姿勢です。
価値共創マーケティングは、単なる調査手法ではなく、「生活者との共感と発見を通じて、未来の価値をつくる」実践的な方法論です。
本当のニーズは、調査用紙の中にはありません。対話の中にこそ、“次に選ばれる価値”が隠れているのです。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)