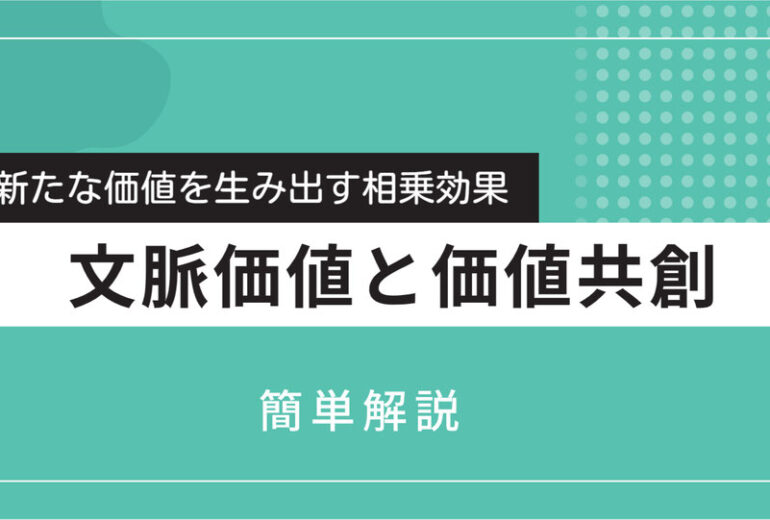私たちこらぼたうんが実践する「共創マーケティング」の中心には、いつも企業と生活者の“対話”があります。
ここで言う対話は、アンケートや一方向のヒアリングではありません。相手の価値観や感情に触れ、自分たちの前提を揺さぶり直しながら、新しい意味を一緒に見つける時間です。
その瞬間、企業の意思決定や戦略は「改善」ではなく、別の世界へ移るような転換(パラダイムシフト)を起こします。
🧭 3行で結論(忙しい方向け)
- 共創の対話は「意見を集める」ではなく、前提を揺らし“意味”を更新する営み
- 議論は勝ち負け、対話は理解と探索。共創では差異こそが発想の材料になる
- 対話が深まると、商品・戦略・組織の“見方”が変わり、選ばれる理由が育つ
共創における「対話」の本当の力
日常会話と、共創の場で行う対話は似ているようで別物です。共創の対話は、情報や知識に“新しい意味”を与える創造的コミュニケーション。 意味が変わると、意思決定が変わり、戦略が変わり、やがて組織の行動まで変わっていきます。
🧪 会話・ヒアリングで止まると…
- 「便利」「いいね」で終わり、次の打ち手が見えない
- 生活者の言葉が評価コメントとして棚に並ぶだけ
- 結果:企画が“既存の延長”から抜け出しにくい
🔥 対話になると起きること
- 「なぜ?」を重ねて、背景の価値観が見えてくる
- “行動の理由”が分かり、設計の焦点が定まる
- 生活者も企業も、前提を更新できる
例えば生活者が「この商品、便利なんです」と語ったとき。そこで止まれば満足度情報です。 しかし対話を深めて「なぜ便利?」「その便利さは何を助けてる?」「それが叶うと何が変わる?」を掘ると、 背景には“家事を短縮して、家族との時間を増やしたい”のような価値観が立ち上がってきます。
この瞬間、企業が向き合うべき問いは「機能を足すか?」ではなく、“その人の暮らしの何を守り、何を増やすか?”へ変わります。 ここに、共創の対話が生む転換があります。
「議論」と「対話」は似て非なるもの
共創を語る上で、まず整理しておきたいのは「議論」と「対話」の違いです。どちらも必要ですが、共創の原点は“対話モード”にあります。
| 議論(ディスカッション) | 対話(ダイアログ) |
|---|---|
| 目的は「正しさを示す」「意思決定する」 | 目的は「理解する」「意味を更新する」 |
| 結論ありきで進みやすい | 結論は開かれていて、探索が中心 |
| 相手の主張に反論し、自分の正当性を示す | 相手の視点を受け入れ、自分の前提も開く |
| 勝ち負けが残りやすい | 共感と納得が残りやすい |
議論は「正しさの競争」になりやすい一方、対話は「可能性の探索」です。共創の場では、意見の違いこそが新しい発想の源泉。 違いを“潰す”のではなく、“材料に変える”姿勢が重要です。
💡 共創の現場で起きていること
「相手を説得する」より先に、相手の世界を理解する。
その上で、自分の前提も揺らしてみる。
ここから、企業にも生活者にも“見えていなかった価値”が立ち上がります。
対話が生むパラダイムシフトの瞬間
共創の場では、双方の意見を足し合わせただけでは生まれない、まったく新しい視点が誕生します。 それは、対話の中で感情の奥にある価値観が言葉になり、企業の前提が揺らぐからです。
例えば、ある家電メーカーの場で「見られると恥ずかしいから隠す」という声が出たことがきっかけで、 “家電は機能があれば良い”という前提が崩れ、生活空間と調和するデザイン家電という発想が生まれた。 こうした飛躍は、議論よりも、安心できる対話の場で起きやすいのです。
🔍 シフトの前(企業の前提)
- 価値=機能・性能
- 売れる理由=スペックの優位
- 改善=足りない機能を足す
🌱 シフトの後(価値の再定義)
- 価値=暮らしの中で“どう見られるか”
- 選ばれる理由=空間と心理の安心
- 改善=体験のストレスを減らす
この転換は、企業にとって「本当に届けるべき価値とは何か?」という問いを立ち上げます。 対話は、正解を“探す”のではなく、正解の定義を“作り直す”営みでもあるのです。
共創の対話を“起こす”ための設計
対話は、偶然に任せるほど難しくなります。共創マーケティングでは、対話が起きる条件を設計しておくことが大切です。 ここでは、現場で効くポイントを5つにまとめます。
1「結論を急がない」場を宣言する
最初に「今日は決めない。探索する日」と共有すると、発言の質が変わります。
2評価・採点をいったん止める
「それは違う」を封印し、まず「そう感じた背景」を聞きます。安心が生まれます。
3“場面”から入る(いつ・どこで・誰が)
抽象論より、具体の生活シーンから始めると、言葉が立ち上がりやすくなります。
4「なぜ?」を3回、丁寧に
1回目は理由、2回目は価値観、3回目で“守りたいもの”が見えてきます。
5最後に“言葉を一緒に整える”
生活者の言葉を企業側が勝手に翻訳せず、本人と一緒に表現を磨くとブレません。
対話による“共創価値”の創発
こらぼたうんでは、生活者との対話を通して、単なる「声」ではなく、次のような“設計に使える情報”を引き出します。
🧩 対話で見えてくる3つの要素
- 使い方のストーリー:購入前後の行動・つまずき・工夫(体験の流れ)
- 選ぶ意味:なぜそれを選ぶのか/何を守りたいのか(価値観の核)
- 隠れたインサイト:本人も言語化していなかった“本音”(転換点)
対話によって引き出されたストーリーは、商品企画やブランドコミュニケーションの軸になります。さらに重要なのは、 それが企業だけの発見ではなく、生活者と一緒に見つけ出した価値であること。だから、言葉が強く、伝わり、ぶれにくいのです。
🔁 対話は“関係性の資産”にもなる
共創の対話がもたらすのは、アイデアだけではありません。
「この会社は私たちの暮らしを見てくれている」という信頼が積み上がり、継続的な関係へつながります。
最後に──共創の出発点は「対話」から
かつては「商品を作り、売る」だけで関係が終わっていました。ですがこれからは、企業と生活者が継続的な関係性の中で価値を育てていく時代です。
求められるのは「聞く力」だけではありません。共に考える力、そして気づきを交換する力が、ブランド価値を根底から変えていきます。
対話が創る、関係性から生まれる価値。
それこそが、これからの時代に求められる共創マーケティングの真髄です。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)