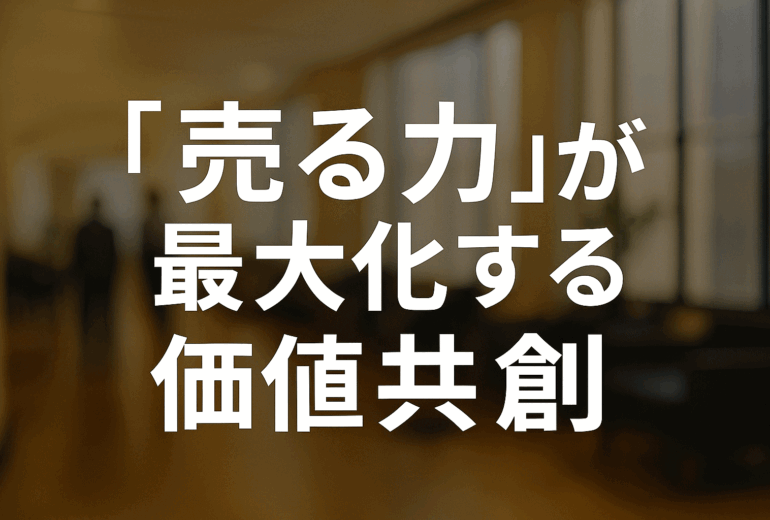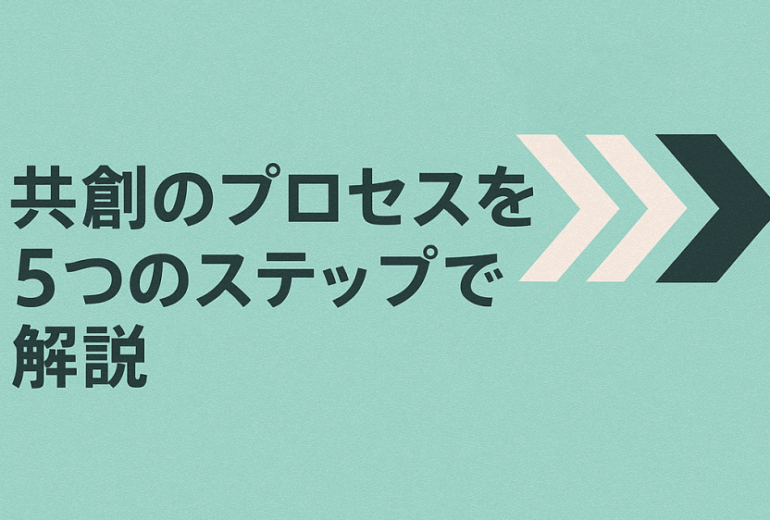KPI・評価設計×顧客ロイヤリティ|数字と心理をつなぐ実践ガイド
ロイヤリティは「ふわっとした好感」ではなく、“次の購買行動”を生む力です。
でも現場では、売上やCVだけ見ていると「原因がわからない」「改善がブレる」ことが起きがち。
ここでは、マーケ担当が施策の評価→改善まで回せるように、最低限のKPIでロイヤリティを育てる型をまとめます。
1. マーケ担当が「ロイヤリティKPI」を持つべき理由
施策が当たらない時、よくあるのは「結果(売上・CV)」しか見えていない状態です。
たとえば広告やキャンペーンでCVが増えても、2回目が続かないと利益は積み上がりません。
「何が効いた?」「どこが詰まった?」を、早く・小さく判断できるようにします。
✅ 改善の打ち手が具体化
“なぜ”が見えると、やるべき改善が明確になります。
✅ 施策の良し悪しが早い
売上を待たずに、体験や気持ちの変化で判断できます。
✅ 社内説明がラクになる
「数字+理由」で話せるので、合意形成が進みます。
2. ロイヤリティを4つに分けると、改善点が見える
ロイヤリティを「好きになった」で止めると、改善はふわっとします。
そこで4つに分けます。どこが弱いかが見えると、次の一手が決めやすくなります。
| 領域 | 例(よく使う指標) | ここが弱いと起きること |
|---|---|---|
| 行動 | リピート率/定期継続率/再購入までの日数 | 2回目が続かず、施策が積み上がらない |
| 体験 | 満足度/問い合わせの解決感/配送・使い方の分かりやすさ | 不満が残り、レビューや離脱が増える |
| 気持ち | おすすめ度(NPS)/信頼/好き/応援したい | 乗り換えが起きやすく、指名が育たない |
| 結果 | LTV/紹介経由売上/解約が減る | 利益が安定せず、値引き頼みになる |
3. 最初に決めるのは“定義”だけ(難しい設計なし)
KPIづくりで一番こけるのは、指標そのものより「言葉のズレ」です。
例えば「リピート率」と言いながら、部署Aは“30日以内”、部署Bは“90日以内”で見ている…これが起きると改善が止まります。
🧷 定義固定テンプレ(A4一枚でOK)
- 指標名:(例)リピート率
- 対象:(例)初回購入者
- 期間:(例)購入から60日以内に再購入した割合
- 見る頻度:週次(軽く)+月次(まとめ)
- 次の動き:数字を見る→理由を3件読む→改善を1つ決める
最初は、指標を増やさず2本で十分です。
- 行動:リピート率(また買ったか)
- 気持ち:おすすめ度(すすめたいと思ったか)
4. NPS(おすすめ度)はどう使う?
NPSは「友人にすすめたいですか?」を0〜10点で聞く、シンプルな指標です。
ただし大事なのは点数そのものより理由(自由記述)です。理由があると、施策の改善に直結します。
💬 質問はこれだけでもOK
0〜10点で、友人に勧めたいですか?
※点数は“温度計”。理由が“改善の地図”になります。
あくまで学ぶための指標として運用するのが一番うまく回ります。
5. ミニアンケ(5問)+“見るべき自由記述”
長いアンケは回収率が下がり、現場も疲れます。最初は5問以内で十分です。
マーケ担当としては、自由記述を「全部読む」より、週に3件だけ読む運用のほうが続きます。
📝 ミニアンケ(5問)テンプレ
- おすすめ度:0〜10点で、友人に勧めたいですか?
- 理由(自由記述):そう思った理由を一言で教えてください。
- 良かった点:特に良かったところはどこですか?
- 困った点:少しでも不便だった点はありますか?
- 次の期待:次に改善してほしいことはありますか?
自由記述で“宝”になりやすいのは「迷った」「わからなかった」「不安だった」「面倒だった」という言葉です。
6. 運用の型:週15分で「次の一手」を決める
KPIは作って終わりではなく、短時間で定期的に見ると効果が出ます。おすすめは週15分。
重要なのは、会議を増やすことではなく改善を1つだけ決めることです。
① 数字を見る
リピート率/おすすめ度を確認。
② 理由を読む
自由記述を3件だけ読む。
③ 仮説を1つ
原因を1つに絞る。
④ 改善を1つ
次週までにやることを決める。
例:LPの訴求を1行変える/FAQを1つ足す/同梱物の説明を1文だけ直す…これでも十分に効きます。
7. 施策別:KPIが効くシーン(キャンペーン/CRM/改善)
キャンペーン(短期で数字は出るが、続かない時)
CVは増えたのに、2回目が続かない時は「体験」か「気持ち」が弱いことが多いです。
その場合、リピート率に加えておすすめ度+理由を見ると、改善の当たりがつきます。
CRM(メルマガ・LINE・同梱物・購入後フォロー)
開封率やクリック率だけで終わらせず、“不安が減ったか”“迷いが消えたか”に注目すると成果が積み上がります。
自由記述で「使い方がわかった」「安心した」が増えると、継続や紹介が伸びやすくなります。
商品・サービス改善(レビュー/問い合わせが増えた時)
低評価レビューが増えた時は、点数を見るより同じ表現が繰り返されていないかをチェックします。
「サイズがわかりにくい」「期待と違った」「説明が足りない」など、直せる改善が必ずあります。
8. 価値共創マーケティングと相性が良い理由
価値共創は、お客様との対話や体験づくりで、「好き」「信頼」「応援したい」を育てやすい方法です。
ただ社内では「それって効果あるの?」と聞かれがち。そこでKPIが役立ちます。
共創が「良い話」で終わらず、施策として再現できるようになります。
「AI×共創の全体像」も合わせて読みたい方はこちら:
AIの発達と、人の心を動かす価値提供──価値共創マーケティングの視点
9. まとめ:KPIは“評価”ではなく“前に進む道具”
ロイヤリティはセンスではなく、少ない指標で、ちゃんと改善することで育ちます。
まずはリピート率とおすすめ度(NPS)の2本から。
週15分で「理由を3件読む→改善を1つ決める」を回すだけでも、現場の手応えが変わります。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ