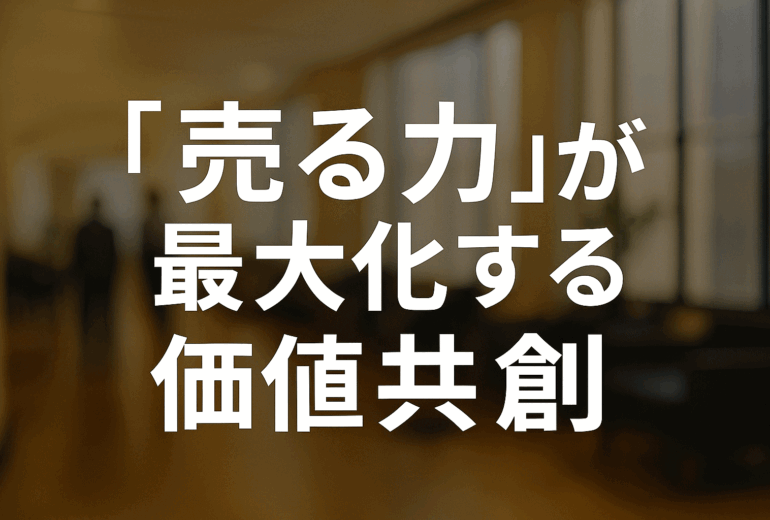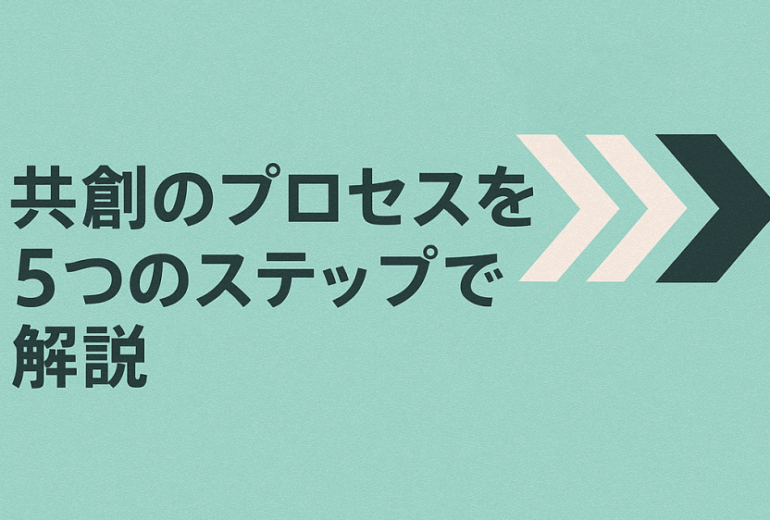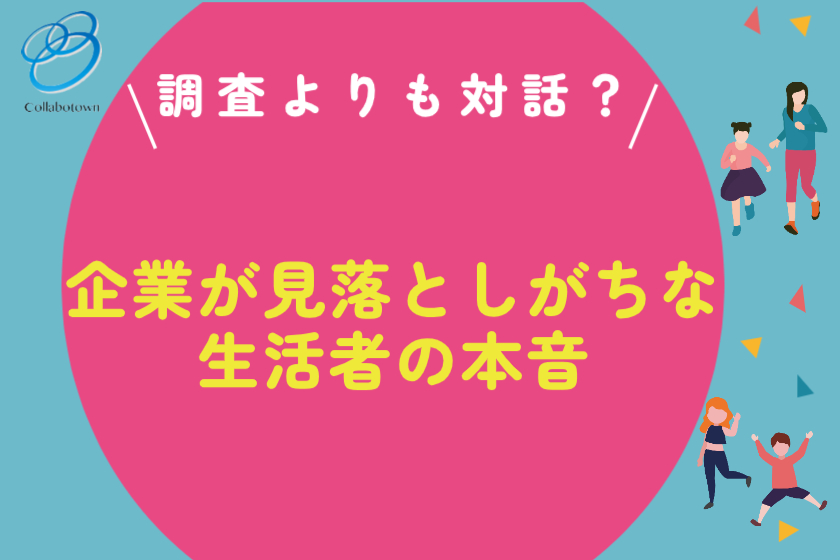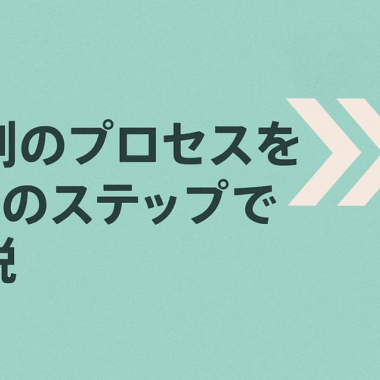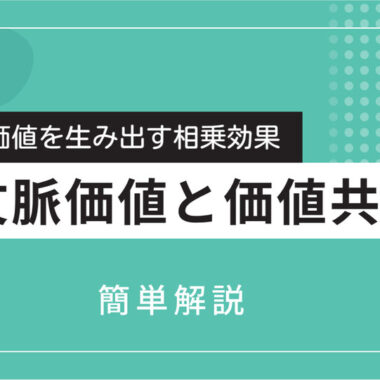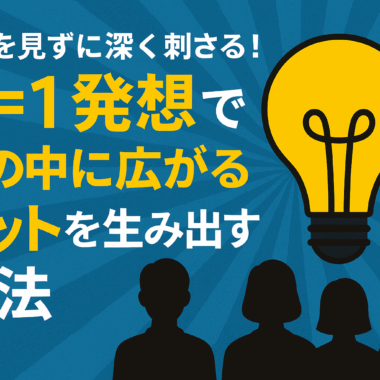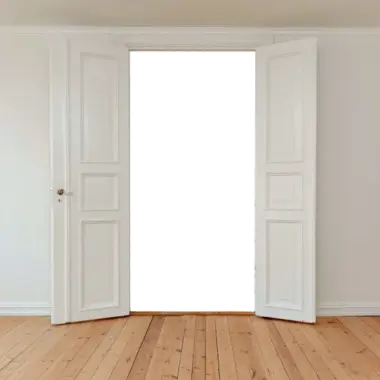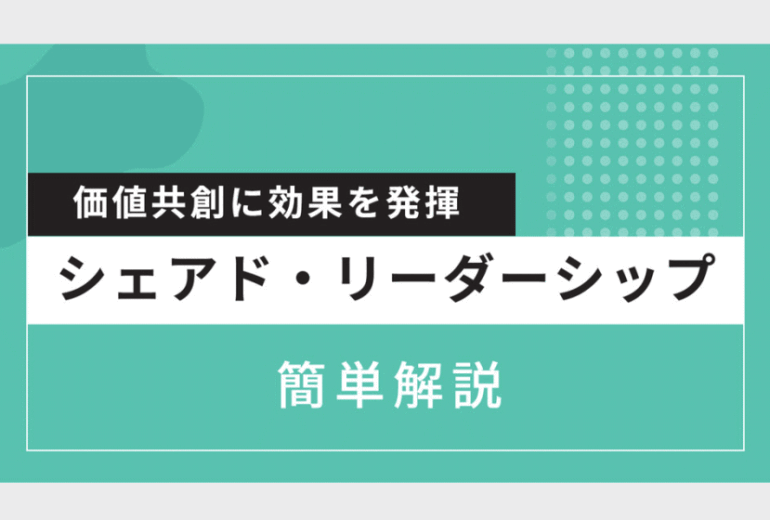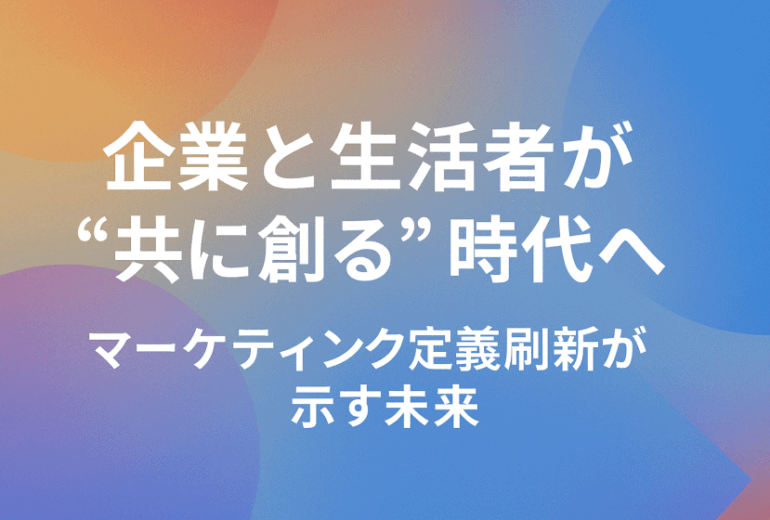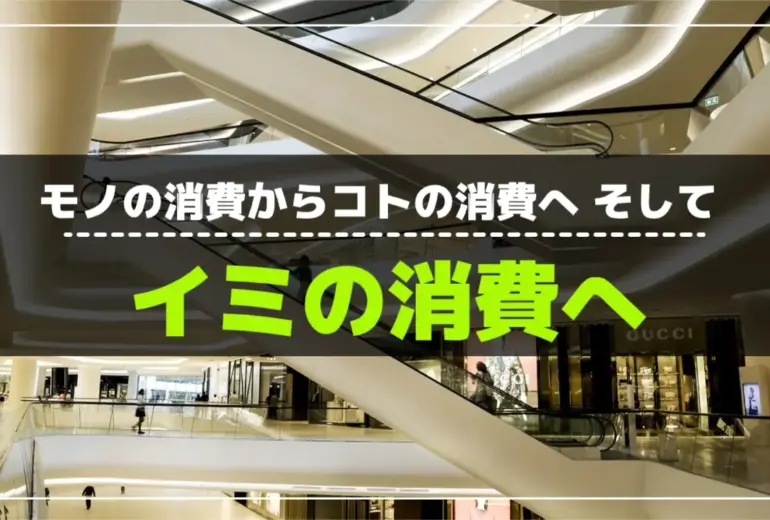この記事は「リサーチから共創へ」の実践編です。まず全体像から把握したい方はこちらをご覧ください。
新商品や施策検討の現場で頼りにされるのは、アンケート・データ・レポート。しかし、数字では説明できても、心は動かない──そんな壁に多くの企業が直面します。本稿は、調査の価値を認めつつも、対話が引き出す「気づいていない本音」と「文脈」をどのように企画へ活かすかを、実践に沿って解説します。
目次
はじめに──「調査すれば分かる」という思い込み
新しい商品やサービスの意思決定を根拠づけるものとして、調査は長らく重宝されてきました。しかし、調査結果に忠実に動いたにもかかわらず「思ったほど売れない」「共感が得られない」ケースは珍しくありません。理由の一端は明快です。調査は“説明可能な回答”を回収するが、実際の行動を方向づける“言葉にならない要因”は掬いきれないからです。
第1章 調査の限界と見えない本音
1-1. 数字が示すのは「表層」
アンケートでの「買いたい」は、店頭での「買う」とは異なります。隣接する競合・その日の気分・支払いタイミング・店員の一言──行動は微細な文脈に影響されるため、調査時の意思は簡単に上書きされます。
1-2. 設問の枠が答えを制限する
「A/Bどちらが良いか」を問えば、回答もA/Bに閉じます。実態としては「Cのような在り方が欲しい」かもしれないのに、企業が設定した枠外のニーズは表面化しないのです。
1-3. 生活者自身が言語化できない欲求
購買は、感情・習慣・直感・同調・罪悪感の回避など、非言語的要因に左右されます。調査で拾えるのは「説明可能な理由」。本音は水面下に沈んだままです。
- 調査は傾向を掴む道具。個別の動機は取りこぼしやすい。
- 設問設計は回答の範囲を狭める。枠外の声は上がりにくい。
- 非言語要因(感情・習慣・状況)が購買を方向づける。
第2章 対話が引き出す「気づいていない本音」
2-1. 自然な会話の中に“生活文脈”が現れる
買い物同行の現場では、「冷蔵庫で悪目立ちする色は嫌」「職場で取り出すときの視線が気になる」など、アンケートでは出ない“生活の真ん中”の言葉が飛び出します。
2-2. 雑談こそ宝の山
本題前の雑談に、最良の示唆が眠ります。「最近、子どもが野菜を食べなくて…」という愚痴から、パッケージ表現や味付けの方向性が決まることもあります。
2-3. “一緒に考える”と潜在欲求が立ち上がる
「どうすれば使いやすくなる?」と共に考える共創型の場では、生活者自身が自覚していなかったニーズに気づきます。これは聞き取りではなく、価値の共同発見です。
第3章 調査と対話の補完関係
| 観点 | 調査(Survey) | 対話(Dialogue / Co-Creation) |
|---|---|---|
| 目的 | 傾向の把握・規模感の推定 | 動機・文脈・隠れた障害の理解 |
| 強み | 再現性・説得力(数値) | 発見性・示唆の深さ(物語) |
| 弱み | 枠外を拾いにくい | サンプルが小さく一般化しにくい |
| 使いどころ | 方向の確認・優先度付け | Whyの解明・解決策の共創 |
両者を掛け合わせてこそ、「なぜこの数字になったのか」と「では何を作る/直すべきか」が一本の線でつながります。
第4章 対話を避けてしまう理由
4-1. コストと時間の先入観
「数千サンプルの調査」と比較すれば、対話の効率は悪く見えます。ですが、方向を誤ったままの開発コストはもっと高い。少数の深い対話が、後戻りを劇的に減らします。
4-2. 本音が怖い問題
耳の痛い意見は、前提や誇りを揺さぶります。だからこそ、早く・小さく・安全に失敗できる場として対話を設計すべきです。
4-3. 社内説得の難しさ
数字は会議に通りやすい。エピソードは軽んじられがち。“数×物語”の併記(例:N=12の対話で現れた3パターン+全体調査での出現率)で橋渡ししましょう。
- 「対話で聞いた=正しい」ではない。仮説→軽量検証→調査で補強の順で。
- 声の大きい人の意見に引っ張られない。多様性のある場を必ず設計。
- 開発後半で本音確認をしない。最初の1週間で一度は生活者に当てる。
第5章 現場に対話を組み込む方法
5-1. 買い物同行(Shop-Along)
- 目的:選択の瞬間の迷い・比較軸・手に取り戻す理由を捉える。
- 観察ポイント:最初に視線が向く棚、触る順番、価格札の見方、戻す理由の一言。
- アウトプット:「つい手に取る/戻すトリガー」一覧→棚・パッケージ・コピー改善へ。
5-2. 共創ワークショップ
- 構成:共感ウォームアップ→課題の翻訳→アイデア拡散→絞り込み→即席プロト。
- 役割:生活者は使用文脈を供給、社員は実現文脈を供給。交差点で解が生まれる。
- コツ:「反対意見の役割」をあえて置く。合意ではなく学習量をKPIに。
5-3. オンライン対話コミュニティ
- 狙い:点の調査→線の対話へ。シーズナルな変化や生活イベントを早取り。
- 運用:週1テーマ投稿/月1投票/四半期で“小さな実装”を必ず返す。
第6章 ミニケーススタディ
6-1. 菓子メーカー:パッケージ“場違い感”の解消
味・価格評価は高いのに売上停滞。買い物同行で「職場で出しにくい」の声。色調とトーンを控えめに変更して、オフィス常備需要を獲得。
6-2. 地域農産品:贈答偏重から“普段使い”へ
共創ワークショップで「少量・自分用・冷蔵庫で収まり良い」ニーズを発見。小ロット化+適正価格帯で新規チャネル開拓に成功。
第7章 これからの企業に求められる姿勢
調査で「市場の声」を聴き、対話で「人の声」を聴く。
その両輪が回ったとき、企画は“売れる理由”を獲得する。
多様化・個別化が進む市場では、「傾向」と「文脈」の二層取得が不可欠。対話は情報収集ではなく、信頼関係の設計であり、選ばれ続けるための土台です。
まとめ──調査から対話へ
- 調査=傾向の把握、対話=本音と文脈の発見と定義する。
- 企画初期から“小さく当てる”対話を必ず入れる(最初の1~2週間)。
- 示唆は仮説→軽量検証→数的補強で社内合意形成へつなぐ。
実践チェックリスト(保存版)
- 「A/Bどちら?」の設問を、自由記述+写真/現物を扱う問いに置換。
- 企画キックオフから2週間以内に生活者3〜5名と対話する場を設定。
- 買い物同行で“戻す瞬間”の一言を記録(迷いの理由が宝)。
- ワークショップは合意より学習量をKPIにする。
- 対話の示唆は写真付き1ページ要約で経営会議へ。
- “場違い感”を測るために利用シーン写真に置いたときの違和感を確認。
- 「買わない理由」を引き出す役をファシリに割り当てる。
- オンラインコミュニティで週1テーマ・月1投票・四半期1実装。
- パッケージ/棚/コピーの3つのトライアルを同時に小規模検証。
- 数値報告には1エピソード+1写真+1数値をセットで添える。
よくある質問(社内説得のために)
Q1. サンプルが少ない対話で意思決定して大丈夫?
A. 対話は意思決定の“出発点”。示唆→軽量実験→数量補強の三段でリスクを制御します。
Q2. 時間がないときの最小構成は?
A. 「買い物同行×2名+在宅ヒアリング×2名+社員クロスレビュー×1回」で最短実装。
Q3. 経営が数字しか見ない場合は?
A. 対話の発見を「仮説指標」に翻訳し、ミニテストで数字化→意思決定へ。
「調査はやっているのに、心が動かない」──その違和感は、対話で埋められます。小さな一歩から設計しましょう。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 43 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)