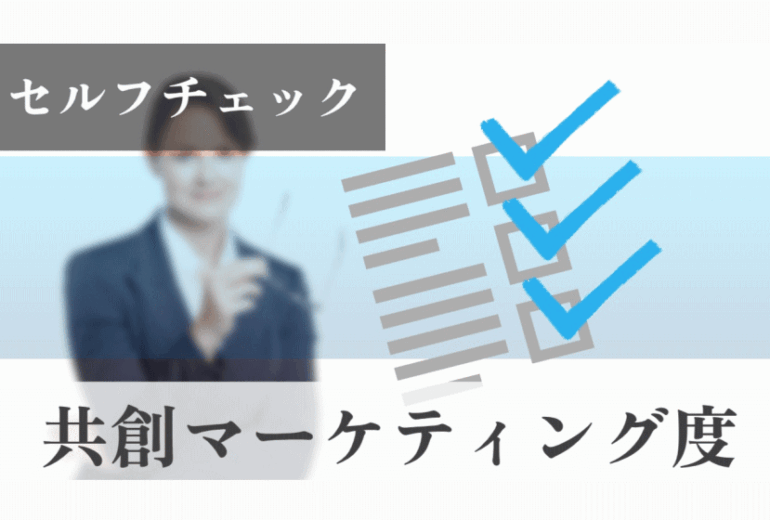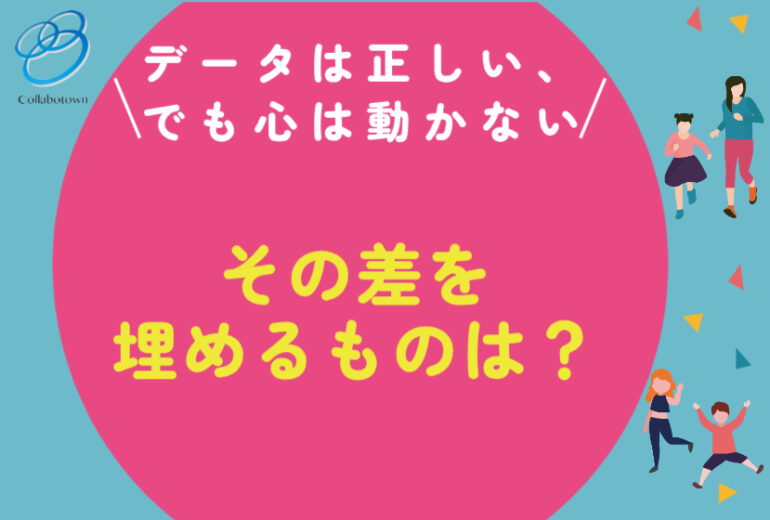──部門を越えて「語れる組織」になると、中小企業は“売れる力”が一段上がります。
「広報も販促も頑張っているのに、成果につながらない」
その原因は施策の質ではなく、組織の中でマーケティングが“点”になっていることかもしれません。
本記事では、価値共創マーケティングを“社内から”実践すると、なぜ売上だけでなく 言葉・熱量・連携まで変わっていくのかを、実務の型で整理します。
1. はじめに:マーケティングの成果が“点”で終わっていないか?
中小企業の経営者・責任者からよく聞くのが、 「SNSや広報、販促をやっているのに売上が伸びない」という悩みです。
その背景にあるのは、施策が“点”で完結してしまい、 企画→開発→製造→営業→販売の間で意図がつながっていない状態です。
よくある状態:企画が考えた施策を、営業が「よく分からないまま」実行する。
→ 現場の言葉から熱が消え、顧客には「響かない提案」になりやすい。
✅ 要点3行まとめ
・成果が出ない原因は、施策ではなく“社内のつながり”にあることが多い。
・企画の意図が現場に伝わらないと、顧客には熱が届かない。
・まずは「点」を「線」にする=社内共創が鍵。
2. 共創マーケティングの本質とは何か?
価値共創マーケティングは、単なる「顧客参加型の企画」や「イベント」ではありません。
本質は、顧客と企業が一緒に価値をつくり上げるための関係性と対話の設計にあります。
誤解されがちなポイント
- 共創=外部(顧客)との企画だけ、と思われがち
- しかし実際は、社内で共創が起きていないと外部共創は続かない
第一歩:社員一人ひとりが「なぜこの商品なのか」「誰のどんな困りごとに応えるのか」を、
自分の言葉で語れる状態をつくること。
それが顧客接点で、圧倒的な説得力になります。
✅ 要点3行まとめ
・共創の本質は「関係性と対話の設計」。
・外部共創の前に、社内共創(部門間の共鳴)が必要。
・社員が“自分の言葉”で語れる状態が、売れる力になる。
3. 商品が「部門横断の物語」になるとき
社内共創が進むと、商品やサービスに「部門を越えた物語」が宿ります。
これはスペックや価格では伝えきれない情緒的価値(共感・納得・誇り)を生みます。
物語が生まれる典型パターン
- 営業:現場で拾った「お客様の困りごと」を言語化
- 企画:困りごとを“価値”に翻訳し、仮説として形にする
- 製造/開発:要望を満たすだけでなく「使いやすさの理由」まで整える
- 販売/広報:「なぜこう作ったか」をストーリーとして届ける
結果:現場の言葉にリアリティが生まれ、顧客は「この会社は自分たちのことを考えている」と感じやすくなる。
→ 価格競争ではなく、“意味”で選ばれる状態へ。
✅ 要点3行まとめ
・部門がつながると、商品に“物語”が宿る。
・物語は情緒的価値を生み、共感で選ばれる。
・結果として、価格比較から抜けやすくなる。
4. 共創型組織の実践例:ある中小企業での変化
🗣️実践者の声
現場で何が変わったのか──“当事者の言葉”で確認できます
社内共創が進むと、売上だけでなく“言葉”が変わります。
営業の言葉/部門の連携/商品への誇り——当事者の声で確かめてください。
実践者が感じたリアルな変化はこちら。
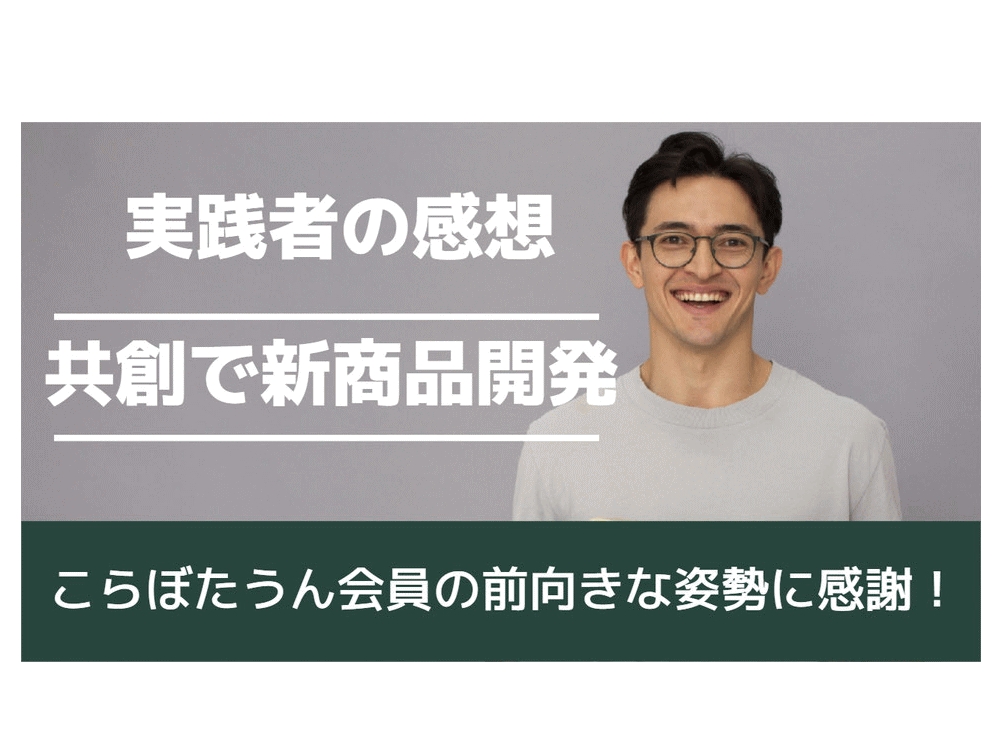
ある地方の製造業では、企画と営業が完全に分断され、「売りにくい商品」が量産される悪循環が続いていました。
営業は現場で苦戦し、企画は「良い商品なのに…」と空回り。社内の熱量は落ちていきました。
導入したのは「開発初期からの営業参加」
- 週次で営業が顧客接点の“生の声”を持ち寄る
- 企画が仮説を更新し、製造が柔軟に調整する
- 開発背景を営業が理解し、現場で自分の言葉で語れるようにする
変化:「これは自分たちが形にした商品だ」という実感が生まれ、営業の提案が“説明”から“提案”へ。
結果、受注率が改善し、社内のコミュニケーションも増加。つながっている感覚が組織に根づき始めました。
✅ 要点3行まとめ
・分断は「売りにくい商品」を生み、現場の熱量を奪う。
・初期から営業を巻き込むと、商品が“自分ごと化”する。
・提案の言葉が変わり、受注力と組織の一体感が上がる。
5. 社内共創を進めるための3つのポイント
社内共創は「仲良くする」ことではなく、意図的に設計する仕組みです。 中小企業でも今日から始めやすい3点に絞ります。
1 想いの共有を“場”として設計する
情報共有だけでなく「なぜやるのか」「誰の困りごとか」を語る時間をつくる。共創は理屈ではなく、納得感の醸成です。
2 部門を“つなぐ人”を決める
小規模ほどハブ役が重要。社長・幹部・リーダーが横串を通すだけで、連携の摩擦は一気に減ります。
3 “語りたくなる商品”を目指す
ストーリーがある商品は、社員の言葉が自然に強くなる。結果として顧客にも伝わり、売れる状態が生まれます。
✅ 要点3行まとめ
・共創は“場”と“役割”で仕組み化できる。
・ハブ役が決まるだけで、部門の壁は薄くなる。
・語りたくなる商品は、自然と売れる商品になる。
6. 共創が組織に根付いたときに得られる成果
共創が根付くと、売上以外にも“目に見える変化”が連鎖します。代表的な5つを整理します。
① 営業の言葉に「重み」が生まれ、信頼が増す
開発背景や顧客の声を理解して語れるため、セールストークではなく“提案”として伝わりやすくなります。
② 顧客接点が増え、口コミ・紹介が自然に広がる
顧客が関わった実感を持つと、ストーリーを自分の言葉で語り始めます。関係性そのものが資産になります。
③ 商品に対する“誇り”が社内全体に満ちる
一緒につくった過程が共有されるほど、誇りが生まれ、挑戦が続く組織の土台になります。
④ 価格競争から抜け出し、「理由があって選ばれる」
共創で形成された価値は文脈の中にあるため、単純な比較から外れやすい。“意味”で選ばれる状態へ。
⑤ 部門連携が深まり、組織風土が活性化する
相互理解が進むと摩擦が減り、チームワークが上がります。挑戦を応援し合える空気が育ちます。
補足:これらは売上アップに加えて、組織の「自己効力感(やればできる感)」が高まる副次的成果にもつながります。
✅ 要点3行まとめ
・共創は売上だけでなく、言葉・誇り・紹介が増える。
・“理由があって選ばれる”状態が生まれ、価格競争から離れやすい。
・組織風土が変わると、挑戦が続く会社になる。
7. おわりに:中小企業だからこそできる、組織ぐるみの価値共創
価値共創マーケティングは、大企業の専売特許ではありません。むしろ中小企業には、 意思決定が速い/距離が近い/改善が回しやすいという強みがあります。
「伝える」ではなく「伝わる」状態をつくるには、顧客との対話の前に、 まず社内で対話が起きる設計が欠かせません。
今日できる一歩は小さくて構いません。
企画の意図を“現場の言葉”に翻訳する場をつくることから、始めてみてください。
社内共創の設計から、実務の型まで整理します(無料オンライン相談)
部門連携の詰まり・営業の言葉の弱さ・商品ストーリーの設計など、状況に合わせて最短ルートを整理します。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ