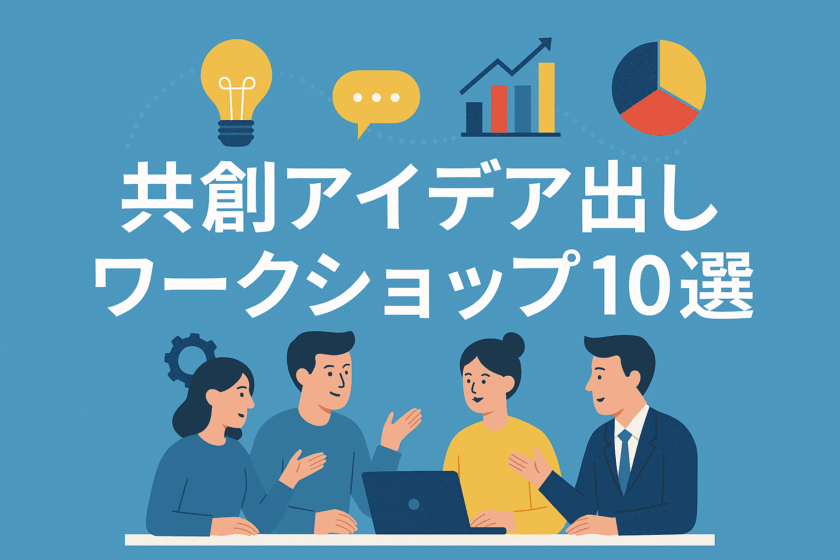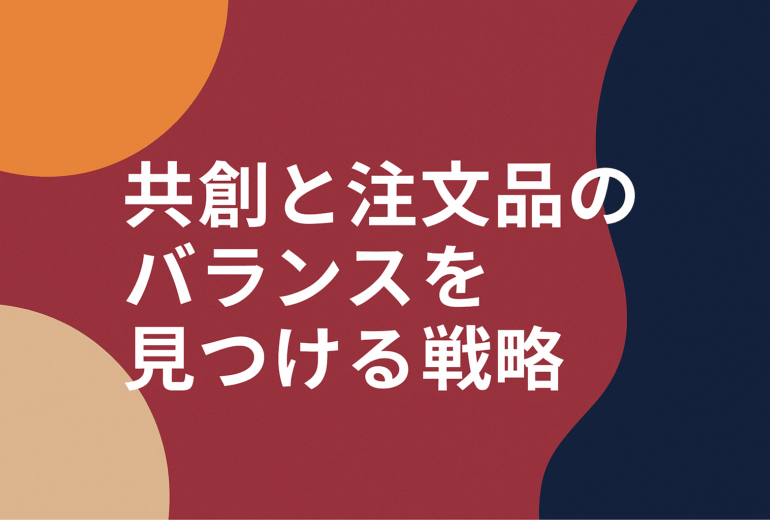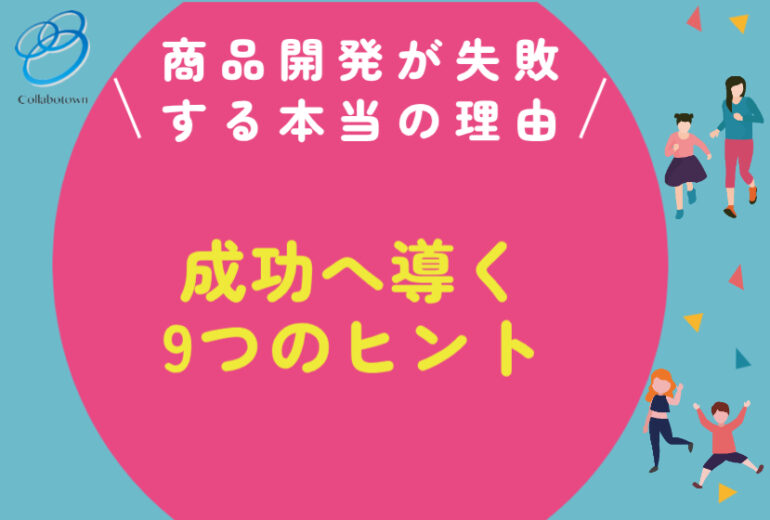共創アイデア出しワークショップ10選──社員・顧客と価値を生み出す実践手法
「やり方・進行」でつまずかないために
このページは手法の全体像(10選)をまとめています。
すぐ現場で回すなら、アジェンダ/進行台本/詰まりどころの対処まで整理した
共創ファシリテーション決定版(/cluster-facilitation/)を先に見るのが最短です。
※ 派生記事が未整備のため、各手法の詳細は用語集リンクで補完します。
🔍 この記事でわかること
- なぜ今「共創ワークショップ」が求められているのか(背景と狙い)
- 共創ワークショップを設計する際の基本視点(目的・対象・プロセス)
- 実務で使えるアイデア出しワークショップ10種(※詳細は用語集リンク)
- 実施時の注意点・成功のコツ・導入事例と、次の一歩につなげるヒント
はじめに|共創が求められる背景
近年、企業に求められているのは「創造力」だけではなく「共創力」です。市場の変化が早まり、顧客ニーズが多様化する中で、ひとつの部署や限られたチームだけで画期的なアイデアを生み出すことが難しくなってきました。
そこで注目されるのが共創ワークショップ。社員や顧客、外部の協力者などを巻き込み、対話と協働を通じて新しい価値を生み出す場の設計です。本記事では、そうした共創の場をより実践的に活用するためのアイデア出し手法を10個ご紹介します。
共創ワークショップ設計の基本視点
共創型ワークショップの成功は、実施そのものよりも「事前の設計」にかかっていると言っても過言ではありません。以下の3視点を押さえることで、参加者の創造性と主体性を引き出し、実りある共創の場をつくれます。
- ● 目的の明確化: 発散か、課題の可視化か、合意形成までか——到達ゴールによって手法・時間配分・参加者属性が変わります。
- ● 対象者の選定: 社員/顧客/パートナー/地域などの混成で多様性を確保。上下関係が強い場は、進行や席順に配慮が必要です。
- ● プロセス設計: 発散→収束→可視化の流れを明確化。見える化されたアウトプットは共有知となり、次アクションの足場になります。
生活者に寄り添う対話から、生まれてきたアイデアたち

化粧品メーカー × 生活者
“自分らしく輝く”をテーマに、共感と試作を重ねて。

家庭用品メーカー × 生活者
日常の声をヒントに、“使いやすさ”と“安心感”をカタチに。

学習塾 × 地域住民
子どもたちの未来を支える学びの場を、地域と一緒に設計。

工業用製品 × 主婦
家事・育児の知見を活かし、BtoC製品のヒントに。

家電メーカー × 消費者
“ちょっとした不便”から、使い勝手の良い家電へ。

日用品メーカー × 生活者
“あったらいいな”を丁寧に掘り起こし、共感設計へ。
共創を活かすアイデア出しワークショップ10選
-
01
ブレインライティング
無言でアイデアを書き出し、他者が発展。発言の得意・不得意に左右されず多様性を確保。
📖 用語解説を見る -
02
KJ法
カード化→グルーピングで構造化。潜在的なつながりの発見に有効。
📖 用語解説を見る -
03
未来新聞
架空の新聞で理想の未来を描く“バックキャスト”。ビジョン共有に効果的。
📖 用語解説を見る -
04
オズボーンのチェックリスト
転用・結合・代用…9視点で既存案を拡張。
📖 用語解説を見る -
05
インサイトスケッチ
行動や感情を絵で可視化して“気づき”を促す。
📖 用語解説を見る -
06
ストーリーボード法
体験を時系列の絵で共有し、課題発見と認識合わせ。
📖 用語解説を見る -
07
アイデアスピードラウンド
短時間で量を出すラピッド発散。評価は後半に分離。
📖 用語解説を見る -
08
ヒーロージャーニー
主人公の物語構造で感情とモチベーションを伴う発想へ。
📖 用語解説を見る -
09
デザインスプリント・ダイジェスト
1日凝縮で課題明確化→発想→選定→検証まで。
📖 用語解説を見る -
10
ChatGPT共創法
AIを“参加者”化して異質刺激を得る。人×AIで発想幅を拡張。
📖 用語解説を見る
実施時の注意点と成功のコツ
出てきたアイデアを必ず可視化する
- 発言はその場で付箋やボードに書き出し、「見える化」する。
- 似た意見をグルーピングして整理し、チームで構造を共有する。
- 進行役と記録係を分け、対話と記録を両立させる。
上下関係や部署を越えて意見を交わす
- 座席は役職を混ぜて配置し、呼称はニックネームなどフラットにする。
- 「立場ではなく意見を尊重する」ルールを冒頭で共有する。
- 多様な視点を歓迎し、安心して発言できる空気をつくる。
記録と振り返りを次のアクションにつなげる
- 終了時にKPT法(Keep/Problem/Try)などで感想を共有する。
- 当日中に要点を写真やメモでまとめ、チームで共有する。
- 次回ワークへの改善点を明文化し、実践のサイクルを回す。
導入事例|テーマ別 共創ワークショップの実践と成果
● 素材を製品に ──「素材の活かし方」から一緒に考える
地元の農家 × 中小メーカー:生活者と「どんな暮らしで使いたいか」を共創。お菓子など複数案を試作し、製品化に成功。地域ブランドとして販路拡大につながった。
● パッケージをリニューアル ──「第一印象」を共に再設計
家庭用品メーカー:購入者・店舗スタッフと“手に取りたくなる”をテーマに共創。色・素材・開けやすさを見直し、パッケージ刷新後に初回購入率が大幅に増加。
● ゼロからのアイデア出し ──「こんな商品あったらいいな」を共創で
雑貨系スタートアップ:生活者参加の妄想商品会議を開催。日常の不満や願望をヒントに複数の試作品を創出し、“欲しいから生まれた商品”を実現。
💡 共通の成功要因
- 生活者と一緒に「意味づけ」を行う:使い方・価値・体験の文脈を共有する。
- プロトタイプを見せながら対話する:言葉だけでなく「形」にして議論する。
- 当事者意識を育てる:社内外の関係者が「自分ごと」として関わる環境をつくる。
まとめ|共創ワークショップがもたらす変化
共創ワークショップは、単なる“アイデア出しの場”ではなく、組織の対話文化を育て、創造力を開く仕組みです。ここで紹介した10の手法を組み合わせ、自社の目的やテーマに合わせてカスタマイズしていくことで、「社員と顧客が一緒に価値をつくる」状態に近づいていきます。
まずは小さく始め、目的と相手を明確にしながら継続することが、未来の価値創造につながります。
📚 深掘りガイド
次のワークで“そのまま使える型”を集めました
「やり方は分かった。でも、実務で回すと詰まる」——その“詰まりどころ”を解消するための型を、テーマ別にまとめています。
台本・チェック・声かけ例まで載せているので、まずは気になるテーマを1つ、3分だけ覗いてみてください。
アジェンダの作り方
議論が散らかる/結論が出ない…を防ぐために。時間割と進行台本で、会議を“進む場”に変えます。
- 課題再定義/発散/合意形成の時間割
- 進行台本とチェック
心理的安全性を高める場づくり
声が出ないのは“人”ではなく“場”の設計かもしれません。6つのルールと難所の対処で、発言が自然に増えます。
- 6つのルール
- 声の拾い方・難所対処
アイスブレイク20選
最初の5分で空気は決まります。目的別に選べる台本つきで、初対面でも一気に話しやすく。
- 目的別・台本付き
- オンライン/大人数
ファシリ失敗あるあると対策
沈黙/脱線/対立…“あるある”は想定しておけば怖くない。リカバリ台本で整理しています。
- 兆候→原因→対処
- リカバリ台本
ふりかえり&記録の型
ワークを“やりっぱなし”にしないために。写真・原文カード・共有テンプレで、学びを次の行動に接続します。
- 写真・原文カード
- 共有テンプレ
顧客インサイトとは?
アンケートでは出ない“本音”をどう掘るか。見つけ方・質問例・原文カードで、インサイト発見を再現可能にします。
- 見つけ方・質問例
- 事例と原文カード
「自社の場合、どこから着手すべき?」を一緒に整理します
施策の優先順位は、業種・客層・販売チャネルで変わります。
まずは現状(行動×心理)を見立てて、最短ルートを設計しましょう。
※ 相談は「やり方・進行」からでもOKです。無理な営業はしません。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ