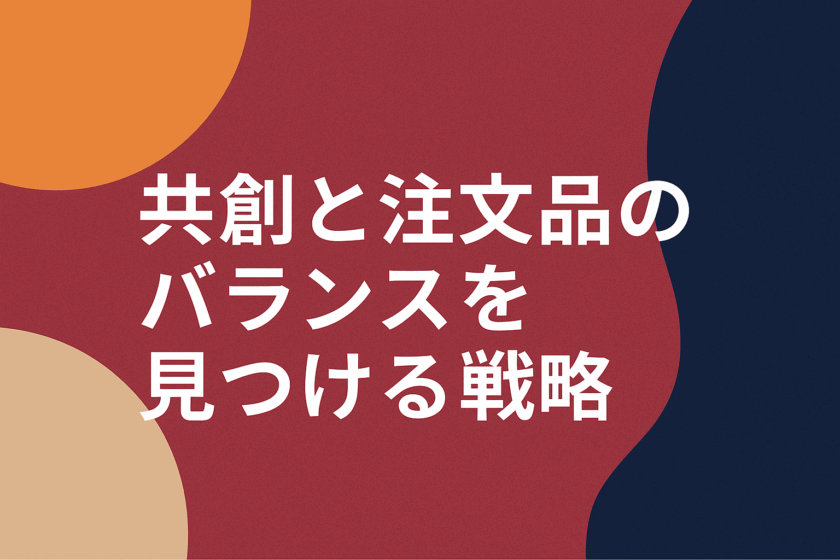「消費者の声を聞け」とはよく言われる言葉です。もちろんそれは重要です。しかし、企業が目指すべき真の価値創造は、単なる“注文通り”では到達できません。本当に求められているのは、「共に創る」こと、つまり共創なのです。
「もっと速い馬が欲しい」問題
「もし顧客に、彼らの望むものを聞いたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えただろう。」
この有名な言葉は、表面の要望ではなく、その背後にあるニーズを洞察する力が求められることを示しています。消費者は今ある枠組みの中でしか「欲しいもの」を語れない。だからこそ、企業側が一歩深く掘り下げる必要があるのです。
SNSの声は「需要」ではない
「バズったから売れる」は幻想です。SNSに投稿された声は、しばしば「一部の強い意見」に過ぎません。しかも、それは瞬間的な感情に基づくものであり、継続的な支持や購買に直結するとは限らないのです。
マーケティングリサーチの限界
調査データもまた、「過去」を基にしています。アンケート結果や行動履歴からは見えてこない、言語化されていない本音や未来志向の欲求にこそ、新しい価値の種が眠っています。
- 数字に現れない「想い」や「こだわり」
- 生活の中の違和感や小さな不満
- 感情や文脈に支えられた意思決定
注文品と共創の違い
注文品とは?
「○○の香りが欲しい」と言われたから作る石けん。これが典型的な“注文品”です。顧客のリクエストを忠実に再現する姿勢は誠実ですが、差別化が難しく、価格競争に巻き込まれるリスクもあります。
共創とは?
一方、共創ではこう尋ねます。「どんな気持ちのときに、どんな香りが欲しいですか?」。そこから生まれるのは、単なる“モノ”ではなく、文脈に根差したストーリー性ある商品です。
共創×注文品のバランス戦略
どちらか一方に偏る必要はありません。ポイントは、注文品的要望をきっかけに、共創的な探求へと発展させる設計です。
- 表面の声を「入り口」にする
- 共創によってストーリーや背景を掘り下げる
- 結果として“欲しいと言われていなかった”商品が生まれる
「抹茶の香りが欲しい」→「どんな時に、どんな気持ちでその香りが必要なのか?」→
“リラックスしたい夜に寄り添う抹茶石けん”という新たな切り口が生まれる。
まとめ:本当の価値は「声の奥」にある
これからの時代、生活者の声をどう拾うかではなく、どう共に創っていくかが鍵となります。
注文品=忠実な反映、
共創=対話による洞察と共感。
どちらも大切ですが、それぞれの役割と限界を知り、戦略的にバランスさせることが、真に価値あるマーケティングの姿だと言えるでしょう。