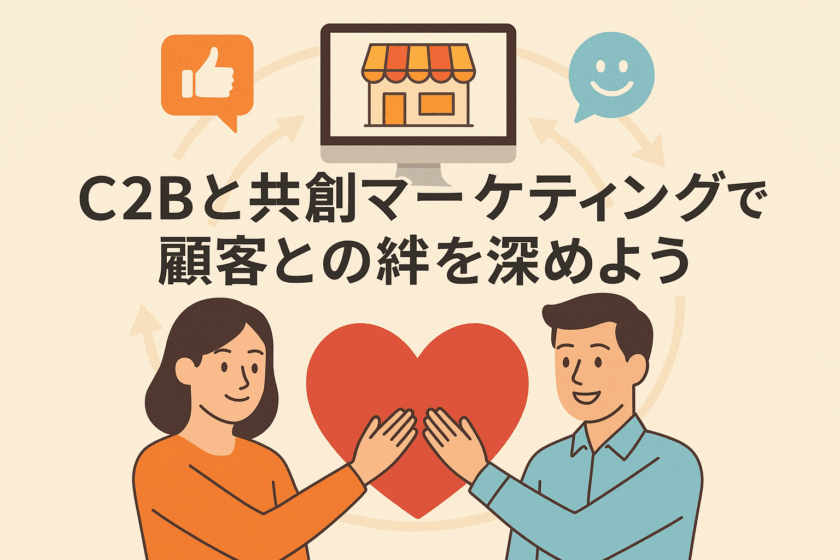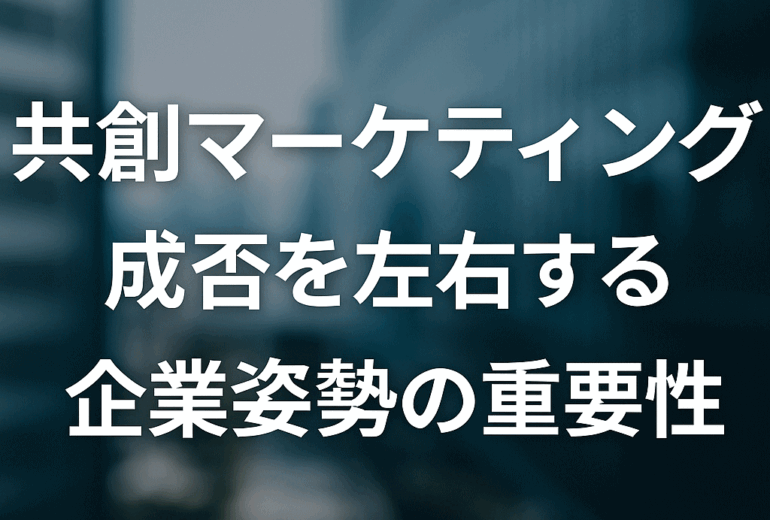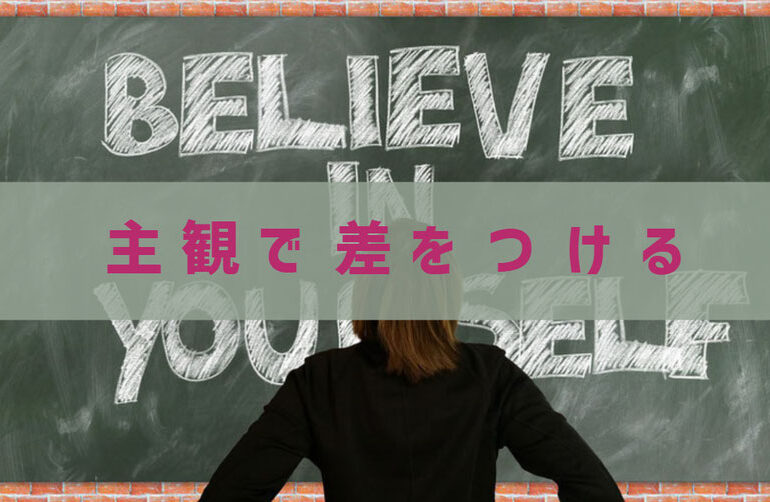導入:C2B(Consumer to Business)とは?
🔍 この記事でわかること
- C2Bと共創マーケティングの違いと共通点
- 顧客を「購入者」ではなくパートナーとして見る視点
- 中小企業でもできるC2B×共創の具体的な取り組み例
- デジタル時代に共創力を高める3つのポイント
1.「売る側」から「一緒につくる側」へ
ここ数年、C2B(Consumer to Business)という言葉を耳にする機会が増えてきました。従来の B2C(Business to Consumer)では、企業が商品やサービスを企画し、完成したものを市場に「届ける」ことが前提でした。
それに対してC2Bは、「顧客の声やアイデアが出発点になり、それをもとに企業が商品・サービスを形にしていく」 という、流れの向きが逆転したような考え方です。
- SNSでの「こんなサービスがあったらいいのに」というつぶやき
- ECサイトのレビューやアンケートで寄せられた不満や要望
- ファンコミュニティで交わされるアイデアや本音の会話
こうした“生活者の日常のつぶやき”が、次のビジネスのタネになる時代。顧客は単なる「情報の受け手」ではなく、 企業と一緒に市場をつくる存在へと変わりつつあります。
2.C2Bと共創マーケティングの共通点・違い
📊 C2Bと共創マーケティングのざっくり比較
| 項目 | C2B | 共創マーケティング |
|---|---|---|
| 出発点 | 顧客の声・要望 | 顧客と企業の対話・共感 |
| イメージ | 「顧客の声から企画が生まれる」 | 「一緒に市場や体験をつくる」 |
| 強み | ニーズに合った商品・サービス | 長期的な関係性・ファンづくり |
C2Bと非常に親和性が高いのが、共創マーケティングという考え方です。共創マーケティングとは、 企業と顧客(生活者)が、お互いの知恵や経験を持ち寄って価値を共につくり出すアプローチです。
両者の共通点は、大きく3つあります。
1)顧客起点で考える
「企業が売りたいもの」ではなく、「顧客が本当に望んでいること」から出発する。C2Bも共創マーケティングも、 この顧客起点の発想がベースになっています。
2)顧客の能動的な参加を前提にしている
アンケートにチェックだけしてもらうのではなく、 アイデア出し・試作品の評価・対話の場への参加など、顧客が「一緒に考え、一緒に悩む」パートナーになります。
3)関係性づくりそのものが価値になる
商品が売れたかどうかだけでなく、「このブランドは、ちゃんと私たちの声を聞いてくれる」という実感が、 信頼やファン化につながっていきます。
一方で、違いがあるとすれば、
・C2Bは「顧客 → 企業」という構造や流れの呼び名
・共創マーケティングは、アイデア発掘から商品化・コミュニケーションまでを含むプロセス全体の考え方
というイメージです。
C2B的な取り組みを、きちんと設計された共創プロセスの中に位置づけることで、 単発のキャンペーンで終わらない「長く続く関係」をつくることができます。
3.顧客を「購入者」ではなく「パートナー」として見る
C2Bや共創マーケティングを実践するうえで、最も大きな転換点は「顧客の見え方」を変えることです。
これまでのように、
・売上をつくってくれる“お客様”
・アンケートに答えてくれる“調査対象者”
としてではなく、「一緒に事業を育ててくれるパートナー」として見られるかどうか。
その視点の変化は、次のような具体的な行動に表れます。
- 不満やクレームを「攻撃」ではなく「改善のヒント」として受け止める
- 都合のいい意見だけを集めるのではなく、あえて耳の痛い声にも向き合う
- 「ご意見ありがとうございました」で終わらず、どう反映したかをきちんと伝える
「あなたの声が、私たちの事業を前に進めています」というメッセージを、言葉だけでなく行動で示せる企業は、 顧客からの信頼を着実に積み上げていきます。
4.中小企業でもできる、C2B×共創的な取り組み例
🍪 食品メーカー
製品のファンに試作品を食べてもらい、その場で一言フィードバックをもらう。気に入ったものだけを商品化検討。
🧴 日用品メーカー
候補企業の担当者と一緒に売場を見て回り、「なぜ売れているのか」を対話しながらOEMアイデアを整理。
💼 BtoBサービス
新サービス案を既存顧客数名にだけ共有し、「不安な点」「使う場面」をヒアリングしてから正式リリース。
「そんなのは大企業の話でしょ?」と思われがちですが、実は中小企業こそ、C2Bと共創マーケティングの相性が良いと言えます。
例えば――
- 試作品をこっそり食べてもらい、率直な一言をメモする企画担当者
- OEM先候補の担当者と一緒に売場や通販サイトを見て回り、「なぜ売れているのか」を対話する日用品メーカー
- 新サービス案を既存顧客数名にだけ共有し、「どこに不安を感じるか」「実際に使う場面がイメージできるか」を聞いてから形にするBtoB企業
特別なシステムや大きな予算がなくても、「顧客と一緒に考える時間をちゃんとつくること」から共創は始まります。
ポイントは、次の3つです。
- “聞いた感想”を集めっぱなしにしない
- 社内で共有し、次の企画や改善に結びつける
- 「あの時の声をこんな形で活かしました」と顧客に返す
このサイクルを短く、何度も回していくことで、小さな会社でも“C2B×共創”の強い武器を持つことができます。
5.デジタル時代だからこそ生きるC2B
⚙ デジタル時代にC2Bを活かす3ステップ
- “声”を拾う場所を決める(フォーム・SNS・コミュニティなど)
- リアクションを早く・正直に返す(できること/時間がかかることを分けて伝える)
- 「共創ストーリー」として発信する(声→改善→結果の流れを見せる)
インターネットやSNSの普及により、顧客が自分の声を届けるハードルは一気に下がりました。 X(旧Twitter)やInstagramでの投稿、オンラインコミュニティでの雑談、ECレビューや問い合わせフォームからのメッセージなど、 どれもが大切なヒントです。
デジタル時代にC2Bと共創マーケティングを生かすポイントは、次の3つです。
1)“声”を拾う場所を決めておく
自社サイトのお問い合わせフォーム、SNSのハッシュタグ、既存顧客向けの小さなオンラインアンケートなど、 「どこでどんな声を集めるのか」をざっくり設計しておきます。
2)リアクションを早く、正直に
「ご意見ありがとうございます」で終わらせず、すぐにできることは早めに反映し、 時間がかかることは経過も含めて共有することで、「本当に聞いてくれている」という実感につながります。
3)“共創のストーリー”として発信する
「こういう声をきっかけに、こんな改善をしました」「お客様のアイデアから生まれた新商品です」といったストーリーを、 ブログやSNSで伝えていくと、関わった顧客だけでなく、周りの人にも共感が広がります。
6.C2Bと共創マーケティングがもたらすもの
C2Bと共創マーケティングは、「顧客の声を聞いて、商品を少し直す」ためだけの手法ではありません。
・顧客が企業に対して、遠慮なく本音を言える関係
・企業が顧客に対して、「ちゃんと向き合っている」と胸を張って言える関係
・そのやりとり自体が、ブランドの信頼とファンを育てていくプロセス
このような、長く続く関係性を育てるための考え方です。価格や機能だけで差別化が難しくなっている今だからこそ、 「この会社と一緒に未来をつくりたい」と思ってもらえるかどうかが、最大の競争力になります。
顧客を“お客様”という枠に閉じ込めず、一緒に考え、一緒に悩み、一緒に喜ぶ 「共創パートナー」として迎え入れること。その第一歩として、
- C2B的な顧客の声の集め方を整えること
- 共創マーケティングの視点で、対話とプロセスを設計し直すこと
を、あなたのビジネスにも少しずつ取り入れてみませんか。
✅ まずはここから一歩だけやってみる
- 最近のお客様の声・クレーム・レビューを3件だけ選んで読み直す
- 社内で「この声から何が学べるか?」を5〜10分だけ話す時間をつくる
- 1つでいいので、「すぐできる小さな改善」を決めて実行してみる
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)