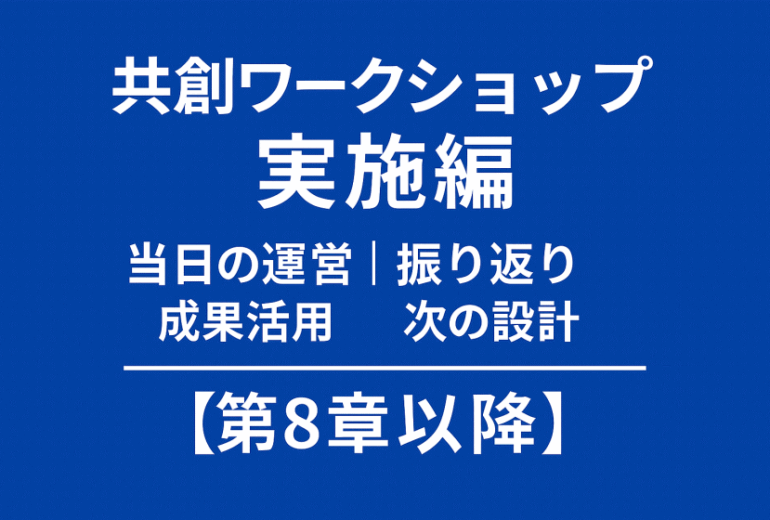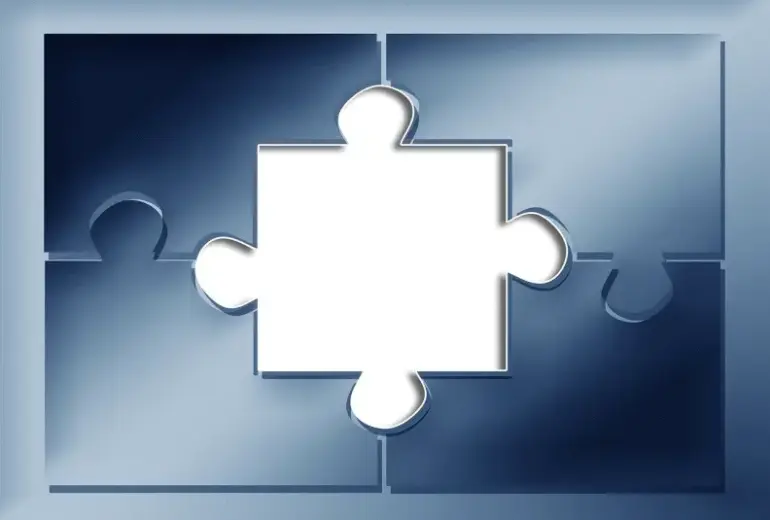・共創に必要なのは「地位」ではなく「関係性」
・“さん付け文化”が信頼と創造性を生む
・組織横断で「寄ってたかって考える」から新しい価値が生まれる
🧩 3行で結論(忙しい方向け)
- 共創が回るチームは、上下ではなく横の関係性で動いている
- “さん付け”は小さなルールだが、心理的安全性を一気に上げる
- 組織横断で「寄ってたかって」考えると、意思決定が速くなり、学びが残る
“なんでも言える”空気が価値を生む
こらぼたうんが企業と共に共創マーケティングを進める際、最初にお願いしていることがあります。
それは「年齢・役職に関係なく、全員を“さん付け”で呼び合うこと」です。
たった一つのルールですが、ここが整うと、共創の質が変わります。
共創の場では、立場や年齢の序列よりも、気づき・意見・違和感が価値を生むからです。
一人のリーダーが引っ張るのではなく、全員がそれぞれの視点で力を発揮する。これがシェアド・リーダーシップの入口になります。

スピードの早い時代、ひとつの正解を探すよりも、チーム全員で考え、試し、修正していく柔軟さが求められます。
上からの指示で動くのではなく、“誰からでも意見が出る状態”をいかにつくれるか。ここが共創を成功に導く鍵です。
ズレを早く見つけて修正できる強さであり、共創のスピードを上げる仕組みです。
シェアド・リーダーシップとは何か?
「シェアド(Shared)」とは、“分かち合う”“共有する”という意味。
つまり「一人のリーダーに依存せず、全員がリーダーシップを発揮する状態」を指します。
⬇️ 垂直的リーダーシップ(従来型)
- 意思決定が「上→下」で流れる
- 指示待ちが起きやすい
- 現場の違和感が上に届きにくい
↔️ シェアド・リーダーシップ(共創向き)
- チーム全員が影響し合う
- 役職より意見・行動・気づきが尊重される
- ズレの修正が早く、学びが残る

価値共創の現場では、生活者もチームの一員です。上下関係ではなく、対話と信頼が価値を生む。
この関係性ができたとき、生活者の本音や隠れたニーズが、自然に表れてきます。
縦ではなく横──創造が生まれる関係
新しい価値は、異なる意見や視点が混ざり合うことで生まれます。
誰か一人が引っ張るよりも、チーム全員がアイデアを出し合うほうが、はるかに創造的です。
たとえば商品企画の会議に、営業・開発・広報・カスタマーサポートなどの他部署を加えると、想定外の視点が生まれます。
ある人の発言が別の人の気づきを呼び、そこから新しい発想が連鎖していく──この状態が、共創の強さです。
部署や役職を超えて、互いに刺激し合う環境こそが創造の土壌です。
この「横のつながり」を促すのがシェアド・リーダーシップであり、共創マーケティングの真髄です。
組織を越えて「寄ってたかって考える」
こらぼたうんの共創支援では、企業と生活者が一緒に商品を考える場に、あえて企画部門だけでなく営業や開発担当者も参加してもらいます。
「現場で何が起きているのか」「どこで詰まるのか」を、同じ場で共有できるからです。

✅ 目に見える効果
- 意思決定のスピードが上がる
- 調整コストが減り、やり直しが減る
- 顧客変化への反応が早くなる
✨ 実は大きい効果
- 部署間の“誤解”が減る
- 情報共有が自然に回り始める
- 「自分ごと」として実行されやすくなる
“寄ってたかって”という言葉には、少しユーモアも込めています。
でも実際、複数の部署や生活者が一堂に会して真剣に語り合う姿こそが、共創の理想形です。
こうした「寄ってたかって」型の取り組みは、部署や立場を越えて共創を進める際に非常に効果的です。
詳しくは、「寄ってたかってやってみよう」もご覧ください。
まとめ:立場を超えて共創するチームへ
「あの部署が考えた商品は売れない」「どうせ上が決める」──そんな言葉が社内で聞こえるうちは、共創は始まりません。
共創マーケティングの現場では、誰か一人がリーダーシップを独占するのではなく、全員が“共創型リーダー”になることが大切です。
立場や年齢、役職を越えて、「なんでも言える」「本音で話せる」関係性を築く。
その中で、一人ひとりの想いとアイデアが混ざり合い、組織も商品も変わっていきます。
それが共創マーケティングの醍醐味です。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)