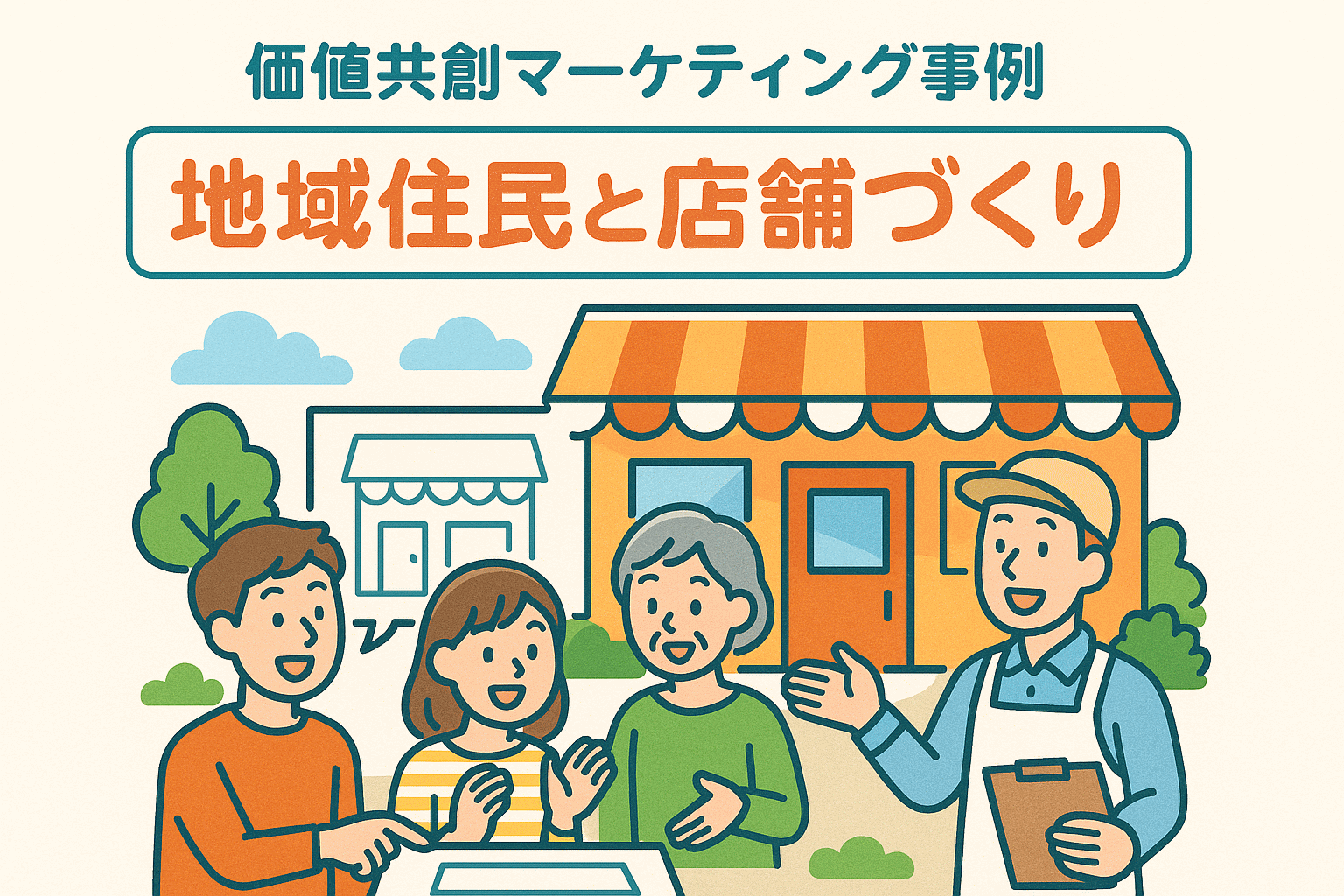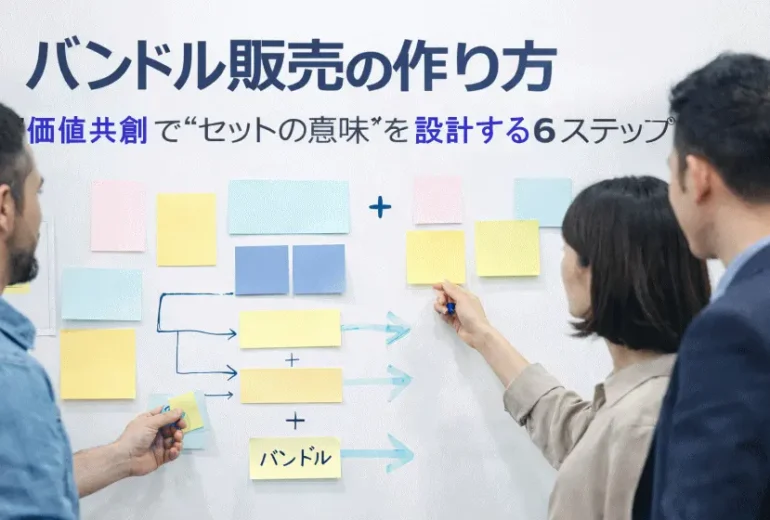まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。
テクノロジーの進化により、共創のあり方は大きく変わりました。SNS、オンラインフォーラム、クラウド上のコラボレーションツール―― いまや世界中の人々が、場所や時間の制約を越えてアイデアを交わし、プロジェクトを進められます。
その一方で、便利さと引き換えに見落としがちなものがあります。――それが、 「リアルな場に身を置いて、顔を合わせて話す」ことの力です。
“空気感”から生まれる信頼と共感
対面の共創には、オンラインでは得がたい「空気感」があります。呼吸を合わせる相づち、目線の交わり、沈黙の間合い、そして場に流れる雰囲気―― これらはすべて、言葉以上のメッセージを発しています。
価値共創では、意見を「情報」として受け取るだけでは足りません。 参加者それぞれの背景・文脈・気持ちに耳を澄ませることで、初めて「本当に届けるべき価値」が輪郭を持ちます。 そのとき必要になるのが、リアルな場でしか得にくい“身体感覚”です。
リアルではそれが拾えるからこそ、「この言葉の奥に、もっと大事な気づきがある」と感じ取れます。
雑談や余白が“共創の芽”を育てる
共創の場づくりで意外と大切なのが「余白のある時間」です。 会議室に集まり、あいさつを交わし、お茶を飲みながら話す―― 一見非効率に見える時間の中に、相手の人間性や価値観を感じ取り、関係性を耕すチャンスがあります。
実際、共創セッションでは「休憩中のふとした一言」や「雑談から派生したアイデア」が、後の革新につながることが少なくありません。 偶発性が混ざることで、共創は“予定調和”から抜け出します。
一体感が行動を生む
共創を一過性のイベントにしないためには、「熱量」と「共感の連鎖」が必要です。 リアルの場でともに悩み、笑い、うなずきあった経験は、参加者の心に強く残ります。 そして「自分ごと」として、その後の行動につながります。
リアル共創が“広がり”に変わる瞬間
ある企業が新商品開発の共創ワークショップを、あえて対面で実施しました。
普段SNSでつながっていた顧客層が、リアルに会って互いの熱意を交わす中で
「こんなに真剣に考えてくれていたんだ」という気づきが何度も生まれたのです。
結果としてプロジェクトは商品化にとどまらず、ファンが広報やイベントにも自発的に関わる形へと広がりました。
「あの場にいたから」という経験が、行動を自然に引き出したのです。
特に“顔の見える共創”は、地域密着の店舗づくりや商店街の再活性化、まちづくりなどで大きな効果を発揮します。 住民や顧客と実際に会い、声を聞き、想いを共有することで、単なるニーズ把握を超えた 「共に育てる関係性」が築かれ、その場そのものが愛されるブランドへと育っていきます。
参考事例
リアルとオンライン、それぞれの役割を見極める
もちろん、オンライン共創にはオンラインならではの強みがあります。遠方の人々とすぐに接続できる、記録が残る、反復しやすい―― これらは、アイデアの収集や全体管理にとって非常に有効です。
こらぼたうんでも、オンラインのワークショップやヒアリング、情報共有の場を積極的に取り入れています。 参加者が時間や場所の制約を受けずに関われることで、多様な視点が集まりやすくなるという利点があります。
信頼構築・深い対話はリアル、整理・継続はオンライン――補完関係として設計すると共創は強くなります。
オンライン共創とリアル共創の違い
| オンライン共創 | リアル共創 |
|---|---|
| 時間・場所に縛られず、遠隔でも参加しやすい | その場の空気感・感情のやりとりを共有しやすい |
| 録画やログで記録が残りやすい | 表情や沈黙など、非言語情報が受け取りやすい |
| 参加のハードルが低く、多様な人を巻き込みやすい | 関係性が深まり、信頼と共感が生まれやすい |
| 短時間で目的を絞った議論に適している | 雑談や余白が偶発的なアイデアを生みやすい |
| 多拠点・多人数の情報共有に強い | 「その場にいる」体験が一体感や当事者意識を育む |
だからこそ、“会う”という選択を大切にしたい
すべてがオンラインで完結する時代だからこそ、あえて「会いに行く」「顔を合わせる」ことの価値は、むしろ高まっているように思います。 それは非効率かもしれません。コストも時間もかかるでしょう。 でも、一度リアルに築いた関係性は、何より強く、深く、持続的です。
共創とは、単にアイデアを出し合うことではなく、「ともに考え、ともに育て、ともに前に進む」関係性そのもの。 その土壌を耕すのは、やはり人と人が直接向き合う時間に他なりません。
デジタルが進化するほど、リアルで会う価値は“消える”どころか“濃くなる”。
だから私は、顔を合わせる共創に、これからもこだわり続けたいと思うのです。
この記事のポイント
- リアルの空気感が、信頼・共感・洞察を生む
- 雑談や余白が、予定調和を超えるアイデアを育てる
- 一体感が当事者意識になり、行動が続く
- オンラインは整理・継続・多様性に強い
- 結論は「対立」ではなく補完として設計すること
まずは 価値共創マーケティングのフレームワーク を確認してから読み進めると理解が深まります。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)