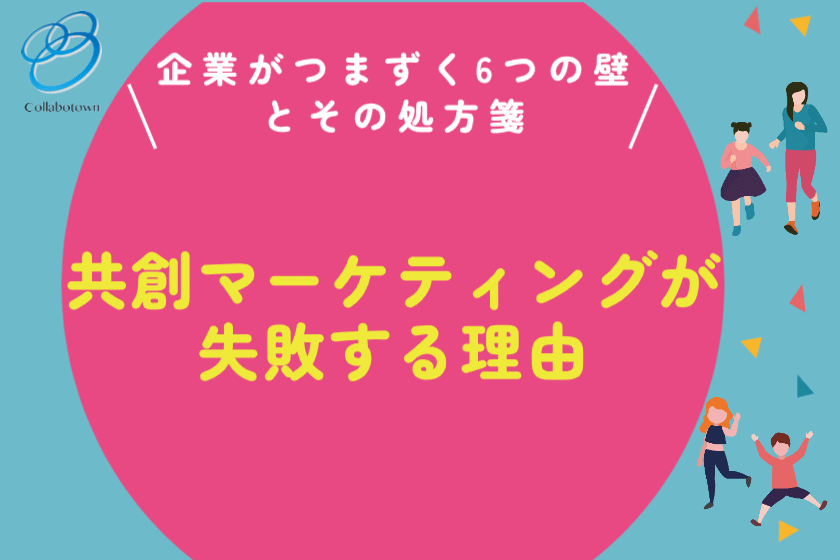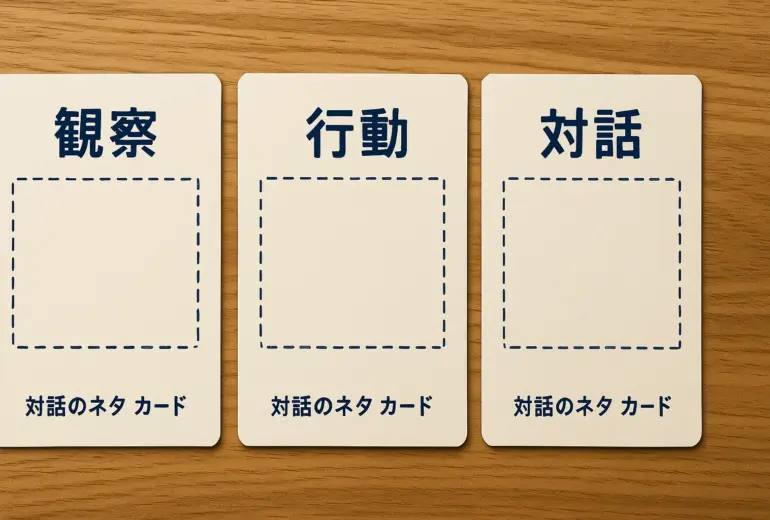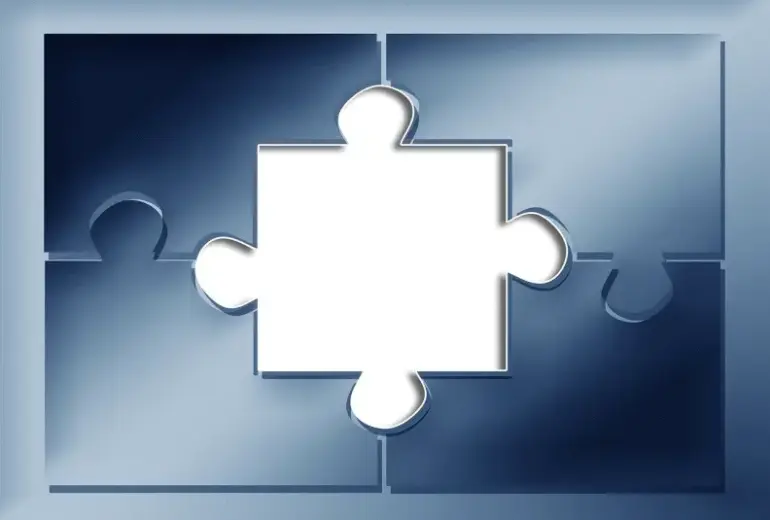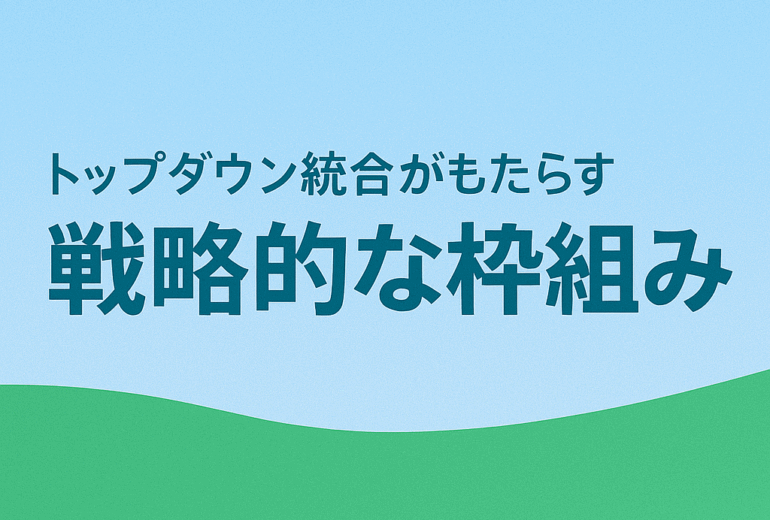この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。
この記事の結論
共創マーケティングは、始め方を間違えると「盛り上がったのに進まない」「声は集まったのに活きない」になりがちです。
ただし、つまずきには典型パターン(壁)があり、順番に手当てすれば、現場はちゃんと前に進みます。
なお、導入前の不安やよくあるQ&Aは 共創導入前に知っておきたいQ&Aと失敗回避のチェックリスト もあわせてご覧ください。
共創マーケティングは、企業と顧客(生活者)が双方向の関係性を築きながら、新たな価値をともに創り出す戦略的アプローチです。 消費者の声を「情報」としてではなく、「共に育てる価値の源泉」として捉える視点は、今後の持続可能な経営やブランド形成に欠かせない考え方として注目されています。
一方で、導入時に組織構造・文化・設計・仕組みのどこかが欠けると、 「思ったように成果が出ない」「途中で頓挫した」という形になりがちです。 ここからは、現場でよく起きる6つの壁と、その処方箋を整理します。
壁1:縦割りで“誰が責任を持つか”が曖昧
1組織構造の壁
よくある症状
- 企画は頑張るが、営業・広報・CSがバラバラ
- 顧客接点の言い方が統一されず、信頼が積み上がらない
- 「誰が最終判断するのか」が曖昧で止まる
起きる理由
- マーケ部門が販促扱いで、戦略機能が弱い
- 横串の会議がなく、情報が部門内に閉じる
処方箋:最小単位で“横串”を作る
- 経営層主導で「全社横断の意思」を明言する
- 部門横断の共創推進チームを設置(週1・30分でもOK)
- 「マーケ=販促」ではなく価値創造として再定義
すぐやる一手:営業・企画・広報(またはCS)の3名で「共創の目的/判断者/次の一歩」をA4一枚に書き出し、共有する。
壁2:「やってみた」で終わる(戦略不在)
2戦略の壁
よくある症状
- SNSやコミュニティを作ったが、成果が説明できない
- 声は集まったのに、どこに反映するか決まらない
- 担当者が疲弊して自然消滅
起きる理由
- 目的・KPI・運用ルールがない
- 「何をもって成功か」が曖昧で判断できない
処方箋:“共創の位置づけ”を言語化する
- 中期計画・ブランド戦略の中で、共創の役割を一文で定義
- KPIは定量+定性で設計(参加率/採用率/満足度 など)
- 成果は「企画化→商品化→販売」まで追い、定期共有する
すぐやる一手:「何を生み出したい共創か(例:選ぶ理由/提案トーク/新用途)」を1つ決め、KPIを3つだけ置く。
壁3:トップの理解不足/現場の納得感不足
3文化・意識の壁
よくある症状
- 「また新しい施策が来た」と冷める
- やらされ感が強く、場が“無難な意見”になる
- 「どうせ採用されない」が蔓延
起きる理由
- プロダクトアウト/営業主導の文化が強い
- 成果や変化が見えず、体感がない
処方箋:行動と“見える化”で納得を作る
- トップが共創の場に短時間でも参加し、姿勢を示す
- 小さな成功を早期に共有(社内報/朝礼/社長メッセージ)
- 共創への貢献を評価・表彰に反映させる
すぐやる一手:「参加者の声→変えたこと→結果」を1枚の“共創レポート”にして、社内に掲示する。
壁4:参加設計ミス(関わりしろがない)
4顧客参加設計の壁
よくある症状
- 「ご意見ください」で終わり、参加者が受け身
- 集まる声が断片的で、結局使えない
- “共創している実感”がなく、離脱する
起きる理由
- 誰に/何を/どの深さで聞くかが曖昧
- 関与度(育てる・試す・決める)の設計がない
処方箋:“関わりしろ”を段階設計する
- 「共に創りたい顧客像」を明確に(属性より生活文脈)
- 意見収集→アイデア育成→試作品FBまで、参加を段階化
- オンラインだけでなく、座談会・買い物同行なども組み合わせる
すぐやる一手:参加者に「あなたの意見でここが変わりました」を必ず返す(返信テンプレを作る)。
壁5:一過性(キャンペーンで終わる)
5継続性の壁
よくある症状
- 実施して満足し、次が決まらない
- 参加者へのフォローがなく、関係が深まらない
- 短期数字で評価され、打ち切りになる
起きる理由
- 共創をイベント扱いしてしまう
- 関係性を積み上げる設計がない
処方箋:「イベント→日常」へ接続する
- 終了後の情報発信・フィードバックを必ず行う
- コミュニティ運営を小さく継続(頻度より“途切れない”)
- 顧客とともに成長する“ブランドストーリー”を社内共有
すぐやる一手:共創後の「次の連絡日」を決めてから解散する(例:2週間後に経過報告)。
壁6:声が活かされない(仕組み未整備)
6仕組みの壁
よくある症状
- 声は集まったのに「誰が見るの?」で止まる
- 採用/不採用の判断が曖昧で、納得が生まれない
- 結局“お蔵入り”が増え、熱が冷める
起きる理由
- 収集→選定→実装の流れが定義されていない
- スピードが遅く、体感が積み上がらない
処方箋:「扱い方の型」を作る
- 顧客の声を扱う専任(兼務でもOK)を決める
- 変化を“見える化”し、社内共有&社外発信を徹底
- 小さく速く試す(試作→検証→改善)仕組みを用意する
すぐやる一手:「採用する声の条件」を3つだけ決める(頻度/影響度/実装難易度)。
まとめ:失敗しない“最初の整え方”
押さえるべき3本柱
- 戦略的な位置づけ(何を生み出す共創かを言語化)
- トップの関与(行動で示し、成功を早期に共有)
- 継続的な関係性設計(イベント→日常へ接続)
共創マーケティングは“魔法の杖”ではありません。ですが、壁を見立てて順番に整えれば、 顧客との信頼を土台に「選ばれる理由」を育てる力として、確実に効いてきます。
もし「どの壁から手当てすべきか」「自社の場合は何がボトルネックか」を整理したい場合は、 現状の体制・顧客接点・運用の流れを一緒に棚卸しし、最短で効く打ち手に落とし込むことも可能です。
「失敗の壁」を越える共創設計を、一緒に整えます
共創を始めたのに進まない/声が活きない/部門間で止まる…という場合、
目的(位置づけ)・参加設計・社内の回し方(仕組み)を整えるだけで、成果の出方が大きく変わります。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ