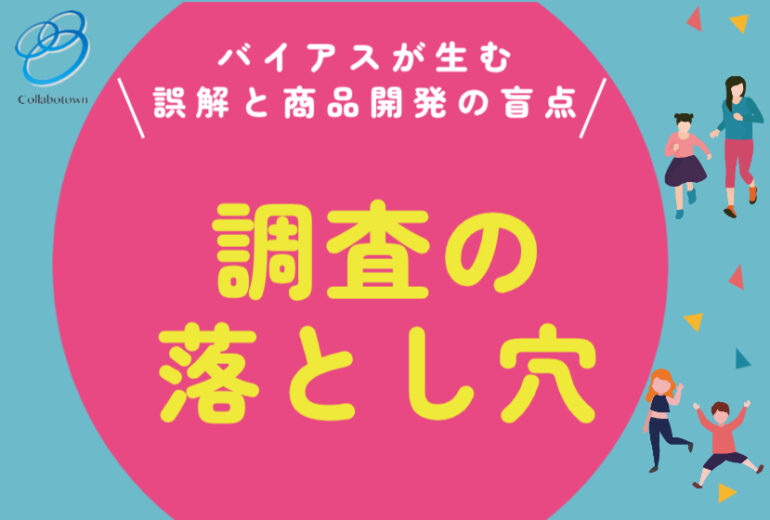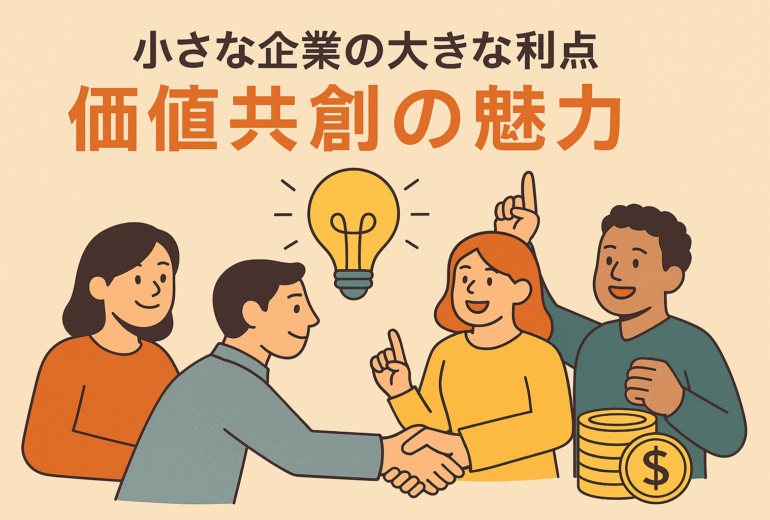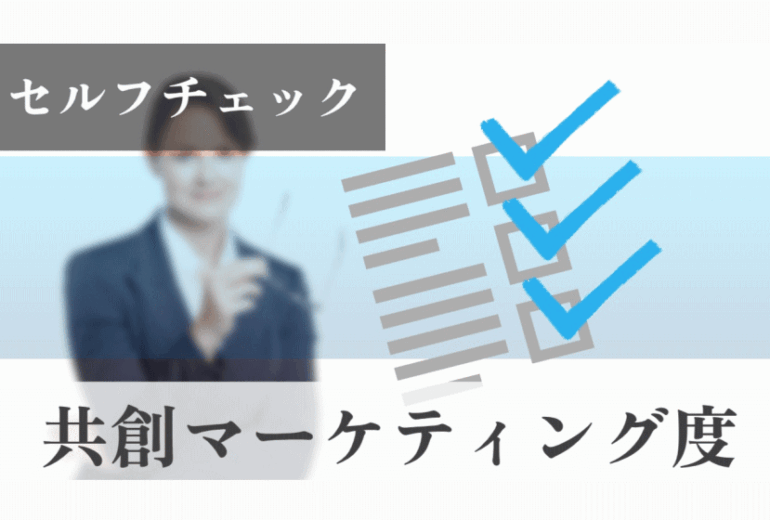1. はじめに──“共創”という言葉が誤解されていないか?
ここ数年、「共創(きょうそう)」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。
企業と生活者が一緒に取り組む商品開発、ユーザー参加型のキャンペーン、SNSでの意見募集──一見すると、消費者の声に寄り添う姿勢が広がっているようにも見えます。
しかし、その中には、「共創」の本質をすり替えてしまっている取り組みも散見されます。
たとえば、すでに企画の骨子が固まっているのに「一緒につくりました」と後付けで見せるケース。あるいは、生活者の声を本当に聴くことなく「共創風の演出」だけを目的としたイベント──。
そうした形だけの共創は、企業と生活者の信頼関係を逆に損ねかねません。
本来、共創は「本当に良いものを、一緒につくっていく営み」であるはずです。単なる広告宣伝や話題づくりとは一線を画す、“誠実なものづくりのプロセス”こそが、共創の真価なのです。
2. PR型“なんちゃって共創”と本質的な共創の違い
共創を名乗りながらも、実態は「広告・宣伝の延長」にすぎない活動も少なくありません。ここでは、PR型“なんちゃって共創”と、本質的な共創の違いを一覧で整理します。
| PR型“なんちゃって共創” | 本質的な共創 |
|---|---|
| 話題性やメディア映えがゴール | 新しい価値の発見・創造がゴール |
| 生活者の声は「演出用の材料」 | 生活者の声は「気づきの源泉」 |
| 既に決まった企画に“後付け”で参加を装う | ゼロから共に考え、形をつくり上げる |
| 短期的なキャンペーンで終了 | 継続的な対話と学びが積み重なる |
| 企業主体でコントロールする | 企業と生活者が対等なパートナーになる |
この表にある通り、両者は似ているようで根本がまったく異なります。
「生活者を巻き込んで見せるための共創」か、「生活者と本当に未来を創るための共創」か──その違いが、企業の姿勢を如実に表しているのです。
3. 共創のよくある失敗事例
共創を掲げても、実際にはうまくいかないケースが少なくありません。
よくある失敗パターンを整理しました。
- ⚠️ 参加者を「イベント客」にしてしまう
→ その場限りで終わり、意見が商品やサービスに反映されない。 - ⚠️ すでに決まった企画に「後付け共創」
→ 実は完成品に形だけ参加させるため、不信感を招く。 - ⚠️ 意見を“都合のいい部分”だけ切り取る
→ 批判や本質的な声を無視し、参加者は「利用された」と感じる。 - ⚠️ PR目的が透けて見える
→ 拡散狙いが見えてしまい、ブランドが安っぽくなる。 - ⚠️ 社内の合意形成が不十分
→ 実行に移せず「共創は形だけ」という評価になる。 - ⚠️ 継続性がない
→ イベントで終わり、知見も信頼も積み重ならない。
4. 共創のよくある成功事例
失敗パターンと対で、「何がうまくいくのか」を一目で把握できるように整理しました。
- ✅ 生活者の声を企画に反映
→ ワークショップの気づきから改善。「自分の声が形になった」と実感が生まれ、購入や口コミに直結。 - ✅ 試作品段階からの共創
→ 完成前に見せて意見を反映。物語共有で愛着が育ち、完成度と市場適合が高まる。 - ✅ 継続コミュニティ運営
→ 単発で終わらせず、オンライン/オフラインで継続。共創ファンが育ち、「共感の資産」を蓄積。 - ✅ 社内の学習と横断連携を促進
→ 社員が現場の声を直接聴く。部門横断での合意形成が進み、改善が迅速に回る。 - ✅ 社会的意義を持つテーマ設定
→ 環境配慮・地域共生などを共創に組み込む。参加動機が強まり、ブランド価値とメディア露出が相乗的に向上。
成功の共通点: 反映(採用)・共有(プロセスの見える化)・継続(場の積み上げ)の3点を設計に織り込みます。
5. 本来の共創の目的は“価値をつくること”
共創の本質は、「新しい価値を生活者とともに生み出す」ことにあります。
企業が「何をしてもらうか」を考えるのではなく、生活者の視点に学び、共に答えを探す姿勢そのものが重要です。
● 「生活者の声」は“正解”ではなく“気づき”
生活者の言葉には、企業が見落としていた文脈があります。声そのものが解決策ではなく、そこから「何が本当に大切か」を探るのが共創の第一歩です。
● 共創は“プロセスそのもの”に価値がある
共創はアウトプットだけでなく、その過程にも価値があります。対話や試行錯誤を通じて、参加者の実感と信頼が芽生えます。
また社員にとっても、現場に触れ、生活者と対話する経験は学びと成長の機会になります。部門を超えて関わることで、組織全体の柔軟性や創造性も高まります。
🔍 要点まとめ
- 共創は広告ではない —— “見せかけ”ではなく、価値を共につくる営み。
- 失敗例に共通するのは —— 生活者の声を活かさず、企業都合に寄せること。
- 成功の鍵は —— 反映・共有・継続の3点を設計に組み込むこと。
まとめ──“つくる共創”を、本気で取り組むあなたと共に
共創は、単なるブームやプロモーションの手段ではありません。
生活者のリアルな声に耳を傾け、ともに悩み、試し、磨き上げていく──そこにこそ、本当の価値があります。
形だけの“なんちゃって共創”ではなく、生活者との対等な関係を築きながら、共に未来をつくろうとする企業やチームこそが、これからの時代に選ばれる存在になると、私たちは信じています。
こらぼたうんは、そうした“本気の共創”を実践する人たちの伴走者として、日々活動しています。
・「形にしたい想いがあるけれど、どこから始めたらいいかわからない」
・「社内を巻き込んで共創に取り組みたいが、理解が得られない」
・「本音を引き出す共創の設計や進め方に悩んでいる」
こうした声に応えながら、企業と生活者の間に“共感の橋”を架け、持続可能で意味のある共創の場づくりを支援しています。
共創は手段ではなく、未来を変える力です。
こらぼたうんは、その力を本気で信じ、実践するあなたと共に歩んでいきます。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)