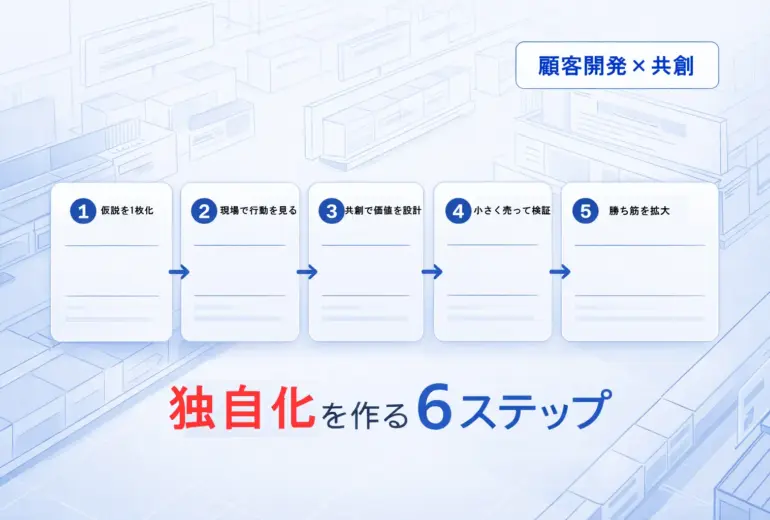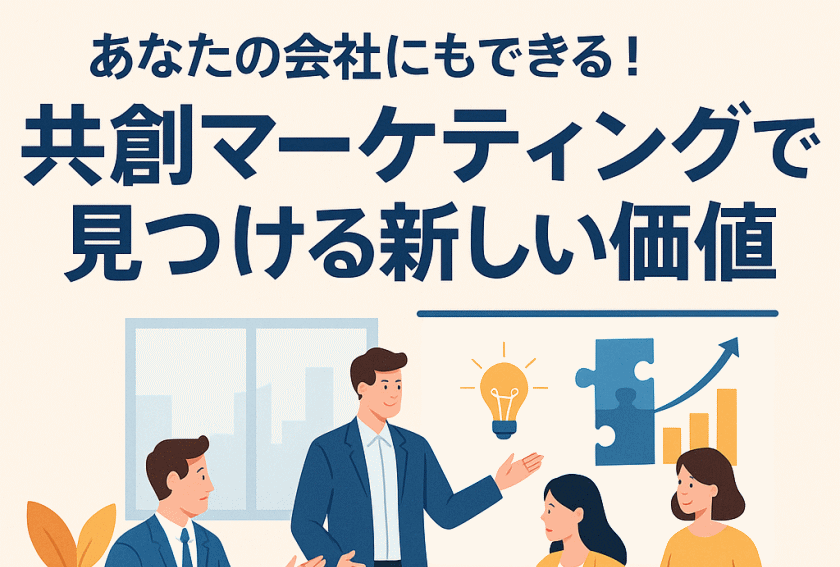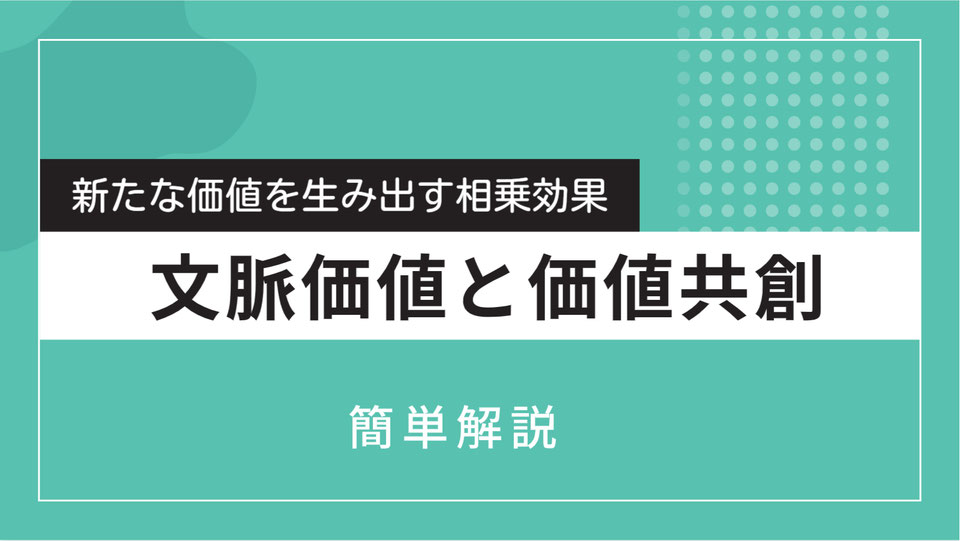カノニカルタグ
定義
カノニカルタグ(canonical)とは、複数のURLで同一・類似コンテンツが存在する場合に、検索エンジンへ「正規URL(評価を集約したいURL)」を伝えるための指定です。
HTMLの<head>内に <link rel="canonical" href="正規URL"> を記述します。
使われる主なケース
- パラメータ付きURL: 例)
?utm_source=などのトラッキング付きページ。 - 並び替え・絞り込み: ECのソート/フィルタでURLが増えるケース。
- HTTPとHTTPS・wwwの有無: 同一内容が複数ホスト/プロトコルに存在。
- 複製/転載ページ: 同内容を複数のカテゴリやドメインに掲載。
- 印刷用ページ: /print/ など別テンプレートの重複回避。
効果
- 評価の集約: 被リンクや利用指標が正規URLに集中しやすい。
- 重複コンテンツ対策: インデックスの無駄と順位低下リスクを軽減。
- クロール効率化: クローラが重要ページにリソースを割きやすくなる。
実装のポイント
- 自己参照(セルフカノニカル): 正規ページ自身にも絶対URLで設定。
- URL表記の一貫性:
https:///www有無//の末尾などを統一。 - 1ページ1つ: カノニカルの多重指定は避ける。
- Noindexとの併用に注意:
noindexと矛盾する指示は避ける。 - hreflangと整合: 多言語/地域ターゲットでは、各言語版が自分自身をcanonicalにし、
hreflangで相互参照。 - クロスドメイン: 別ドメインの正規URLを指す「クロスドメイン・カノニカル」も可(合意と運用管理を明確に)。
- ページネーション: 1,2,3…の各ページは各自を正規にするのが基本(第1ページへ一律で向けない)。
- 恒久的な統合はリダイレクト: 本当に統合するなら
301リダイレクトを検討。
よくある誤用と対策
- 相対パス指定: 環境で解決が変わるため絶対URLにする。
- 正規URLが404/リダイレクト先: 正規URLは200で即時表示される実体ページに。
- 内容が異なるのに同じ正規: 別内容を無理に統合しない。検索意図ごとにページを分ける。
- パラメータを正規にしてしまう: 基本はパラメータなしのクリーンURLを正規に。
- CMSテンプレの二重出力: テーマやプラグインで重複していないか確認。
FAQ
- Q. カノニカルを入れれば重複は必ず解決しますか?
- A. 強いシグナルですが「指示」であり、最終判断は検索エンジン側です。他の要素(内部リンク、サイトマップ、リダイレクト)とも整合させましょう。
- Q. UTM付きURLからの評価は正規URLに移りますか?
- A. 適切に正規指定していれば、評価は正規URLに集約されやすくなります。
- Q. 正規URLはサイトマップにも入れるべき?
- A. はい。サイトマップは正規URLのみを掲載するのが原則です。
👉 他の用語も調べたい方はこちら