「顧客ロイヤリティ」とは、顧客が企業やその商品・サービスに対して感じる愛着・信頼・継続意向を指します。単なる「満足したからまた買う」という表層的な関係性ではなく、「この企業を応援したい」「このブランドとともに成長したい」といった心理的な絆の強さを含みます。
実際、競合商品が溢れる現代では、性能や価格だけで選ばれる時代は終わりました。似たような品質・価格帯の商品が並ぶ中、選ばれる理由は「共感できるか」「信頼できるか」「好きかどうか」といった心理的な要因にシフトしています。これが、顧客ロイヤリティの重要性が高まっている背景です。
顧客ロイヤリティは2つの軸で成り立つ
顧客ロイヤリティには、「心理ロイヤリティ」と「行動ロイヤリティ」の2つの側面があります。
顧客ロイヤリティは単一の要素ではなく、大きく分けて2つの側面から成り立っています。それが「心理ロイヤリティ」と「行動ロイヤリティ」です。これらは密接に関連しながらも、それぞれ異なる観点から顧客の忠誠度を表すものです。
- 心理ロイヤリティ:これは顧客が企業やブランド、商品・サービスに対して抱く好意・信頼・愛着・共感など、内面的な感情や認識を指します。「このブランドが好き」「この企業の考え方に共感する」「このサービスには安心感がある」といった感情が、心理ロイヤリティの表れです。SNSでの応援投稿やブランドイベントへの参加、アンケートやフィードバックへの協力といった行動も、心理的なつながりがあるからこそ生まれます。
- 行動ロイヤリティ:これは実際の購買・利用・推奨など、顧客の行動として表出する忠誠心を意味します。たとえば、特定のブランドの商品を継続して購入している、ポイントを貯めている、知人に積極的に薦めているといった具体的な行動です。また、解約せずにサブスクリプションを継続していたり、キャンペーンに積極的に参加することも、行動ロイヤリティの一環です。
心理ロイヤリティと行動ロイヤリティは両方が高い状態が理想ですが、現実にはどちらか一方が高くもう一方が低いというケースも多くあります。
- 心理ロイヤリティは高いが行動が伴っていない:ブランドには共感しているが、価格や利便性の面で他社を選んでしまう。
- 行動ロイヤリティは高いが心理的つながりが弱い:利便性や習慣で使っているだけで、状況が変われば他社に乗り換える可能性がある。
そのため、企業が顧客ロイヤリティを高めるには、「感情(心理)」と「行動」の両面を意識した施策設計が重要です。共創マーケティングのように、顧客と共に価値を生み出すアプローチは、心理的な絆と具体的な行動の両方を引き出す上で非常に有効といえるでしょう。
この2つを同時に育てていくことが、持続的な事業成長の基盤となるのです。
企業の成長を支える顧客ロイヤリティのメリット
顧客ロイヤリティを高めることにより、企業には多くの戦略的メリットがもたらされます。ロイヤルな顧客は単なるリピーターではなく、企業にとって長期的な価値を生み出す“共創パートナー”にもなり得る存在です。以下に代表的な5つのメリットを詳しくご紹介します。
- リピート率の向上:
顧客ロイヤリティが高い顧客は、一度購入した商品・サービスに満足し、さらに「この企業だから買いたい」「他には替えがきかない」という気持ちを持っています。そのため、多少価格が高くても継続的に購入してくれる傾向があります。特に日用品やサブスク型ビジネスにおいては、このリピート率の高さが安定した収益基盤となります。 - 顧客単価の上昇:
信頼しているブランドの商品であれば、顧客は価格だけで判断しなくなります。結果として、高単価商品にも抵抗が少なく、アップセル(より高価格な商品への誘導)やクロスセル(関連商品の提案)がしやすくなります。「このブランドが勧めるなら間違いない」という信頼感が、購買単価の向上につながるのです。 - 口コミの拡散:
心から信頼しているブランドについては、顧客は積極的に他者に紹介したくなるものです。SNS投稿やレビューサイト、ブログなどを通じてリアルな声が拡散され、新たな顧客を呼び込む「自然な広告塔」としての役割を果たします。特に共感や感動体験があれば、それは強力な口コミ資源になります。 - 解約率の低下:
サブスクリプション型サービスでは、解約率をいかに下げるかが重要な指標です。顧客ロイヤリティが高い顧客は、「一時的な不満」や「他社のキャンペーン」では動じず、長く継続して利用してくれます。「このブランドを応援したい」「使い続けたい」という気持ちは、顧客維持に直結します。 - 新サービスへの関心:
ロイヤル顧客は企業のビジョンや価値観にも共感しているため、新商品のリリースや新規事業への取り組みに対しても好意的です。「応援したい」「誰よりも早く使いたい」という心理が働き、モニター参加や初期購入、フィードバック提供といった形で事業成長に協力してくれます。まさに価値共創の担い手とも言える存在です。
これらは一時的な販促では得られない、「ブランドとともに生きる顧客」だからこそ起きる現象です。
顧客満足度との違い──ロイヤリティは“心の絆”を育てる視点
顧客ロイヤリティと混同されやすい概念に「顧客満足度(Customer Satisfaction)」があります。どちらも重要な指標ですが、企業との関係性の深さや持続性という観点で大きな違いがあります。
■ 顧客満足度とは?
顧客満足度は、商品やサービスの購入・利用後に「期待通りだったか」「満足できたか」という短期的な評価を表すものです。たとえば「対応が丁寧だった」「味がよかった」など、利用直後の印象や感想がベースとなります。
この満足度が高ければ、再購入の可能性はありますが、他社により良い選択肢があれば簡単に乗り換えてしまうのも事実です。つまり、満足はしていても“心がつながっている”状態とは限らないのです。
■ 顧客ロイヤリティとは?
一方で顧客ロイヤリティは、「この企業だから選ぶ」「このブランドを応援したい」といった感情的な信頼・共感・絆の強さを指します。価格や利便性よりも、「この会社の姿勢が好きだから続けたい」という心理が購買行動を支えるのです。
たとえば、満足度では他社と差がない場合でも、ロイヤリティの高い顧客は乗り換えずに同じ企業を選び続けます。つまり、顧客満足が“点”だとすれば、顧客ロイヤリティは“線”であり、さらに“関係性の太さ”にあたります。
| 項目 | 顧客満足度 | 顧客ロイヤリティ |
|---|---|---|
| 意味 | 期待に対する満足 | 信頼・愛着・共感 |
| 期間 | 短期的(1回ごとの判断) | 中長期的(関係の継続) |
| 影響 | 再購入の可能性はあるが、離反も起こりやすい | 価格や利便性では揺らがず、企業を支持する |
| 測定方法 | CS調査(アンケート・5段階評価など) | ※NPS・LTV・継続利用意向など |
つまり、満足してもらうことは出発点に過ぎず、「この企業と関わり続けたい」と思ってもらえるかが、持続的な成長のカギとなるのです。そしてそれを実現するのが、企業と顧客が共に価値を育てる「価値共創マーケティング」なのです。
※顧客ロイヤリティの測定には NPS(Net Promoter Score:顧客がどれだけ企業を他人に薦めたいかを示す指標) や、LTV(Life Time Value:顧客が生涯にわたって企業にもたらす利益の総額)、継続利用意向(今後もサービスを使い続けたいと思っているかを示す意向)といった指標がよく使われます。
価値共創マーケティングが、ロイヤリティ向上の鍵となる理由
顧客ロイヤリティを高めるにはどうすればよいのでしょうか?
その問いに対する答えのひとつが、近年注目されている「価値共創マーケティング」というアプローチです。
これまでのマーケティングでは、企業が商品やサービスを一方的に作り、それを市場に届けて顧客に購入してもらうという「提供型」のスタイルが主流でした。いわば、企業が“つくる人”、顧客が“買う人”という構図です。
しかし今、顧客との関係は大きく変化しています。商品力や価格だけでは選ばれにくい時代において、「企業と一緒に価値を生み出す」という関係性こそが、顧客の心に深く根づくロイヤリティを育てるカギになっているのです。
■ 「共創」は単なる参加ではない
価値共創マーケティングとは、顧客をただの“消費者”としてではなく、一緒に価値を創る「共創者」として位置づける考え方です。商品開発の段階から顧客の声を取り入れたり、改善アイデアを対話の中から生み出したり、体験そのものを顧客と共有したりするプロセスを重視します。
たとえば、「使いづらい」という意見をフィードバックとして聞くだけでなく、「どうすればもっと良くなると思うか?」という問いを一緒に考える。このような姿勢が、顧客に「私はこの企業の一部だ」という当事者意識を芽生えさせます。
■ ロイヤリティの2つの側面を同時に高める
この当事者意識は、顧客の内面にある心理ロイヤリティ(共感・信頼・愛着)を強くし、さらにその感情は自然と行動ロイヤリティ(継続購入・推薦・参加)へとつながります。
たとえば、自分のアイデアが取り入れられた商品であれば、多少高くても購入し、SNSでその喜びを投稿したくなるのが自然な流れです。また、企業のプロジェクトに関わったことで、「このブランドのファン」として継続的に応援するようになります。
■ 共創は“絆”を育てるブランド戦略
このように、価値共創マーケティングは商品やサービスの開発手法というだけでなく、顧客との関係性を深め、絆を育てるブランド戦略そのものです。企業と顧客が信頼を土台に共に価値を育てることで、表面的な満足ではなく、「この企業とこれからも関わっていたい」という感情的なつながりが形成されます。
この深いつながりがあるからこそ、顧客は長く企業に関心を持ち続け、企業側もまた継続的に価値提供を改善し続ける「共創の循環」が生まれていくのです。
👥 顧客の心に届く関係を築きたいなら、
価値は“届ける”ものではなく、“一緒に育てる”ものへ。
顧客ロイヤリティ × 共創マーケティングの実践例
- 共創ワークショップ:商品開発やサービス改善を顧客と一緒に考える場をつくる
- ファンコミュニティ運営:日常的な対話のなかで信頼と絆を育てる
- モニター・レビュー施策:顧客の声をプロダクトに反映し、その成果を伝える
- 特別体験の提供:共創に参加した顧客に感謝と特別感を返す
“売る”から“聴く”へ──企業姿勢の転換が鍵
共創マーケティングの真髄は、単なる施策ではなく、企業姿勢の転換にあります。「伝える・売る」から、「聴き、共に創り、共に育てる」へ。
顧客の声を“意見”として聞くだけでなく、“共創の素材”として活かす姿勢が、顧客の心に響き、信頼と愛着へとつながります。
また、こうした姿勢は社員の意識変革にもつながります。現場で顧客と接するスタッフが共創の主役になることで、社内エンゲージメントも高まり、全社的な価値創造の推進力となります。
まとめ:ロイヤリティの時代に必要なのは、「共創」という視点
顧客ロイヤリティは、売上やリピートの源泉であると同時に、企業と生活者の関係の深さを示すバロメーターです。そしてこのロイヤリティを本質的に高めるには、表層的な満足ではなく、一緒に価値を創り上げるプロセスが不可欠です。
顧客を「ターゲット」ではなく「仲間」と捉え、ともに未来を描く。そのような価値共創マーケティングの視点を持つことで、競争ではなく共感によって選ばれるブランドへと進化していくことができるでしょう。
選ばれる理由を、商品力から関係性へ──
今、顧客ロイヤリティの本質が問われています。
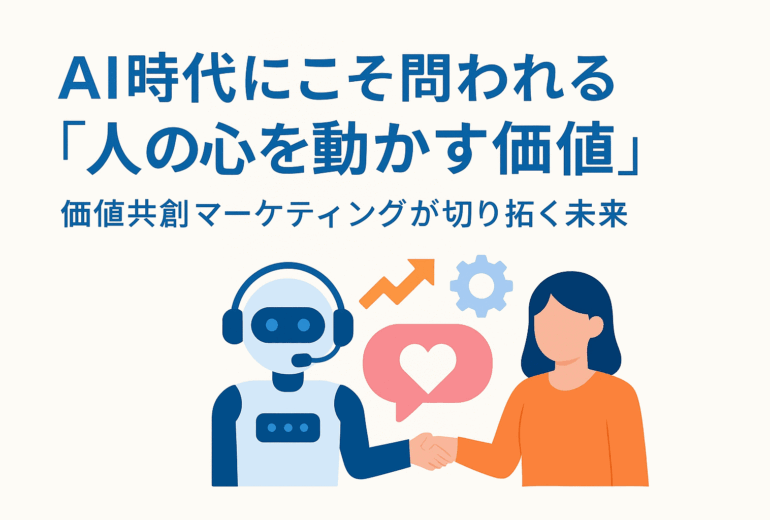
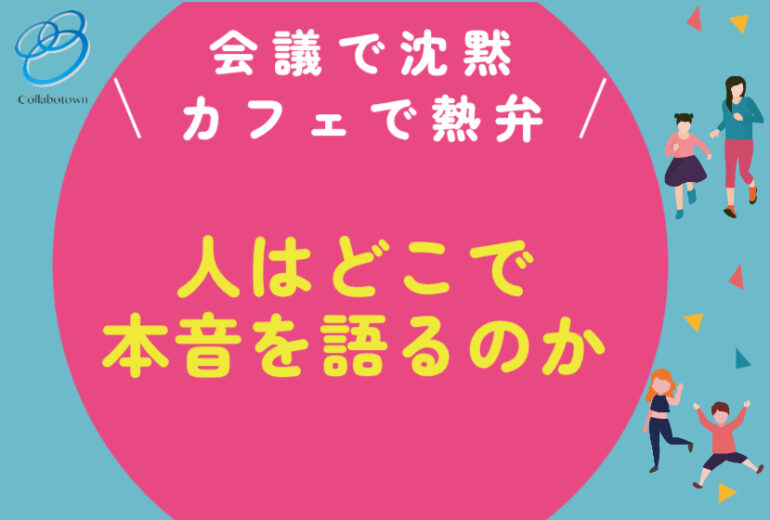
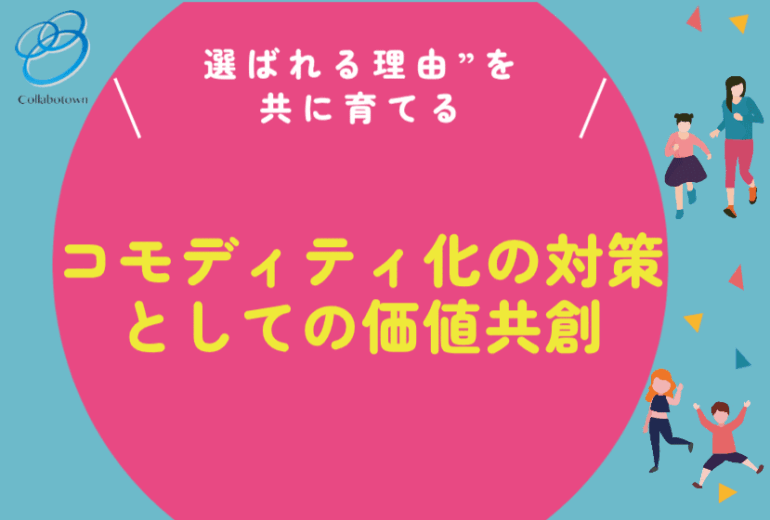
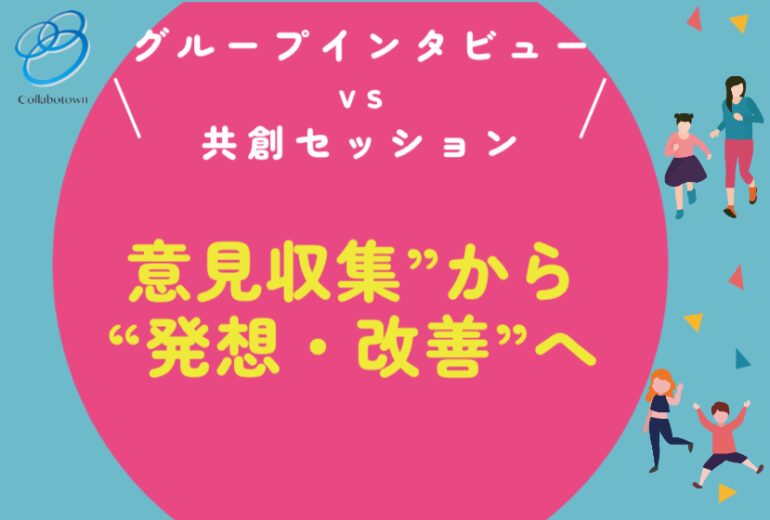
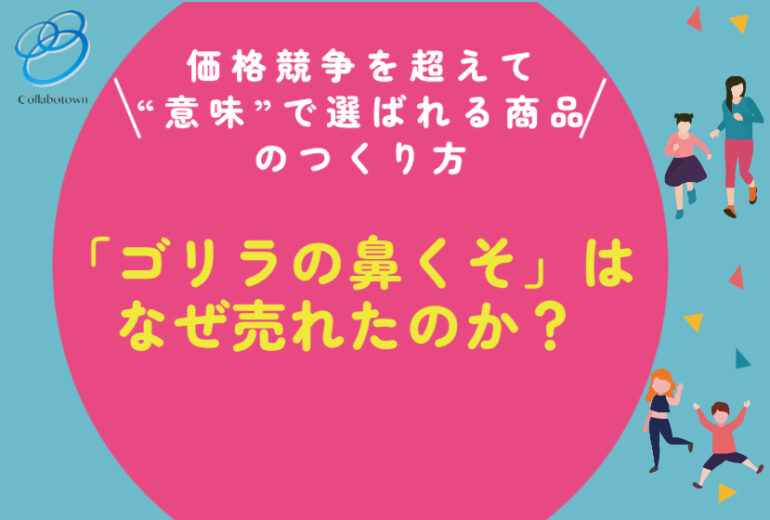
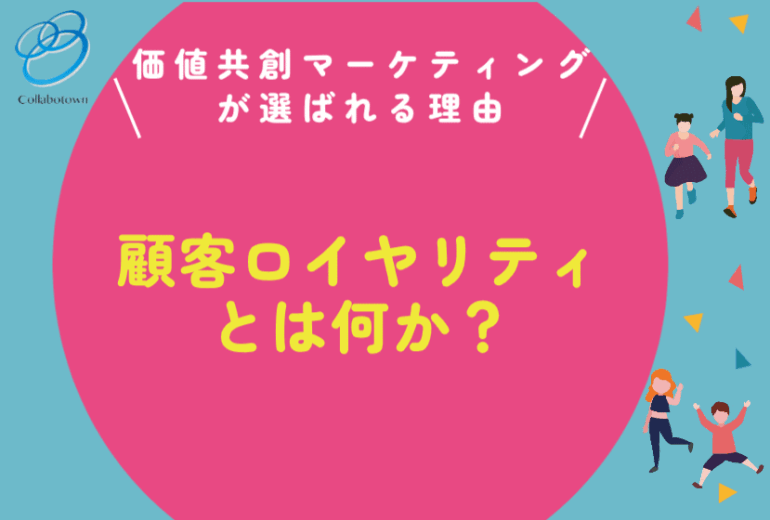
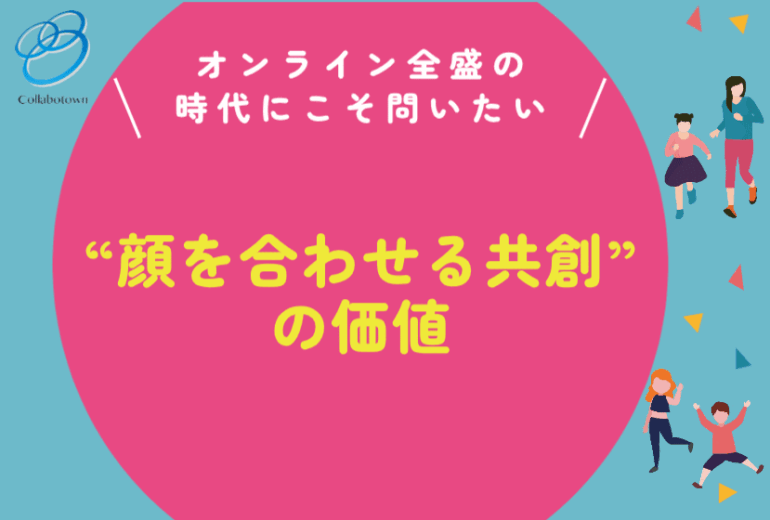

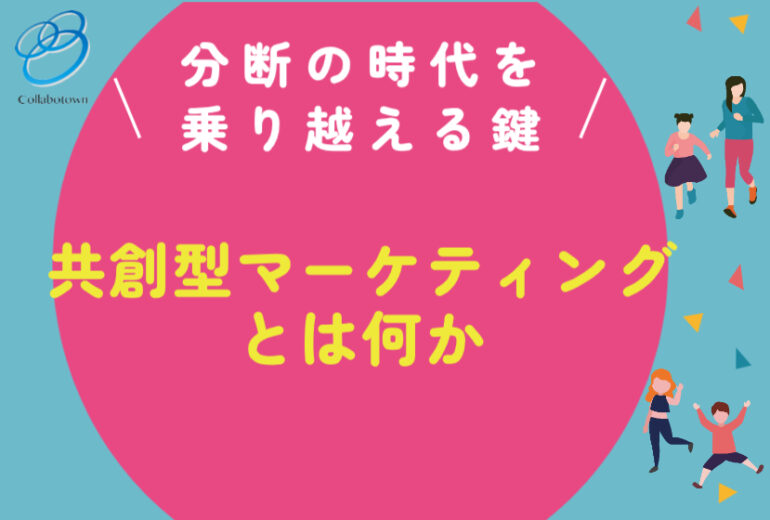
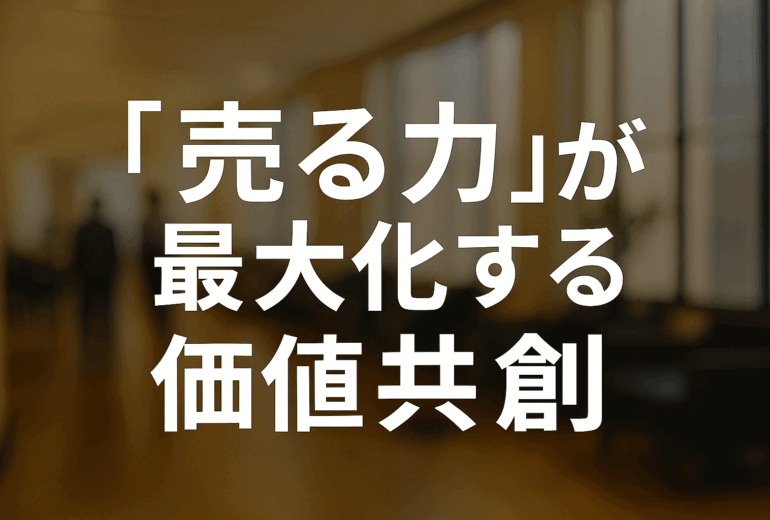
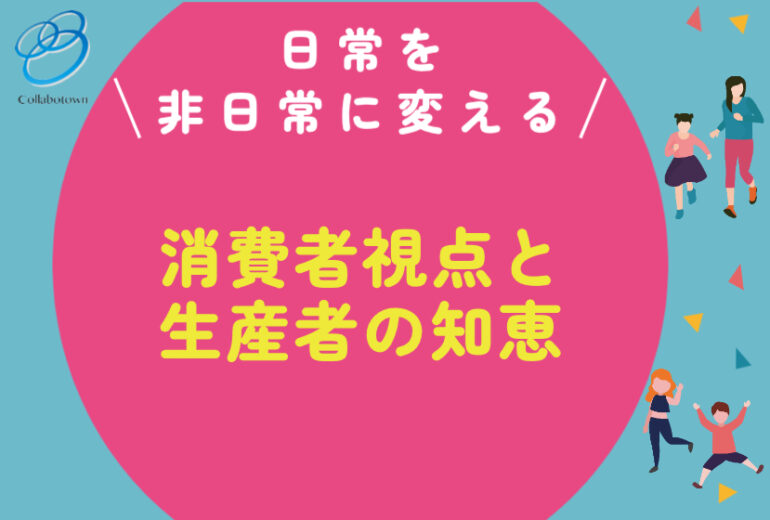
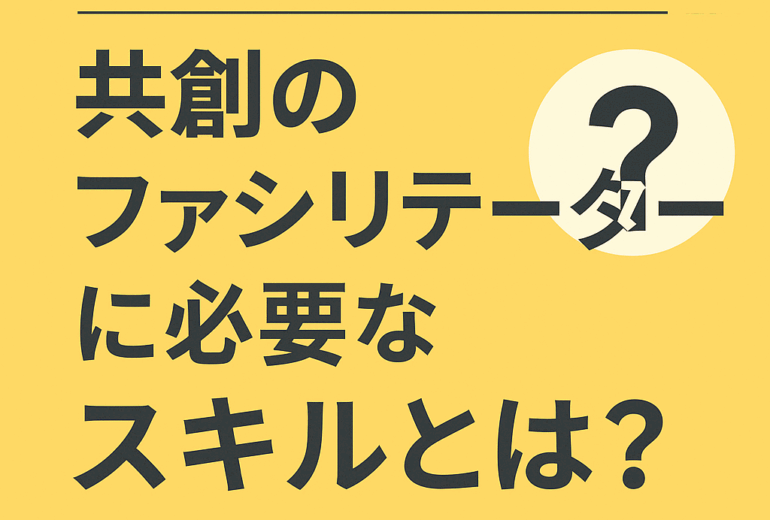

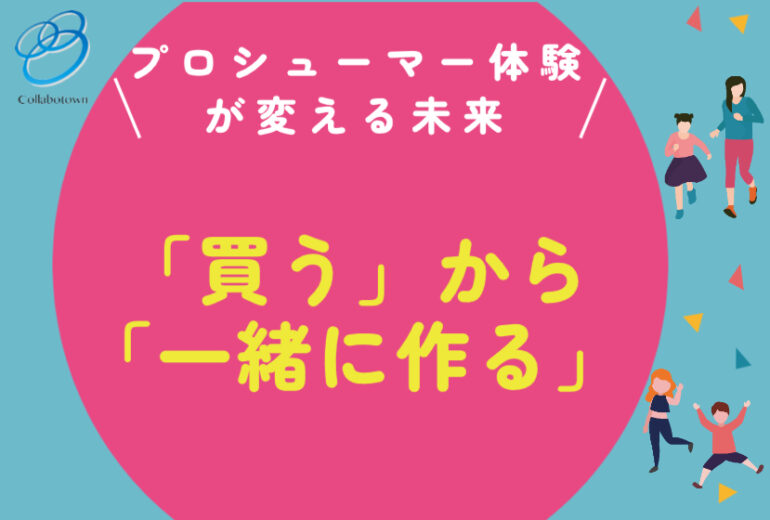
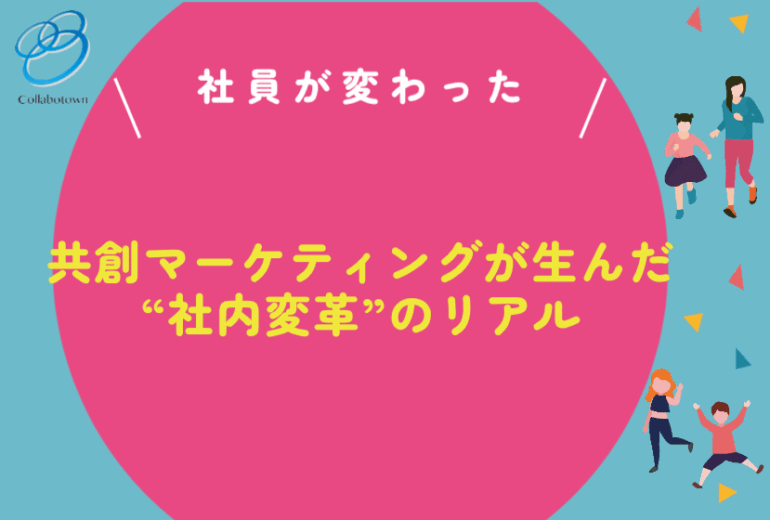
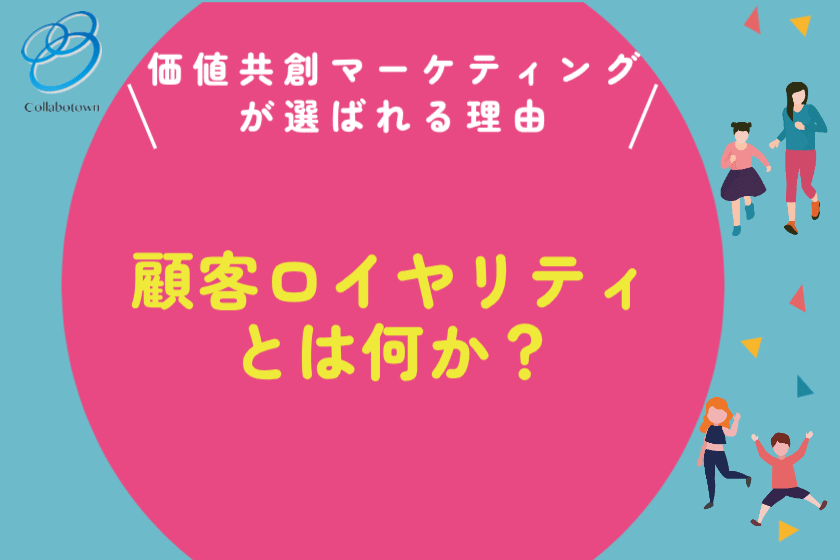
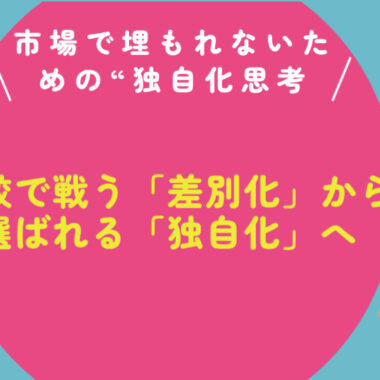
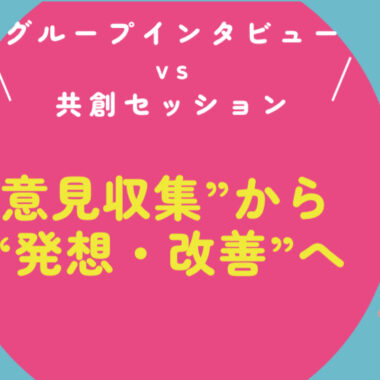
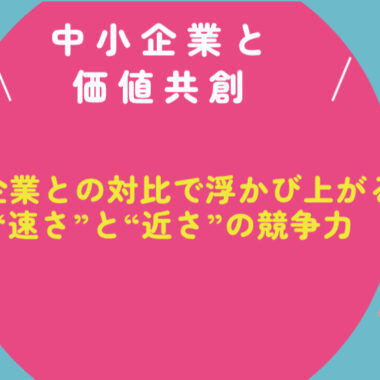
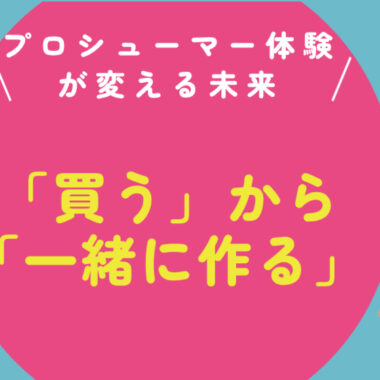
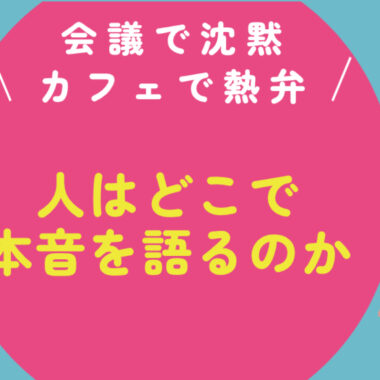
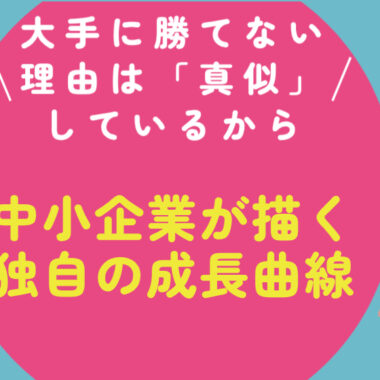
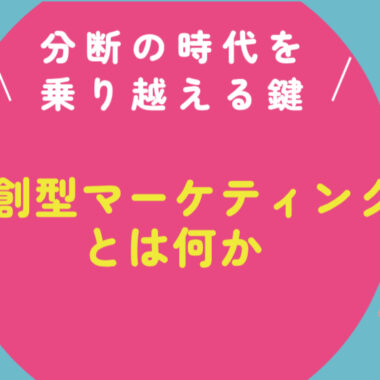
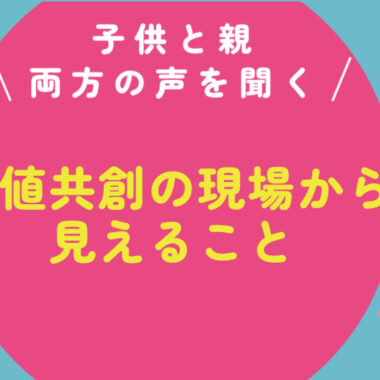
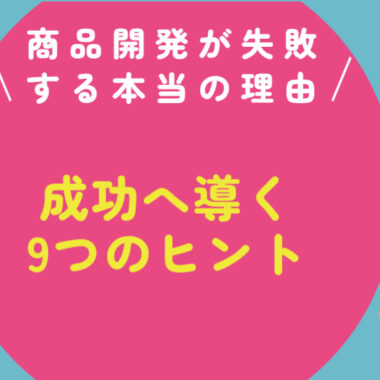
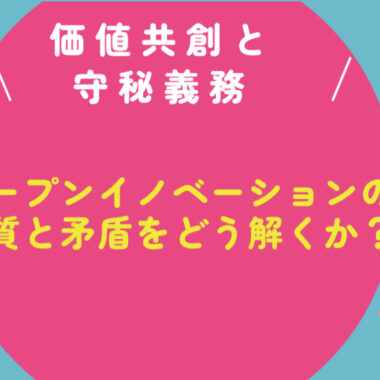
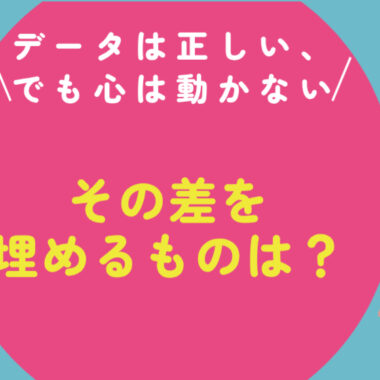
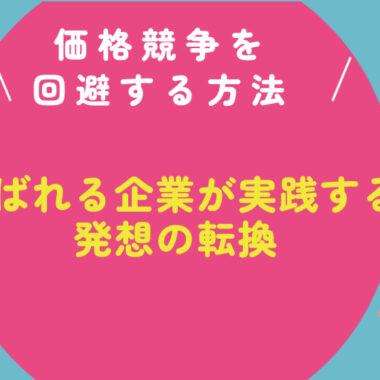
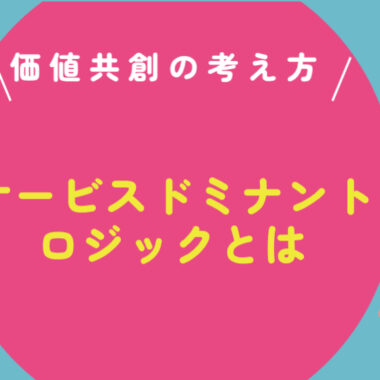
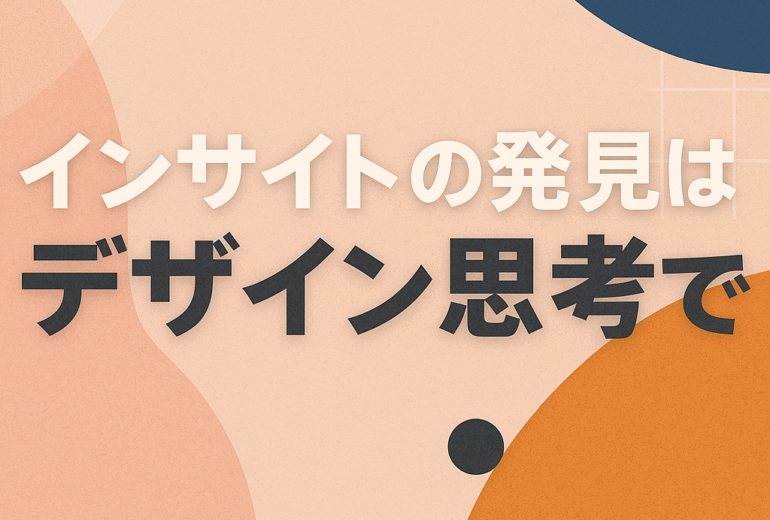
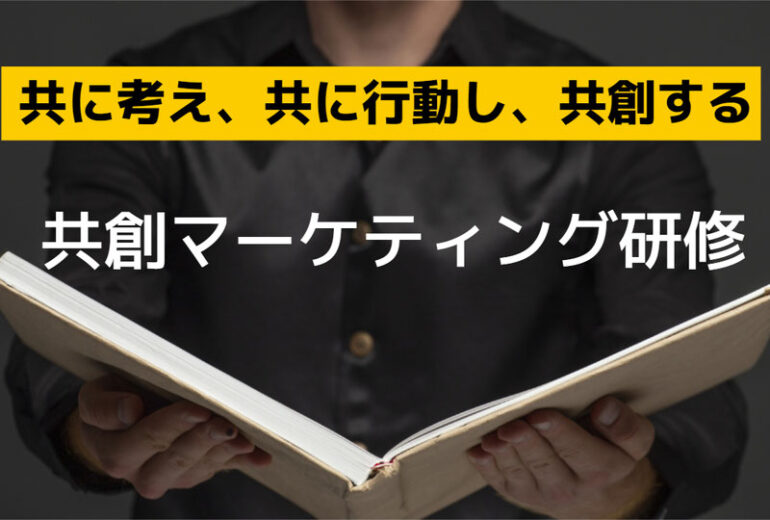
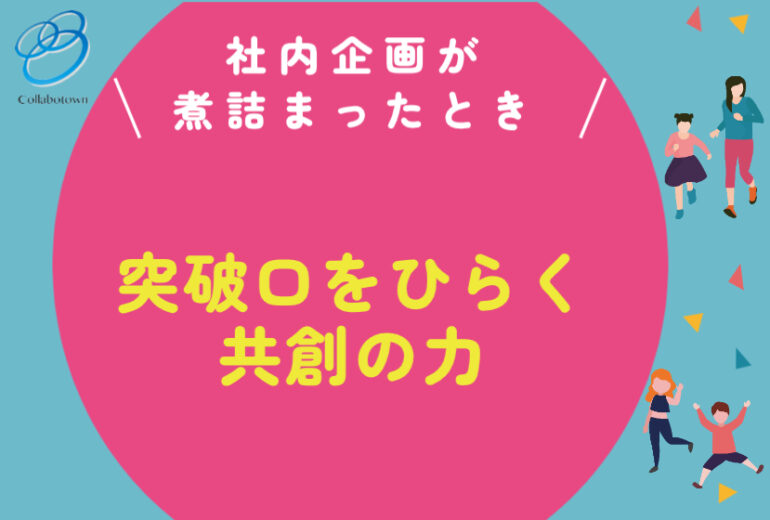

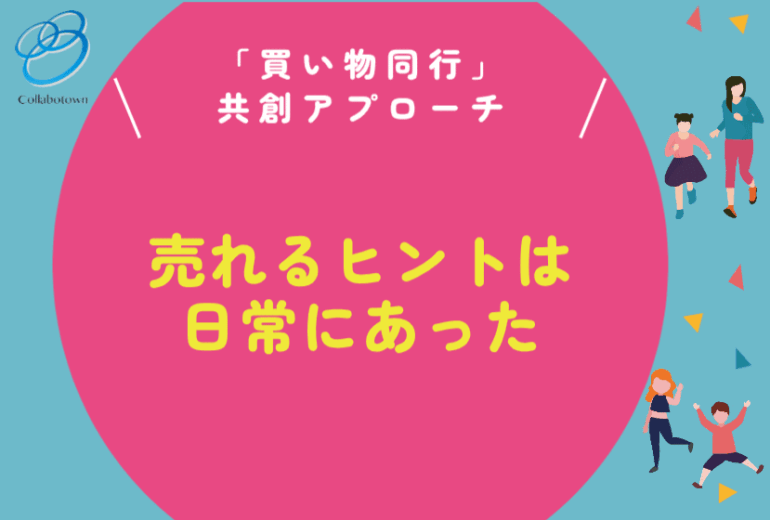

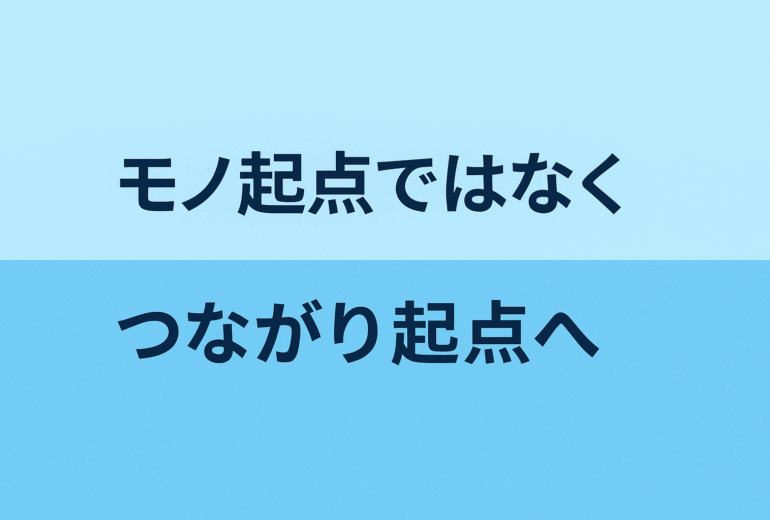
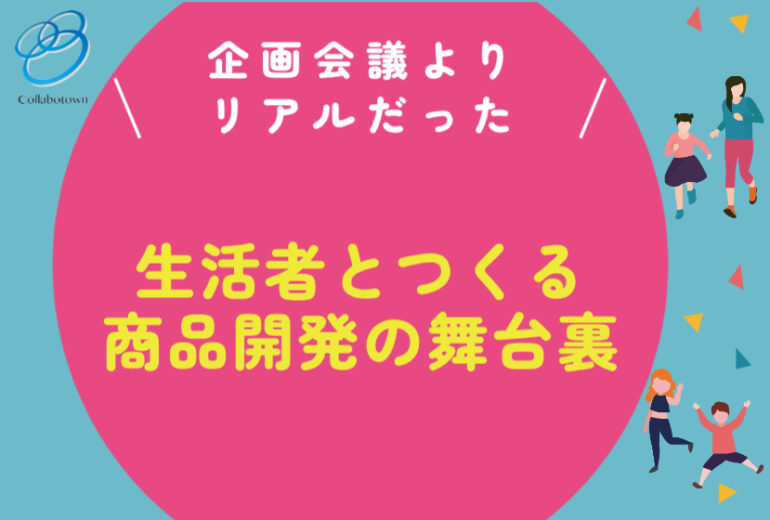

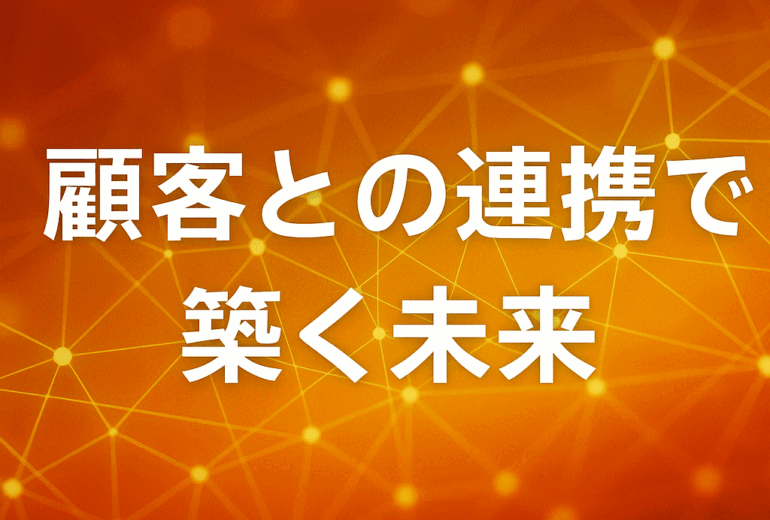
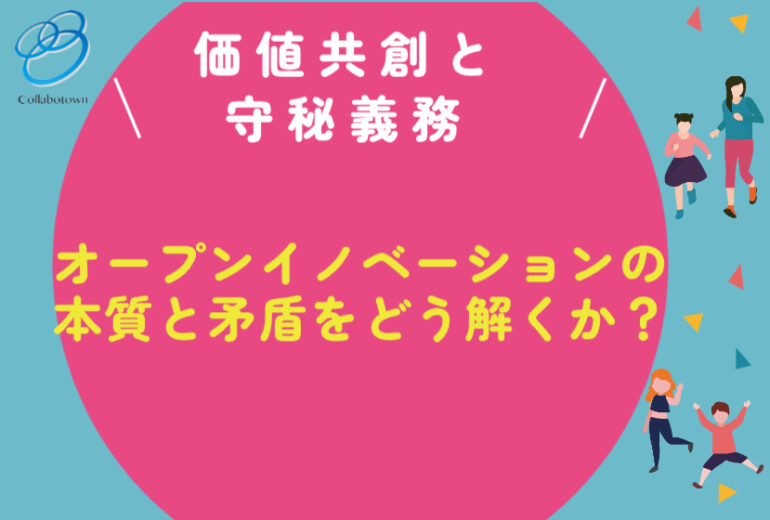
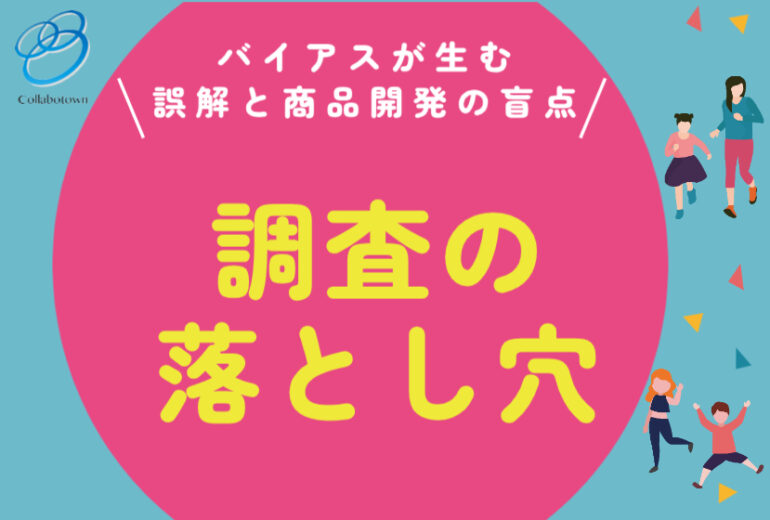
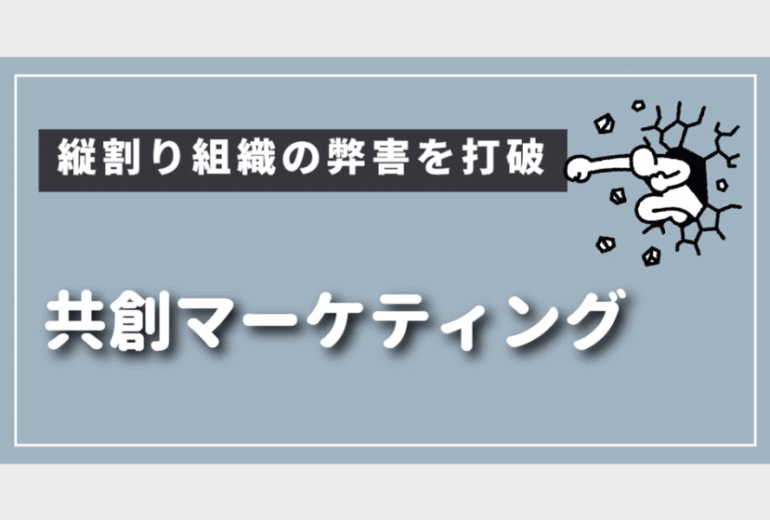

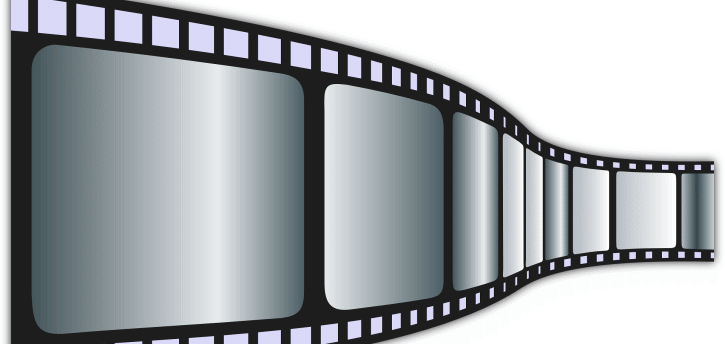
コメント