この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)の実践パートです。まず全体像を押さえたい方は上記をご覧ください。
企画会議で落ちる理由と、通すための共感設計
会議室の空気が一瞬止まる。「いい企画だね」と言われたのに、結局見送られた──。 そんな経験をしたことはありませんか? 本記事では、なぜ“良い企画”ほど通らないのかを整理し、社内の共感を得ながら企画を通す方法を解説します。
1. 「通らない企画」は、必ずしも“悪い企画”ではない
通らない企画=内容が悪い企画ではありません。多くの場合、原因は「通し方」にあります。
- 上層部の判断軸に合っていない(視点のズレ)
- 会議の場で共感が生まれていない
- 「誰のための企画か」が曖昧なまま提案している
つまり、企画の質よりも“理解のされ方”が壁になることが多いのです。
2. 会議で落ちる企画の3つの落とし穴
落ちる企画には、いくつかの共通構造があります。視点を変えると、原因が浮かび上がります。
① 判断軸を読み違えている
上司や経営層は、企画の“正しさ”よりも納得感を重視します。 「安心してGOサインを出せるか」が判断の本音です。
② 背景の共有が抜けている
現場で得た顧客の声やインサイトが資料に反映されていないと、「なぜこの企画なのか」が伝わりません。
③ 説得を優先し、共感を欠いている
論理や数字で押し切ると相手は防御的になります。必要なのは、共に考える姿勢です。
3. 「通す」ための3ステップ共感設計
“通す”とは、共感を設計することです。次の3つのステップで、企画は通りやすくなります。
ステップ1:相手の目的・リスク感覚を把握する
上司・経営層・他部門──それぞれが何を守りたいかを理解することが、共感設計の出発点です。
ステップ2:共通の「目的地」を言語化する
「何のために」「誰のために」を一致させるだけで、判断が変わります。企画を“通す”のではなく、合意をつくる発想です。
ステップ3:“一緒に考える余白”を残す
完成度100%ではなく、80%で「どう思いますか?」と問いかける。その余白が対話を生みます。
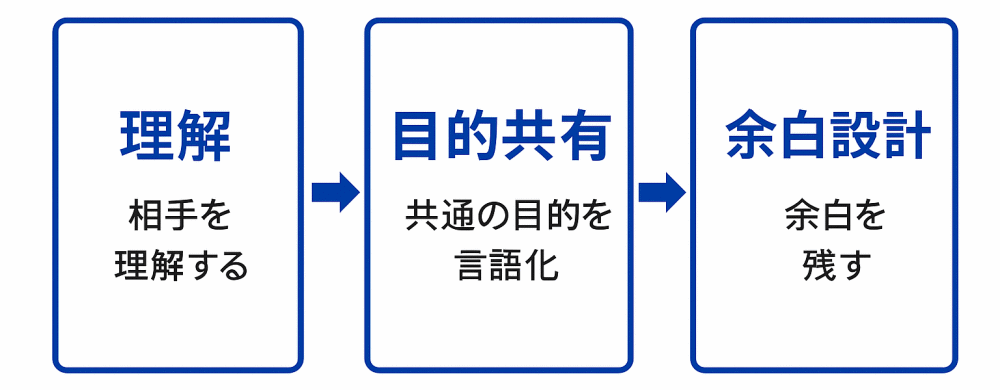
① 理解 → ② 目的共有 → ③ 余白設計
シンプルな3段階で、社内外の共感を生む企画づくりの流れを表しています。
4. 共感設計のヒントは「価値共創マーケティング」にある
共感を得る力は、社内だけでなく顧客との関係にも応用できます。 私たちが提唱する「価値共創マーケティング」は、まさにこの“共感のデザイン”を外部に広げた考え方です。
- 上司や関係部門を「巻き込む対象」ではなく「共に考える仲間」と捉える
- 自分の企画を“答え”ではなく、“問いの共有”から始める
- 小さな共感を積み重ね、合意を形にする
“通る企画”とは、完璧な資料ではなく、共感を軸に磨かれていくプロセスです。
5. まとめ|通す力は「共感を設計する力」
- “通らない”原因は内容ではなく共感づくりの設計ミス
- 相手の目的とリスクを理解し、目的地を共有する
- 80%で対話を始め、共創的に磨く
共感設計を意識するだけで、会議の空気は変わります。 否定から始まっていた議論が、「一緒に考えよう」へと変わるのです。 通す力とは、情報量ではなく共感を設計する力。 社内の壁を超える第一歩は、“通したい企画”を“共に育てる企画”へ変えることから始まります。
企画会議で通らない原因を整理し、共感を生む提案構造の設計を一緒に行います。
まずはお気軽にご相談ください。
👉 無料オンライン相談へ企画が“通る”をつくる 共感設計ガイド
共感設計の基本を押さえる起点記事
評価バイアスを超えて、納得を得る企画へ
本当のターゲットを再定義する方法
“意味の差別化”へ導く最終ステップ
共創マーケティングに役立つ無料資料
「共創マーケティング導入」「インサイト発見」「成果活用」など、 実務に役立つ資料を複数ご用意しています。



















