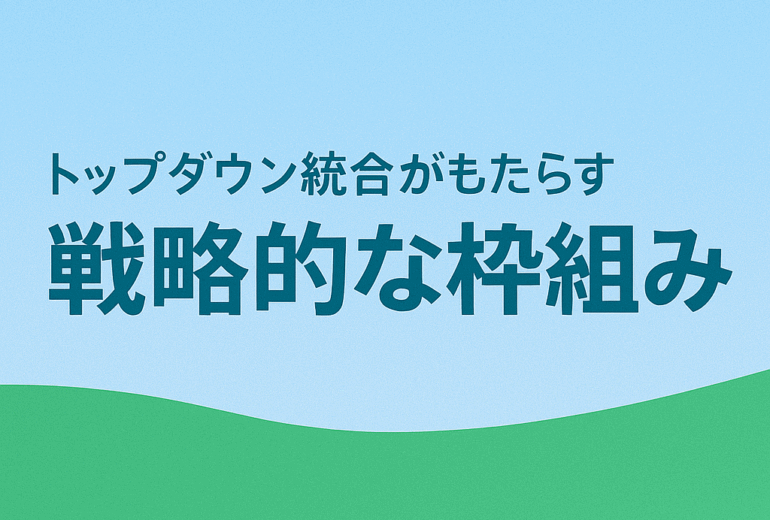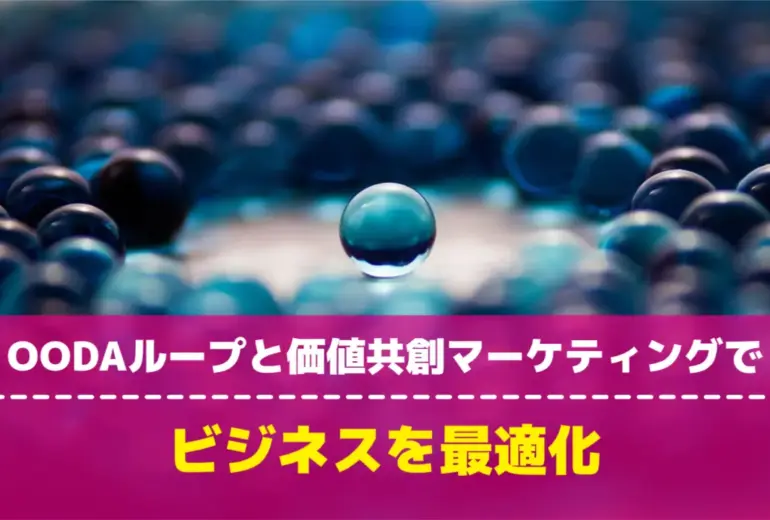最終更新日:2026.01.15
この記事は価値共創マーケティングの全体像(基本・ポイント・導入法)で紹介しているテーマの一部を掘り下げた内容です。実務で使えるコツや事例を中心に解説します。
コモディティ化が進むほど、企業は「違い」を作ろうとして機能追加や値下げに走りがちです。
しかし生活者側では、選択肢が増えすぎて「比較疲れ」が起き、最後は“無難なもの”に流れたり、“いつもの”に戻ったりします。
ここで必要なのは、商品そのものの差ではなく、選ばれる理由(意味・納得・関係性)を顧客と一緒に育てるという発想です。
✅ 結論:コモディティ化の対策は「差」ではなく「理由」を育てること
- コモディティ化=“どれでもいい”状態。比較軸が価格に寄りやすく、利益もブランドも削られる。
- 価値共創は「文脈(使われ方)」と「関係性」を育て、模倣されにくい“選ばれる理由”をつくる。
- 成功の鍵は共創の場を設計し、声を可視化し、商品・体験・発信に反映すること。
はじめに:モノがあふれる時代に、何を選ぶのか?
スーパーには似たようなドレッシングが何十種類も並び、ネット検索をすれば、同じような機能を持つ製品が無数に出てきます。 選べるのは便利なはずなのに、逆に選ぶことがつらくなる――そんな体験はありませんか?
この状態が、いわゆるコモディティ化です。機能・品質・価格の差が縮まり、生活者から見ると「どれを選んでも同じ」になってしまう。 企業側は差別化しようとするほど模倣され、最後は価格競争へ――という消耗戦に入りやすくなります。
コモディティ化の本質とリスク
コモディティ化は「似てきた」という現象に見えますが、本質は生活者の判断材料が“機能と価格”に収束してしまうことです。 そこには構造的な問題が潜んでいます。
① 製品中心主義の限界
企業が「良い」と思う改善が、生活者の「必要」とズレると、差別化は空回りします。
- 追加機能が増えるほど、選びにくい
- 魅力が説明依存になり、伝わりにくい
② 模倣スピードの加速
技術・情報の拡散が早く、優位性が短命化。差はすぐに追いつかれます。
- 機能やデザインは真似されやすい
- 「似た商品」が増えるほど価格へ
③ 価格競争の消耗戦
違いが伝わらないと、比較は値段に寄ります。結果、利益も投資余力も削られます。
- 利益率の低下
- ブランドの希薄化
- ロイヤルティの低下
“選ばれる理由が言語化できない”状態になると、次の新商品も同じ罠にハマります。
「価値共創」という逆転の発想
ここで有効なのが、企業が一方的に価値を“提供する”のではなく、顧客や生活者とともに価値そのものをつくるという 価値共創(Co-creation of Value)の考え方です。
なぜ共創がコモディティ化に効くのか?
模倣されにくい「文脈」
商品そのものより、使われる場面・背景・関係性が価値になると、簡単に真似されません。
- 誰と、どんな対話で作ったか
- どんな場面で役立つかの具体性
“声”がイノベーションになる
現場の「困りごと」「不便」「違和感」は、改善の種であり、新しい価値の起点です。
- 机上の仮説よりも精度が高い
- ズレを早期に修正できる
🤝 心理的ロイヤルティが育つ
共に創った体験は、単なる満足を超えて、共感や応援へつながります。
結果として「価格ではなく意味で選ぶ」状態が生まれ、コモディティ化の外へ出やすくなります。
共創によって生まれた“独自化”の実例
事例:地元農家と連携したスナックの開発
ある菓子メーカーは、地元農家と「旬の素材を活かしたお菓子を共に作る」プロジェクトを始動しました。 農家のこだわりや苦労、地域の文脈を商品に織り込むことで、単なる“おいしいスナック”ではなく、 “地域との絆を味わう”価値が生まれました。

生産者の言葉や表情、畑の風景まで五感で感じることで、開発チームは「商品に込める意味」を見直しました。
こうした共創ストーリーは、都市部のファンの心を動かし、価格競争とは別次元の意味の価値を提供します。
そして重要なのは、これが大企業ではなく中小規模のメーカーでも実現できている点です。
現場の声にすぐ耳を傾け、意思決定を早く回せる中小企業だからこそ、柔軟な共創が強みになります。
コモディティ化の時代に「選ばれる理由」をつくる3つのポイント
① 顧客を“パートナー”として捉える(調べる→一緒に考える)
「顧客のニーズを調べる」だけだと、結局は“企業が解釈した結論”になりがちです。
共創では、顧客をリサーチ対象ではなくプロジェクトの仲間として関わってもらい、
解釈のズレをその場で整えていきます。
② 共創の場を“仕組み”として設計する(偶然にしない)
共創は「やる気」だけでは続きません。場・頻度・役割・アウトプットを決めて、運用できる形に落とします。
チェック
- ✅ 誰とやるか(ユーザー像・人数・選び方)を決めている
- ✅ 何を決める場か(コンセプト/体験/パッケージ等)が明確
- ✅ 頻度と所要時間が現実的(小さく回せる)
- ✅ 議事録・学びを残し、次に活かす仕組みがある
③ 声やアイデアを“可視化して活かす”(反映→発信まで)
参加者が「自分の声が活かされた」と実感すると、共創者としての誇りが生まれます。
その結果、口コミ・紹介・応援が起き、「選ばれる理由」が強く育ちます。
可視化の例
- “声→企画”の変化をBefore/Afterで見せる
- 試作の変遷(A→B→C)を共有する
- 生活者コメントを、店頭・EC・SNSで活用
やりがちな失敗
- 声を集めたが、反映が曖昧
- 結果だけ発信し、プロセスが見えない
- 社内だけで止まり、外に出ない
実践: “選ばれる理由”を共に育てる5ステップ
最後に、現場で回しやすい形に落とした手順です。まずは小さく始めてOKです。
1現場の「違和感」を集める
顧客の不満だけでなく、使い方の工夫・迷い・比較の理由など“文脈”を拾います。
2生活シーンで意味を言語化する
機能ではなく「どんな場面で、何が楽になるか/嬉しいか」を言葉にします。
3共創セッションで解釈を整える
ズレをその場で修正し、“選ばれる理由”の核を共同で作ります。
4試作・試験で“理由”を強くする
小さく試して改善し、言い切れる魅力(納得)に育てます。
5プロセスごと発信して共感を増やす
完成品だけでなく、声が活きたプロセスを伝えることで模倣困難性が上がります。
“選ばれる理由が社内で共有される”こと自体が、次の企画を強くします。
まとめ:コモディティを超えて、「意味のある選択肢」を共に育てよう
市場に似た商品があふれ、価格が競争軸になりやすい今、企業が取るべきは 「一方的な売り込み」ではなく、顧客と一緒に選ばれる理由を育てることです。
価値共創は、生活者との関係性を通じて“文脈のある商品”を育て、模倣されにくい独自性を作ります。
そしてそれは、価格ではなく意味で選ばれる状態を生み出します。
“選ばれる理由”を、顧客と一緒に育てていく――その一歩が、企業の未来を変えていきます。
FAQ:よくある質問
Q. 共創は大企業向けの取り組みではありませんか?
A. いいえ。むしろ中小企業は意思決定が早く、現場に近い分、共創を回しやすい強みがあります。小さな人数・小さな検証から始めるのが効果的です。
Q. 何から始めれば良いですか?
A. まずは「顧客が迷うポイント(比較の理由)」と「現場の違和感」を集め、生活シーンに落とした言語化をします。その後、少人数の対話で解釈を整えるのが近道です。
Q. 値下げ以外の打ち手が見つかりません。
A. 値下げが効くのは短期です。共創で“選ばれる理由”を言語化し、プロセスと一緒に伝えると、意味で選ばれやすくなり、価格競争から抜けやすくなります。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)