価値共創マーケティング
マーケティングの行き詰まりを価値共創で打破する
共感が“支持される理由”になる
選ばれる理由を、対話でつくる。
生活者と共に育てる「価値共創マーケティング」
🧭 初めての方へ
先に 「共創って結局なに?」→ 読む順番 を整理したい方は、入口ガイドからどうぞ。
迷ったらここ:読む順番・おすすめルートを案内しています。
このページは、「価値共創マーケティングって、結局なにをどう進めればいいの?」という
経営者・ご担当者の方向けに、全体像と進め方・こらぼたうんの支援内容を一枚にまとめた総合ガイドです。
社内の縦割りや価格競争に悩む企業でも、小さく試しながら共創のサイクルを回していけるよう、
必要なステップを整理しています。
- 価値共創マーケティングが「従来のマーケティング」とどう違うのか
- 中小企業でも取り入れやすい、最初の3か月でやるべきこと
- 社内の巻き込み方や、営業・開発を含めた「共創チーム」のつくり方
- こらぼたうんが提供する支援メニューと、よくある成果・活用パターン
※ 「まずは内容を知りたい」方は導入ガイド、「自社の状況を相談したい」方は無料オンライン相談がおすすめです。
価値共創マーケティングの基本と実践の全体像
定義: 価値共創マーケティングは、企業と生活者が一緒に企画・検証し、商品や体験の価値を共同で高めるアプローチです。
用語としての意味だけをシンプルに確認したい方は、 「価値共創マーケティング」の用語解説ページもご覧ください。
Q. 何から始めればいい?
A. 30〜60分の小規模セッションで気づきを集め、試作→顧客検証→改善を1スプリント回します。 成果が出たテーマに絞って反復するとコスパが高いです。
下のサイト設計ロードマップから、気になる領域へ進めます。全体像を掴みたい方は上から順にどうぞ。
調査では見えない“生活者の本音”を共創で形にする
観察・対話
生活者のリアルな行動や声から“隠れたニーズ”を抽出。
インサイト発見
調査では届かない“選ばれる理由”を見える化。
商品・体験づくり
共創ワークで企画を磨き、現場に即した戦略に。
「うちの会社でもできるのか?」と気になったら
共創マーケティングの進め方や、社内への伝え方について、
現在の状況をお聞きしながら具体的なステップをご提案します。
※ 無理な営業は一切いたしません。情報収集や現状整理だけのご相談も歓迎です。
顧客にとっての“意味ある価値”を生み出したい。
その想いこそが、共創の第一歩です。
共創の始まりは現場の“悩み”から
現場ならではのモヤモヤを、共創の“出発点”として整理していきます。
こんな課題がある企業に向いています
「何となく不安」「決め手がない」を、生活者との対話で“確信”に変えていくための整理です。
経営判断
- 新商品の成否が「運まかせ」になっている。
- 社内評価と市場の反応がいつもズレてしまう。
- 価格以外で選ばれる「強み」が言語化できていない。
商品企画
- 素材や技術はあるが、何を作るべきか方向性が定まらない。
- インサイトは見えているのに、企画に落とし込めない。
- 改良を重ねても「決め手」に欠けている気がする。
ブランド/コミュニケーション
- ブランドパーパスを掲げても、社内外に浸透していない。
- 機能ばかり訴求してしまい、共感ストーリーが弱い。
- SNSやPRで「何をどう発信すべきか」が定まらない。
販路・営業
- 卸・小売から「刺さらない」と言われてしまう。
- 営業が価値よりも価格で勝負せざるを得ない。
- 見込み客との接点はあるが、成約まで結びつかない。
他のケースも見る
実際には、上記以外にも次のようなご相談をいただいています。
- 社内の企画がルーティン化し、新しい発想が出にくい。
- 顧客の声は集まるが、意思決定に活かし切れていない。
- ブランドの「言語資産(言葉・ストーリー)」が弱いと感じている。
- 販路ごとの勝ちパターンが見えず、打ち手が散らばっている。
- 定量調査だけでは、生活者の本音やリスクが読み切れない。
この中に1つでも当てはまるものがあれば、
貴社に合った「共創の第一歩」を一緒に整理してみませんか?
企業担当者との継続的な対話が新たな価値を生み出します。

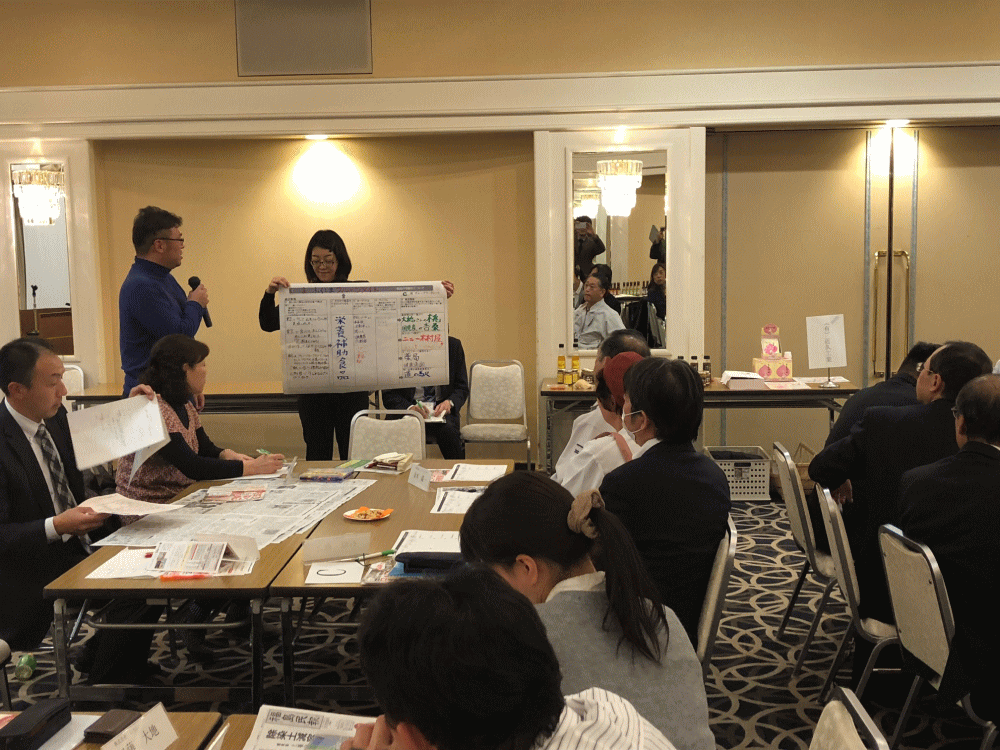






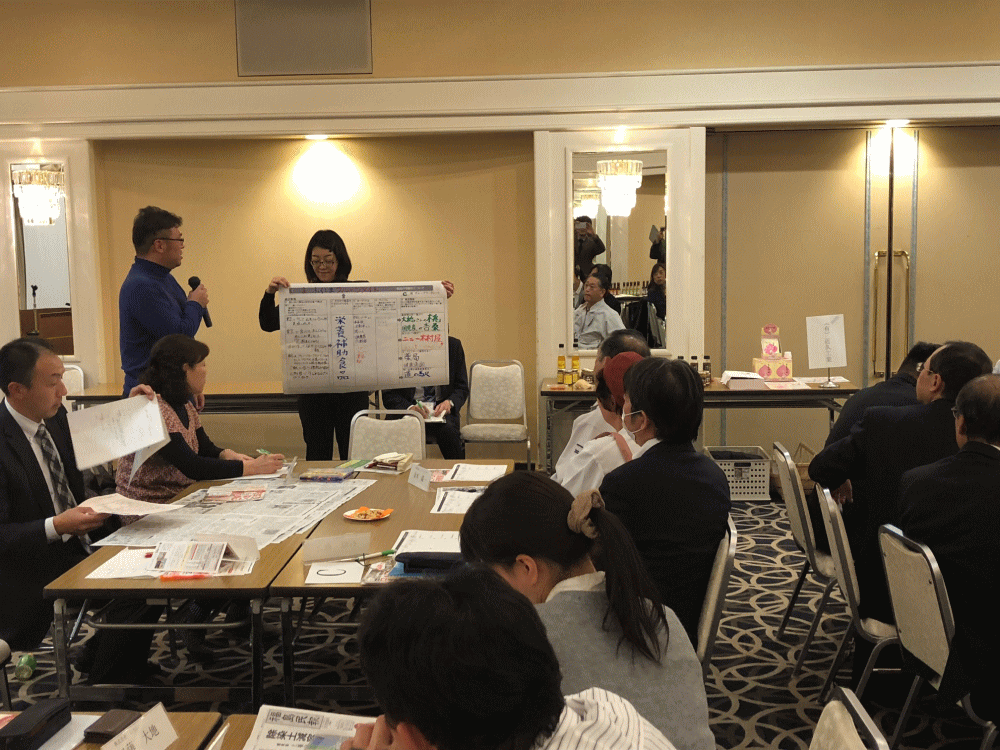












価値共創マーケティング:定義・導入ステップ・KPIまで一気にわかる決定版
🔍 この記事でわかること
- 価値共創マーケティングの基本概念
- 実践のための3つの要素
- アンケートやリサーチとの違い
- KPI設計と評価の視点
- よくある誤解・FAQ・注意点(統合)
マーケティングと聞くと「調査して分析して売り方を考えるもの」というイメージが強いかもしれません。
でも今は、機能や価格だけでは選ばれにくい時代。価値共創マーケティングは、企業とお客様が一緒に商品やサービスを作り上げていくやり方です。
たとえるなら、シェフとお客さんが一緒に味見をしながら料理を完成させるようなもの。作り手だけで決めず、対話・観察・試作を通じて「本当に使われる形」に近づけていきます。
1. なぜ、価値共創マーケティングなのか
モノやサービスが十分に行き渡った今、差は「スペック」よりも体験や意味で生まれます。お客様が感じる“しっくり感”や“物語”が選ばれる理由になります。
従来のアンケート中心のやり方では、こうした“心の動き”をつかまえにくいのが実情。そこで、現場での観察や対話、試作を通じてお客様と一緒に形にしていくのが共創の考え方です。
こらぼたうんは、企業と生活者が一緒に価値を作る現場を多数支援してきました。企業と生活者との共創ワークショップなど、様々な方法で意思決定に直結する実装を重視しています。
👉 実際に社員の働き方がどう変わるかは、 こちらの事例記事 でも詳しく紹介しています。
価値共創マーケティングと共創マーケティングの関係
「共創マーケティング」とは、企業と顧客、あるいは生活者や地域などが協働して新しい価値を生み出す考え方を指します。
一方、こらぼたうんが提唱する「価値共創マーケティング」は、その中でも“共に創る”過程を通じて意味のある価値を見出し、事業の成果につなげる実践的なアプローチです。
つまり、共創マーケティングが「共に取り組む枠組み」だとすれば、価値共創マーケティングは「その中でどのように価値を見出し、共有し、成果へつなげるか」に焦点を当てた具体的な方法論です。
この違いを意識することで、共創の取り組みが単なるイベントやアイデア出しに終わらず、組織や顧客との関係性を深める戦略へと変わります。
💡 こらぼたうんでは、「共創マーケティング=価値共創マーケティングの入り口」と捉えています。
共創の枠を超えて「顧客にとっての意味ある価値」を中心に据えることが、持続的なブランド信頼を育てる第一歩です。
2. 価値共創マーケティングとは(定義と背景)
共創マーケティングは、企業が一方的に「作って売る」のではなく、お客様と一緒に考えて作るアプローチです。
たとえば、遊園地で新しいアトラクションを作るとき――従来は調査をして設計図を引き、一気に完成まで進めていました。
共創では、実際に来園者に試し乗りしてもらい、その場の反応を見ながら改善していきます。だからこそ、完成品は「選ばれやすい体験」に近づきます。
理論背景のキーワード
- サービス・ドミナント・ロジック(S-D Logic):価値は企業から一方的に提供されるのではなく、相互作用の中で共創されるという考え方。
- 文脈価値:同じ商品でも、使う場面や背景が変わると価値が変わるという視点。
- CSV(Creating Shared Value):社会や顧客に良いことが、結果として企業価値も高めるという発想。
👉 詳しくは S-Dロジックと価値共創 / 文脈価値と共創マーケティング / CSVとサステナブルな共創戦略
数字で見る、共創マーケティングの成果
“共創”は売上・組織・ブランドに確かな変化をもたらします。
実際の支援事例から、その効果を数字でご紹介します。
卸会社から食品メーカーへ転業
生活者と共創し新商品を開発、事業転換を成功。
社員エンゲージメントの向上
共創の成功体験が職場の一体感と定着率向上を促進。
ブランド好意度アップ
共創体験を通じて「自分ごと化」されたブランドに成長。
体験価値の刷新
購入後の利用シーンに寄り添い、“続けたくなる理由”を強化。
共創キャンペーン
顧客参加型の施策で、購入意欲と関与度を大幅に向上。
3. 従来手法との違い(比較表)
| 項目 | 従来マーケティング | 共創マーケティング |
|---|---|---|
| 情報収集 | アンケート/定量調査中心 | 対話・観察・買い物同行・ワークショップ |
| 顧客の位置づけ | 分析対象(調査協力者) | 共創パートナー(意思決定に関与) |
| アウトプット | 企業が決めた仕様 | 顧客と作り上げた体験・仕様 |
| 価値の基準 | 機能・価格・短期売上 | 文脈価値・ロイヤリティ・中長期LTV |
| 学び方 | 事前調査→一括投入 | 小さく作る→試す→直すの反復 |
左の「従来マーケティング」は“お客様はデータ”という扱い。
右の「共創マーケティング」は“お客様は仲間”という立ち位置。
この発想の転換こそが一番の違いです。
ここまで読んで「自社の場合はどう進めればいいのだろう」と感じた方へ。
こらぼたうんは、貴社の状況に合わせて“共創の第一歩”をご提案します。
課題:価格競争から抜け出せない
同質化が進むと比較軸が価格に偏り、粗利が削られて投資が止まり、さらに差別化できない――という悪循環に陥ります。
値下げに頼らず「選ばれる理由」をつくるには、差別化・体験価値・顧客ロイヤリティを生活者の文脈から設計することが近道です。
🧭 全体の考え方と実務ステップは 価格競争からの脱却|中小企業のための実践ガイド に詳しくまとめています(原因分析/差別化・体験/ロイヤリティ/小さく試して仕組み化)。
関連リソース: 差別化・独自化 / 顧客ロイヤリティ(KPI設計) / インサイト発見法
4. 導入ステップ(小さく始めて磨く)
いきなり大掛かりに始める必要はありません。
ここでは、小さなお菓子メーカーを例に、最初の3か月で進めるイメージをご紹介します。
① 準備:目的と言語化(1〜2週)
- 狙いを明確化(例:リピート率↑/単価↑/返品↓)
- 対象生活者を定義(購入/未購入/離反 など)
- テーマ設定(どんな場面で食べるか/誰と食べるかなど)
② 共創セッション/買い物同行(3〜4週)
実際の購入・使用場面を観察しながら対話。「言葉になっていない手がかり」を拾います。たとえば、手に取るきっかけや置き場所、食べ終わった後の気持ちなど。
③ 試作・検証(5〜8週)
気づきを素早く形にし、小規模にテスト。試食会で反応を集め、包装やメッセージも一緒に確かめます。
④ 改善・展開(9〜12週)
反応の良い要素を磨き込み、体験全体(導線/POP/同梱物/アフター)に波及。小さく当てて、次の改善に活かします。
👉 実際の準備から導入の流れをさらに詳しく知りたい方は、
セッション初日までの準備(第1章〜第7章)
をご覧ください。
5. よくある誤解・FAQ・注意点
❌ 誤解:「お客様の言う通りに作れば良い?」
共創では観察と深掘りで「なぜそう言うのか」という意図や文脈を見極めます。
例:「もっと甘く」の背後に「子どもと一緒に食べたい」など。
❌ 誤解:共創は「大企業向け」?
❌ 誤解:アンケートやリサーチと同じ?
Q. 共創をやると結局なにが良いの?
Q. 「共創マーケティング」と「価値共創マーケティング」は同じですか?
一方で「共創マーケティング」は、より広い概念として、 企業と生活者・取引先・地域など多様なパートナーとの共創全般を含みます。
言い換えれば、共創マーケティングが「共に取り組む枠組み」だとすれば、価値共創マーケティングは 「その中でどんな価値を生み出し、どのように成果へつなげるか」を具体化した実践アプローチです。
Q. 社員が少なくてもできますか?
Q. 成果はどう測れば良い?
Q. 実際に導入するにはどんな流れ?
Q. BtoBビジネスでも有効?
Q. コストはどのくらい?
⚠ 注意:参加者が安心して話せる場づくりは?
6. KPI設計と評価(定量×定性)
KPIとは「成果を測るためのものさし」です。売上やシェアのような数字だけでなく、お客様の喜びやファン度も合わせて見るのが共創のポイントです。
- 繰り返し率(リピート/継続)・口コミ/UGC数・紹介率
- 試作品数・採用率・改善回数・開発リードタイム短縮
- NPS/満足度・共創参加者の再参加意欲
- 体験指標:パッケージ想起・棚前滞在・同伴購入率 など
定量(比率・回数)と定性(発話・観察ログ)を組み合わせ、月次レビューで学習サイクルを回します。
7. 次の一歩:まずは小さく“共創”を試してみませんか?
ここまで見てきたように、価値共創マーケティングは 「顧客の声をそのまま形にする」のではなく、 観察と対話を通じて本音を引き出し、共に磨いていくプロセスです。小さく始めても確かな学びが得られ、 組織や商品に“選ばれる理由”を育てられます。
「まずは情報を整理したい」「自社の状況に当てはめて話を聞いてみたい」―― どちらの方にも、負担の少ない“共創の第一歩”をご用意しています。
まずは情報収集からの方へ
📑 共創マーケティング導入ガイド自社のケースを相談してみたい方へ
💡 無料オンライン相談※ どちらも無料です。状況を伺い、無理なご提案や営業は行いません。
🏢 商工会・商工会議所・金融機関のみなさまへ
中小企業支援機関向けの研修・参加型セミナー・共創プロジェクト伴走については、
専用ページもごらんください。
関連記事
中小企業マーケティング実践ガイド
成功事例・営業強化・販路拡大・DXを共創で進める
顧客参加型の商品企画・商品開発
生活者とともにアイデアを形にし、共創で価値を高める
価格競争からの脱却
“選ばれる理由”を設計して単価と利益を守る
顧客ロイヤリティ
継続購入・推奨を生むKPIと育て方
インサイト発見
観察・対話・行動データで隠れた欲求を掴む
ワークショップ設計
設計/進行/心理的安全性/失敗回避
生活者視点の商品企画・開発
本音→検証→合意→WSで、企画を前に進める総合ガイド
文脈価値で差別化
“使う場面”から価値を再設計して選ばれる
理論・フレームワーク
S-Dロジック/プロシューマー/文脈価値
🔰 初めて共創マーケティングに触れる方へ
共創マーケティングの考え方を、自社の取り組みにどう活かせるかをわかりやすく紹介した記事があります。
あなたの会社にもできる!共創マーケティングで見つける新たな価値
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ




















