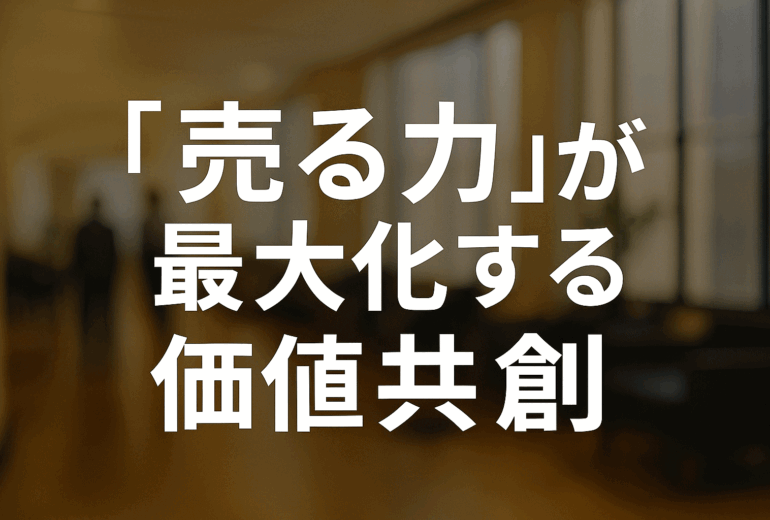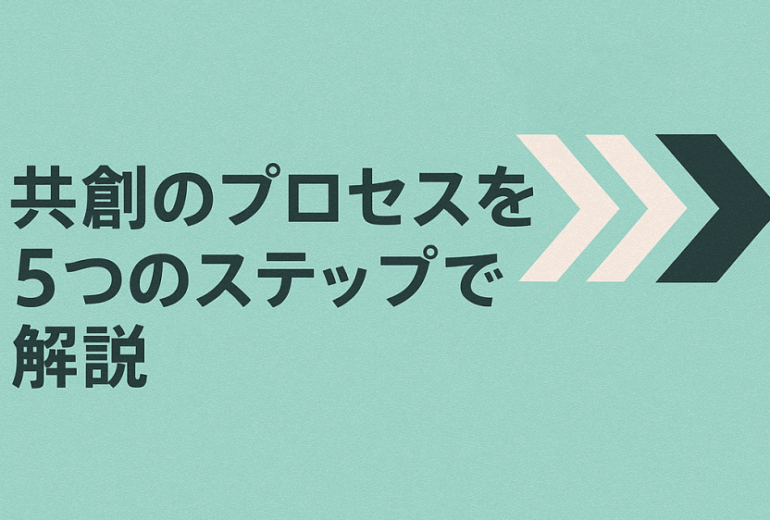未来新聞ワークで「共有された未来像」をつくる
── 企業研修への活用と価値共創マーケティング
「未来新聞」は、単なるアイデア発想ワークではなく、組織と生活者が“同じ未来”を描き、その実現に向けて共に動き出すための起点になります。
ここでは、企業研修・ワークショップで未来新聞をどう活用できるのか、そして価値共創マーケティングとのつながりをわかりやすくご紹介します。
※基本的な定義は「未来新聞とは(用語集)」で整理しています。用語の意味を確認したい方は、そちらも併せてご覧ください。
→ 「未来新聞とは」用語集ページはこちら
1. 未来新聞とは? ─ 「達成された未来」を記事にするワーク
未来新聞とは、「数年後、理想の成果が実現した」という前提で、新聞記事風にストーリーを書く手法です。

未来新聞とは、「数年後、理想の成果が実現した」という前提で、新聞記事風にストーリーを書く手法です。
- ● いつ頃の話か(◯年後・◯年◯月)
- ● どんな見出しで報じられているか
- ● どんな人たちが喜んでいるのか(顧客・社員・地域など)
- ● 何が評価され、どんな変化が起きているのか
こうした要素を、新聞の一面記事のように書き出していくことで、参加者それぞれの頭の中にあった“バラバラのイメージ”が、1枚の紙に可視化されていきます。
未来新聞のポイント
- ・「こうなったらいいな」という抽象的な願望を、具体的な場面・ストーリーに落とし込める
- ・実現したいのは売上だけでなく「誰の、どんな笑顔なのか」が見えてくる
- ・バックキャスティング(未来からの逆算)の起点として使える
2. なぜ企業研修で注目されているのか
企業研修・組織開発の現場では、
- ・部門ごとにゴールのイメージが違う
- ・短期の数値目標ばかりが前面に出てしまう
- ・「なぜこの仕事をするのか」という意味が共有されていない
といった課題がよく聞かれます。
そこで未来新聞を活用すると、次のような効果が生まれます。
◆ 組織開発としての効果
- ・役職や部署を超えて「同じ未来像」を語れる
- ・数字だけではない、仕事の“意味”や“誇り”を再確認できる
- ・対話を通じて、心理的安全性のある場づくりにつながる
◆ 戦略・企画としての効果
- ・事業の「ありたい姿」が言語化される
- ・社内合意のベースとなるストーリーができる
- ・中長期の施策やKPIを考える“軸”が明確になる
3. 価値共創マーケティングとの深い関係
価値共創マーケティングは、企業と生活者が一緒になって「意味のある価値」をつくり出していく考え方・実践です。
ここで大切になるのが、「何を売るか」ではなく「なぜそれが価値なのか」という文脈価値です。
未来新聞は、この文脈価値を引き出すのにとても適したワークです。未来の新聞記事には、次のような内容が自然と書き込まれます。
- ・その商品・サービスによって、生活者のどんな悩みが解消されたか
- ・地域や社会にどんな良い変化が起きたか
- ・社員自身がどんな誇りを感じているか
つまり未来新聞は、 「企業の視点」と「生活者の視点」をつなげて未来を描く共創のツールと言えます。
4. チームビルディングとしての未来新聞
こらぼたうんの支援でも、未来新聞は次のような場面でよく使われます。
新商品開発プロジェクトのキックオフや、共創プロジェクトの初回ワークとして、
「このプロジェクトがうまくいった1〜3年後、どんな新聞記事になっていたら最高か?」をテーマに、部署横断のメンバーで未来新聞を書きます。
このプロセスを通じて、
- ・普段の会議では出てこない、メンバーの「本当に大事にしたいこと」が見える
- ・目先の施策ではなく、中長期のありたい姿が共有される
- ・上司・部下の関係を越えた、フラットな対話が生まれる
など、チームビルディングの効果が自然と得られます。
5. 新規事業・商品開発への応用
未来新聞は、新規事業・商品開発のフェーズでも活用できます。例えば、
- ・「◯年後、この商品がどんな人に愛されているか」をテーマに未来記事を書く
- ・生活者の立場で「◯◯さんのおかげで、うちの暮らしがこう変わった」という利用者の声風に書く
- ・経営層の視点で「地域からこう評価されている」という社外の評価を書いてみる
こうして複数の視点から未来を描き出し、その共通点を探っていくと、
- ・その事業が「選ばれる理由」
- ・価格だけに頼らない「共感軸」
- ・ストーリーとして伝えるべきメッセージ
といった、共創マーケティングに不可欠な要素が浮かび上がってきます。
6. こらぼたうん版「未来新聞ワークショップ」の流れ(イメージ)
ご相談内容や対象者によって設計は変わりますが、代表的なパターンを例としてご紹介します。
◆ 2〜3時間のコンパクト研修(社内向け)
- 1)導入:未来新聞とは? 共創マーケティングとの関係を解説
- 2)個人ワーク:一人ひとりが「理想の未来記事」を書いてみる
- 3)小グループ共有:記事を持ち寄り、共通点・違いを話し合う
- 4)グループ版未来新聞づくり:意見を統合し、チームの未来記事を作成
- 5)全体共有・振り返り:気づきと、明日からの一歩を言語化
◆ 半日〜1日の共創ワークショップ(生活者との共創も含む)
- 1)生活者インタビューや買い物同行などで“今”を深く知る
- 2)インサイトの整理:「本音」や「隠れた願い」を抽出
- 3)未来新聞づくり:企業・生活者が一緒になって「理想の未来」を記事化
- 4)バックキャスティング:未来から逆算して、必要なアクションを洗い出す
- 5)社内での活用設計:企画書や社内プレゼンへの落とし込み方を検討
このように、未来新聞は単発のワークで完結させることも、共創プロジェクト全体の“核”として位置づけることもできます。
7. 導入のステップ ─ まずは小さく試すところから
こらぼたうんでは、いきなり大規模な全社研修を行うのではなく、次のようなステップでの導入をご提案しています。
- ① 課題と目的のヒアリング
「何のための未来新聞なのか?」を一緒に整理します。
例)新商品開発/部門横断プロジェクト/次世代リーダー育成 など - ② 小さな単位での試行
まずは1チーム・1部署など、コンパクトな単位で半日〜1日のワークを実施し、手応えを確認します。 - ③ 社内展開・共有
未来新聞で描かれたストーリーを、社内資料やプレゼン、施策検討の場で活用していきます。 - ④ 共創マーケティング全体への接続
必要に応じて、生活者との共創セッションや、インサイト発掘ワーク、KPI・評価設計などにもつなげていきます。
8. よくあるご質問
- Q. 参加者は何名くらいから対応できますか?
- A. 少人数のプロジェクトチーム(4〜6名程度)から、部署単位・全社研修まで幅広く対応可能です。目的や会場環境に応じて設計いたします。
- Q. オンライン(ハイブリッド)でも実施できますか?
- A. はい、オンラインホワイトボードツールなどを活用し、オンラインや拠点間接続での実施も可能です。現場のご状況に合わせてご相談ください。
- Q. 自社でファシリテーションできるようになりたいのですが…
- A. 研修として実施しながら、社内ファシリテーター育成を組み合わせることもできます。進行台本やワークシートの設計支援も行っています。
未来新聞をきっかけに、共創の一歩を踏み出しませんか?
「まずは一度、内容を詳しく聞いてみたい」「うちの課題に合うか相談したい」といった段階でも大歓迎です。
業種・規模・体制に合わせて、ムリのない小さな一歩からご提案いたします。
※本ページの内容は一例です。実際のプログラムは、貴社の状況・目的に合わせて個別に設計いたします。
※商工会・商工会議所・金融機関など、中小企業支援機関の方からのご依頼もいただいています。
支援機関向けの専用メニューは
👉「支援機関のみなさま向け共創支援のご案内」
にまとめています。