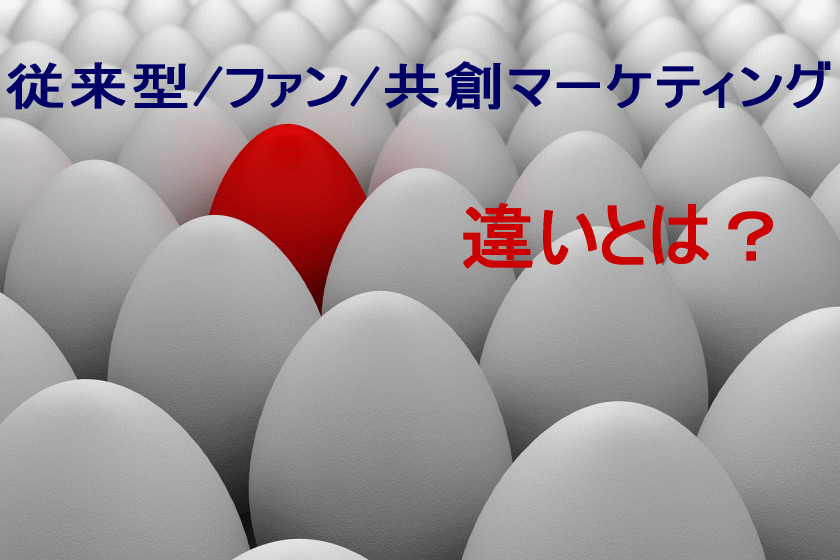私たちが企業のマーケティング支援を行う中で、よくいただくご質問のひとつがこれです:
「従来のマーケティングとファンマーケティング、そして価値共創マーケティングは何がどう違うのですか?」
たしかに、これら3つのアプローチは似ているようで根本的な考え方が異なります。そこで今回は、比較しやすいように以下の表にまとめてご説明します。
| 従来のマーケティング | ファンマーケティング | 共創マーケティング |
|---|---|---|
| 企業主導で広告を打ち、情報を一方的に届ける | ファンが自発的に口コミやSNS投稿で広める | 企業と生活者が一緒に意味ある体験・価値を創る |
| 購買促進のためのキャンペーンや割引中心 | ファン同士の使用感や活用アイデアが自然に広がる | 顧客のインサイトをもとにニーズを共に探索する |
| 企業の視点で商品やサービスを企画・開発 | ファンの声を一部参考にすることもある | 初期構想から顧客と共に考え、試し、創り上げる |
| 成果指標は売上・認知度などの数値 | エンゲージメントやSNS波及が主な評価軸 | 共感度、共創プロセス、組織変容など多面的に評価 |
| 顧客は「ターゲット」や「購買者」 | 顧客は「応援者」や「愛用者」 | 顧客は「パートナー」や「共創者」 |
| 関係は売って終わりの短期的なもの | 共感を軸にした中長期の関係性 | 共に育てる循環型・参加型の関係性 |
この表から見えてくる本質的な違いとは?
表から読み取れる大きな違いは、「誰が主導しているのか」「どのような関係性を築こうとしているのか」という点です。
従来型マーケティングでは、企業が情報発信の主導権を持ち、顧客はそのメッセージを受け取る存在です。主語は企業であり、顧客は“対象”として扱われがちです。
一方、ファンマーケティングでは、顧客が“応援者”として商品やブランドの魅力を周囲に広めてくれます。企業と顧客の距離は縮まりますが、依然として発信のタイミングやテーマは企業が管理している場合も多くあります。
そして共創マーケティングでは、企業と生活者が同じテーブルで意見を交わし、初期の構想段階から一緒に「価値づくり」に取り組む関係が築かれます。ここでは、顧客は単なる“応援者”ではなく、ブランドづくりの共同パートナーです。
この違いは、単にマーケティング手法の比較にとどまりません。企業文化の変革や事業の持続性、顧客との信頼関係の構築に直結する重要な視点です。
共創マーケティングが目指すもの
このように見ると、共創マーケティングは単に「広める手段」を変えるだけでなく、企業と顧客の関係性そのものを変えるアプローチだとわかります。
従来のマーケティングでは、企業が作った価値を「どう売るか」「どう伝えるか」が重視されてきました。しかし、生活者の価値観が多様化し、情報があふれる現代においては、「誰が伝えるか」「どのように共感されるか」が問われています。
共創マーケティングは、こうした時代の変化に応えるアプローチです。生活者の声を“聞く”のではなく、“一緒に考える”ことから始まり、アイデアの発想、開発プロセス、改善の仕組みに至るまでをパートナーとして共に進めていきます。
このプロセスを通じて、企業と顧客の間には、単なる「取引関係」ではない、感情的なつながり=共感関係が育まれていきます。商品やサービスを提供するだけでなく、「なぜそれをつくるのか」「どういう想いで社会に届けるのか」という物語が共有されることで、ブランドに対する愛着や信頼が深まっていくのです。
一過性のキャンペーンで注目を集めるのではなく、対話と協働を積み重ねながら“共に育てる”ブランド。それが、共創マーケティングが目指す姿です。
特に中小企業や地域ブランド、スタートアップなど、資源が限られる組織にとっては、顧客との共創が最大の強みになります。広告費をかけずとも、共感と参加を軸にした関係性が育てば、自然な拡散と支持が得られるからです。
もし今、「ファンはいるが、次の一手が見えない」「もっとお客様と深くつながりたい」と感じているのであれば、“何を届けるか”の前に、“誰と、なぜ創るのか”を見直すことが重要です。そこにこそ、共創型マーケティングの真価があります。
「伝える」から「一緒に育てる」へ──
マーケティングの未来は、共創のなかにあります。
🗒️ コラム・運営視点 一覧へ
📘 共創マーケティングに役立つ無料資料
企業の「共創マーケティング導入」や「成果活用」に役立つ資料を複数ご用意しています。必要なテーマだけを選んでダウンロードできます。
✅ まずは資料だけでもOK
これまでに 48 件の資料請求 (2025年9月〜)
営業電話はしません。返信メール1通でダウンロードできます(所要30秒)。
💬 共創で「次の一手」を一緒に整理しませんか?
自社の状況をお聞きしながら、「共創マーケティングをどう取り入れるか」を一緒に整理します。10分だけの相談でも大歓迎です。
✅ まずは状況整理だけでもOK(売り込み目的ではなく、選択肢を一緒に整えます)