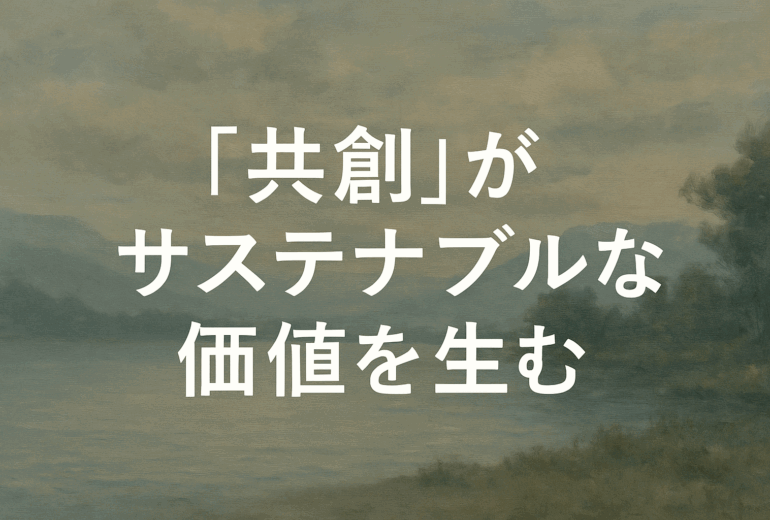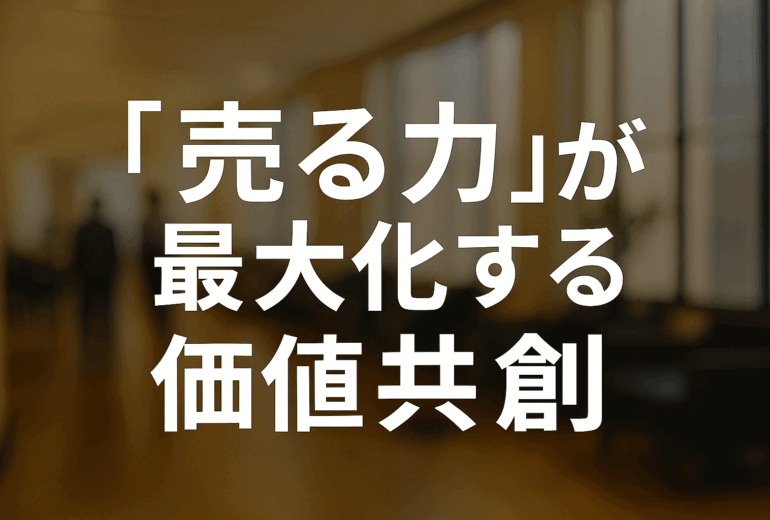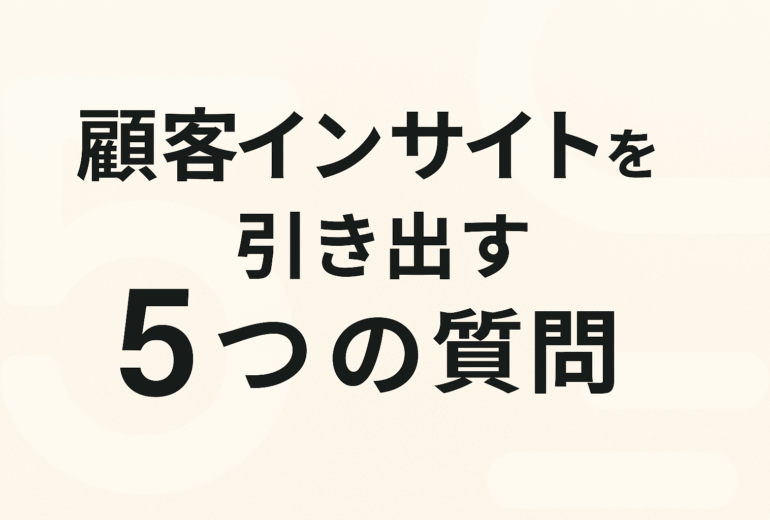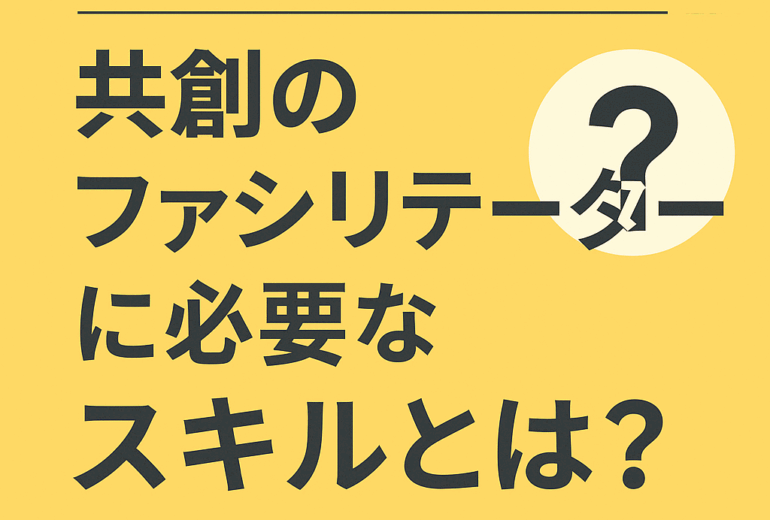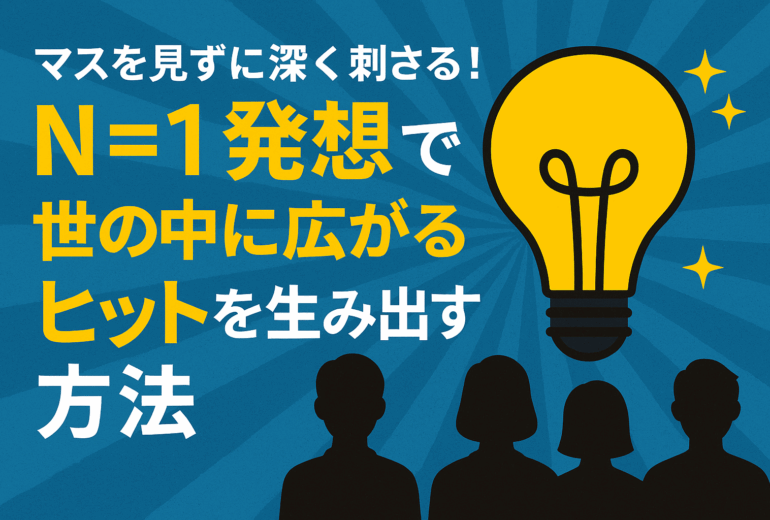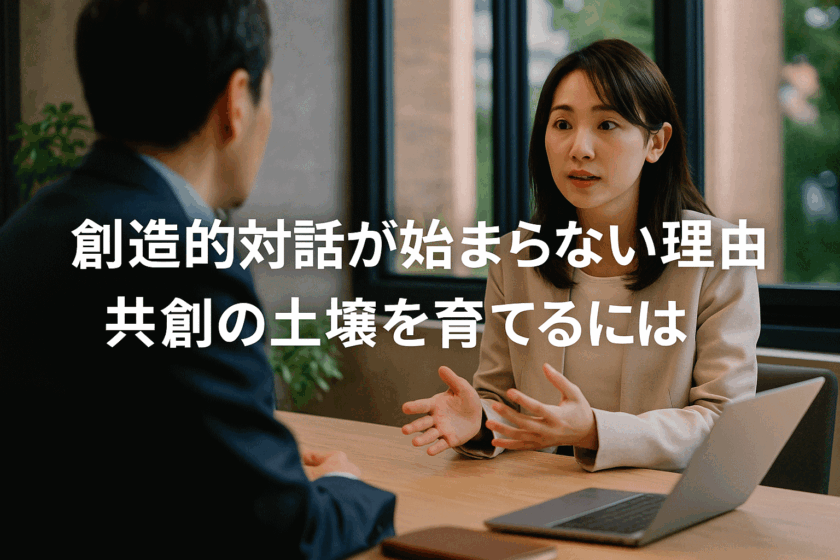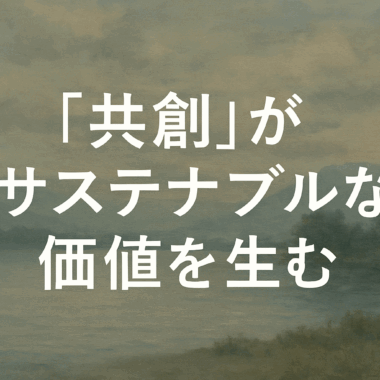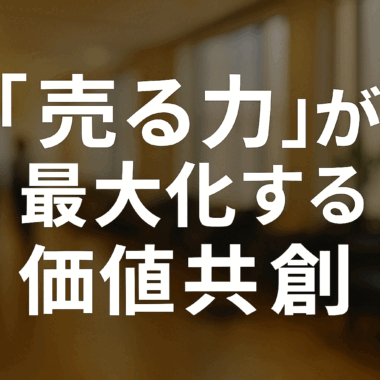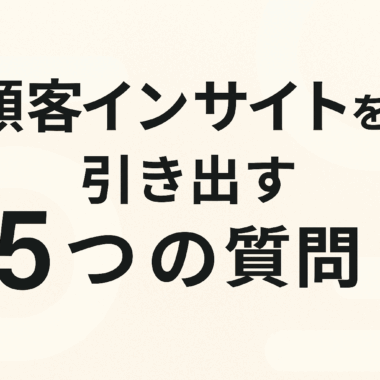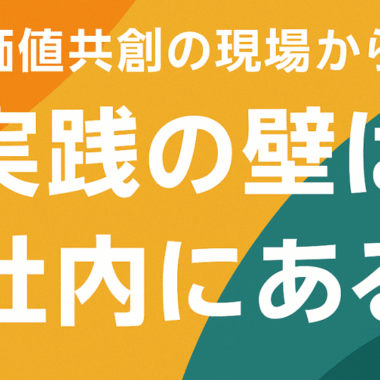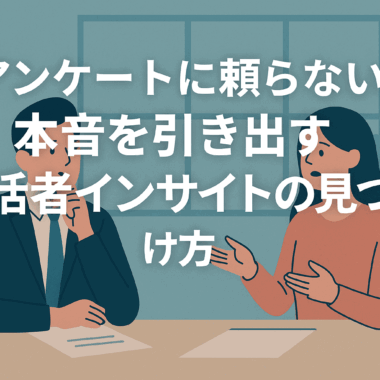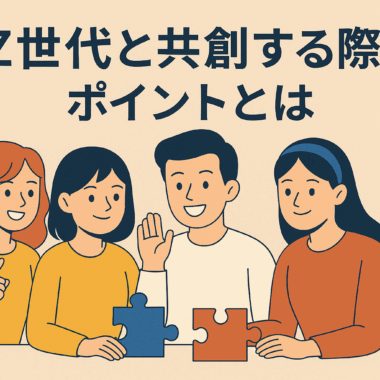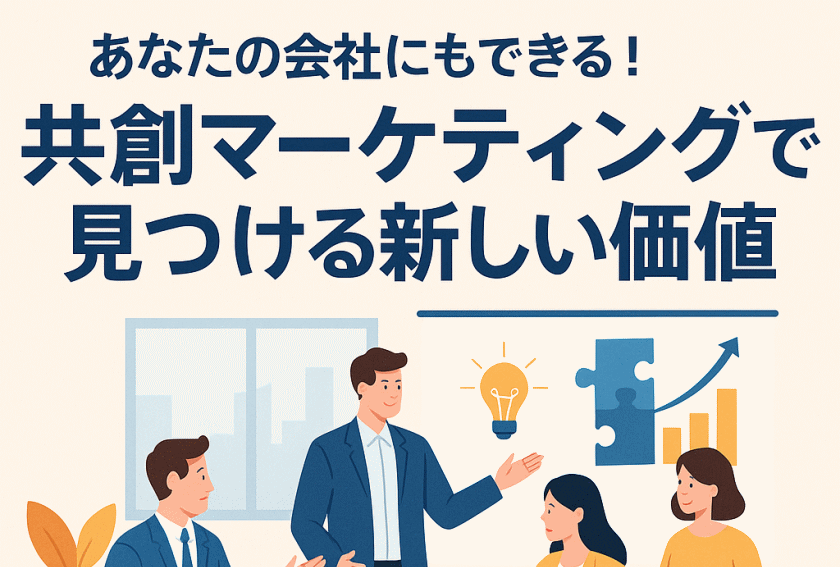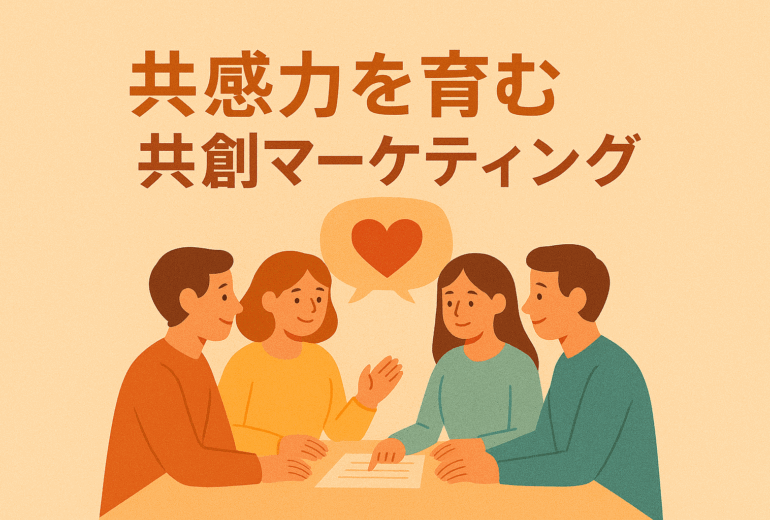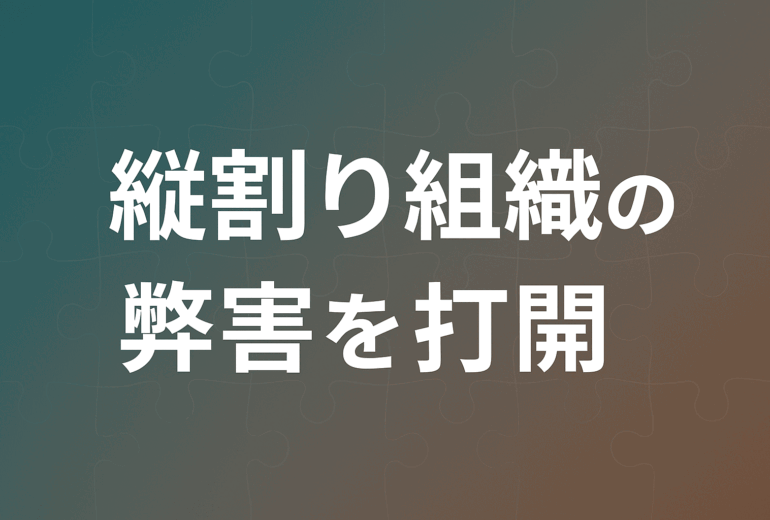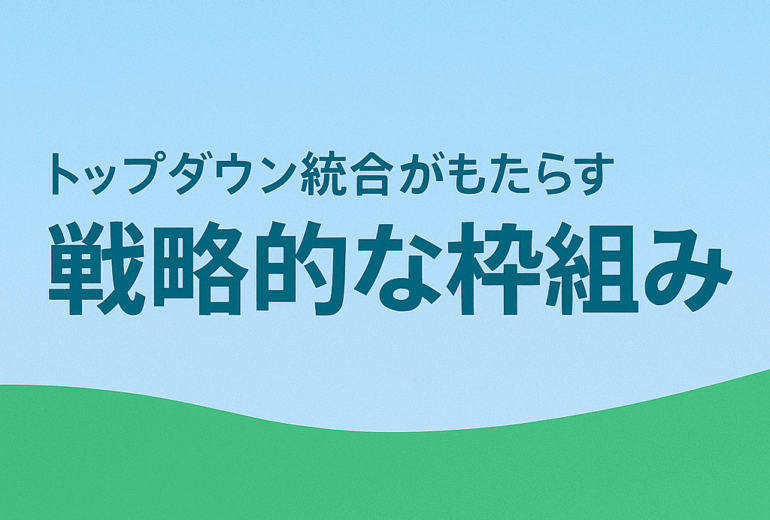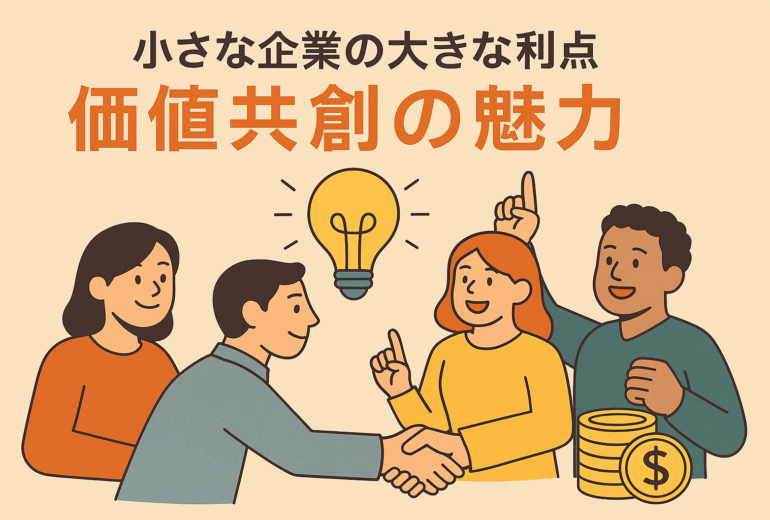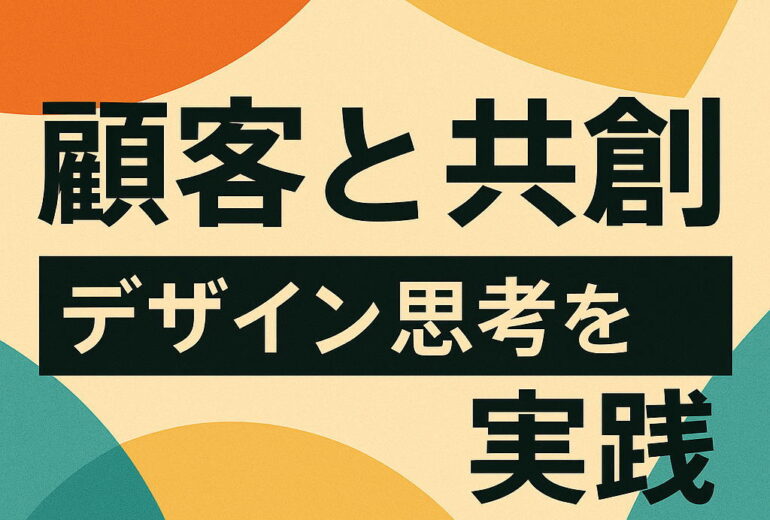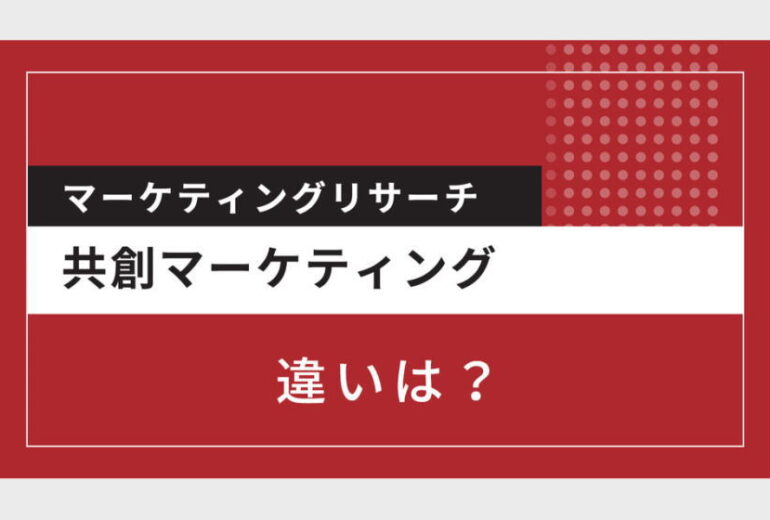「共創しましょう」「お客様と一緒に価値をつくっていきましょう」。
そんな言葉を企業の担当者に投げかけると、返ってくるのは決まってこんな答えです。
「はい、やっていますよ。アンケートを取ったり、ユーザー会も定期的に開催しています」
確かに、それらは大切な取り組みです。お客様の声を拾い、ニーズを確認することは、マーケティングの基本とも言えるでしょう。
しかし、私たちが価値共創の現場で問う「対話」とは、もう少し違ったものです。
表面的な情報交換ではなく、自分たちの中にある体験、感情、価値観まで持ち出して、共に揺さぶられながら「本質」を見つめ直す対話。その過程でしか生まれない、新しい意味やつながりこそが、真の共創の源になると感じています。
形式的な対話と、創造的な対話の違い
企業内の「対話」が、どこか形式的な枠に収まっているように感じることがあります。
月次の情報共有会、部門横断の報告ミーティング……それらの場では、論理的で整った発言が飛び交い、どれも正しいように聞こえます。
でもそこに、参加者自身の「想い」や「信念」はあるでしょうか?
「このままでは会社はまずいかもしれない」「この仕事が好きだから、もっとこうしたい」——そんな、少し青臭くても生々しい声こそが、共創の場に必要なのです。
このような創造的対話が進まない背景には、実は企業の“姿勢”や“空気”が大きく影響しています。
創造的対話を阻む三つの壁
1. 危機感の欠如
「今のやり方でうまくいっている」「変わる必要は感じない」。
こうした楽観的な空気が社内にあると、創造的な対話は始まりません。変化の必要性が薄く感じられると、面倒な対話は避けたくなるのが人間です。
特に中小企業の場合、トップと現場が近い分、現状への危機感が共有されているように見えて、実は「まだ何とかなる」との空気が蔓延していることがあります。
創造的対話の出発点には、「今のままではダメかもしれない」という切実さが必要です。これは、まるで洞窟に閉じ込められた人々が、光を求めて出口を探るような状況に近い。
「このままでいいのか?」という内なる問いを持てるかどうかが、共創の第一歩なのです。
2. 主体性の欠如
「共創の取り組みに参加してください」
そう呼びかけると、形式上参加してくれる担当者は多くいます。しかし実際には、「上司に言われたから」「仕方なく」といった受け身の姿勢で関わる人も少なくありません。
主体性を持たない参加者が集まっても、本気の対話にはなりません。
熱意のない対話では、言葉も感情も表層をなぞるだけになってしまい、「お客様と共につくる」という本質には到達しないのです。
共創は、企業の戦略として進めるプロジェクトであると同時に、人の感情とつながりが基盤です。自分ごととして捉える姿勢が、対話を動かす力になります。
3. 主観の軽視
ビジネスの現場では「客観性」が重視されます。「数字で語れ」「根拠を示せ」——それはもちろん大切な姿勢です。
しかし、共創の対話では、もう一つの大切な要素——主観が欠かせません。
お客様の気持ちに寄り添うには、自分の経験や価値観を通じて“感じる力”が求められます。それは、決してデータだけでは手に入らないものです。
「正しく話さなければならない」という思い込みが、創造性の芽を摘んでしまう。だからこそ、私はクライアント企業と接するとき、「無駄話」や「雑談」を意識的に取り入れます。
そこからこそ、組織が忘れていた“人間らしさ”がにじみ出てきて、創造的対話のきっかけになることがあるのです。
「実践」こそが、対話を次に進める
創造的対話が進み、「新たな解」が見え始めたとき、しばしば現れるのが“実行へのブレーキ”です。
「それは本当にうまくいくのか?」「失敗したらどうする?」——そうした不安から、せっかくのアイデアが棚上げされてしまうことがあります。
もちろん、無謀なチャレンジは避けるべきです。しかし、「新たな解」には、それなりのコンセプトや背景があります。それをもとに、小さな一歩からテストすることはできるはずです。
未来に絶対的な正解がない以上、実践を通してしか次の対話の材料は育ちません。
つまり、共創のサイクルとは、「対話」と「実践」を交互に繰り返すことによって動き出すのです。
共創の文化を育てるために
共創を目指す企業において、最も大切なのは「共創を実現できる土壌づくり」です。
それは戦略やスキル以前に、「人として語れる関係性」があるかどうか、そして「変わる必要がある」と本気で感じているかどうか、にかかっています。
もし、社内で創造的な対話がうまくいっていないと感じるのであれば——
- 危機意識は共有されているか?
- 担当者は本気で取り組んでいるか?
- 主観を語れる空気があるか?
- 言葉を行動に移す勇気はあるか?
ぜひ、こうした問いをチーム内で投げかけてみてください。
共創とは、一部の特別な人たちだけがやることではありません。どんな組織にも、その可能性は眠っています。
その芽を育てるのが、私たち支援者の役割であり、醍醐味でもあるのです。